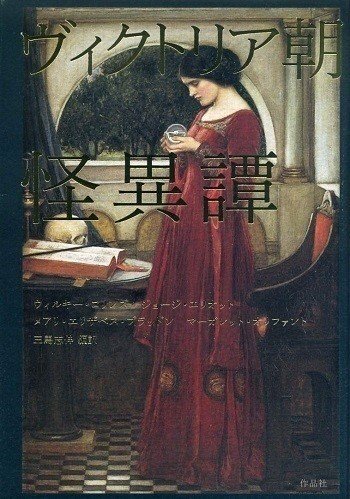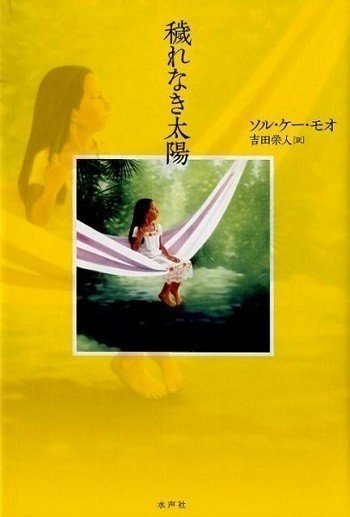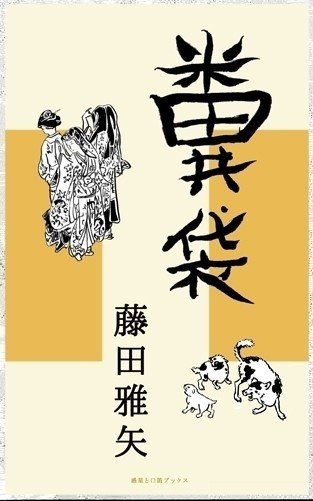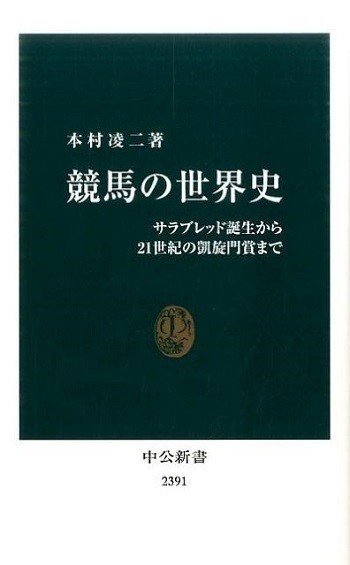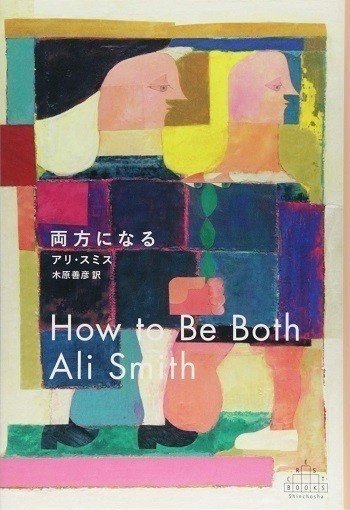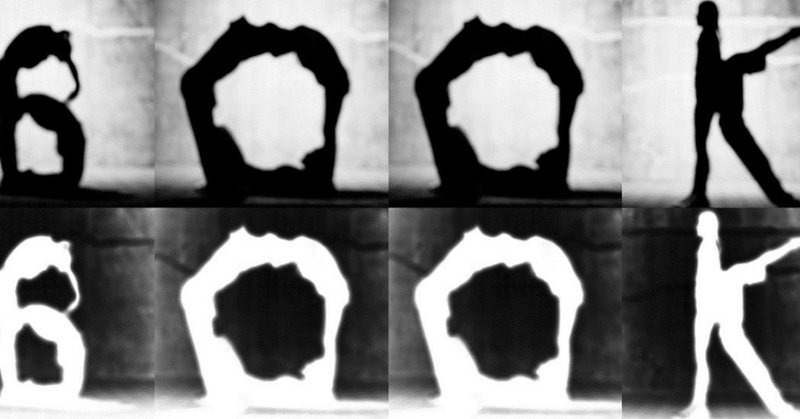
【読書備忘録】ヴィクトリア朝怪異譚からガルヴェイアスの犬まで
一二月頭の夏日は何だったのでしょう。数日後には一転して寒風が吹き、師走らしい寒気に見舞われています。もう奇怪な気象に馴染み始めているのであまり驚きませんが、お世辞にも健康的とはいいがたい現象だけに勘弁していただきたいものです。さて。今回の【読書備忘録】は二〇一八年刊行物が多いですね。復刊も含まれています。これから名著になる素敵な書籍が並んでいるので、少しでも読書のお手伝いができれば幸いです。
* * * * *
ヴィクトリア朝怪異譚
*作品社(2018)
*ウィルキー・コリンズ(著)
ジョージ・エリオット(著)
メアリ・エリザベス・ブラッドン(著)
マーガレット・オリファント(著)
*三馬志伸(編訳)
一九世紀のヴィクトリア朝では文芸雑誌の興隆等もあり大衆文学が最大の娯楽として親しまれていた。中でも恐怖を題材とする幽霊物語は読者の支持を集め、クリスマスの頃には挙って恐怖小説が寄稿されたという。イギリスは怪談の宝庫でもあるが、その歴史は一八〇〇年代まで遡ることができる。ただし文芸雑誌に掲載された中短編小説には単行本として刊行されず、文芸雑誌とともに忘れ去られた作品もたくさんあって、今では入手困難な幻の原稿もあるようだ。そうした掲載作から近年再評価されている中編小説を四編収録したのが本書。どれも幽霊譚として共通しているが、みずからの呪われた血筋を恐れるあまり狂気に囚われるありさまや予知能力を有するが故の苦痛、さらには霊であることの恐ろしさを物語る作品群は現代の目で見ても斬新であり、新鮮味のある驚嘆を覚えさせてくれる。気品をただよわせる恐怖の書としておすすめしたい一冊だ。
わたしたちが火の中で失くしたもの
*河出書房新社(2018)
*マリアーナ・エンリケス(著)
*安藤哲行(訳)
著者マリアーナ・エンリケス氏はアルゼンチン出身の作家であり、母国では「ホラーのプリンセス」とも呼ばれている。ただしこの肩書きはスティーヴン・キング作品の愛読者であるエンリケス氏の読書傾向から連想された感も否めず、本書に関してもホラー小説集と呼ぶのがふさわしいか判断し兼ねる。非常に特殊な小説だ。強いていえばアルゼンチン文学を代表する作家フリオ・コルタサルの悪夢的な表現に近く、ある貧民街での悲劇を物語る『汚い子』や『黒い水の下』に認められるモラルの崩壊、さらには不気味な家や麻薬の幻覚などを含めた日常に潜む恐怖がポイントになっている。特定の分野におさめるのは難しそうだ。ホラーといえばホラーだが、ホラー要素を主題に組み込むというより装置として機能させることで物語に深みを持たせているという方が正鵠を射ているのではないか、と思う。とはいえこれはあくまでも小生の読み方。この短編小説集に収録された狂気にさまざまな読み解き方があるのは明白で、他者がどう解釈するのか興味深いところだ。
穢れなき太陽
*水声社(2018)
*ソル・ケー・モオ(著)
*吉田栄人(訳)
本書はメキシコのマヤ先住民作家ソル・ケー・モオ氏の中編小説『穢れなき日』に、短編小説集『タビタとマヤの短編集』『酒は他人の心をも傷つける』二冊を併録したアンソロジーである。先住民による先住民言語の小説は先住民文学として注目されており、ユカタン大学主催の文学コンクールでマヤ語部門最優秀賞、メキシコ教育省のネサワルコヨトル文学賞を受賞したモオ氏はメキシコ文学界にとどまらず、現代ラテンアメリカ文学界の重要人物として名を馳せている。本書ではマヤにおける伝統的な社会規範や日常風景が活写されている。もっとも伝統には理不尽ともいえる悲劇が付きものであり、土着信仰の観念が負の色を帯びてうずまいている。生まれながらにして穢れていると見なされる女たち、社会的な逸脱者として堕ちていく男たち。そうした先住民の世界を描きながら、ユカタン半島のある村を舞台に繰り広げられる饗宴に繋がるという構成は見事で、非常に優れた編集といえる。ソル・ケー・モオ氏の他作品は言わずもがな先住民文学に対する興味を深めてくれる一冊だった。
糞袋
*惑星と口笛ブックス(2018)
*藤田雅矢(著)
僧曰く「誰もみな、糞の詰まった糞袋よ」と。第七回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作品が〈ブックス・ファンタスティック〉シリーズ第二作として復刊。舞台は一七〇〇年代の京の都。夜明けの高瀬川は濃厚な糞尿の臭気に包まれる。それは大量の排泄物をたくわえた肥たごを積載する糞舟が通るためである。かつて農業において人糞は貴重な肥料(下肥)とされており、京の都では「肥えとりはん」と呼ばれる人夫が家々を巡回して糞尿を集めていた。大変重要な役目だ。しかし、やはり色眼鏡で見られがちだったのか子供には露骨な反応を示されたりもしたようだ。孤児のイチは何の因果か、その「肥えとりはん」の家に預けられて連日下肥集めを手伝わされていた。この小説はイチの人生を通じて展開される珠玉のスカトロジーである。一癖も二癖もあるスカトロジストとの交流。糞尿で繋がる友情。本作品はウンコの風味を哲学の域に高めており、軽妙洒脱な文体でとても親しみやすい内容となっている。それでいて根底には人体の異名ともされる糞袋の意味が秘められていて、説話的な説得力を仄めかせているのだ。
餓死した英霊たち
*ちくま学芸文庫(2018)
*藤原彰(著)
陸軍経理部将校の父に続くため陸軍士官学校に入学、後には中国に赴任して一九四四年の大陸打通作戦に従軍するなど、日中戦争・太平洋戦争を経験した藤原彰氏が約二三〇万人にのぼる日本側戦死者の過半数が餓死や戦病死である事実に言及し、お粗末な大本営の戦略を痛烈に批判する。焦点はおもに糧食や銃器を筆頭とする補給面の問題。制空権を奪われている中、占領対象の島の地理をろくに調査しないまま兵士を密林の大地に上陸させるばかりか、食料や銃器さえまともに補給しないという無計画にして無謀極まりない対応には唖然とさせられた。銃器の不足に関しては軍需生産の遅延も影響しているが、上層部が補給を蔑ろにする背景には常に白兵突撃を盲信する精神主義があった。忠君愛国より発する攻撃精神が敵を倒すといった笑い話にもならない信念を本気で提唱する上層部は、権力の名のもとに兵士にも実行させたのである。その結果、銃剣を手に突撃した兵士は米軍の自動小銃で蜂の巣にされ、空腹や病気に苦しむ兵士は野垂れ死んでいった。衝撃的な内容だが、歴史に学ぶためにもおさえておきたい本だ。
恐い間取り 事故物件怪談
*二見書房(2018)
*松原タニシ(著)
松竹芸能所属の「事故物件住みます芸人」松原タニシ氏は怪談関連のイベントではおなじみの芸人であり、番組やインターネット配信を通してさまざまな体験談や伝聞を紹介している。松原氏の芸風は肩書きが示す通り事故物件に居住して心霊現象を検証するというもので、これまで滞在した事故物件は六軒に及ぶ。本書には松原氏の経験、松原氏と関わりのある人々の経験が収録されており、短めの話から長めの話まで奇妙な逸話がずらりと並んでいる。事故物件になる原因は多種多様だ。孤独死もあれば自殺や殺人など物騒な経緯もある。そうした部屋には幽霊が出現するという恐怖だけではなく、部屋自体に死や狂気の要因が隠されているようで人間的なものとは別種の恐ろしさを感じる。この「間取りの恐さ」を追究するという松原氏のスタイルは悪趣味な好奇心を刺激してくれるので、怪談好きは言わずもがな都市伝説やオカルトが好きな人も楽しめるだろう。また松原氏の淡々とした文体も魅力的で、信じる・信じないの問題を抜いても、純粋にコワい読みものとしても楽しめる。
競馬の世界史 サラブレッド誕生から21世紀の凱旋門賞まで
*中公新書(2016)
*本村凌二(著)
現代では世界的競技として親しまれている競馬。競馬発祥国といえばイギリスと認知されているが、競馬の原型は紀元前の古代オリンピックでおこなわれていた戦車競走にまで遡ることができる。もっとも戦車競走は複数頭の馬に引かせる形式で、速度を競うというより生き残りを懸けた戦闘的な行事だった。イギリスで近代競馬の基礎が築かれるには十六世紀まで待たなければならなかった。歴史研究者にして無類の競馬愛好家である本村凌二氏が綴る『競馬の世界史』は、世界史の観点から競馬の発展を概観する珠玉の手引きだ。競馬の解釈はどこに視座を設けるかで大きく変わる。例えばスポーツとして見るかギャンブルとして見るか、あるいは生物学的に見るか政治的に見るかで変容する。この複雑な仕組みが生まれた要因は古代から現代に至る競馬の変遷を眺望することで理解できる。本書はまさしく競馬の多面性を学び、理解を深める絶好の本だろう。読み方次第で初心者向けの入門書にも、より知識を蓄える学術書にもなり得るので、競馬歴なんて概念は忘れて気軽に読もう。
両方になる
*新潮クレスト・ブックス(2018)
*アリ・スミス(著)
*木原善彦(訳)
アリ・スミス氏は二〇一八年に実施されたイギリス・アイルランド在住のもっとも優れた存命作家というアンケートで、第一位に選出された気鋭の作家である。コスタ賞、ベイリーズ賞、ゴールドスミス賞を受賞した『両方になる』は木原善彦氏の『実験する小説たち』でも語られており、当時から注目していた。一五世紀イタリアの画家と二一世紀イギリスの少女を結び付ける概要自体好奇心を刺激するものだが、読み返しを想定した第一部と第一部の二部構成、鶏と卵のジレンマを応用した両者の関連性、多言語翻訳が困難な言葉遊び、などなど随所に用意されている実験はパズルゲームか精密機械の製造業を思わせるほど緻密だ。この蜘蛛の巣のように張りめぐらされた物語の隠し通路は探さなくても見付けなくても、時代を超える壮大な物語としての面白さを味わえるので問題はない。ただ、できることなら読書中だけではなく読了後の楽しみも追求していただきたい。一つ一つの繋がりを発見するたび新たな悦びを得られるはずだ。前述した『実験する小説たち』も併せて読むとなおよし。
ガルシア=マルケス「東欧」を行く
*新潮社(2018)
*ガブリエル・ガルシア=マルケス(著)
*木村榮一(訳)
ラテンアメリカにとどまらず、世界的作家として名を馳せたガブリエル・ガルシア=マルケスにも無名の時代があった。家も金もなくて友人の借りている女中部屋で糊口を凌いでいた時期もある。やがて『百年の孤独』で軌道に乗る彼だが、極貧に陥る前にはジャーナリストとして駆けまわっていた。本書にはジャーナリスト・ガルシア=マルケスの貴重な取材記録が収録されている。ベルリンの壁が築かれる以前の東西ドイツに始まり、後半はソ連での体験談が綴られる。そこで語られている事柄は必ずしも新発見に繋がるとは限らないが、未来のノーベル文学賞作家の観察眼と筆致で描きだされた貧困・憂愁・不安・暴力のはびこる情景は暗澹たる色彩を帯びており、ルポルタージュでありながら物語的な悲劇性を仄めかせている。一九六一年に建設された巨大な壁。その壁で遮られる以前から東西の格差は非常に大きなものであった。しかし東の国民が西に希望を託して移住すると思えば、西には西の悲哀が立ちこめていた。若き日の大作家が書き残した東欧の厳しい現実に読みながら息を呑んだ。
ガルヴェイアスの犬
*新潮クレスト・ブックス(2018)
*ジョゼ・ルイス・ペイショット(著)
*木下眞穂(訳)
原題にもある『Galveias』とはポルトガルのアレンテージョ地方に実在する村の名で、作者ジョゼ・ルイス・ペイショット氏の故郷でもある。夏は酷暑、冬は極寒が押し寄せる同地方の環境は厳しい。そこで育まれた感性は、宇宙から謎の巨大物体が墜落して以来大規模な豪雨と旱魃に見舞われてしまう村の、その乾燥した情景描写に生かされている。ガルヴェイアスに落ちた巨大物体は強烈な硫黄臭を放ち、やがて臭気は村全体を覆うことになる。日常に戻った住人たちは巨大物体を忘れていくが、不気味な硫黄臭はすでに彼らの生活にまで浸透していた。変化は食物の味から住人たちの心の内にも及ぶ。本作品は落下物の影響を受けた人々の物語を追跡する群像劇をなしている。一九八四年の一月と九月の二部構成で語られるガルヴェイアスの風景は喧嘩や確執で彩られており、お世辞にも綺麗とはいえない。しかし、絶望的で醜悪な交わりには滑稽味も含まれていて、憔悴しながらも明日に目を向けるような、ポジティブな色彩が認められる点が特徴的だ。
〈読書備忘録〉とは?
読書備忘録ではお気に入りの本をピックアップし、感想と紹介を兼ねて短評的な文章を記述しています。翻訳書籍・小説の割合が多いのは国内外を問わず良書を読みたいという小生の気持ち、物語が好きで自分自身も書いている小生の趣味嗜好が顔を覘かせているためです。読書家を自称できるほどの読書量ではありませんし、また、そうした肩書きにも興味はなく、とにかく「面白い本をたくさん読みたい」の一心で本探しの旅を続けています。その過程で出会った良書を少しでも広められたら、一人でも多くの人と共有できたら、という願いを込めて当マガジンを作成しました。
このマガジンは評論でも批評でもなく、ひたすら好きな書籍をあげていくというテーマで書いています。短評や推薦と称するのはおこがましいかも知れませんが一〇〇~五〇〇字を目安に紹介文を付記しています。何とも身勝手な書き方をしており恐縮。もしも当ノートで興味を覚えて紹介した書籍をご購入し、関係者の皆さまにお力添えできれば望外の喜びです。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。