
言葉は踊る - ウィリアム・ギャディス 『JR』 感想
──くそ、問題は声に出して書かれるために読まれた文章じゃないってこと、じゃあ、自分で読め、ここからだ、ほら。
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.744)
<購入して分かった! 『JR』 のオススメポイント>
ポイント1:人を殴るときに使える
人間関係でのストレスに満ちたこの現代社会、「こいつ殴りてえ」と思ったことはありませんか?ありますよね?そんなときにはこの『JR』!
なんといっても本商品はとにかく重い。出版社が重量で商品説明するレベル。

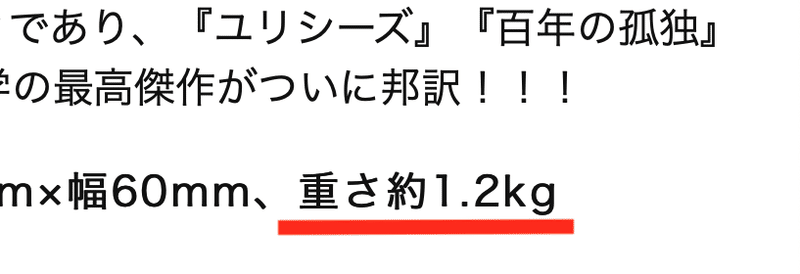
その重さは1.2キログラム!装丁も硬く、いい具合に角ばっていて、これなら安心してヤることが出来ます。「一発で仕留められるか心配…」と思っているそこのか弱き乙女のあなたも、『JR』をお手にとれば解決です!
ポイント2:身を護るのに使える
人間関係でのストレスに満ちたこの現代社会、街角を歩いていて狙撃されそうになったことはありませんか?ありますよね?そんなときはこの『JR』!
使用方法は簡単、本書を胸元に忍ばせておくだけ。こうしておけばもしものときも颯爽と『JR』を取り出して「危うく死ぬところだったぜ……こいつが無ければな」と決め台詞を放てること間違いなし!
あなたの胸ポケットに『JR』、お一ついかがですか?
さて、ここまででなんと鈍器にも護身グッズにもなるという『JR』の使い勝手の良さを紹介しましたが、実はこれだけではないんです!本商品の知る人ぞ知る裏ワザ的活用法をみなさんに特別にご紹介しちゃいましょう!
それはなんと……
…………
…………
ポイント3:読める
な、なんだってええええええええええ!!!!!!!!
…というわけでここからは真面目にやります。各方面の方々ごめんなさい。
『JR』は、トマス・ピンチョンやドン・デリーロと並ぶアメリカのポストモダン作家の代表的存在であるウィリアム・ギャディスが1975年に発表した2作目の長編小説であり、本作で彼は全米図書賞を受賞した。(ちなみに彼は後に『自己責任の遊び』で再び全米図書賞をとっている。)
本作が難解と言われるのはその長さ(邦訳は2段組で本文が約900ページ)というよりも、その特異な文体形式にある。なんと本文のほとんど全てが登場人物のセリフに占められているのだ。地の文がまったく無いわけではないが、後述するようにその出現頻度・役割はかなり限定されている。
全編会話調の小説、と言ってわたしが真っ先に思い浮かべるのはニコルソン・ベイカーの『もしもし』だ。会員制テレフォン・セックスでの男女の一夜の会話劇。しかし本書の発表は1992年なので、『JR』のほうが早い。
歴史的に先んじているだけでなく、『JR』の会話劇は『もしもし』のそれと途方もなく性質を異にしている。『もしもし』の会話を構成するのはたったの2人だ。しかも彼らの間で交わされる言葉のキャッチボールは、基本的に上手くいっている。つまり、それぞれが何を話しているのかがわれわれ読者にも明瞭で、かつお互いに尊重し合って、"大人な"会話を楽しむ。
それに対して『JR』の会話は同じ電話口でも上手くいっていない。全編を通じてとことん上手くいかない。どこのページを開いてもいいのだが、例えばこんな感じ。
──もしもし?
──他の人にはアシスタントがいるんだぞ、ウィリー、でも、私はいつも、一から十まで自分でやらなきゃならない…
──バルクさん?この電話は一体…
──オペレーターです、ご用件は?
──ああ、電話を切ってくれ。シャーリー……?
──お電話がまた混線しているようです、ビートンさん、でも、それ以外のお電話が二つともつながっています……
──彼らを訴えることになったら、私自身が自分の弁護人として出廷を……
──畜生、チャーリー、この電話を切って、スタンパーの自動車電話に連絡をしろ。
──もしもし?
──はい、もしもし、そちらにジュベール夫人はいらっしゃいますか、緊急の用事でお伝えしたいことがあるのですが……
──それからこっちに来て、このくそズボンの裾をどうにかしてくれ。
──少々お待ちを、はい、先ほどまでこちらにいらしたのですが、今少しご気分が、ダン?
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.552)
以上を見ればわかるように、本作中では人物のセリフは「」のなかでなく、──のあとに置かれている。本作の訳者である木原義彦氏は、著書『実験する小説たち』のなかで本作を「ト書きのない戯曲」と呼んでいる。まさしくその通りで、ト書きがないため誰がこのセリフを言っているのかが非常にわかりづらい。
それだけでなく、誰に向けて話しているのか、そしてそもそもその場に誰がいるのかを知ることが極めて困難なのが本書の最大の特徴だろう。われわれ読者は、文脈やセリフの端々の情報をもとに、シーン毎の視覚的イメージを"推測"しながら読み進めていかなくてはならない。
ここまで聞いて「なんでわざわざそんな苦行みたいなことしなくちゃいけないの、ドMかよ」と思うかもしれない。
たしかにピンチョンを始めとするポストモダン小説の愛読者はドMであると断定してしまってもそれほど間違いではないと思う。しかし本書に関しては安心してほしい。一見して読むのが難しいかわりに、ものすごく面白いのだ。
これは別にピンチョンの悪口を言いたいわけでなく(むしろ愛してる)、『JR』は多くの難解と言われる小説と違ってコメディなのだ。しかもアメリカのホームコメディ……ちょうどフルハウスのような感じの。ただし、客席からの「HAHAHA」は聞こえてこない。われわれが「HAHAHA」と言う必要がある。
本作には全編を通じてツッコミどころが溢れている。わたしたちがそこを見つけて、いかに「おい!」「そうはならんやろ」「草」などとつっこむか、本書の面白さはそれに掛かっている。
もちろん、わたしだって膨大なツッコミどころの全てを目ざとく見つけることができたかといえば全然そんなことはない。張り巡らされた多くの小ネタ、伏線、ジョークをスルーしてしまったことだろう。それでもなお、本作の読書体験はとても楽しいものになった。それほどに愉快なドタバタ劇なのである。
……あ、そもそも本書が何の話なのかを説明していなかった。
帯にもどデカく書かれているが、本書は金融ブラックコメディだ。JRという11歳の少年が会社を立ち上げ、いかにアメリカや世界の経済を大崩壊に陥れるまでになるかを描く。
金融業界の話なので、当然株式の用語や知識がこれでもかと詰め込まれている。
わたしは経済方面にはまったくと言っていいほど興味がない人間だし、そもそも株なんてどうぶつの森からの知識しかない。

(画像はこちらのブログよりお借りしました)
その程度のわたしでも、なんとか読み通すことができた。専門用語でややこしい法律の話が飛び交う箇所は流し読みをした。実際のところそれであまり支障はなかった。なぜならそもそも登場人物たちはお互いに他人の話を聞いていないからだ。
──今はそんな話をしなくてもいいんじゃないの、アン。
──構いませんよ、ご婦人方。ここに入れておいたはずなんですが……
──ねえ、アン……
──はい、ありました、準州の制定法が婚姻夫婦の間に生まれた子供の嫡出性を無効と規定している場合もあって、白人男性とインディアン女性との間に生まれた子供が非嫡出とされています……
──チェロキー族の血なんです、分かりますか、コーヘンさん。チェロキー族は独自の文字を持っていた唯一の部族だったんですよ。
──しかも、申し立てられた結婚が当該準州内のインディアン保留地においてインディアンの慣習に従って執り行われたとしても無効なんです、先ほどの件はおそらくこれで解決ですね。この話はこれくらいにしておきましょう、バストさん。
──頭飾りを付けたシャーロットのあの写真をコーヘンさんに見ていただこうかしら、巡業先で撮った……
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.31)
小難しく言い回す法律家たちを風刺した側面も大いにあるため、難しいと思ったら「なにいってんだこいつ」という目で流し読みしてまったく問題はないと思う。(もちろん、細部に目を凝らすことによって見えてくる、ハッとするような伏線は数多くあるらしいのだが、そこまで味わうのは一部の専門家とマゾヒストに任せておけばいいだろう)
というわけで、『JR』の内容と特徴の紹介を超大雑把にではあるが行った。以下では、本書を読んでわたしが感じたこと、考えたことをあることないこと書き連ねようと思う。言わば素人による批評のマネごとだ。
といっても前述の通りわたしは経済も法律も詳しくないので話のそうした筋について深く考察することはできないしする気もない。わたしが注目したいのは、やはり会話主体で進められるテキストの形式自体についてである。
「発話」と「地の文」の関係性
本書は全編が会話調であると何度も述べてきた。ただし会話といっても独り言やラジオ・テレビ等から流れる言葉も頻繁に登場するため、ここからはより広く意味をとって"発話"と呼称したい。要するにこの小説内で生きる人物が(どんな形であれ)発したセリフのことだ。
発話と対になるのが地の文である。対になるというより、むしろ発話の補集合(埋め合わせ)としての立ち位置に地の文はあるように思える。本書において地の文は大きく分けて3パターンの登場の仕方がある。「鈍器用」「護身用」「読書用」…ではなく、「場面のミクロな補完」「空間的移動」「時間的移動」の3種類だ。1つずつ具体例を挙げていこう。
1.場面のミクロな補完
これはもっとも一般的な地の文の使われ方である。つまり、各発話の間に挟まって誰が何をしているのか、その場で何が起こっているのかを補完する。こうした地の文がたくさんあるところは読みやすいので、ギャディスありがとうという気持ちになる。(以下の引用において、こうした地の文にはわたしが太字を付けている。)
──ママ?
──何、デビッド。
──僕は神様に呼ばれたくない。
──デビッド、神様は誰も呼んだりしない……突然、彼女は彼を抱き寄せた。──ママのこと、愛してる?
──うん。
──どれくらい(How much)?
──お金で言うとってこと……?彼女がそうして彼を抱いていると、チャイムが鳴った。──パパかな?
──ジャックかも。
─ジャック!と彼は腕をふりほどき、廊下を駆け抜けて玄関の錠を外した。
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.339)
例えば2つ目の地の文「〜チャイムが鳴った。」がもし挿入されていなかったら、母と子の会話の最中に何の脈絡もなく「パパかな?」と子が言い出しているように読めてしまう。チャイムは音ではあるがセリフではないので、本作中では"発話"としてすくい取られないからだ。こうした"発話"の間をスムーズにつなぐのが、場面のミクロな補完としての地の文である。
"ミクロな"と注釈を付けたのはあくまで人物の動作やその場での素朴な現象(「チャイムが鳴った」など)しか守備範囲ではないからで、もっとマクロな場面説明(ここはどこで、誰が誰と何のために話しているのか)は地の文ではまったく触れられない。読者が補完するしかない。
そして、上記の引用で驚いたひともいるだろうが、本作中では地の文と発話はほとんどシームレスに混ざり合っている。発話の目印となるのは頭の"──"のみなので、逆にどこで発話が終わっているのかが少しわかりにくい。「お金で言うとってこと〜〜パパかな?」のところなんて改行やスペースなしに1行のなかで「発話→地の文→発話」というテキスト上の移行が起きている。こうした発話と地の文の連続性については後に考察の対象となるので覚えていてほしい。
2.空間的移動
これが本書の地の文の役割のなかでももっとも特徴的で、読者を驚かせるポイントである。本文を引用したほうが早いだろう。
──と六十三セント、とジュベール先生は言い終えた。彼女がその場を去ろうと重心を移すと、スカートの膝の辺りが柔らかなさざ波のように膨らんで渦を巻き、膨らんだリボンの折り返しから飛び出した二十五セントを取ろうとしたバストは縁石から離れていくホワイトバックの車の排気ガスに頭から突っ込んだ。車は角を曲がってバーゴイン通りに入り、チェーンソーの金切り声と無麻酔の空中手術を施されてぶら下がっている枝の中を疾走し、最後に教員用駐車場に入ると同時に二階の階段の窓から外を見ているギブズの狭い視界に入った。ジュベール先生が車から降り、彼の真下の入り口に向かうのが見えた。冷たい暖房機を掴んでいるギブズの拳は色が白くなっていた。建物に近づいてくる彼女のゆったりした膨らみを窓の桟でその姿が見えなくなるまで目で追った。明かりを消した教室の方へ彼が向き直ると画面上でしゃべるアニメの顔が正面に見え、何も聞かないままで見続けるという緊張に耐えられなくなると、彼自身の唇がピクリと動き、再び窓の方を向いて下を見下ろした。すると大きなカメラの目が彼に狙いを定めた。同じように窓際で暇そうにしている教師たちの下には学校の入り口があり、献辞が刻まれていた。
──ΕΒΦΜ ΣΑΟΗ ΑΘΘΦΒΡ……
──え、読めるの?
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.41)
要するに、ジュベール先生が銀行から小学校に車で移動し、最後はその入り口にシーンが空間的に移動している。それをまるで映画の長回し(ワンカット)のように地の文で表現しているのだ。
たしかに発話(会話)だけでは場面の移動を表現することは不可能に近い。そこでギャディスは上記のように、いっそ場面移動のときだけは地の文を雄弁に用いる方針を採ったのだろう。
3.時間的移動
場面の移動だけでなく、同じ場所での時間の移り変わりを表現するのも発話だけでは難しい。なぜなら、例えば「1人で夜を過ごす」場面では基本的に人物は無言だからだ。発話が存在しなければさすがに地の文に頼らざるを得ない。
──(略)まったく、畜生!彼が腰を下ろすとフィルムの缶がその後に続き、床に落ちて蓋が開いて中から飛び出したフィルムが目の前で陽気に転がり、H-Oで座礁した。彼は一瞬、そこに身を沈め、──片付けるぞ、畜生、今夜一晩で最初の部分を仕上げられたかもしれないのに……彼は穴の開いたランプの笠の闇の下に手を伸ばし、ソファまで戻って毛布を引き上げ、奥から響く奔流と、もっと近いところから滴がしたたるように聞こえるラジオの声に耳をふさいだ。
──大事な家宝、その多くは名家の……
ついに光が差して、何かの邪魔になるのを遠慮するかのように慎重にブラインドの板を一枚一枚に分け、吹っ切れたかのようにその幅が広がった。何も動くもののないその場所では、秒針だけが弧を巡り、やがて長針が "預け金がない場合" から上り、何度か失敗した後にようやく、短針を引っ張り上げた。
(ウィリアム・ギャディス『JR』pp.715-716、ラジオの強調は原文ママ)
地の文で時間の移り変わりを表現すると言っても、「そして翌朝…」のような直接的な言い回しは決してしない。あくまで「ついに光が差して」のように、その場で実際に起っている現象にのみ着目して、時間を表現する。
この「実際の動作・現象しか書かない」特徴はいま見てきた1-3の全ての地の文のパターンについて言えることだろう。「彼女は不審に思った」とは書かずに「彼女は眉をひそめた」と書く。「一方その頃学校では…」とは書かずに、車などの具体物を利用してワンカットでその行動を追うことで学校へと場面を実際に"持っていく"。
つまり、本書における地の文(=語り手)はかなり特殊な立ち位置にある。普通、語り手はその小説での神様のような存在である。登場人物の心情を見透かし、行動原理をペラペラ喋り、シーンの俯瞰的説明をし、回想など時間の移動も自由自在。一方『JR』の語り手は「"いま-ここ"で五感を通じて直接知覚できること」しか言及しない。極めて人間的である。いや、味覚や嗅覚、触覚はたしか描写されていないはずだから、目と耳しか持たない存在、つまりビデオカメラのようなものだ。
その場で見えること、聞こえることだけを執拗に何百ページにも渡って捉え続ける──しかももちろん登場人物には認識されないのだから、もはや盗撮・盗聴器ごしの音声映像をわたしたち読者は見せられているというほうが適切だろう。
「本書は盗撮器ごしの音声映像である」という観点で考えれば、ややこしい会話の描写の理由も納得がいく。本作は世界を"ありのまま"写し撮っているに過ぎないのだ。われわれの日常的な会話を試しに手元のスマートフォンで録音してみればよい。音声はガサガサと不明瞭で、発言は「えっと…」や言い淀み、謎の間、聞き違いなどで溢れているだろう。本作はそもそもの1文目からしてそうなのだ。
──お金……?と、かさかさした声。
──紙の、ええ。
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.21)
また、多くの読者を苦しめる「電話ごしの会話なのに一方の発話しか書かれない」というイジワルな特徴も納得がいく。
考えてみれば当たり前のことで、その場にあるビデオカメラにとって電話越しの声なんて聞こえるはずがない。電話越しの会話をちゃんと両側から聞き取るなんて、それこそ電話機に盗聴器でも仕掛けられていない限り不可能だ。
──(略)いえ、いえ、静かに……この電話、何か変なノーズが聞こえませんか? ノイズ……? 彼は受話器を持ち上げ、振り、送話口のねじを緩め始めた。──え? どうしてです、ホンジュラスはいいところですからね、買う気でいるのかもしれません、広大な平原、紫色の、もしもし……? 聞こえてます……? 聞こえない……彼は外れた蓋を顔に近づけ、配線の下に爪を入れてひねった。──畜生、盗聴器か……
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.734)
さて、ここまでの流れを整理する。
本文を「発話」とそれ以外の「地の文」にバッサリ分けて、地の文には3つの役割があると述べた。更にその3パターンに共通する性質を見出すことで、「本作は盗撮・盗聴器ごしの音声映像である」という仮説を導いた。
ここで注意してほしいのは、地の文について考えていたはずなのに、いつの間にか「発話も地の文もひっくるめて盗撮・盗聴器ごしの音声映像」という形になってしまっている点である。
すなわち、「本文を大きく発話と地の文に分ける」という最初の方針は的を外していたということだ。発話と地の文の区別は本質的ではない。言い換えれば、本書においては発話と地の文は本質的に同等である、両者は混ざり合い一体となって『JR』という長大なテキストを構成している。
これは本作における極めて重要なポイントだと思う。発話-地の文がシームレスであることは、何よりもまずテキストの形式として現れる。つまり"見ればわかる"。前述の通り、発話を表す記号が罫線(──)だということ。
なぜ普通の小説のようにかぎ括弧「」を使わないのだろうか。あまりにも発話が多すぎるせいでかぎ括弧をいちいち使っていると煩雑になってしまうため、だと最初は思っていた。しかしそのような消極的理由ではなく、もっと積極的な理由を今なら導き出せる。すなわち、わざと地の文との差異を排除したかったのではないだろうか。
かぎ括弧を使うと、当然のことながら発話の冒頭と末尾に「」が装着され、そうして発話はテキスト上で"浮いて見える"。縛るもののない地の文と異なり、発話はかぎ括弧という角ばった牢獄に厳格に収容されているのだ。(もちろん英語版の原著ではかぎ括弧の代わりに""という引用符が同じような働きを示す。)
一方、罫線(──)ならどうか。その視覚的イメージは、まさしく発話を"区切る"かぎ括弧とは違って、一本の直線で地の文と発話を"繋げて"いるように見える。
しかも罫線は発話の冒頭に付くだけなので、発話に続いてすぐに地の文が来る場合、文字通りシームレスに繋がることになる。どこまでが発話でどこからが地の文なのかがパッと見てわかりづらい。それはすなわち、語り手であるビデオカメラからしてみれば、発話だろうが地の文だろうが全てはそのカメラに見えているもの・聞こえているものであり、区別する必要はない・区別できないということを示している。
発話とはその小説世界内で人物が実際に発した言葉であり、地の文とはその小説世界をひとつメタな次元から俯瞰している語り手の言葉である。つまり次元としては「発話<地の文」となっているハズである、従来の小説では。
『JR』では発話と地の文の次元にもはや大小関係はない。ビデオカメラを通じて両者が溶け合うために、地の文の語り手が小説世界を俯瞰して描写するという構造が崩壊しているのだ。株式市場の崩壊どころの騒ぎではない。発話と地の文が渾然一体となって、ぐちゃぐちゃした原始的な言葉──純粋な言葉──としてわたしたちの前に現れる。
こうしたテキスト上の発話と地の文の関係性に注目するなかで、非常に興味深いシーンがある。ギブズが長年執筆している社会についての批評文を推敲する場面だ。
──(略)「さっさと事実を示せ!」、こんなことはくどくど書くまでもない。さて……煙が上がった。──よそでは文学に分類されている、いや。これらはよそでは文学に分類されており、そうしたものが『街の女マギー』を踏みつけにした、ここは受動態か、他の事象とあいまって、いや……煙が上り、たばこは最後にエンチラーダの中に落ち、彼の頭は後ろにもたれた。──そうしたものが……
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.705)
太字強調はわたしが「本当の地の文」に付けた。というのも、このシーンではギブズが原稿の文章を読み上げることで、発話のなかに「見かけ上の地の文」が登場しており極めてややこしいのだ。もっとややこしいことに、その見かけ上の地の文(=原稿)のなかに更に「さっさと事実を示せ!」という見かけ上の発話(=原稿の中のセリフ)が存在する。つまり、この数行の文章は4重の構造を持っている。
もちろん、やろうと思えば普通の小説でもこのような多層構造は簡単に作れる。しかし重要なのは「発話と地の文が渾然一体となっている」本書のなかで4重構造ができているということである。
語りの構造が崩壊しているのかしていないのかハッキリしろと言われそうだが、この異常事態はこのように矛盾を孕んだ形でしか表現できない。構造が崩壊しているなかで構造が成立しているのである。
書かれた言葉と話された言葉、それらが聞かれたり読まれたりすることで、言葉は互いの属性・位相を入れ替え合い、影響し合い、包含し合ってただひとつのテキストとなる。このような倒錯的な事態を端的に表したシーンがある。
──くそ、問題は声に出して書かれるために読まれた文章じゃないってこと、じゃあ、自分で読め、ここからだ、ほら。
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.744)
太字は原文では傍点として強調されている。ギブズは本当は「読まれるために書かれた文章じゃない」と言いたかったところを言い間違えてしまったのだ(訳者注あり)。このような単なる言い間違いが重大な意味を持つのは、言い間違いや聞き間違いといった実際の言葉につきまとう誤配性を一貫して強調する本書だからこそである。
言いかけた言葉、伝わらなかった言葉、遮られた言葉、誰にも届かなかった言葉、…あらゆるレベルの言葉が『JR』には溢れている。それら無数の言葉が、1冊の本という形を成して「書かれた言葉」になっているということ。それをわたしたちが読むという行為によって「読まれた言葉」になるということ。
重量を記載されるほどの法外なボリュームになってまでして、「鈍器」とか散々ヤジられてまでして、本書が分冊ではなくひとつづき(ワンカット)の1冊の書物になっているという事実。ギャディスが時間を掛けて書き連ね、木原さんが時間を掛けて訳し上げ、こうしてわたしたちのもとに「本」として届いているという事実。それは、わたしが想像できるよりも遥かに奇跡的で、言い表せないほど素晴らしい、感謝すべきことなのかもしれない。
最後にひとつ。本書にはあらゆるレベルの言葉が溢れている、と書いた。しかしただひとつだけ、言葉が書かれなかったシーンがある。
──でも、本当にそれをしている人なら、それはたしかにする価値があると信じているはずだわ、と彼女は彼から顔を背け、──最初からやる価値がないと分かっていたことをやろうとして失敗する、それこそが唯一、たちの悪い失敗だと思う。違う?
そのとき彼が何をささやいたにせよ、その言葉は失われた。
(ウィリアム・ギャディス『JR』p.605)
失われた言葉を求めて、わたしたちは本を読む。
言葉は今もどこかで、あらゆる形式から解き放たれんとして、ビデオカメラの向こう側で踊っている、踊っている、踊っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
