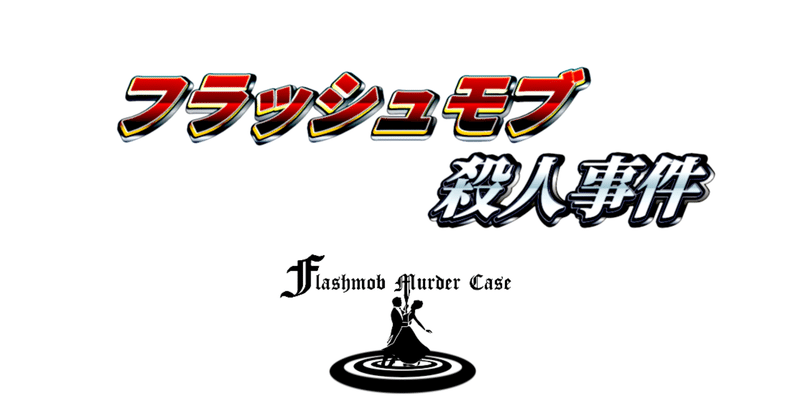
フラッシュモブ殺人事件
「ごめん。今日飲みに行くことになった。ご飯もう片付けていいよ」
崇太がそう言うと、電話の向こうで麻弥子が不満げな声を上げた。
「本当ごめん。近いうちに何か埋め合わせするからさ」
そう話す崇太の声には言葉と裏腹にどこか嬉しげな響きがある。海に面した市街地のテラスを歩く足取りは軽い。まばらに立った街灯が、穏やかな初春の海面に白々とした明かりを投げかけていた。沖から吹き寄せる冷たい風がスーツの上から羽織った長いコートをはためかせている。
「あ、そうだ。帰りに何か買って帰るよ。要るものある?」
電話口で麻弥子が別にない、と答えた。つい先日まではこれで多少は機嫌も取れたのだが、この頃崇太は連日のように遅く帰っているので、帰りに買っていくような物もなくなってしまった。崇太が再び謝罪を口にすると、麻衣子はいいよ、おやすみと言って電話を切った。
先ほどから崇太には行く手に建つ一軒の建物と、その入り口で自分を待つ都築の姿が見えていた。崇太は携帯をポケットにしまうと、都築に声をかけた。
「よお、何かあったのか」
都築はおう、と返事をした。痩身の男で、屋外の寒さが身に応えるのか体をくの字に折り曲げ、マフラーに顎を埋めている。崇太とは大学以来の知り合いで、どちらもまだ二十代だが、都築の方が幾分老けて見えた。
「メンバーの足並みが揃わない」
都築はそう言うなり苛立ちも顕わに煙草を懐から出して吸い始める。煙草の先がちろちろと闇の中で赤く光っている。
「足並みが揃わないってどういうことだ」
「配役に納得がいかないらしい」
崇太の問いに都築は背後の建物の方を見て言った。中は都築の経営するダイニングになっている。ログハウス風の外観で、海が見える洒落たレストランとして近ごろ若者からの支持が厚い。夜となれば日ごろディナー客で賑わうその店が、今日は都築の個人的な知己によって貸し切られている。彼らが集まったのには理由があり、一月後にこの店で行われる崇太から麻弥子へのプロポーズへ向けて、今店内ではダンスフラッシュモブの入念な打ち合わせが行われているのだった。
「子供かよ」崇太が呆れ顔で言う。
「そう言うなよ……こっちはお前がいない間中々大変だったんだ。加藤と田淵なんだがな」
崇太は二人の顔を思い浮かべた。加藤も田淵も崇太にとっては数年来の友人だ。加藤は裏表のないスポーツマンで、崇太は彼の誘いでハンドボールチームの試合に時折助っ人に出ることがある。田淵は資産家の長男で、自身も大学在学中から人材派遣会社の経営を始め、成功を収めている。
「ああ。その二人がどうかしたのか」
崇太から見てどちらも我の強いところがある二人だったが、特に仲の悪かった事実はない。彼らの間に諍いがあろうとは思えなかった。
「それがな、途中でお前に婚約指輪を渡す役割があるだろう」
自分で発案した手前、崇太はダンスの流れを覚えていた。振付の最中にウェイターに扮した知人が、婚約指輪をトレイに乗せて崇太の元まで運ぶことになっている。
「あいつら二人とも自分の方がその役目にふさわしいって言うんだ」
崇太は思わず吹き出しそうになった。
「本気でそんなことを言ってるのか」
「まあそう言ってやるな。二人とも真剣にお前のことを祝福してやりたいと思ってるんだよ」
都築が話すその間も崇太は笑い続けていた。しかし都築の言うことも最もだ。元々崇太の企画していたフラッシュモブはここまで大規模なものではなかった。どこか戸外の開けた場所に予め崇太が地元の知人を呼び集めて起き、そこへ通りがかった崇太と麻弥子を突如として踊りながら取り囲む。盛り上がりが最高潮に達したところで、崇太が麻弥子に結婚を申し込む――当初の計画は言わばそんな軽い余興のようなものだった。もっと言えば決行するかどうかさえも定かでなかった。
そこに具体的な計画と、実行のための場所を提供してくれたのが都築だ。知り合いのダンサーを仲間に引き入れて、振付や演出を考えてくれたのが加藤。田淵も自営業で忙しい中時間を割いて練習にまで出席してくれている。彼らがフラッシュモブにかける熱意は当の崇太を上回っていた。
「とにかく、一度二人の話を聞いてみてくれ」
都築の言葉に崇太はわかった、と返して店の中へと入っていく。都築は戸外に残るつもりらしく、崇太が背後を振り返ると二本目の煙草に火を着けていた。
店内では崇太の見知った顔が何人か声をかけてきた。座席の大部分が邪魔にならないよう壁際に寄せられていて、まばらに残った椅子や床の上に全部で20人ばかりの男女が腰を下ろしている。今日来ていないメンバーに加えて、当日は都築が店の従業員まで駆り出してくれるそうだから、実際にはもっと多くの人数でダンスをすることになる。
崇太は手近なカウンターの座席に腰かけた。
「いらっしゃい、ソウタさん」
カウンターから従業員のジェイコブが崇太に声をかけた。ジェイコブは堂々たる体躯の南国系の男で、数年前から都築の店で働いている。ほかにも従業員は十数名いるが、頻繁に客と接する機会のある言わば店の顔がジェイコブだった。元より店内にはハイビスカス柄のタペストリーや素朴な木彫りの像などが飾られており、異国趣味を感じさせる内装だったのが、ジェイコブが来たことでよりそれらしくなったと言える。
「加藤と田淵が喧嘩してるって?」
ジェイコブに促されて酒を注文しながら崇太が言った。ジェイコブは肩をすくめ、「ノーコメント」の仕草をして見せた。そこへ板張りの床を音高く踏み締めながら田淵がやって来た。
「聞いたよ。俺に指輪を渡したいそうだな」
崇太がからかうように言った。田淵はあからさまにバツの悪そうな顔をしている。
「お前をここに呼び出すことになるとは思わなかった。ごめん、大事な時期だろうに」
「いや、それはいい。元々俺が企画したことだからな」
田淵は崇太のそばまで来てカウンターにもたれ掛かった。チェックシャツにチノパンと言うラフな格好で、件の人材派遣会社で働いてきた帰りなのか、それともオフなのか崇太には見分けがつかない。もう飲み始めているらしく、眼鏡の奥で目が据わっていた。田淵はポツポツと事の経緯を述べ始める。
「都築が役割を決めたんだ。そしたら加藤がその……一番目立つ役になった。始めは俺もそれでいいと思ったんだが、いざ練習を始めると何となく違う気がしてきて……」
田淵はここでちらりと背後を覗った。
「……そもそもお前、そこまで加藤と仲良かったか?」
崇太はこの言葉に面食らった。これまで加藤との不仲を疑われるような出来事があっただろうか。また田淵から加藤への心証が途方もなく悪いらしいこともまた理解できないことだった。
「考えてみろ。アイツは高校も俺たちとは違うし、第一麻弥子のこともよく知らないだろう。なんでそんな奴に婚約指輪を渡させるんだ?」
「待て。加藤は何度もハンドボールの試合で麻弥子に会ってるし、俺たち二人との仲もいいよ。お前の勘違いだ」
崇太は周りの注目を集めないよう声を抑えて言った。田淵の言葉はひどい言い草だと思ったが、自分のことを思ってくれている相手にそう強くは言えない。
崇太は店の奥に目をやる。加藤は隅の方でダンサーの知人相手に談笑していた。あくまでこちらのことを気にしていないように見えたが、そういう振りをしているのかもしれない。
「ともかく」崇太は田淵の方に向き直った。「俺のことを思ってくれてるのなら、そういう考え方はやめろ」
「わかった。ただ、指輪を渡す役割が誰にふさわしいかは、一度よく考えてみてくれ」
田淵がむっつりと言った。そこへ二人の共通の友人である広前がやって来て声をかけた。崇太の来た用件を知ってか知らずか、広前が朗らかに世間話を始めると、気持ちのやり場がないらしい田淵は店の奥へと去っていった。
そのうちに他の面子も崇太のそばに集まって来たが、これはひょっとすると田淵と崇太が話し終えるのを待っていたのかもしれなかった。知人が入れ代わり立ち代わり彼の元を訪れ、麻弥子のことや、独身の身でなければとても口にできないような下世話な話をこれが最後と存分に語り合った。そうするうちに渦中の加藤も談笑に加わった。
「ちょっとした行き違いなんだ」加藤は今回の件について、自らの見解を自信に満ちた口調で語った。「田淵はああ言ってるけど、実際にはみんながやりたがってたから、事前に誰が指輪を渡すか話し合って決めた。ただ、田淵は忙しくてその日の集まりに参加できなかったから、その事で文句を言ってるんだと思う」
スリーピースのスーツに身を包んだ加藤は、スポーツ刈りの似合う爽やかな顔に渋面を浮かべて見せる。男女問わずよく好かれる性質で、崇太は彼が人の陰口を叩くところを見たことがなかった。
「なあ、今さらわかり切ったことを聞くようで申し訳ないんだけど」
酒を口元に運びながら崇太が言う。
「なんだ」
「みんな俺に指輪を渡す役割をそんなに大事に思ってるのか?」
加藤はそれはそうだという顔をした。崇太は納得した。何はともあれこれまでそういう前提で話してきたのだから、今さら実はそうではなかったと言われても戸惑うだけだ。
「冗談でなく、俺がお前に指輪を渡す役割で良かったと思ってる。自分で気づいていないかもしれないが、色々な人から感謝されてるんだよ、お前は」
加藤がそう言うのを聞いて崇太が周囲を見渡すと、皆自分にこやかな表情を向けていた。それでは本当に釈然としていないのは自分一人だけなのか。特別何か恩を着せるような事をした覚えはないし、内心照れくさいやら驚くやらだが、それならその事を受け入れてもいいか――崇太はそんな風に感じ始めていた。
小一時間も雑談に興じていると、都築が店の中に戻って来た。崇太の隣へ来てそれとなく首尾を訊ねてくる。
「田淵と話したか」
「話したけどあんまり上手くいかなかった。酔ってるみたいだ」
「そうか」
崇太の前で都築は思案気に視線をさまよわせ、そのうち近くの壁にかかった木彫りの面に目を止めた。酒瓶やグラスに混じってカウンター内のラックに立てかけられたそれは一見すると地味な工芸品なのだが、せせら笑うような独特の表情と言い、赤味を帯びた木目といい、奇妙に人目を惹くところがある。崇太は田淵が隣に来た際も仮面のある方を見ていたことを思い出した。
結局都築は田淵について話をそこで打ち切った。じきダンスのリハーサルを始めるので、崇太にその模様を見ていかないかと言う。崇太は都築らのことを信頼しているから、当日の楽しみにとっておきたい、と言ってそれを断った。
帰り支度を始めた崇太は、カウンターにジェイコブの姿が見当たらないことに気が付いた。先ほど自分が木彫りの面に気が付いたのも、カウンターに立つジェイコブが姿を消したかららしい。おかげで代金を誰に払えばいいかわからず困っていると、加藤が後で払っておくというので、押し問答の末に任せることに決めた。それから帰る前に便所を借りていこうと思い、ホールの隅の扉から廊下へ出ると何やらすぐそこでガサゴソと動き回る音がしている。
廊下には窓があり、物音はそのすぐ外から聞こえてきていた。始め崇太は野良猫か大きめの虫でもいるのだろうと思っていたが、何かにぶつかる音とともに「こんちきしょう」という耳慣れない悪態が聞かれるにあたって外にいるのがジェイコブだとわかった。
「ジェイコブ、どうかしたのか?」
窓を開けて声をかけると、冷たい風が崇太の顔を打った。廊下の窓は店の裏手に面していて、すぐ前がコンクリートで舗装された土手になっている。店があるのは土手の下で、見ればジェイコブは重たげな風呂敷包みを背負って階段を上っていた。こちらに気づいた様子がないので崇太が再び声をかけると、ジェイコブは窓の方を振り向いた。
「ソウタさん、私辞めます」
「辞めるってまたなんで」
崇太には寝耳に水だった。驚いて大きな声を出した崇太に、ジェイコブは身ぶりで声量を抑えるよう促した。暗闇の中に二つの目が爛々と光って見える。
「家族が倒れたんです」
「だったら都築に言って休みをとるのが筋なんじゃないか」
「休み取れないです。私たちみんなツヅキさんに借金のカタで働かされてます。辞められないし休めません」
崇太は唖然として二の句が継げない。にわかには信じがたい話だった。
「貴方も逃げてください」ジェイコブは続けて言った。巨漢がまるで子供のように怯えきっている。「ツヅキさん本当は恐ろしい人です。貴方に指輪を渡す役割をカトウさんに取られたことも、実は全然よく思っていない。逃げられなくなってからでは遅いんです」
ここでもまた指輪か。いったい何がどうなっているんだ――崇太の中で再び疑問が首をもたげた。吹きすさぶ春の風が、窓の桟をガタガタと鳴らしている。先ほど外にいたときと比べて明らかに風が勢いを増していた。まるで走行中の電車の車窓から身を乗り出して話しているかのようだ。風が強まってくるにしたがってジェイコブも大声を出し始めた。
「ソウタさん、ごめんなさい。家族が倒れたっていうのは実はウソです。私このままだと良くないことが起きるから逃げるつもりです。タブチさんとツヅキさん以外の指輪を渡したがってた人も、皆平気じゃないです。本当は従業員もツヅキさんにずっと怒ってます。まともなところじゃない。ソウタさんも逃げてください」
その言葉を最後にジェイコブは闇の中へ駆け出し、あっという間に見えなくなってしまった。後はただ風の音が響くばかりで、崇太がジェイコブの名を大声で呼んでも、返事が聞こえてくることはなかった。
崇太は窓辺を離れて、今見たものについて考えを巡らせた。ジェイコブの言っていたことが本当なら、都築はジェイコブを奴隷同然の身分で働かせていたことになる。確かに大学を中退して以降の都築には得体の知れないところがあり、この店の開業資金をどのように手に入れたのかは崇太ら友人たちにとっても定かでない。良からぬ商売に手を出しているのではないかというもっぱらの噂だった。
崇太が気持ちを整理しきれないままホールに戻ると、知人たちは三々五々店内の所定の位置に散ってリハーサルを始める合図を待っていた。大多数は座席についているが、加藤を始め麻弥子と面識のある者たちは本番では顔を隠しながらウェイターやシェフに扮することになる。彼らは壁の前で並んで出番を待っていた。都築は店内が一望できるところにいて、満足げに周囲を見渡している。どうやらジェイコブの不在にはまだ気づいていないらしい。
崇太はその場を動こうとしない彼らの合間を縫って出口に向かった。出ていく際誰もいないカウンターに木彫りの面が立てかけられているのが目に入った。ジェイコブの置き土産だった。外へ出て後ろ手にドアを閉めると、ドア越しに「始め」という都築の声が聞こえた。壁の内側で大勢の人間が動き回るバタバタというくぐもった音があたりに木霊した。
一月後、崇太と麻弥子は都築の店へ続くテラスを歩いていた。あれ以来崇太は都築の店に近づいていない。都築を始めとした友人たちには任せる、信頼していると言っておきながら、実際は足を踏み入れるのを避けていた。だから崇太はジェイコブがいなくなった後のことを知らないし、まして今日誰が婚約指輪を渡してくるのかなど知る由もない。数日前都築に指輪を引き渡して、後はそれきりだ。
道に吹き寄せる潮風は春の温かさを帯びていた。ジェイコブのいなくなった晩とは比べるべくもない。晴れ渡った空の下を海鳥が飛び交う、穏やかな週末だった。
「ねえ、見てあれ」
隣にいる麻弥子が、上空を弧を描いて飛ぶトンビを見て声を上げた。都築の店に行かなくなって以来、崇太の帰りが早くなったことを麻弥子は喜んだ。今の崇太はなぜ麻弥子のことを後回しにしてフラッシュモブに精を出すことができたのだろう、と自分で自分を訝しく思っている。麻弥子を二の次にするなど本末転倒だった。
「あ、なんだろあれ。人が集まってるよ」
麻弥子が前方を指さした。崇太がそちらに目をやると、道幅の半分ほどが非常線で封鎖されていた。線の内外に厳めしい顔の警察官が佇んでいる。空の青が暗く凝ったような紺色の制服姿だった。麻弥子もじき物々しい雰囲気に気づいて、二人ともどちらが先に言い出すでもなく非常線の張られた側から離れて歩いた。周囲をカモメやトンビが落ち着きなく飛び回っていた。
数分も歩くと二人は都築の店に辿り着いた。店に入るとき崇太は強いて表情を引き締めた。後ろめたい思いがするのは何も麻弥子に対してだけでなく、中にいる都築たちに対してもそうだった。
「いらっしゃいませ。何名様ですか?」
浅黒い顔をした従業員が二人を出迎えた。フロアの中央にある卓に座るように促された後で、麻弥子は男に「ジェイコブは?」と聞いた。男はちょっと困ったような顔をして、「彼はやめました」とだけ言って去っていった。
席に着いた崇太はさりげなく周囲を見回した。麻弥子の背中側の席には広前と加藤が仲間に引き入れたダンサーの女が座ってどうでもいいような話をしている。それを見ているうちに崇太の気分は段々と不安から好奇心に傾き始め、もっと大っぴらに周りに誰がいるのか見てみたい気持ちに駆られた。
「都築のやつはいないのかな」
崇太はそう言って座席の上で上半身をひねり、カウンターの方に目線をやった。見覚えのある顔ぶれが視界の端にちらりと見えたほか、カウンターに先程の浅黒い顔の男が立っているのが見えた。背後のラックに飾られていたはずの木彫りの面はなくなっていた。
「ご注文お決まりでしょうか」
聞き覚えのある声に崇太が席に向き直ると、コンタクトレンズと付け髭で変装した田淵が席の前に立っていた。麻弥子に対してほとんど目と鼻の先と言ってもよく、いくら顔を隠しているとは言え近寄りすぎだと崇太は内心肝を冷やした。
「タラと明太子のパスタを二つ」崇太は平静を装いながら、予め仲間との間で決めてあったメニューを頼んだ。厨房にいる従業員たちもフラッシュモブに参加する以上、ここではあまり凝った料理を頼めない。注文した後で、崇太は先ほどの一件を田淵が自分が周囲を見すぎていたのを咄嗟にフォローしてくれていたように思い始めた。改めて身が引き締まる思いだった。
海産物をふんだんに使ったパスタが席に供されると、崇太と麻弥子は黙々と料理を口に運んだ。ダンス開始の合図は、実のところ崇太の判断に委ねられている。本人としてはいつまでも周囲で他人のフリを続けている仲間のためにもなるべく早くするつもりでいたが、いざとなるとふんぎりがつきかねた。麻弥子が料理を食べ終えてから合図をすべきか、プロポーズの後は酒を頼もうかなどと、そんなことばかり思い浮かぶのだった。
そこへ出し抜けに崇太の携帯が鳴った。ポケットから出して表示を見るとそこに加藤の名前があった。さてはいつまでも合図を先のばしする自分に痺れを切らしたか。崇太は麻弥子に断りをいれて通話に応じた。
「加藤はこれなくなった」電話の相手は言った。「けど大丈夫だ。時間がないからすぐ始めてくれ」
返事に窮している崇太をよそに通話が切れた。目前で麻弥子が見ている手前動揺を顔に出すわけにはいかず、崇太は強いて落ち着き払った態度で「そうか。わかった。ありがとう」と言って携帯をしまった。それから一度息を深く吸って吐き、対面に座る相手の目を見て「今日は麻弥子に伝えたいことがあるんだ」と言った。
それが合図だった。
それまで小さな音でフォークソングを流していた店内の放送が、奔放なドラムのリードするビッグバンドジャズにとって代わった。始めに広前とダンサーの女が席を立った。二人は滑るように隣の広い空間へ移動し、手を取りあってその場で回り始めた。驚いた麻弥子が背後を振り返るとその間に仲間たちが一斉に立ち上がり、音楽に合わせて板張りの床を踏み鳴らし始めた。足音はホールの壁や天井に幾重に反射し、圧倒せんばかりの轟音となって二人を圧し包んだ。
「ワン、ツー、スリー、フォー!」
広前がカウントを怒鳴り、最後に女の手を離した。するとその場にいた全員が大きな円となって回りだし、その一人一人が一糸乱れぬ動きで振り付けを実行をした。崇太からすれば見知った顔が、思い思いに着飾った衣装で目の前を通り過ぎていく。曲と同期したダンスの完成度の高さに崇太は舌を巻いた。上から見れば彼らはまるで複雑な模様を描く万華鏡のように見えたことだろう。
カウンターからは次々と店の従業員が現れた。いずれも浅黒い肌のポリネシア人種で、首からハイビスカスのレイをかけている。彼らは輪の内側に潜り込み、ハカダンスじみた踊りを披露して一時完全にその場の主役となった。輪の外周をひらひらと舞い踊り、腕にかけたバケットの中からそこら中に造花の花びらを振り撒いている者もいた。
絶え間ない動きが不意に鎮まり、皆が手拍子で複雑なリズムを刻み始めた。同時に円陣を割って崇太と麻弥子の前へ躍り出たのは田淵だ。彼は現れるなり床に手をついて頭を下げ、脚を大きく開いて一周二周と大きく振り回した。崇太はこの瞬間まで田淵にブレイクダンスの覚えがあるとは知らなかった。隣を見ると麻弥子もすっかりこの場を楽しむ心構えになっていて、はしゃいだ表情で周囲の人間と一緒になって手を叩いていた。
便所へ続くドアから木彫りの面で顔を隠したレインコート姿の人物が現れ、手に持った刃渡りの長いナイフで近くにいた宮永の首を切りつけた。宮永が倒れる際わずかに上げた吐血交じりの悲鳴を鳴り響く手拍子とジャズの音が覆い隠した。仮面の人物は首から上を返り血で真っ赤に染め、目に狂気じみた光を湛えながら踊りの輪に加わった。
輪の中心では田淵のソロパートが終わり、ダンス全体のクライマックスが近づいていた。崇太は皆の尽力に感激し、一時やる気を失いかけていた自分のことを恥じていた。自分の思い付きが多くの人を巻き込んでいくのを見るにつれ、当初自分が持っていたコントロールを失い、やりたいことから遠く離れていってしまったように感じた。だがそれは事実ではなかった。始めから崇太が主導権を握る必要すらなかったのだ。なぜなら力を貸してくれている皆が、心の底から崇太のためを思ってくれているのだから。
崇太は隣にいる麻弥子に目をやった。この場にいる全員が自分たちのことを祝福してくれている。今ならきっと臆することなく結婚を申し込むことができるだろう。二人の前に田淵が気取った仕草で歩み寄り、柔和な笑みを浮かべて銀のトレーを差し出した。トレーの上で指輪に嵌ったダイヤがキラリと輝いた。
突然周囲の人垣が割れ、両腕をぶらぶらと頭の上で振り回す奇怪な動作と共に仮面の人物が現れた。身につけたコートはひだのついた襟から裾まで、ぐっしょりと垂れ落ちる血に塗れている。すぐそばにいた従業員たちは泡を食ってその場を飛びのいた。何かのサプライズだと思ったのか、ホールの離れたところにいるダンサーたちはそれでも皆踊り続けていた。
「誰だおまえは?」
異変に気付いた者のうち、米原が田淵と仮面の人物の間に割って入ろうとした。仮面の人物は相変わらず腕を振り回す動作をやめようとせず、体をくるりと半転させた拍子に米原の二の腕に切り込んだ。米原は驚愕の表情を浮かべて、後ろにこてんと尻もちをついた。隣にいた田淵も事態が飲み込めず、呆然としているところに仮面の人物が近づいてきて正面から切り付けた。刃は胴体を斜めに裂き、痛みに呻きながら膝から崩折れた田淵の前で仮面の人物は一回転して獲物の首を掻き切った。
田淵の手からずるりと落ちたトレーが床に落ちて跳ね回り、その音で皆闖入者の存在に気が付いた。その場にいた者の大部分は逃げ出したが、軽快なBGMが止むことはなく、従業員の中には何かに憑かれたように躍り続けるものもいた。田淵の首の傷から流れ出た血はテラテラと鈍く輝きながら床を滑り、崇太と麻弥子が座っているテーブルの下まで流れ着いた。崇太が跳ねるように立ち上がり、麻弥子を庇おうと前へ出た。
「お前は誰だ?」
崇太は仮面の人物に訊ねた。体つきだけを見れば、その正体は都築とも鈴木とも、はたまたジェイコブだとも思えた。仮面の人物が絶えず舞っている奇妙な踊りのせいで、崇太には相手の上背を見極めることすら困難だった。
「お前は一体誰なんだ?」
仮面の人物は崇太の問いかけに答えない。無言のまま足を一歩踏み出し、おこりのようにその身を震わせる。両腕を降ろすと、ナイフを床の上に投げ出した。そして崇太の顔を真っ直ぐ見据え、燃え上がるように激しく踊り始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
