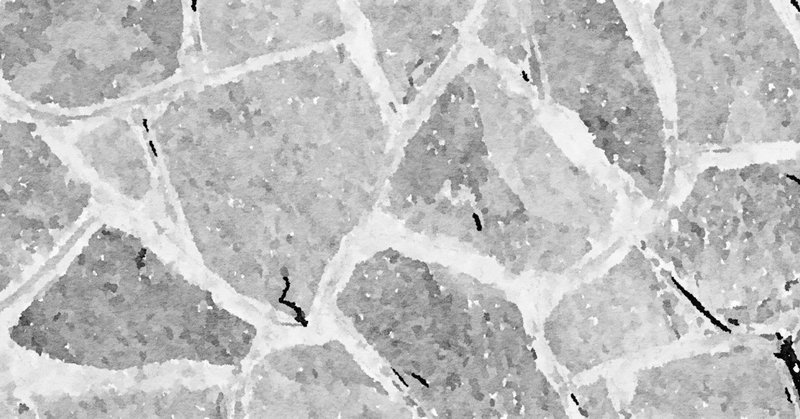
夢のあいだの満ち引きに
眠りに落ちる直前に、例えようのない浮遊感を味わうことがある。現実の世界を抜け出す瞬間は、ジェットコースターが頂点から駆け降りる数秒に似ている。下るにつれて、思考回路がじょじょに動きを止めていく。
ああ、また「あれ」だ、落ちる、落ちる……感覚に身をまかせれば、いつも引き潮の早さで意識を持っていかれる。昨日の夜もその前も、変わることのない真夜中の海。内なる海は今晩も、生あたたかい眠りへと僕をいざなうはずだった。
足の裏に全体重がかかっている。ということは、立っている。僕は自室のベッドに寝そべっていたはずで、つまり、これは夢だ。視界は暗く何も見えない。周囲は静まりかえっている。
ああ、今夜はぐっすりと、朝まで眠りたかったのに。目覚めて仕切り直すには、いったいどうすればいいんだろう。疲れたわけではないけれど、何も考えずにすむ時間をただむさぼりたい気分だった。
残念ながら、両目はぴくりとも動かなかった。子どもみたいにこすっても、こめかみを指でおさえても、目頭を刺激してみたって動く予感はない。
まぶたの裏の暗闇に、不安が大きくなってくる。体の芯が少しずつ冷えて熱を失っていく。ままならない夢にため息でもつこうかと口を開いたそのとき、不意に「カシャリ」と音が響いた。
注意が聴覚にシフトする。嘘のように「音」が聞こえだす。
水が流れている。誰かが、歩いている。
ザ、ザ、ザ、ザ、と大勢の人間が足音を鳴らす。リズムにわずかのずれもない、そして曲もない完璧なマーチ。左から右へ。左から右へ。黙々と続く行進が、繰りかえし打ち寄せる波のように背後から耳へと迫る。
延々と続くステップの中、再び「カシャリ」とかすかな機械音が届いた。斜め上から落ちてきた音に顔を上げると、あっさりと視界が開く。どこかで見たことがある、けれど行った記憶のない景色が広がっている。どっしりとした石造りの通路と、ゆるやかに流れる水路が見渡す限りに絡みあい、遠くにゆったりと回る風車が見えた。
空は厚い雲がかかったような白さで、少しも暗くはない。陽の光を感じず、電灯も見当たらないのに明るいなんて、夢らしい奇妙な場所だ。僕のまぶたをこじ開けた音の主は、そのただなかに佇んでいた。なぜか、片手に携帯電話を構えながら。
「驚いたなぁ」
その人物はゆかいそうに笑った。突然知らない景色に囲まれ、見知らぬ誰かが現れ、携帯電話のカメラでとはいえ写真を撮られたわけだから、驚いたのはこちらのほうだ。見下ろしてくる表情は遠目でよく見えない。石畳を踏みしめる硬い音が相変わらずにぎやかで、少しだけ声を張った。
「ここはどこ? きみは誰だい? それにどうして写真を撮った?」
「色つきはみんなせっかちなのか? そんないっぺんに質問するな」
「確かにちょっと混乱してる。……色つきって?」
「あんたみたいなやつのことさ」
その答え方に、あらためて彼の姿を眺めてみる。言われてみれば、ただただ白い。髪にも肌にも、身につけている衣服にも、まったく彩度が感じられない。携帯電話をもてあそびつつ、肩をすくめる仕草が見えた。
「ここはどこ? だったか。俺はここしか知らないし、ここがどこかは分からない」
「え?」
「ここしか知らない。道の上をそいつらが歩き続けて、脇では水が流れていて、時々誰かが落ちてきて、時々誰かがいなくなる、そんなここしか知らないんだ」
「僕は、落ちてきたのかい」
「ああ、落ちてきたな」
こくりとうなずくジェスチャーに、あの浮遊感を思い出す。深い眠りに落ちる前、時たま味わう落下の感触。僕は文字通り、この世界に落ちてしまったのだ。
「じゃあ、この人たちも落ちてきたの?」
二人して、ザ、ザ、ザ、と淀みなく進む人々の群れに視線をうつす。
「そいつらも、まぁそうだな。落ちてきたかと思えばひたすら歩いて、いつの間にかまたどっかに消えてくんだ。もしかしたら、ずっと同じやつが落ちてきてんじゃないかと思うよ」
そうだとしたらぞっとする。少なくとも僕は初めてだ。
既に頭の中からは、これは夢だという認識がすっぽりと抜け落ちていた。
通路を道なりに進む。アーチ状の石橋で二本、三本の水路を越え、特大の石を組み上げた階段をのぼる。着地したらしい場所からぐるりと回りこむ経路をたどって、ようやく彼の傍らに立つことができた。
見渡せば、自分の体や服以外はすべてモノトーンの色彩を帯びている。だからだろうか、道がひどく歩きにくい。一つひとつの物が見分けづらい。
「少しは落ち着いたか?」
「まあね」
この人は僕のような、この世界にとって闖入者である「色つき」のうろたえる姿をしばしば見かけるのだろう。わざわざ尋ねなくても、色のない空気がそう告げていた。それなら驚きを取りつくろう必要もない。
白い肌。白い髪。彫像のような顔立ち。ショーウインドウでしか見かけない造形と陰影だけで構成された彼は、話し相手に不自由していたらしい。あの隊列への参加者は、どんなに声を荒らげたところで何の反応も示さないという。僕にとっては味気なくも目新しい景色を前に、他愛もない会話を交わした。
ここの水はきれいだね。冷たくて気持ちいいぞ。あの風車で循環させてるの。根元に水車があるから行ってみるか。いいね、見てみたい。
先導する彼を追って風車へと向かった。清流をさかのぼる道すがら、パシャリとあがった水音に振り返ると、きらきらと飛沫が輝いている。石橋の陰に目を凝らすと、かすかだけれどたくさんの魚影。
物言わぬ行列に背を向けて歩みを進めるにつれ、規則正しい足音が少しずつ薄れていく。通る者の少ない通路では、敷き詰めた石の隙間からたくましく草が伸びていた。構わずさくさく踏み歩く。足元から青い香りが立ちのぼった。
「あの人たち、なぜ歩き続けるんだろう」
「さあ。聞いても答えてくれないからな。理由があるにしても」
「あるにしても?」
「歩かされてるだけ、って感じがするな。……さあ、もうすぐだぞ」
また写真でも撮るのだろうか、彼はポケットにしまっていた携帯電話を取り出していじり始める。モノクロームに慣れた視覚にとって、オレンジ色の鮮やかさはまぶしすぎた。
真っ白な手のひらとは不釣り合いな携帯電話に、まっさらなシーツに浮いた一点のシミを連想する。勝手に気まずさを感じて、彼がただひとつ持っていた色彩に目を背けた。
高台に張りめぐらされた石の階段を登りきると、いつのまにか風車が目の前に迫っていた。ぶうん、とうなるような音を立てて羽根車が回転している。説明のとおり、真下では水車が勢いよく水をかき混ぜていた。額ににじんだ汗をすすぐと、濡れた頬や手をなでる柔らかい風が気持ちいい。
ここは世界の頂点のようで、四方八方を見渡せた。石造りの回廊が規則正しく縦横に広がり、澄みきった水路と絡みあう。崩れかけの太鼓橋に朽ちた巨木。そこから繁茂する雑草。誰もいない泉。誰も来ない広場。前へ前へと進み続ける無言の行列、すべてを照らす不可思議な白い光。
ぼうっと景色を眺めていると、三度目のシャッター音が鳴る。間抜けな表情を撮られたに違いなくて、眉を思い切りしかめて見せた。彼の口元に笑いの影がおどる。
「ここで人を撮るのは初めてなんだ。いいだろ」
嬉しそうにまた「カシャリ」と鳴らすものだから、好きにしなよ、と笑った。
ひとしきり風景を堪能した頃には、汗もそよ風に引いていた。何か花でも植えられたらいいのに、とつまらないことを思う。目が無彩色に慣れたとはいえ、僕はフルカラーの美しさを知っていた。
飽きてしまったのだ、明度しかないこの景色に。
生きて活動するものが、あまり存在しえないこの場所に。
「ねえ、色つきって結局、どういうもののことなんだい」
「だからあんたみたいな人のことさ」
「うーん、全然分からないよ」
「でもなあ、たまに落ちてくるってことしか知らないし」
「じゃあ、それで撮った写真、見せてくれないかな」
「これかあ? まあ、いいけどさ」
先ほどまで、高台からの撮影に忙しかった携帯電話。中には僕が写った画像も入っているはずで、この世界における自分のありようを確認できる気がした。自分の目ほど信用ならないものはないけれど、頼るべきものがもう、そのくらいしか残っていない。
あの行列に呼びかけたところで、立ち止まってもらえるだろうとは考えられなかった。同じように落ちてきたらしい人たちだけど、どうも僕とは違う世界から落ちてきたように思えてならない。
ほらよ、という声とともに携帯電話を受け取る。白い、冷たい指が一瞬だけ僕の手をかすめた。ビビッドオレンジは血色のよい僕の手のひらにしっくりとはまる。いや、色のせいじゃない。僕はこれを知っている、と直感が告げた。
……この携帯電話は、僕のものだ。
「このケータイ、どうしてきみが?」
「俺がお前だから、じゃないのか?」
どういう意味? と口にする前に、激しい吐き気が僕を襲った。口の中が酸っぱい。頭の先から血が下がり、心臓が音を立てて空回りしだす。暗闇だったはずのまぶたの裏はただ白く、景色の残像すら映し出さない。
つのる焦燥感に考えはまとまらず、彼の言葉だけがぐるぐると回った。俺がお前だから、じゃないのか? オレガオマエダカラ、ジャナイノカ?
嘔吐をこらえて薄目を開けると、オレンジ色を握り締めた自分の手が目に入る。そうだ、ケータイだ。彼が撮った写真を見なくては。おぼつかない指先で画面を開くと、やはり見慣れた待受が僕を迎えた。
データフォルダを開きながら、指まで真っ青だなあと動かない頭で思う。けれど違和感に気がついた。血の気が引いたからといって、ここまで白くなるだろうか?
指先の色がみるみるうちに薄れていく。重いまぶたをぎゅっと閉じ、もう一度開けて確かめる。そんなわずかの間にも、指先の色は抜けてしまった。白と肌色の境目が、ゆっくりと手首へ移っていく。
まさかと思い彼を見る。彼もまた、自分の両手を凝視していた。爪先や手の甲に血色が見える。脈打つ血管の青さが認められた。彼をふちどる陰影も、かすかに鮮やかさを増している。
ようやく写真を探し当て、僕は愕然とした。落ちてきたときの僕を見下ろすアングルが二枚、油断していて撮られた横顔一枚、正面を向いて話しながらの一枚の、どれにも僕の色彩はなかった。ハーフパンツの迷彩柄も、Tシャツに入った黄色いラインも、もちろん体の肌色からも、彩度が失われている。
自分の体を見下ろせば、もう膝から下くらいしか元の色をとどめてはいない。もうろうとした意識の中、そもそも僕に色なんてあっただろうかという思いがよぎる。貧血のせいだけでなく冷たくなった僕の両手を、温かな手が包みこむのを感じた。
「まあ、しばらく休んどけ」
「ああ、そうだね。……行っておいで」
真夜中に響く着信音に目が覚める。瞬く蛍光色が天井を照らした。枕元に置いた携帯電話を手に取ると、待受画面に「非通知着信」の文字。暗さに慣れた目にはまぶしすぎ、目を背けて鳴り止むのを待った。
こんな時間にかけてくるなんてロクなやつじゃない。そう思うものの、電源ボタンは押さなかった。自分から切ることはしない。後で面倒くさくなっても困るからだ。
輝くことをやめない画面。主張する無粋な五文字。握る手のひらが温まり、ケータイが熱を帯びた。
鳴り続ける機械音が呼び起こしたのはたぶん、夢に見たイメージ。石畳の通路を横切る無言の隊列。水車によって循環する清流、堂々とたたずむ風車。魚が跳びはねた後の波紋、そよぐ草の音、色彩のない光。人と談笑した後に残る、独特の疲労感。生々しい残像の断片。
不意にこの通話が誰からなのか、気にかかった。出なければならないという圧迫感を感じて、急いで通話ボタンを押す。
もしもし。
十数秒の静寂が、左の鼓膜にしみわたる。
ようやく耳にできたのは、通話が途絶えたことを知らせる冷たい電子音だった。
夢のあいだの満ち引きに 終
再掲元:pixiv 2010/10/25
読んでくださり、ありがとうございます。 スキ♡やご感想はとても励みになります、よろしければぜひお願いします。
