
「企画は魔法みたいなところがある」 30歳までに福祉領域で勝負したいという思いから生まれたヘラルボニーの創業者・松田崇弥さんの企て方。
「へラルボニー、ヘラルボニー」
まるで呪文のような、魔法のことばのような不思議な響き。意味を知らなくても、なぜか耳に残る。
コピーライター・作詞家の阿部広太郎さんが主宰する連続講座「企画でメシを食っていく2022」。11月19日に開催された第6回「文化の企画」のゲスト講師は、株式会社へラルボニー代表取締役社長の松田崇弥(たかや)さん。
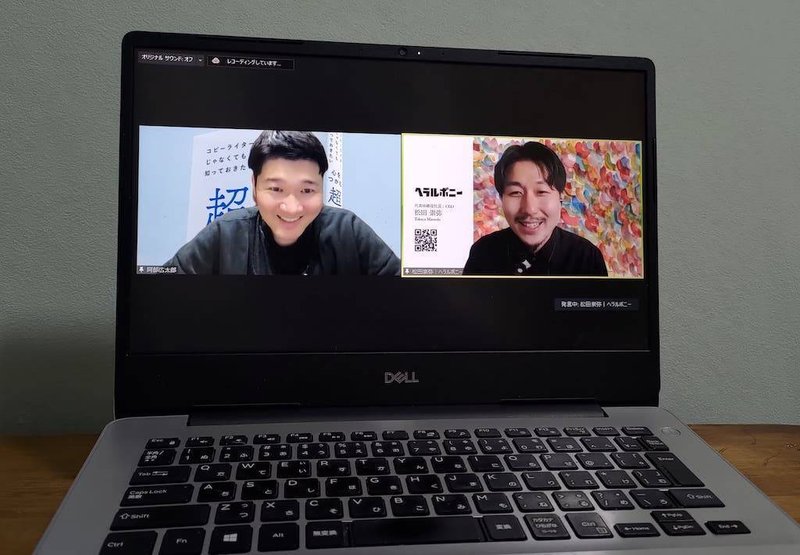
オンラインで行われた講義の様子を、「企画メシ2021」企画生、野口祥子がレポートします。
30歳までに福祉領域で勝負したい
ヘラルボニーは、2018年に設立した岩手発の企業。崇弥さんが社長、双子の兄・文登(ふみと)さんが副社長を務め、福祉を起点に新たな文化やライフスタイルをつくりだすための活動をしている。
崇弥さんと文登さんには、4つ年上の兄・翔太さんがいる。重度の知的障害を伴う自閉症と診断されている翔太さんの存在が、二人の運命を決定づけた。時折、謎の言葉を発する翔太さん。その声が、環境音のように聞こえていた子どものころ。でも、一歩外に出ると、さっと人が離れていく。周囲の反応に、悔しい思いもしてきたという崇弥さん。
小学校のころから知的障害に関わる仕事に就きたいと考え、30歳になるまでに福祉領域で勝負しようと思っていました。ただそれが何なのかは、まだ分かっていませんでした。
「知的障害のイメージを変える」という決意を胸に二人が起業したのは、27歳の時だった。
ネットが世界の扉を開いた
岩手県で生まれ育った崇弥さんと文登さん。高校では寮生活を送りながら、卓球に打ち込む。練習に明け暮れる日々の中で、ネットだけが世の中とつながる手段。ジャパニーズヒップホップやグラフィティが好きで、当時流行っていたSNSのサークルを二人で立ち上げると、会員数は約3万人にも上った。
田舎でよくやってたなと思いますね。この時の経験が、今に生きている。インターネットの力を感じました。
やがて崇弥さんの中に、デザイナーになりたいという思いが芽生える。しかし、身近に絵を学べる場所もない。そんな時、東京から移住してきたイラストレーターがいると知り、手紙を届け、デッサンを教えてもらうようになった。東京の美大を目指していたが、放送作家で脚本家の小山薫堂さんが学科長(当時) を務めていると知り、東北芸術工科大学の企画構想学科へ進学する。
小山さんや教授たちを見て、こんなに仕事を楽しんでいる大人がいるんだと知ったのは大きな衝撃でした。大学では、自発性やアイデアの突飛性などが評価される環境。パラダイムシフトですごく楽しかった。
テレビ局でADのアルバイトをし、企画やメディアに触れた学生時代。インターンを経て小山さんの会社に就職することになった時、迷いはなかった。一方で、「30歳までに福祉という領域で起業したい」という夢は変わらず胸にあった。
「おまえ、こんなに静かなやつだったっけ?」-もがき続けた若手のころ
憧れの東京での仕事は、決して順風満帆なものではなかった。一言も発言できずに終わる会議が続く。
大学の時、自分はちょっとできると思っていたんですよね。会議の後、薫堂さんに「お前、こんなに静かなやつだったっけ」と言われて。最初の1、2年はすごく辛かった。
このままでは先輩たちの企画書のベースを作る「企画書マシーン」で終わってしまう。そう思った崇弥さんは、社外の評価を社内に「逆輸入」しようと考え、多くの広告賞に挑戦し、受賞を果たす。「風向きが変わる瞬間というのがありますよね」と企画メシ主宰の阿部さんもうなずく。大きな転機となる出来事だった。
情熱を捧げられるものにフルコミットしたい
仕事が面白くなってくる一方で、自分の中で決めた「30歳までに起業する」というリミットは近づいてくる。社会人2年目の夏、崇弥さんは母と一緒に岩手県花巻市にある「るんびにい美術館」を訪れた。知的障害など障害のある作者の作品が多く展示され、「ボーダレス・アート」と称し、「障害者」と「健常者」などの区別を越えた多様な表現物を紹介する美術館だ。
めっちゃカッコいいなと衝撃を受けて。素晴らしい作品を素晴らしいまま出していく、すごくシンプルなことをやれたらいいなと漠然と思いました。
これを機に、崇弥さんと文登さん、学生時代の友人の4人で立ち上げたのが「MUKU」というブランド。クオリティはどうあれ、まずアウトプットする。早朝や深夜、休日を活動に充て、ネクタイを作るところから始めた。

「若手でやりたい気持ちはあるのに、チャンスが回ってこない時期は、どう動くか次第で実はものすごくチャンスでもある」と阿部さん。「列に並んで待ち続けるのか、自分の意志で一歩を踏み出すのか」。阿部さんの著書『待っていても、はじまらない。 潔く前に進め』の一節を思い出した。
踏み出した一歩は、新たな道につながっていく。2018年の4月。年度はじめの会議で、全社員が今期の個人目標を発表する中、崇弥さんは「本気でやりたいことに時間を使おう」と退職を決意する。
リスクはあっても今、情熱を捧げられるものにフルコミットしてみたいと思いました。
やるからには兄弟で。文登さんと一緒に起業する、というのは心の中で決まっていた。
言葉を育て、言葉に育てられていく
崇弥さんが大学生の時、兄の翔太さんの自由帳に「ヘラルボニー」という言葉を見つける。それも何十冊も。母に聞いても、兄に聞いても意味は分からない。この言葉が会社の名前になる。その後ブランド名も「ヘラルボニー」に統一した。
「言葉をみんなで育てていくことで、愛着が芽生え、自分ごとになる」と阿部さんも名づけの力を感じてきたと言う。崇弥さんの前職の先輩で、コピーライターの株式会社パーク代表取締役・田村大輔さんが会社のコピーを考えてくれた。崇弥さん・文登さんと議論を重ね、「福祉実験ユニット」という会社を定義づける言葉も生まれた。
福祉業界の外の認知を獲得しにいく会社だと狙いを明確にし、実験という言葉を使うことで、どんどん新規事業にチャレンジし、失敗も含めて可視化する。多様な団体や人と組んで、福祉領域を拡張していくと宣言したいと思いました。
「福祉実験ユニット ヘラルボニー」は、「異彩を、放て。」という力強いミッションのもと、歩み始める。
「障害者」に代わる新しい言葉を考える
後半は課題について。事前に崇弥さんから企画生(「企画メシ」の受講生)に向けて、課題が出された。
「障害者」という言葉に代わる、次の表記や呼称を考えてください。そして、それを実現していくための企画やアクションも考えてください。
2020年2月、ヘラルボニーは東京・霞ヶ関にある弁護士会館敷地内の掲示スペースに、意見広告を出した。
この国のいちばんの障害は「障害者」という言葉だ。
「障害者という表記は必ず変わると思うし、早く変わっていくべき呼称や表現だと確信は持っている」と崇弥さんは言う。企画生からは、新しい価値への挑戦、あえて言葉にしない選択、苦心の跡が見える企画が揃った。
「そういう発想があるんだ!」と崇弥さんをうならせたのは、熊澤さんの「手帳保持者」という企画。熊澤さんは、「障害者」と「健常者」という対義語のような言葉に壁を感じた経験から、「あまり感情をのせた言葉でない方が使いやすいし、自分の解釈で考えてもらえるのでは」と、障害者手帳にフォーカスした言葉を提案した。
障害は個性だとか可能性だとか、誰しもが光るものがあるという価値観を作っていくことに、アレルギーがある方も多い。足が速い人もいれば遅い人もいるように、障害のある人の中でもさまざまな人がいる中で、「手帳保持者」という言葉は「そうだよね」と感じられる。
「枠組みで捉えるところから一歩ずらしていて面白い」と崇弥さんも驚くアイデアだった。
続いて企画生との対話の時間が設けられた。企画の背景を伝える人、「ヘラルボニー」への熱い思いを語る人、自分自身の体験について話す人。崇弥さんが一人一人の言葉に耳を傾け、共感した部分や懸念点も丁寧に伝える姿が印象的だった。
「言葉が変わることには意味がないという方もいると思うが、障害者という言葉は変わっていってほしい」と崇弥さん。「呼び方を変えることで、今すぐ何かが起きるわけではないかもしれないが、数年先の空気作りに大事だと思うので、未来に向けて考えつづけたい」と阿部さんも言う。
私は編集やライティングの仕事をしてきたが、「障害」という言葉を用いる時、その強い印象に戸惑うことがあった。普段の生活で何気なく使ってしまう言葉は多いが、考えて言葉を選び、使いたいと思う。
阿部さんが書いた「異彩者」という呼び方も話題に上った。崇弥さん自身、会社で「障害者」という表記を「異彩者」に統一することを考えていたという。ヘラルボニーが「異彩者」という言葉を使い始めた時、また新たな未来が生まれる予感がした。
企画に振れ幅を作ることで、求心力が生まれる
「企画は魔法みたいなところがある」と崇弥さんは言う。企画や事業にどれだけ振れ幅を作れるかを意識する。高い値段で勝負し、あえてラグジュアリーブランドの隣に出店する。振れ幅を大きく作ることによって、共感され、求心力が生まれる。
今年の「企画メシ」が掲げる思いは、『自分の道を言葉でつくるための連続講座』。最後に崇弥さんが大事にしていることを聞いた。
崇弥さんと文登さんと母の「松田家」というLINEがある。そこには「びっくりするくらいヘラルボニーの追っかけ」だという母の言葉が、毎日シャワーのようにたまっていく。
一番身近な人、一番共感してほしい人が、応援してくれていると感じられる大切なものです。兄や母が喜ぶような事業をやっていきたいという強い意志が「軸」にある。本当に大切な人がどう思うのかという「軸」が大事だと思いました。
「どんな環境にいるか、誰を大事にして、どんな人と一緒にいるか。そこで聞こえてくる言葉や音が、自分を導いてくれると思う」という阿部さんの言葉で、熱い2時間が終わった。
言葉の力と自分の「軸」
私が「ヘラルボニー」の名を知ったのは、2019年。「企画メシ」のイベント「企画祭」のゲストだったコピーライターの澤田智洋さんのnoteの記事を読み、私の住む町で開かれたイベントにコラボ作品が登場した。その活動に共感する友人がシェアする情報も目にしていた。
ルーシー・モード・モンゴメリの小説『赤毛のアン』の中に、「バラはどんな名前でも同じように匂うというが、ほかの名前だったら、あんなにすてきだとは思えない」とアンが語る場面がある。
「福祉実験ユニット ヘラルボニー」「異彩を、放て。」という言葉があるから、たどり着けた場所があり、切り拓かれる未来があるのではないか、と思った。
「30歳までに勝負しよう」と思い定め、27歳の時に起業した松田さん兄弟。私が28歳の時、友人と出かけた海外旅行で出会った年上の日本人女性から、「何か始めるなら30歳までに」と聞いたことを思い出した。その時一緒だった友人は、30歳になる前に転職し上京した。私がライターへの一歩を踏み出したのも30歳の年だった。その後も転機は何度も訪れたが、30歳を前にした時期は特別なものだった。改めて自分の「軸」について考えてみたくなった。
いよいよ「企画メシ2022」は次回で最終回。2022企画生のみなさんにとって、素晴らしい時間となりますように。
▼「ヘラルボニー」の歩みが綴られた松田文登さん・崇弥さんの著書
▼note「ヘラルボニーマガジン」
▼「企画メシ」のレポートはこちら
▼「企画メシ2022」企画生たちが綴るnote
執筆:野口祥子 (企画メシ2021)
お読みいただきありがとうございます! 2023企画生が気づきや学びを発信中の noteマガジンもぜひご覧ください🍙 https://note.com/kotaroa/m/m4404fe17fb59 いつか企画で会いましょう〜!
