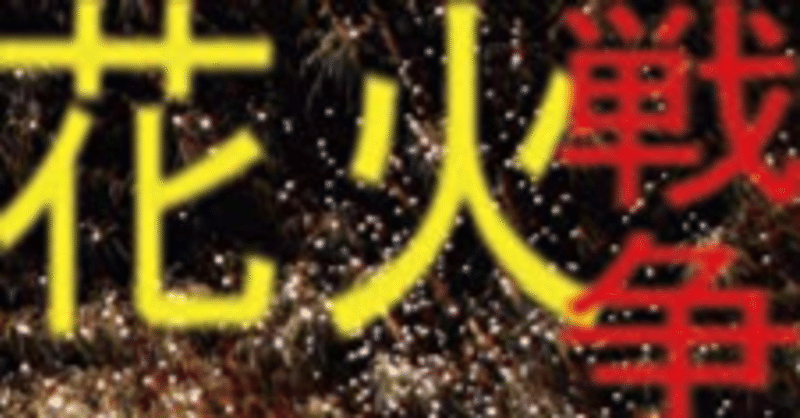
作者が本気で自分の小説を解説してみた4「戦争と娼婦・花火」
こちらは八幡謙介が2021年に発表した解説本です。
作品の位置付け
僕は2012年頃から小説を書き始め、2015年にギターのフォーム研究を開始するため断筆をしました。ですので、2012年~2015年頭ぐらいまでが僕の第1期作品群となります。本作「戦争と娼婦・花火」は2014年10月刊行なので、第1期の集大成的作品となります。そこらへんを念頭に解説をお読みいただければ幸いです。
女性を書く
女性を書くことは男性小説家の永遠の課題といえます。僕自身は「セームセーム・バット・ディッファレン」で〈反転描写〉というスタイルを編み出したものの(詳しくは「作者が自分の―」シリーズ3作目を参照)、所詮ワンシーンをなんとか描くための場当たり的なテクニックであり、女性主人公そのものを書くことにはまだまだ不慣れであることを実感していました。そこで、女性を主人公にした短編を書こうと決意したと記憶しています。ですから、本作の主人公はいずれも女性です。
なお、本作では〈反転描写〉(本シリーズ3作目参照)は使っていません。
戦争と娼婦 創作ノート
主題
フランスの作家マルグリット・ユルスナールの「とどめの一撃」に、
【一般には善より悪のほうが多いから、戦争の雰囲気は結局このうえなく不愉快なものだ。だからといって、まれではあっても戦争にもふくまれうる偉大さの瞬間にたいして不当であってはなるまい。】
という一文があり、僕はこれを読んだときに衝撃を受けました。ちょっと文章が難しいのですが、要約すると、『戦争は悪い、でもそんな中にも素晴らしいことはたまにあるから、それはそれでちゃんと評価しようよ』ということです。戦争を知らない世代からすると戦争というものは1から10まで悪いものだと想像してしまいますが、よく考えればその中でも腹をかかえて笑い転げることもあれば、感動すること、幸せを感じることなども少しはあるはずです。戦争というものは、そうした当たり前の出来事すら覆い隠してしまうほど巨大な悪であるということにも改めて驚かされます。
実は僕はこのユルスナールの文章を体感したことがあります。それは911に端を発するイラク戦争です。これらは全て僕がアメリカに滞在していたときに起こりました。ある国が戦争へと突き進む様子をその国の内部から体感したという意味で、僕はいわは戦争体験者なのです。では戦時中のアメリカはどうだったかというと、確かにどこか暗く、また不穏な空気感が漂っていましたが、日常は日常で特別変わったことはありませんでした。そういった体験から右の一文に深く頷いたのでした。
では【戦争にも含まれうる偉大さ】とは、もっと言えば、戦争の偉大さとは何でしょう? 勇敢さ、自己犠牲、信じる心、協力、家族の絆……いろいろ思いつきますが、小説としてはありきたりで面白くない。もっとひねくれた、それでいて説得力のある【戦争の偉大さ】とは?……僕がたどりついた主題は〈小さな悪の救済〉です。
平時なら耐えられないような悪(犯罪というよりは、もっと根源的な悪)が、戦争というより巨大な悪のおかげで帳消しにされたり、なぜか生き生きと輝いて見える……そんな悪とは何か? と考えたとき、僕が思いついたのは娼婦の存在でした。
ただでさえ悲惨な戦争中に売春をして生きていくなんてまるで生き地獄だ! そんな状況の女性が生き生きとしているなんておかしい! と思う人もいるかもしれません。しかし、平時であれば自分が娼婦に身を落としたのは自己責任と考えがちですが、戦時であれば「私がこんな風に身を持ち崩したのは全て戦争のせい!」と逆に開き直ることもできます。だから逆に戦時下の娼婦の方が生き生きとし、平時の娼婦の方が心身を病んでしまうのではないか僕は想像しました。これ自体が正しいがどうかというより、そういう想像の元に書いた小説ということです。
設定
まず、戦時下であることが大前提となります。ではどことどこの国のいつの時代の戦争にするか? 正直めんどくさかったのでヨーロッパ風の架空の国同士にし、時代はなんとなく第二次世界大戦頃としました。この辺で手を抜いているところがまだまだ甘いですね……。ただ、戦時下の娼婦という点でいろいろややこしい問題があるので、改めて読むとこれで正解だった気もします。
主人公
主人公は元売春婦の老婆です。戦時下は自ら娼婦として客を取り、戦後はいわゆるやり手婆として手腕を振るいながら、仲間の娼婦たちを見てきました。人生の酸いも甘いも全てを経験し、達観した強いおばあちゃんというイメージです。
文体
独白体ですが、口語っぽいところがポイントです。イメージは江戸川乱歩の短編あたりです。これも特に深い意味はありませんが、主人公の老婆の回想がメインなので、なんとなくこうなりました。
では本文を解説していきましょう。
戦争と娼婦 解説
□
一般には善より悪のほうが多いから、戦争の雰囲気は結局このうえなく不愉快なものだ。だからといって、まれではあっても戦争にもふくまれうる偉大さの瞬間にたいして不当であってはなるまい。
――マルグリット・ユルスナール『とどめの一撃』(岩波文庫・岩崎力訳)
□
こちらは序文となります。意味は既に説明したので省きます。純文学作品にはこうした、他作品からの引用から始まるものが多く、僕も一度やってみたかったというのもあります。ただ、単にコピペ的に引用するのではなく、きちんと主題に絡めてというのが自分なりの条件でした。その点はクリアできていると思います。
□
あぁ、またあんたかい。しつっこいね、ほんと、ブン屋ってのはさ。で、今度は何さ? 前話しただろ? ところで後ろにいるのは……まあ! 可愛らしいお嬢さんじゃないかい。いいさ、とにかく入って座んな、えぇ、また何かくれるのかい? 悪いね、前いただいたお菓子はご近所さんと分けたからすぐになくなっちゃったのよ……。えぇ、なに? 男には話し辛いこともあるからって、それであんたこんな娘っ子を連れてきのかい! ば……馬鹿いっちゃ、ヒッヒッッ! この歳で恥じらいもへちまもあるもんですか! 全く馬鹿だよ男ってのは、ねえお嬢さん。ほうらさっさと座んな、今お茶淹れるからね。
□
いきなり誰かの話口調で始まります。
【しつっこいね、ほんと、ブン屋ってのはさ】とあるので、新聞記者が何度も取材に来ているとわかります。また、はっきりとは述べていませんが、口調や内容からこの主人公が老婆であることも文体からわかると思います。
冒頭、説明せずにこれだけの情報をさらっと提示できているという点で、自分の文章力が上がっていることが理解できて、ちょっと安心しました。
□
さあ、準備はいいのかい、その薄っぺらいのでパチパチやって記録するんだろ? 全く、便利な世の中になったもんだね、え、あんたもできるのかい、お嬢ちゃん。それは凄いね! 手に職持つってのは大事だよ、でないとあたしみたいに一生男のアレ臭い部屋で過ごすことになっちまうからね、ヒッ!
――で、前はどれだけ話したのかね? 歳をとっちまうと物忘れが激しくて嫌んなっちまうよ。昔、お隣と戦争してたのはあんたたちも知ってるだろ? で、国境の町から一般人が避難させられて、軍人が住むようになった、その軍人さんたち相手に身を売って商売をしてたってわけさ。何? 強制……難しい言葉使わないでおくれ、まあ、時代が時代だからね、無理矢理連れてこられたのもいたみたいだよ。それでも仕事があって給料が入ってね、食べ物に困らないってのは魅力だったわね。ああそう、男にも困らないからね! ヒヒッ! おや、お嬢ちゃん、赤くなったね。可愛いもんだね、女は若いうちが花だよ、まったく……。
□
【その薄っぺらいのでパチパチやって記録するんだろ?】
ノートパソコンをイメージしています。老婆の世代にはなかったんでしょう。これは時代を描写しているというよりは、老婆と記者の年代の差を演出するための描写です。ノートパソコンが普及したのは何年だから……という考証は野暮ってもんです……。
【お隣と戦争してた】とあるので、内陸国であると分かります。ここでなんとなくヨーロッパを匂わせています。
【強制……難しい言葉使わないでおくれ】
記者としては女性が強制連行されて売春を強要していたという筋書きを描いているのですが、老婆は「あの時代に給料がもらえて食べ物に困らないというのは魅力的だった」と回想します。当事者の老婆と記者に認識のズレが生じています。記者が一切しゃべらないので、そういったズレが逆にリアルに表現されているような気がします。
赤くなった若い女性記者をからかう老婆、ちょっと下品な性格であることを示唆しています。
□
え、何? 大きい声で言っとくれ、あたしゃもう耳が悪くてね、え? 当時はどんな気持ちだったかって? そりゃあ最初のうちは嫌で嫌で仕方なかったわよ、中には乱暴なのもいたし、中年の将校なんかにはもうヘトヘトにさせられたりもしたわ、もちろんそれだけじゃなくて、ミサイルが飛んできたり銃声が近くで聞こえたりするとみんなで固まってぶるぶる奮えたりしたものよ。そうして、何年だったかしらね、ほらあんたその画面で調べられるんでしょ? 海の向こうの大国がお隣の味方をするって発表した年だよ、あれから一気に国境の雰囲気は変わったね。悲壮感……ていうのかね、ナニしてるときの感じが違うんだよ、男はね。無心で抱かれているとね、だいたいこの人があとどれくらいで戦地に行くか、どんな危険な部隊に送り込まれるのかがぼんやりと分かるんだよ。特に危険なところにいかされる兵隊さんはね、妙に優しくなるのさ……。不思議なもんさね、まだ比較的平和なときは威張りくさっていたくせに、死が近づいた途端あたしの胸に顔を埋めて泣くんだよ……。兵隊相手に体を売るのと、お国のために体を売るの、どっちが嫌だろうね。
□
【ほらあんたその画面で調べられるんでしょ?】
これはインターネットのことです。ただ、はっきりそう言うと気になる読者も出てくると思うので、ぼかしました。この老婆自身もインターネットを知らないからというのもありますが。
【海の向こうの大国がお隣の味方をするって発表した年だよ】
老婆は政治に興味がないので国の名前すら覚えていません。戦争政治の複雑な利害関係も理解できていないんでしょう。ただ、相手をする男性については微細な肌感覚で覚えています。普段威張りくさっているのに、死が近づくと優しくなるというのは、たぶんそうなるんじゃないかという僕の想像です。
【兵隊相手に体を売るのと、お国のために体を売るの、どっちが嫌だろうね】
フランス文学風の警句です。どこか自分のしていた仕事に対するプライドも見え隠れします。作家の家田荘子さんが援助交際する未成年の子を取材したとき、彼女たちは自分を買ったおじさんたちを心の中で見下しながら相手をしていたと気づかされたそうです。自分の行為を正当化するために心の防衛システムがそうさせるのか、あるいはもっと業の深い何かなのか……。いずれにせよ、この老婆が単なる可愛そうな被害者ではなさそうだと気づいてもらえればOKです。
(試し読み終了)
花火 創作ノート
主題
本作の主題は〈生のための死〉です。主人公は幼少期から生きている実感が持てず、心の奥底で死に憧れています。しかし、高校生になると生を充実させるための論理を獲得します。そして、自分の生を最大限に咲かせるために死を選ぶという不条理を遂行します。改めて考えると、武士の論理に似ている気がします。
また、本作には〈虚無〉〈皮肉〉〈承認欲求〉といった僕の他の作品にも観られる主題が散見されます。個人的には、本作で僕の文学的な主題がはじめて浮き彫りになってきたと感じています。そういった意味で重要な作品です。
文体
本作は文体に凝りました。まず主人公が思春期の女の子ということで【ぁたし】とネット風の一人称としました。また、少女の一人称独白体なので、ややポエムに近い感じを出そうと苦心しました。
そもそも僕は、良い文章には必ず詩が備わっていると考えます。ただ、ギター教則本やブログで文章を鍛えてきた僕にはそれが苦手です。だからこの作品を借りて一度詩を含んだ文体というものを模索しようと考えました。ただ休筆直前の作品なので後に引き継ぎ、発展させることは2021年現在まだできていませんが。
本作では積極的に執筆当時(2014年)のネットの流行を登場させました。2021年の今となっては完全にピントがずれていますが、それはそれでいいと思っています。
キーワード
本作にはいくつかのキーワードが出てきます。それらを先に説明しておきます。
季節
冬=死、終わり
夏=生、命
春=新しい絶望、生への予感
数の論理
主人公は幼少期に既に「人は本来〝いっこ〟である」と悟ります。その寂しさを紛らわすために友達を増やしていくのですが、余計に自分が〝いっこ〟であることを実感し、虚無感を覚えます。
そんな中、運動会で活躍した島田君が自分の心の中に住み始めたことで、〝にこ〟になれる特別な人種がいることを知ります。
主人公が高校に進学すると、人は〝にこ〟どころか、何百、何千にもなれること、しかも、それが本人の生を充実させることを知ります。これが新たな主人公の数の論理となるのですが、それを実行するためには他人より秀でた特別な何かが必要となります。自分がそれを持っていないことに主人公はあせります。
数の論理=アイデンティティの問題と捉えてもいいでしょう。
花火 解説
□
また、あの季節がくる。
ぁたしの生命を、無理矢理内側から芽吹かせようとする、あの暑苦しい季節。
余計なお世話だと思う。ぁたしの命を、この〝いっこ〟の生命を無駄に感じさせないでほしい。
冬は好きだ。
命がじわじわと削られていく感じがする。硬く、冷たくなった末端からゆっくりと死が侵食してくる感じ。ぁたしの〝いっこ〟が犯されてゆく感じ。ぞくぞくする。
将来は寒い国で暮らしたい。フィンランド、ロシア、アラスカ……最悪北海道でもいい。
冷たく凍えた体に毎日死を、終わりの瞬間を感じながら過ごせたら、生も少しは生き生きするのかもしれない。
□
いきなり死への憧れを夢想する少女。ネクロフィリア的な独白は、もしかしたら昔呼んでいたポーの影響かもしれません。ここで既に〝いっこ〟という概念が出てきます。
【あの暑苦しい季節】とは、夏のことです。夏が彼女の【〝いっこ〟の生命を無駄に感じさせ】るとはどういうことでしょうか?
まず〝いっこ〟とは、誰の中にも自分がいないことです。厳密には両親や友達は彼女のことを大事に思っているはずなのですが、本人はまだそれを実感できていないのでしょう(結局最後までできません)。
夏はそうした自分の本性、あるいは生命そのものを暴かれるようで、主人公は【余計なお世話】と感じています。
この時点でだいたい主題や世界観、主人公の紹介などが完了しています。特に説明的でもないし、我ながら上手くなっているなと感じます。明らかに「セームセーム・バット・ディッファレン」の頃より上達してますね。
□
夏よりも、春の方が嫌いだ。
春はぁたしが〝いっこ〟なことを証明する。
中学に入って、私立に入学した幼なじみとは別れた。まだ携帯も持たせてもらえなかったから、自然と会わなくなった。あんなに仲良く、まるで姉妹みたいね、いっこの命がふたつに別れたみたいねっていつも言われていたのに、佳奈が遠くに行って、会えないのが当たり前になって、それでもぁたしがまだのうのうと生きていることを不思議に思った。
なんでぁたしは死なないのだろう? この世の終わりみたいに泣き叫んだりしないのだろう?
それは、ぁたしと佳奈の、それぞれが〝いっこ〟だから。最初からなんとなくわかってたから。
ぁたしの精神、肉体。いろんなものがくっついてぁたしになっているんだと思っていた。パパやママ、佳奈、おばあちゃん、親戚のおじさんおばさん……。どれかひとつでもなくなればぁたしは死んじゃう、そう思っていた。けどなんとなく、そうじゃないことも知っていた。
人が本来〝いっこ〟なら、なんで他の人と関わろうとするのだろう? ぁたしの中には誰もいないし、誰の中にもぁたしはいられないのに。
誰と出会い別れても、人はこの〝いっこ〟の生命を生き続ける。ぁたしの生命の居場所は、このちいさな体にしかない。そして終わればゼロ、無になる。昔の偉いお坊さんが『人は本来何ももっていない』って言ってたって、パパから聞いた。何も持ってないところから生まれて、何もないところに帰るって。そこがゴールなら、いっそ真っ先に到達した方が勝ち組じゃね? 先週電車に飛び込んだ高校生は、そんな思いでホームからダイブしたのだろうか?
バカみたい。
1が0になることに何の意味があるんだろう?
□
主人公は、幼なじみの佳奈ちゃんと一心同体だと感じていました。相手の中に自分がいて、自分の中にも相手がいる。しかし、離ればなれになったとき、意外なほどダメージがなく、それぞれが〝いっこ〟なんだと悟ります。さら、自分という存在は家族や親戚とも可分であると諦観します。ここから
【人が本来〝いっこ〟なら、なんで他の人と関わろうとするのだろう? ぁたしの中には誰もいないし、誰の中にもぁたしはいられないのに。】
という主人公の虚無が生まれました。
【人は本来何ももっていない】とは「本来無一物」という有名な禅語です。主人公のパパは禅にでもかぶれているのでしょう。そうした【何もない】という思想にかぶれて自殺した高校生を、主人公は冷笑します。彼女にとっては死すら意味がないと感じています。たぶん、この冷笑自体は思春期の強がりで、冬=死への憧れの方が彼女の本質なんだと思います。本能的な死への憧れを冬というメタファーで隠しているのでしょう。
後に主人公は自殺するのですが、そのとき彼女は死にある種の希望を見いだしています。実は主人公を死から守っていたのは彼女の虚無そのものでした。本作で僕は〈虚無が人を救う〉ということをはじめて知りました。といっても、再読するまでは自分でもわかっていませんでしたが。
□
じぶんが〝いっこ〟だって気づいてから、ぁたしは数を信仰した。数は力だ。数は人を信用させる圧倒的な説得力を持つ。そして、数は保険だ。JCやJKがやたらと友達作りに勤しむのを、ぁたしは始めて理解した。
ぁたしは誰にでも愛想を振りまき、すぐ友達ぶった。JCの社会はまだ政治性がすくないから、敵でないことを示せば仲間には入れてくれる。ぁたしの廻りにはすぐに数が揃った。お弁当、トイレ、秘密の手紙、ノートの貸し借り、下校、もちろん休日も、ぁたしの廻りには必ず誰かがいた。数さえ揃えていれば安心できる。もう、佳奈と離れ離れになったときのような〝いっこ〟の寂しさを感じなくてすむ。だから親友は作らなかった。
ママは『お友達がいっぱいできてよかったね』と目尻に皺をよせて喜んだ。単純な女。
そういえば、女は子供を宿せば〝にこ〟になれる。ぁたしの体も、もうそれが可能となってはいる。妊婦さんがいつ見ても晴れやかな顔をしているのは、自分が〝にこ〟であることの充足感ではないか? だとしたら、出産の痛みは、〝いっこ〟に戻ることへの心の痛みだ。
□
主人公は数の論理に傾倒します。それは夢を叶えるためやキラキラしたスクールライフを送るためではなく、自分が〝いっこ〟であることを忘れるためです。
【JCの社会はまだ政治性がすくないから、敵でないことを示せば仲間には入れてくれる】
これはちょっと甘いかなと今では思います。女の子は中学生、もっと言えば小学生ぐらいからもう立派に政治性を持って動いています。とにかく、主人公はやたらと友達を増やし、いつでも複数のグループに属していられるよう気を付けて生活しています。
妊婦のくだりは今読み返すとちょっと陳腐でピントがずれている気がします。〝いっこ〟〝にこ〟とは精神の話なので、物理的に別の命を自分の体に宿すのはまた違う気がします。あと、妊婦さんが【いつ見ても晴れやかな顔をしている】というのもちょっとおかしいですね。まあ主人公にはそう見えていたのかもしれませんが。
□
ちょうど中2(w)それも春先から夏ぐらいにかけて、皆こぞってSNSをやりだす。鈍感な子たちもそろそろ自分が〝いっこ〟だと気づきはじめて、あわててそれを反証しようとする。リーダー格の男子は、ツイッターのフォロワーが1000人越えたらしい。いつもおしゃれな女子は、FB(フェイスブツク)に服装をUPする度「いいね」が100件以上つくとか。そうやって数の論理で〝いっこ〟であることを巧妙に隠そうとする。バカバカしい。フォロワーなんて簡単なことで離れていくのに。そのたび、自分の生の無価値さが露呈されていくだけ。
ネットは確かに、上手くやれば圧倒的な数を誇れる。そのかわり、変動も激しい。フォロワーやフレンドは、ちょっとでも自分の気にいらないことがあると去ってしまう。その点、リアルは手堅い。ネットよりも現実の方が拘束が強いから、リア友の数は、少ないながらもそう簡単には変動しない。よっぽど下手を打たなければ大丈夫だ。
そんなぁたしを、担任は三者面談で『人付き合いのきちんとできる子』だと褒めた。ママはいつもより濃いファンデーションにヒビを入れて破顔した。なんで自分のことのように喜んでいるんだろう? あんたはぁたしじゃないのに。
□
【ちょうど中2(w)】
周りの中二病的な行動と、実際の中二という学年に主人公がひとりで受けていることを表現しています。別に大した意味はありませんが。
SNSに関しては2021年からすると完全に時代遅れな感がありますね。ただ、執筆時(2014年)はこんな感じでした。インスタグラムは日本語版が2014年2月に開設されたので、執筆当時はまだまだ無名だったと記憶しています。今ではおじさん用SNSと化したフェイスブックも、当時は女の子もこぞって使っていたと思います。ツイッターも今ほど殺伐とはしていませんでしたね……。
【鈍感な子たちもそろそろ自分が〝いっこ〟だと気づきはじめて】
自分が他人に影響を与えられる存在ではないということに気づきはじめるという意味。自分よりもそれに遅れて気づき、あせってネットに走る同級生を主人公はやはり冷笑します。この時点で主人公はまだリアルの方が堅実だと考えています(後に考えを改めますが)。2014年頃は、まだネットの〝数〟がそこまで力があるとは考えられていませんでした。ネットが現実を変えたというのも、政情不安定な外国の話でした。TV番組がユーチューブやツイッター、ブログをネタに構成するというのも、今ほど多くはなかったと思います。
□
JC3になって、事件が起きた。
夏の生命の疲れを引きずりながら登校した2学期の運動会、最終種目のリレーで、前から憧れていた男の子が、5人をぶちぬいて逆転優勝した。
運動場はまるで競馬とか競輪のように、拍手、歓声、怒号。だけどぁたしの耳には何も聞こえてこなかった。真っ白い空間を、彼――島田君がスロウモーションで、必死に走っている。おおきく口を開け、肩をやや左右に振りながら、真っ直ぐに見据えたゴールに向かって走り抜けていくその姿は、一瞬の出来事のはずなのに、運動会が終わってもいつまでも、いつまでも目に焼き付いて消えなかった。まるで彼が〝にこ〟になったみたいに……。
どうして?
廊下ですれ違う島田君は、毎回違う様子なのに、ぁたしの中の彼はいつも同じで、風が本格的に冷たくなり、気の早い子がもうマフラーをつけて登校しはじめても、やっぱり半袖にハーパンの体操着で、ゴールを目指している。
□
ここで物語の転換点となる重要な出来事が起こります。主人公は運動会のリレーで大活躍をした島田君に恋をします。哲学的な妄想をするわりには、足が速い子を好きになるという子供っぽいところが可愛いです。重要なのは、島田君は主人公にとって〝にこ〟になったということです。普段の島田君と、ゴールを目指して走っている島田君。それまでの〝いっこ〟だった島田君は主人公にとっては特に気になる存在でもなかったはずです。しかし、〝にこ〟になった島田君は主人公の心にいつまでも残り続けます。この仕組みが主人公を大きく変えていきます。
□
また死と寄り添う季節がやってきたのに、ぁたしはほっと一息つくどころか、余計に不安が募ってきた。まるで夏みたいに、じっとしていても、じんわりと体が熱を帯びてきて、吐く息がねっとりと甘い。
ぁたしの中に、彼が生きている。
いや、生きているというのはたぶん違う。だって、島田君はいつまでも変わらないから。
そっちの方がいい。
ホンモノの島田君がいなくなっても、いちばんカッコイイときの彼だけぁたしの中に残ってくれるから。
だけどそもそも、どうしてあのときの彼は分裂してぁたしの中に残ったんだろう。人は自分の中にしか生きられないはずなのに……。5人抜きしたから? いや違う。ぁたしのグループの子たちは、運動会の直後は島田君のことをカッコイイと言っていたけど、すぐに話題にも出なくなった。みんなの中には、たぶんもう、島田君はいない。それでもぁたしの中には、あのときの彼が生き続けている。
たぶん、ぁたしの問題なんだろう。
これが恋なのかと思い、首を捻った。好きなのかどうかもまだ分からない。
□
主人公は島田君に恋をしていますが、まだ自分でもよく分かっていません。
【まるで夏みたいに、じっとしていても、じんわりと体が熱を帯びてきて、吐く息がねっとりと甘い】
この辺は上手く説明できませんが、強いて言えば主人公がそう感じているからそう書きました。論理で書いていないところが僕としては珍しいですが、こういう文体を目指した作品なので、それなりに成功していると思います。
どうやら〝にこ〟になった島田君に戸惑う主人公。ここは後に伏線となって回収されます。
(試し読み終了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
