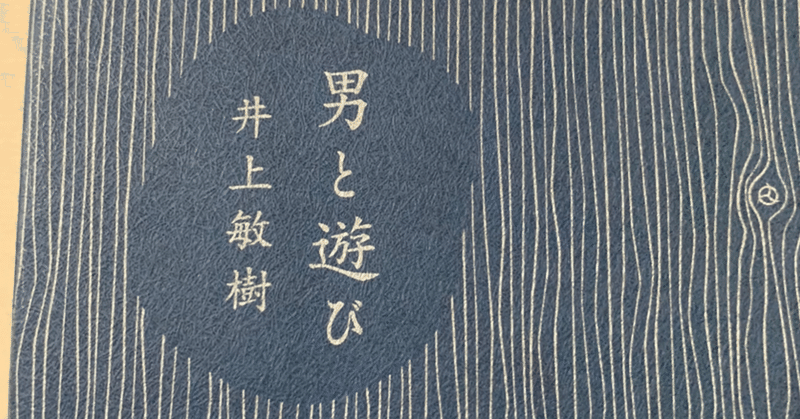
男と遊びを読んで。
『男と遊び』
井上敏樹の初のエッセイである。
これまで手掛けた作品でも、食べることでの自己表出や、コミュニケーションを描いてきた著者の世界観が凝縮された、贅沢な一冊だ。
各エピソードには一癖も二癖もある人物が登場する。例えば、謎かけをしてくるナス顔のギャルソン。笑い上戸のヤブ歯科医。そして、S(仮名)。この人物達は、その極端なキャラクターが際立つように、コミカルに書かれている。彼らがより極端になる流れは、著者本人がしっぺ返しを受けるフラグとなっている。
極端な描写が救済に向かう場合もある。
『男と食3』に出てくるお好み焼き屋のサッちゃんだ。サッちゃんは赤ん坊をおぶりながら、手際良く調理するのだが、客前にも関わらず、夫からDVを受ける。サッちゃんは泣きながらお好み焼きを焼き続けるが、案の定、客足は遠のき、店は潰れる。
『男と酒3』に、アル中の男が二人出てくる。
男達は酒をやり過ぎて、その目には感情が残っていない。もはや、酒以外の欲望を捨て去っているのだ。
著者は、その潔白さに美しさすら感じている。
だが、同時にこう語るのだ。
「死にながら美しいよりは生きながら汚れている方が人間らしい。」
この思考は、初稿の『男と遊び』を読むことで、より深く考えることが出来る。
「芸を磨くという事はなにかを獲得する事ではない。獲得する事で磨かれる芸ならそれはまだ初心者の段階である。捨てていく事で最後に残るものが芸を磨いてくれるものであり、また、芸そのものと言える。」
アル中の二人の男にも、何かがあったのかもしれない。だが、結果として、酒に相対するものは何も残らなかったのだ。
では、サッちゃんはどうか?
先程のエピソードには、続きがある。
著者の記憶の中で、数十年経った今でも、お好み焼きとサッちゃんが密接に結びついている。店の雰囲気こそ最悪の評価を与えたが、お好み焼き自体には、食通の著者が一定の評価が与えたのだ。
サッちゃんがお好み焼きを焼く理由は、家族にある。
サッちゃんにとって、夫は捨て去りたい対象かもしれない。しかし、サッちゃんは捨てることを選べない。
サッちゃんはお好み焼きも家族も諦めないのだ。
さて、本書の中で一風変わった『男とアレルギー』という回がある。
著者がそば屋に出かけると、昼間から酒を飲んでいる男を見つける。着流しが似合いそうな、粋な佇まいが描かれている。男は天抜きを摘んでいるのだが、衣は出汁に浸かり切っている。天ぷらに出汁をかけたのが、天抜きである。本来なら、蕎麦がのびるを避ける為に頼むものであって、出汁に浸かった天抜きというのは、矛盾した存在だ。
なぜ、天ぷらは出汁に沈まなければならなかったのか。それは男が女将を口説き続けているからだ。
女将は体良くあしらうが、男は口説き文句に季語を散らつかせる。手を替え、品を替え、女将に振られ続ける客という距離感を男は離さない。
出汁に浸かった天抜きが、見事にこの状況を表しているのだ。
最後に、間接的ではあるが、割烹のお椀の面白さを知ることが出来たので紹介しよう。
食の満足感において舌による味覚と同じくらい重要な、嚥下しての胃による認知、内臓感覚といわれるものがある。
『男と食21』より、いいお椀の定義は返り味だという。返り味とは、いったん胃袋に納まってから、ゆっくり脳に刺激がいって、再び口に戻ってくること。
一口目ではほとんど味がせず、お椀全てを口にした時にはじめて、うま味を感じるように仕上げるのだ。
近年、うま味の主成分のグルタミン酸の受容体は、口腔内のみならず、胃や小腸にも存在し、神経を通じて、脳に情報伝達を促す事が明らかになった。
しかも、驚くべきことに、20種類あるアミノ酸の中で、グルタミン酸のみが胃から脳への刺激を入れることが分かったのである。本稿に出てくる京都の大御所の料理人は、料理人はこの感覚をお客に啓蒙しなければならないと言う。そして、お客の意見に迷う料理人には、著者(脚本家)が教えてあげるべき、とのことだが、著者もお客側である。しかし、本書に散りばめられた言葉を手繰り、料理の素晴らしさを知ることが出来たのは、エッセイならではの体験ではないだろうか。著者の食への探究が、芸となり、読者の啓蒙に繋がったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
