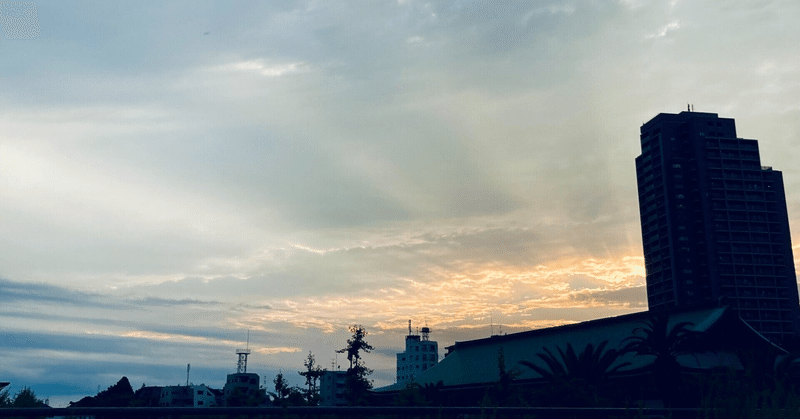
ハードだけどSDGsな働き方をしようじゃないか、という提案
初めに
こんにちは、kenmaro です。
普段はソフトウェアエンジニアとして
キータ、ツイッターに生息しています。
今回は、4年ほどエンジニアとしてスタートアップに関わるなかで、
いろいろな働きかたについて考えた結果、
考えるに至ったことを書いてみようと思います。
忙しい人のために
忙しい人のために簡単に内容をまとめると、タイトルにもある通り
SDGsで指針とされている持続可能な開発って、働き方(特にエンジニアの働き方)の指針としても大事だよね、ハードに楽しく働きつつ、持続可能に働こうじゃないの
ということです。
SDGsについて今一度おさらい
まずは、今一度SDGsについて非常に簡単にはなりますが振り返ってみます。
SDGsの基本概念としては、
いろんな立場(特にジェンダーや社会的に今まで差別を受けてきた人など)の人たちが活躍できる世界
環境に優しい世界
が基本指針です。(というと怒られそうです。もっとたくさんありますのでwikiをご覧ください。)
基本概念となっている持続可能性
このうち、環境に配慮した開発に関して、
次世代のことを考えた環境に配慮した開発を続けていく
ことが政府や企業の行動指針と定められています。
例えば脱炭素化などを通して製造業などのCO2の排出量を削減したり、
電気自動車を使って排気ガスをなるべく削減する、
環境にやさしい発電方法を推進しクリーンな電気を作るように推進する
というようなアクションにつながります。
現在効率がいいと考えられて今まで使い続けられてきた企業の取り組みなども、
今は効率が少し落ちても環境にやさしい手法を取り入れ、お金をかける
環境にやさしい手法の効率改善について研究費用を増資する
等のアクションが積極的にとられるようになっています。
地球環境を破壊することなく半永久的に経済活動を続けていけるよう、みんなで気を付けていきましょう、ということです。
私がスタートアップでエンジニアとして働き始めたのは3年以上前のことですが、その時から今までの経験の中で働き方について色々と考えた結果、
わりとこのSDGsと関連づけられるなと思っています。
働き方(特にエンジニアの働き方)についても、これって取り入れた方がいいじゃないか、と今回は思ったという話です。
それを説明するために、
その考えに至った環境について説明したいと思います。
エンジニア職の元来的オーバーワーク
エンジニアとして4年ほど働いてみて、
エンジニアはオーバーワークが起きやすい職種だなと思っています。
理由としては
仕事がいつでもどこでもできる
無限に勉強する内容がある
趣味と仕事が一緒になる可能性が高い
からです。
仕事がいつでもどこでもできる
エンジニア(特にソフトウェアエンジニアの話をしています)は、基本的にパソコンひとつとWi-Fi環境があればどこでも、いつでも仕事ができます。
また、基本的にはパソコンを触って何か作ったり、プログラミング自体が趣味だったりする人がエンジニアになっていることが多いでしょう。
結果として、家に帰ってからもずっとコードを眺めていたり、深夜に仕事をしたり、はたまた旅行先でも仕事をしたりしてしまう事はとても多い傾向のある職種だと思います。
無限に勉強する内容がある
どんな仕事でも結局知らないことを勉強していくことは大事ですが、
ソフトウェアエンジニアも御多分に洩れず、勉強量が多いです。
広く浅く知っているエンジニア
狭い範囲で深い知識のあるエンジニア
などいろいろなタイプを目指せると思いますが、どの道を選んだとしても学習する量は非常に多くなるかと思います。
趣味と仕事が一緒になる可能性が高い
趣味と仕事の境界がちょっと曖昧になることが多い
こともエンジニアあるあるだと思います。
仕事ではもちろん案件だったり、自社開発を行い、業務の半分くらいはコーディングを行う人が多いと思います。(もちろん比率は役割によって変わると思いますが)
そして、家に帰った後は自分の好きなお酒でも飲みながら(私は飲みながらコーディングするのに幸せを感じたりします、笑)、
仕事のコーディング業務を業務時間以外に行なっている人も多い気がします。その時に、普通に楽しいからやってます、みたいな人も多い印象です。とてもいいことだと思う一方で、今回はその働き方も一旦振り返って考えてみてはどうか、と思っています。
私がどう働いてきたか
私個人の一例とはなってしまいますが、自分がタイトルのような考えに至った働き方について例を挙げてみます。
スタートアップでのエンジニアの働き方(自分の一例)
私はもともとプログラミングを子どもの頃からやってきた人種ではないのですが、大学院くらいからPython を始めたことがきっかけにプログラミングが好きになり、スタートアップで働いている今まで上のような生活を基本的には続けてきました。
大学院ではあまり自分のやったことが評価されにくい環境に居て、そこに少しモヤモヤ感を持っていた私は、
スタートアップに飛び込み、自分のやったことがダイレクトに評価され、
自分の作ったものが製品となって誰かの持っている課題を解決しお金を生むような環境にのめり込みました。
そのような環境の中で、上の例で言うと私は特に仕事のコーディングを家でも無限にやってしまうような生活を3年以上続けていました。特にきついと思ったこともないですし、とても楽しかったので夢中でやっていました。
たまに発生するめちゃくちゃ頭が冴えてコーディングできる時間帯みたいなのに遭遇すると、エンジニアやっててよかったなあと思いつつドーパミンが出るのを感じながら作業したりしていました。
家でずっとやるのは疲れたりするので、カフェ(特にマックをとても頻繁に使わせていただいています)で作業をすることがとても多かったです。
そんなこんなで、仕事をしている時間というのは短い方ではなかったと思います。(もちろん他の業種の人や、同じエンジニアの人でも自分より時間を使っている人もいるのを沢山見ましたが。)
そんな働き方をリスペクトしています。
今でもリスペクトしていますが、ハードに働きつつ、今からお伝えすることについても考えながら働いていけばいいじゃないの、と今は思っています。
なぜエンジニアにもSGDsが必要なのか
持続可能性について考えるに至った「甘くない」現実
そんな中で、スタートアップに関わり始めてから4年目になり、
仕事に対するモチベーションは変わらないまでも、働き方に関してはいろいろと考え方が変わってきたように感じます。
これが、SGDsで使われている「持続可能性」
というワードにつながります。
スタートアップの成功には時間が必要
スタートアップにも色々あるとは思いますが、
私が関わっているところは以下のような特徴があります。
ディープテック領域にフォーカスしていて、技術的にはとても魅力はありそこに投資を受けている
マーケットが立ち上がりそうな黎明期領域であり、完全に見えてはいない
つまり、技術的には面白いもののマーケットを探している段階であり、いろいろな制約(例えば性能や法的な問題)などがあり、技術を実社会にアダプトするところに時間がかかるということです。
これから5年、10年のスパンの中ではとても注目されていく領域であると思いますが、2、3年でユニコーンになるような結果が出るのか?(この辺の領域をVCは一番好物としていると思いますが)
というところに関しては長期戦になることも考えられるなあと思っているのが正直なところです。
ここでの結論は、
どのスタートアップ(事業)であっても、一定期間は腰を据えて開発を行う必要がある
ということです。
この期間、見据えたゴールに向かって愚直にアウトプットを出し続ける「体と心の健康」が大事なのです。
例としてIPOに至った企業の話
例えば、2021年にマザーズ上場を果たした企業は94社ありますが(詳しくは下記のリンクを参照)、
マザーズ上場した企業は全体のIPOの7割を占めており、
IPO全体の企業の設立から上場までの期間は「18.8年」で、2011年の「21.9年」と比べて3.1年短縮しました。
もちろん、数年で上場するような企業もありそれらの企業はメディアなどにも取り上げられていたりしますが、平均を見ると10年とかは余裕でかかるわけです。
ゴールを目指すのはもちろんだが、道中は絶対楽しむべき
10年という時間は人生のうちでとても大きな時間なのはいうまでもありません。
新卒でその会社に入ったとしても、10年経つうちには30歳を超えているわけですし、その間にはいろいろなことがあるでしょう。
それに伴って考え方も変わるでしょうし、いい意味で大人になると思います。
そんな中で、ゴールを目指すのはもちろんその10年間を楽しむ上で非常に大事なことですが、その10年そのものを毎日毎日楽しいと思って過ごすのには勝てないと思います。
その意味でも、自分が楽しいと思える環境を長い目で作っていくことが一番大事だと考えています。
燃え尽きたり、体を壊してしまっては元も子もない
働き方について、もちろんいろんな考え方がありますが、
張り詰めた糸が切れてしまうように、働きすぎる環境を長い期間継続していることはあまり良くない気がしています。
体を壊してしまっては元も子もないからです。
人間みんな、自分は特別な人間であると思いこみがちですが、だれしもボーッと何も考えないような休息の時間は必要です。
もちろん、仕事をする上でいろいろな制約があり頑張る時は無限に働くことも重要ですが、それが例えば数ヶ月とか、1年とか、もしくは数年ずっと続いているとすれば、それはあまり好ましくはないでしょう。
どこかでまとまった休養も必要だと思います。
リフレッシュすることで結局効率もあがる(アメリカでの体験談)
私はアメリカの大学院で3年ほど勉強をしましたが、その際アメリカの研究所に勤めていました。
そこでは、1ヶ月〜1ヶ月半の夏休みがありました。
私はその期間日本に帰国し、家族と時間を過ごしたり友達と沢山遊んだりすることに費やしていました。
これを読んでいる人の中には、1ヶ月より長い例えば半年とか休めるもんなら休みたい、と感じる方も多いかもしれませんが、私の経験から言うと、
1ヶ月が経つ辺りから、逆に仕事をとてもやりたくなってきて早くアメリカに戻りたい、と感じていました。
周りの人に聞いてもそう感じることが多かった印象です。
夏休みの後仕事に戻るとみんなとてもリフレッシュしており、モチベーションがとても高くなっていました。
このように、まとまった休みをとることはやはり大事なことでしょう。
日本では1ヶ月休みを取ることなど不可能に近いですが、2週間とかなら普通に休めるような文化にしていくことから始めていけたらなと思っています。
ちなみに、そのアメリカでの経験上、二週間休んだ程度では「もっと休みたい」と思っていた気がします笑
ですので、1ヶ月あたりにその辺の「仕事がしたいです、、」的なターニングポイントがあるんだと思っています。
今行っているリフレッシュ
日本に帰って働き始めてからはそのような休みをとっていなかったのですが、
半年前くらいから働き方のSDGsについて考え始めていこう、
旅行とか、サウナとかでリフレッシュして効率を上げるというような取り組みを始めて、前よりハッピーになっている気がしています。
また、エンジニアの禁じ手ですが、仕事以外の開発をすることでもリフレッシュはできます。笑
私は個人開発としてモバイルアプリを友達と開発していますが、
仕事で使う技術とは違う技術を使えますし、単純に自分のペースでなんでもやれたりして楽しいので、それもリフレッシュの一環にし、自分の「持続性」を高めています。
働き方にSDGsを取り入れることのメリット
長い目で見た時のアウトプットが最大化される
これは上述の通り、体や心の健康を「最適」に保った状態で、長い目でアウトプットを出し続けることができる、
と言う意味で持続性を考えた働き方をするのも大事だと考えます。
長い期間やり続けると、いいことが沢山ある
前述の通り、燃え尽きてしまったり、病気になってしまったりして仕事を続けられない状況になってしまうのは一番悲しいことだと思います。
燃え尽きた場合、他の会社にもし転職して新たにモチベーションを復活できるのであれば問題はないですが、完全に燃え尽きた場合、エンジニアという仕事自体を辞め、他の職種に転職してしまう結果になることも考えられるでしょう。
ここで言いたいのは、長く続けることもある意味賞賛されるべきであり、その結果として
技術や知識が蓄積し、生涯の趣味になる
やっていること(例えば自分が開発しているプロダクトや関わっているプロジェクト)に愛着が湧き、モチベーションがアップする
という良いことがある、と思っています。
時にはやり続けないことももちろん大事
もちろん、やっていることが楽しくないのであれば、次の楽しいことを見つけるために他を探すことは大事です。数年続けてみて楽しくないと感じるのであればおそらくそれ以上続けても楽しく感じることはないでしょう。そういう意味で、続けた上で辞めるという判断をするのは大事でしょうし、そこでの経験は次に活きるでしょう。
私が言いたいのは、「まず一定期間」は続けてみて判断するということです。
私も少しやってみた結果、あまり続かずに辞めてしまったことがいくつかあります。
やり続けることができずに辞めた行動
AtCoder
楽しいと感じたこともあったのですが、どちらかというと自分の空き時間に取り組むものとしてはモバイルとかウェブ関連のユーザに近いところをやりたいという思いが強くなり、一旦辞めることにしました。
インフラ周りの勉強
実プロジェクトなどで必要になった時に改めて学び直そうと思い、趣味として勉強するのは辞めました。
ゴルフ
半年ほどやりましたがあまり一緒に行く友達がいなかったため、もう少し歳を重ねてからまた始めようと思い、一旦辞めました。
自炊
月2回くらい気が向いた時に自炊すると楽しいですが、毎日自分のためだけに作るのはコスパもよくないですし、辞めました。
ランニング
前たくさんやっていたのですが、筋トレにハマってからはランニングの代わりにジムに行くことにしました。
やり続けれていること
筋トレ
良いストレス発散になりますし、結果が見た目で現れるので楽しくて続けています。太りにくいような体を作る意味でもコスパがいいと思い続けています。
副業
一つの会社にいるとどう頑張っても取り扱う技術が限定されてくるので、副業で他の技術にも業務レベルで話せるようにしておきたいと思い、続けています。
キータの記事執筆
キータはスタートアップに入って以降、なるべくアウトプットしようと思い立ち記事を書くことを続けています。
個人開発
モバイルアプリの開発を友達と半年以上続けています。
SwiftやKotlin楽しいです。また、モバイル開発で個人開発をしている人たちは多く、優秀な人たちなので、その人たちとSNS上で繋がったりできることも良かったと思えているポイントです。
まとめ
もちろん全力で仕事には取り組むべきであるし、仕事に夢中になれることはとても楽しく幸せなことであると考える一方で、
「やりすぎずに、やり続ける」ということも大事であるなあと考えた、というようなことを長々と書いてしまいました。
ただ、この考え方ってSDGsじゃん、と思って
SDGsの考え方を部分的にでもいいので(ハードに働いてもいいので、マインドには少なくとも)取り入れようよ、
ということが言いたかったです。
このような違う分野の関連付けって
個人的に好きというか、面白いなと興奮するところなので、記事にしてみました。
楽しいと思える仕事を思いっきりやって、
無理はしないようにSDGsな働き方を探して最高のアウトプットを出しましょう!
という言葉とともに終わろうと思います。
今回はこの辺で。
kenmaro
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
