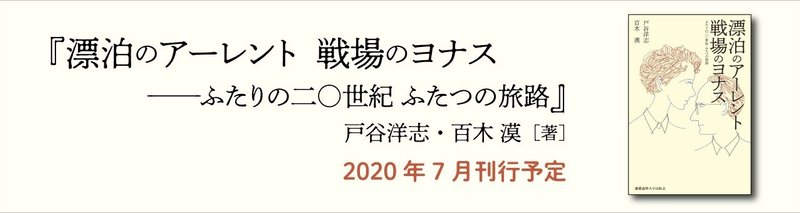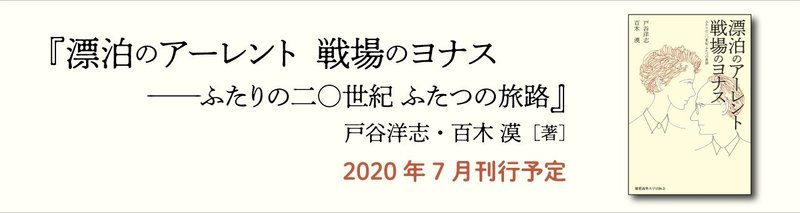【試し読み】『漂泊のアーレント 戦場のヨナス』プロローグ公開
2020年7月に『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』(戸谷 洋志 著、百木 漠 著)が刊行されます。
本書は、二〇世紀を生き抜いた思想家、ハンナ・アーレントとハンス・ヨナスに焦点を当てます。
二人が現在の世界の混沌を見たら、どのような言葉を紡ぎ出すのでしょうか。また二人の生涯と思想からわれわれは何を学びとることができるでしょうか。このような問いに立ち、本書は執筆されました。
その思いが込められたプロローグを公開します。ぜひご一読ください。
* * *
プロローグ 二〇世紀の破局を超えて
われわれは、地上のものに汚れた目で見れば、長いトンネルのなかで事故にあった鉄道旅行者の状況にある。しかもその場所は、入口の光はもう見えないが出口の光もあまりに小さくて、目は絶えず探していなければならないけれども絶えず見失ってしまう、しかも始まりも終わりも、入口も出口も定かではない。われわれのまわりには、感覚の混乱、あるいは感覚の極度の過敏のために、魑魅魍魎と、個人の気分や負傷の程度に応じて恍惚とさせ、あるいは困憊させるような万華鏡的スペクタクルしか見えないのである。
フランツ・カフカ『夢・アフォリズム・詩』吉田仙太郎編訳、平凡社、1996年
この言葉が綴られたとき、カフカが何を念頭に置いていたのかはわからない。しかしそれは今日の社会の状況をあまりにも正確に予言しているように思えてならない。
私たちは紛れもなく真っ暗な「長いトンネル」のなかに取り残されている。複雑化した社会問題によって、グローバル化による人間の移動によって、情報通信技術の発達による情報の過多によって、不意に訪れるテロ攻撃によって、私たちは拠って立つことのできる確かな足場を失っている。入口も出口もわからない。何が原因で今日のような状況が生じたのか、あるいはその先にどんな未来が待っているのか、わからない。その最中で、私たちは「感覚の混乱、あるいは感覚の極度の過敏」に襲われている。拠り所をなくした私たちは「希望」と思えるものが現れると安易にすがりつく。叩きやすい「敵」を発見したら心おきなく罵倒する。そして、見せかけの希望も、叩きやすい敵も、一週間経ったら忘れてしまう。世界はそうした「魑魅魍魎」たちの言論に飲み込まれている。
そうした「万華鏡」的な混乱のなかに、あえて二つの焦点を見定めてみよう。
「全体主義」と「テクノロジー」だ。
近年、世界各国で自国第一主義の機運が異常な盛り上がりを見せている。二〇一〇年以降、ロシアがクリミア半島へと武力侵攻し、イギリスが国民投票によってEUからの離脱を決定し、過激な発言で知られるドナルド・トランプがアメリカの大統領に就任した。世界各国で排外主義が顕在化し、政治的な言論は憎しみで支配されつつある。こうした自国第一主義の台頭は、表現の自由、思想信条の自由、報道の自由、移動の自由など、さまざまな自由の抑圧を伴う。ここには明らかな全体主義の芽が萌している。
そうした自国第一主義はテクノロジーによって支えられ、むしろ加速させられている。たとえば、トランプ大統領はソーシャル・ネットワーキング・サービスのTwitterを自らの政治活動に活用していることで知られている。あるいは、自国第一主義に火を点けた過激派テロ組織も、動画共有サイトを利用して、処刑の映像を世界に配信し続けてきた。こうした情報通信技術の発達を抜きにして今日の国際社会を考えることはできない。私たちは、スマートフォンを一台持ってさえいれば、海の向こう側で繰り広げられるヘイト・スピーチや、モザイクのかかっていない本物の斬首の光景を見ることができてしまう。それは、恐怖や、怒りや、憎しみを増幅させる装置として機能し、分断の溝をいっそう深めていく。「全体主義」と「テクノロジー」は、重なりあい、入り乱れる万華鏡の戯れのように、互いに互いを燃え上がらせる。
もっとも、これらは必ずしも今日において初めて生じてきた問題ではない。全体主義とテクノロジーの出生地を考えるとき、私たちはその起源を20世紀に見出すことができる。
どんなに凡庸な例であると思われたとしても、ナチスはその起源を最も説得的に証言する出来事だった。党首、アドルフ・ヒトラーは、「アーリア人種」の優越性を強調し、天才的な政治手腕で独裁政権を確立させ、世論を一体化させた。ポーランド侵攻によって第二次世界大戦の引き金を引くと、厳しい経済統制を敷くことによって、国民の社会生活や経済活動の様式を合理的に設計しようとした。第一次世界大戦の敗北によって失意のうちに沈んでいたドイツ国民は、戦争遂行を目的とする生活様式を積極的に受け入れ、ヒトラーを支持し、彼に熱狂した。そのようにして、ナチスドイツの全体主義体制は形成されていった。
その体制は反ユダヤ主義に貫かれていた。ヒトラーはアーリア人種至上主義の帰結としてユダヤ人を劣等人種と位置づけ、その強制移住を実施し、最終的に絶滅を画策した。現在のポーランドに建造されたアウシュヴィッツ強制収容所では毒ガスによる大量虐殺が行われ、その決して広大であるとは言えない施設で、一〇〇万人以上が殺害された。この異常な政策を実現させていたものこそテクノロジーに他ならない。アウシュヴィッツ強制収容所は、チクロンBという毒ガスによって、最小の労力で、最短の時間で、最大の効率で収容者を殺害できるよう、徹底的に合理的に設計されていた。そこでは、あらゆる無駄が排除され、目的の効率的な達成を実現するために、透徹した「理性」が発揮されていた。強制収容所の駅はガス室に隣接しており、ガス室には焼却炉が併設され、その横には遺灰を捨てる穴が設けられていた。連行された人々は、ベルトコンベアーに乗せられた製品のように、考える間もなく灰に変えられた。そこには洗練を極めた死の動線が引かれていた。殺す人間も、殺される人間も、誰も何も考えることがないよう、その空間は非情に、理性的に設計されていたのだ。
「人間は理性的な動物である」とアリストテレスは言った。しかし、その「理性」が人類に幸福を約束するわけではないことを、アウシュヴィッツは証言している。国民の生活様式や政治的感情を合理的にコントロールすることも、鉄道とガス室と焼却炉を最適の場所に配置することも、同じ「理性」のなせる業である。ナチスにおいて理性は、全体主義とテクノロジーという姿によって、その暴力性を発揮したのだ。
もちろんナチスは一つの例でしかない。二〇世紀は血の雨が降り止まない時代だった。そしてそれらは今世紀の問題へと途切れることなく連続している。私たちは前世紀において「長いトンネル」に迷い込み、そして事故を起こし、それ以来ずっと出口を探し続けているのである。
そうであるとしたら、私たちは今日の問題を考えるためにこそ、むしろ、こうした二〇世紀の問題を考えるべきなのではないか。言い換えるなら、その時代を生きた人々が、理性の暴力性に対してどのような応答を示していたのかを、改めて問い直す必要があるのではないか。
しばしばナチスの予言者と見なされるカフカは、その凶行を実際に知ることはなく、一九二四年に若くして病死した。一方、この年、ドイツのマールブルクという町では、のちに稀代の思想家として世界を席巻することになる、二人の学生が出会っていた。
ハンナ・アーレントと、ハンス・ヨナスだ。
アーレントとヨナス
本書の主題は、全体主義とテクノロジーをめぐる諸問題を、アーレントとヨナスの思想を手がかりにしながら考察することである。
ハンナ・アーレント(Hannah Arendt 一九〇六~一九七五)は、ドイツ出身のユダヤ人であり、戦後アメリカを拠点として活躍した政治思想家である。生涯にわたって全体主義への問いに取り組み続けた彼女の思索を特徴づけているのは、その視点の多彩さである。一九五一年に公刊された『全体主義の起源』では、一九世紀から二〇世紀にかけてヨーロッパ各地で出現した反ユダヤ主義と帝国主義の形成過程を手がかりに、その帰結として立ち現れる全体主義が歴史的に分析された。また、一九五八年に公刊された『人間の条件』では、そうした全体主義に対抗するために、人間の「複数性」に立脚した政治のあり方が探究された。一九六三年にはアドルフ・アイヒマンの裁判記録『エルサレムのアイヒマン』が公刊される。同書においてアーレントは、アイヒマン裁判そのものに対してさまざまな批判を寄せながらも、全体主義の最中にあってユダヤ人の大量虐殺に加担したアイヒマンの姿に、悪魔的な凶悪さではなく、思考停止によって権力に盲従する「凡庸な悪」を指摘している。
アーレントの政治思想は、彼女の死後、特に1990年代に入ってから「新しい公共性」を開くための道標の一つとして注目を集め、「アーレント・ルネッサンス」とも呼ばれうる状況を生み出した。その影響は学術の領野を超えて、現実の政治やジャーナリズムの世界にも及び、二〇一三年にはアイヒマン裁判の最中のアーレントを描いた映画『ハンナ・アーレント』が公開されるなど、日本でも大きな反響を呼んだ。その影響力は今日においても衰えるところを知らない。
一方、ハンス・ヨナス(Hans Jonas 一九〇三~一九九三)は、アーレントと同様ドイツ出身のユダヤ人であり、環境倫理・生命倫理の黎明期を支えた哲学者である。アーレントが「全体主義」と格闘した思想家であるとしたら、ヨナスは「テクノロジー」と格闘した思想家である。一九七九年に公刊された主著『責任という原理』において、ヨナスは科学技術文明の潜在的な危険性を指摘し、未来の世代への責任を基礎づけた。その思想は世代間倫理と呼ばれる問題圏を開拓し、環境倫理に包括的な理論的基礎を提供することになった。また、一九八五年に公刊された『技術、医療、倫理』では、人体実験、臓器移植、ヒトクローン、遺伝子解析、遺伝子工学など、先端的な生命科学・医療が引き起こす倫理的な問題が論じられている。そうした具体的な問題を扱う一方で、「科学」と「技術」との概念史的な変遷を検討し、それによって今日のテクノロジー概念の形成過程を明らかにすることも、ヨナスの一貫したテーマの一つだった。
ヨナスの思想は、環境倫理・生命倫理の発展に寄与し、国際社会における科学技術政策に多大な影響を与えた。たとえば、国際連合において用いられている「持続可能な発展」や「予防原則」といった指針には、ヨナスの思想の反響を見出すことができる。また、前述の『責任という原理』はドイツにおいて二〇万部のベストセラーになり、同書がドイツにおける環境保護への意識の高まりを動機づけたとも評価されている。
以上のように、アーレントは全体主義を、ヨナスはテクノロジーを自らの主題に設定し、両者の思想は学術の領域を超えて現実の世界に働きかけ続けてきた。しかし、それはアーレントがテクノロジーを、あるいはヨナスが全体主義を軽視していた、ということではない。アーレントは、全体主義の議論を推し進める過程で、その徴候の一つとしてテクノロジーの問題を主題的に論じている。一方ヨナスは、テクノロジーがもたらす破局の可能性の一つとして、技術的に統御された全体主義の危険性を指摘している。すなわち、アーレントは全体主義からテクノロジーへ、ヨナスはテクノロジーから全体主義へと、議論を深化・発展させているのである。その限りにおいて、両者は相似的な関係にある。
しかし、それ以上に興味深い事実がある。それは二人が、哲学史上類を見ないほどに、深い友情で結ばれた親友だったということである。
漂泊と戦場
二人はマールブルク大学で知りあう。当時アーレントは一八歳、ヨナスは二一歳だった。二人は出会った直後から、文字どおりの無二の親友になった。毎日一緒に昼食を食べていたし、アーレントが風邪を引いたらヨナスが見舞いに行っていた。アーレントをナンパしにきた大学生をヨナスが追い払ったこともあった。二人が実質的に同級生であったのはわずか一年間だったが、その日々に培われた友情は生涯にわたって二人を繫ぐことになった。
しかし歴史は二人に牙を剝いた。一九三三年、ナチスが政権を掌握すると、国内で反ユダヤ主義の暴動が活発化し、その状況を憂いてアーレントとヨナスは別々の地に亡命する。この亡命を最後に、二人は十数年にわたって離別し、それぞれまったく異なる境遇に身を置くことになる。
アーレントはパリに亡命した。彼女はそれによって国籍を失い、一九五一年まで、実に一八年間にわたって無国籍状態に陥った。彼女は文字どおり「漂泊」の生活を送ることになった。パリでは、ベンヤミンをはじめとした知識人たちと交流しながら、若いユダヤ人の教育活動に従事していた。しかしそこは彼女にとってまったく安全な場所ではなかった。一九四〇年、アーレントはギュルス強制収容所に収容される。彼女が解放されたとき、フランスはナチスドイツの侵攻を受けて大敗を喫し、パリは占領されていた。翌年、アーレントはアメリカに亡命する。彼女は、文字どおりにどこにも所属せず、何からも守られていなかった。彼女は常に死と隣り合わせの生活を送っていた。
同じ頃、ヨナスはパレスチナにいた。彼はシオニストとして同地に移住し、「ハガナー」という自警団に入隊していた。その後、第二次世界大戦が始まると、ヨナスはイギリス陸軍に志願し、ユダヤ旅団に所属することになった。砲撃部隊の指揮官として、イタリアのセニオ川を挟んでナチスドイツ軍と対峙し、数ヶ月にわたる作戦に従事した。そこは文字どおりの「戦場」の最前線だった。戦況は膠着し、日ごとに互いの陣営から砲撃が行われ、死傷者が続出していった。ヨナスもまた、アーレントとは異なる意味において、死と隣り合わせの生活を送っていた。
漂泊を生きたアーレントと、戦場を生きたヨナス。戦後、アーレントはいくつかの雑誌を媒体として執筆活動を行い、ヨナスは退役後にカナダを経由してアメリカに渡った。やがて二人はともにアメリカを拠点として活動し始めることになる。しかし、両者の関心は異なる方向へと向かっていった。無国籍状態を生き、国家からの承認を受けられず、政治の荒廃と大衆社会の腐敗を目の当たりにしたアーレントは、政治とは何か、公共性とは何か、全体主義とは何か、という政治的な問題に取り組んでいった。一方、ナチスの凶行によって多くの親族を殺害され、戦場でおびただしい数の死傷者を目の当たりにしたヨナスは、生命とは何か、責任とは何か、テクノロジーとは何か、という倫理的な問題に取り組んでいった。
青年時代に出会った二人は、亡命後の異常な環境のなかで、違った仕方で二〇世紀の暴力に直面した。そしてこの体験が二人ののちの思想を規定し、二人はそれぞれの領野で、すなわちアーレントは政治思想の領野で、ヨナスは環境倫理・生命倫理の領野で、第一級の思想家へと成長していった。
二人の交錯点──「出生」
現代思想においてアーレントとヨナスは別々の進路を選んだ。それは疑う余地のない事実である。そのため、先行研究において、二人が並べて比較されることはほとんどない。しかし、同時に二人は極めて近くを並走しもしていた。そして、しばしば電撃的に交錯することさえあった。
戦後にアメリカを拠点とした二人は日常的に会合し、家族ぐるみの社交を楽しみ、旧交を温めていた。もちろんその最中で二人はしばしば哲学的な対話を行った。その頃の様子は前述の映画『ハンナ・アーレント』にも描かれている。
もっとも、その映画を観た者はアーレントとヨナスが良好な関係にあったなどとは信じられないかもしれない。というのも、同作はアイヒマン裁判をめぐる二人の徹底的な対立を描いているからだ。この対立は史実に基づいている。アーレントがユダヤ神秘思想の研究者であるゲルショム・ショーレムとの書簡を発表すると、ヨナスはこれを読んで激怒し、アーレントに対する熾烈な反論の手紙を寄せている。その手紙では、映画で語られた台詞よりも、はるかに強烈な言葉が綴られている。しかし二人はその後すぐに和解する。この対立は、確かに二人の関係に少なくない傷跡を残したのであろう。しかし残された文献を繙いていくとき、この一時的な軋轢を無に帰すような、豊かで刺激的な対話が交わされていたことがわかる。そうした対話のなかで、二人は互いに互いから影響を受け、新たな着想を得て、そして自らの思想を深化させていった。
そうした思想的な交流を顧みるとき、二人がある概念を共有していたことに注意する必要がある。それは「出生 Natality[英]/Natalität[独]」に他ならない。「出生」は、もともとアーレントが『人間の条件』のなかで定式化した最重要概念であり、ごく簡潔に表現するなら、人間がこの世界に新しい存在として誕生する、という現象を意味している。ヨナスはこの概念を継承し、『責任という原理』において展開される自らの倫理思想のなかに取り込んでいく。その意味において、出生概念はアーレントとヨナスの思想史的な連関を問ううえでの鍵概念である。興味深いことは、二人がそれぞれ異なる文脈において同一の概念を用いているということだ。それは二人の思想を単に一体化させるのではなく、むしろ両者の間の根本的な思想の違いを、いっそう鋭く浮かび上がらせもする。しかし、見方を変えるなら、そうした相違は人間の出生が持つさまざまな可能性を描き出すものでもあるだろう。ともに二〇世紀の暴力に立ち向かったアーレントとヨナスは、互いに異なる観点から、人間の出生に希望を託していたのだ。ではそこにはどのような違いが示されているのか、二人の思想史的な連関はどのように捉えられるべきなのか――それが本書の一つの中心的な論点になっていくだろう。
もっとも、アーレントとヨナスを思想史的に繫いでいるのは出生概念だけではない。二人は歴史や感覚の概念についても対話を行っている。本書はこれらの論点を横断的に検討するとともに、そこから二人の思想の比較考察を行うものでもあり、ここに先行研究に対する本書の独自性と新規性がある。そしてそれは、二人の思想史的な連関を解明すると同時に、二〇世紀の思想の地図に新しい線を描くことにも寄与するはずだ。
ただし、こうした学術的研究に資することだけが本書の意図ではない。むしろ本書は、アーレントとヨナスの関係を問うことが、全体主義とテクノロジーの危機の核心へと迫るための、最良の方途であると確信している。なぜなら危機は、それが私たちにとって深刻な問題であればあるほど、たった一つの視点では解決できないものになるからである。アーレントにとっての全体主義とテクノロジーの問題と、ヨナスにとってのそれとは、その性質においても深刻度においても異なっている。そして異なっていて当然である。なぜなら、アーレントとヨナスは別の人間であり、別の人生を生きており、そして危機は常に一回限りの人生のなかで立ち現れるからだ。
だからこそ、翻って、危機は複数の視点から、さまざまな角度から考察されなければならない。アーレントとヨナスという、二つの異なる色彩を帯びた光のもとで危機を照らし出すこと、それによって現代社会を多角的に、そして立体的に考察すること。それが本書の基本的な姿勢である。
本書の構成
本書の執筆は、百木と戸谷によって分担される。原則としてアーレントに関する執筆は百木が担当し、ヨナスに関する執筆は戸谷が担当している。またこのプロローグは戸谷が執筆し、エピローグは百木によって執筆されている。
本書の構成は以下のとおりである。
第1章では、一九〇三年から一九三三年を扱う。ここでは、アーレントとヨナスの幼少期、子ども時代、青年期が描かれたうえで、マールブルク大学における二人の出会いと大学生活、また学生時代の研究テーマなどが論じられる。また、徐々に忍び寄る反ユダヤ主義の足音に対して、二人がどのような反応を示したのかも描かれることになるだろう。
第2章では、一九三三年から一九四五年を扱う。前述のとおり、ナチスの政権掌握によって、二人は別々の場所に亡命し、離れ離れになる。アーレントは無国籍状態のままパリからアメリカへと「漂泊」する。これに対してヨナスはイギリスを経由してパレスチナへ赴き、「戦場」に向かうことになる。この章では、二人がそれぞれの場所で送ることになった、文字どおりに死と隣りあわせの生活が描かれ、そこに後年の思想を育んでいく原体験が示される。
第3章では、一九四五年から一九六一年を扱う。この章の主役はアーレントである。彼女はこの間、『全体主義の起源』や『人間の条件』などの主著を公刊しており、一挙にその名を世界に轟かせていった。この章では、こうした著作群が執筆されるに至った背景や、それらが彼女にもたらした影響などに注意を払いつつ、全体主義あるいはテクノロジーに対する批判的な分析と、それに対して提示される「出生」をめぐる議論が主題化される。一方ヨナスは、パレスチナをあとにしてカナダへと渡り、やがてアーレントのいるアメリカへと流れつくことになる。
第4章では、一九六一年から一九六四年を扱う。この章のメインテーマはアイヒマン裁判をめぐる論争である。前述のとおり、ナチスの将校であったアイヒマンがイスラエルで裁判にかけられると、アーレントはそれに関する記録と分析を『エルサレムのアイヒマン』として公刊した。同書はその挑発的な内容から各方面で論争を巻き起こし、ヨナスもまたアーレントに対して激しい反論を寄せている。他の章と比較すると、この章で扱われる期間は極端に短いが、しかしこの4年間にアーレントとヨナスが初めて本格的に衝突したという意味で、両者の思想史的連関を考えるうえで重要であり、独立した章を当てられるに値する。
第5章では、一九六四年から一九七五年を扱う。ここでは、アーレントの晩年と彼女の死、そしてヨナスの新たな思想の展開が主題になる。この間アーレントは、その関心を〈活動的生活〉から〈精神の生活〉へと移していき、「思考」「意志」「判断」をテーマとした講義・講演を数多く行っている。一方、ヨナスは『生命の哲学』という著作を公刊し、アーレントからいくらか遅れて本格的な著述活動を開始する。
第6章では、一九七五年から一九九三年を扱う。この章の主役はヨナスである。アーレント亡きあと、ヨナスは主著『責任という原理』を公刊し、世界に衝撃を与え、一躍脚光を浴びることになった。前述のとおり、同書のなかではアーレントの「出生」概念が複数回にわたって援用されており、この章ではその機能や意義についても考察する。またアーレントの葬儀におけるヨナスの弔辞や、彼女を悼む追悼論文を紹介し、彼女の死がヨナスにどのような影響を与えたのかを検討する。一方、アーレントの死後に公刊された彼女のテクストも取り上げ、死してなお話題の中心にあった彼女の遺産について考察する。
第7章では、著者である百木漠と戸谷洋志によって、アーレントとヨナスの思想史的連関を踏まえながら、異なる論点について比較考察を行う。本章では、百木と戸谷はあえて意見の摺り合わせを行わず、自由に議論を展開していく。それによって、アーレントとヨナスの今日的な意義を再確認しつつ、より現代的な問題を考えるために、両者の思想をどのように読み解くべきなのかを、あるいは乗り越えていくべきなのかを検討していく。
本書にはアーレントとヨナスを繫ぐ何人かのキーパーソンが登場する。二人の共通の師であるマルティン・ハイデガーや、ルドルフ・カール・ブルトマン。アーレントの師であり、ヨナスの友人であったカール・ヤスパース。アーレントの最初の夫であり、ヨナスとも親交の深かったギュンター・アンダース。『エルサレムのアイヒマン』をめぐってアーレントと論戦を交わし、ヨナスにとってはパレスチナ入植時代の世話人であったゲルショム・ショーレム。本書は、現代思想を彩るこれらの主要人物たちを視野に含めることで、アーレントとヨナスの思想史的な連関をより色彩鮮やかに描き出していくことに努めたい。
前置きが長くなった。早速、本題に入るとしよう。
これは、ハンナ・アーレントと、ハンス・ヨナスの旅路である。
* * *
本書「第1章 友情と恋愛のあいだ――誕生から出会いまで 1903~1933」に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?