
【試し読み】ペク・スリン「時間の軌跡」(『夏のヴィラ』より)
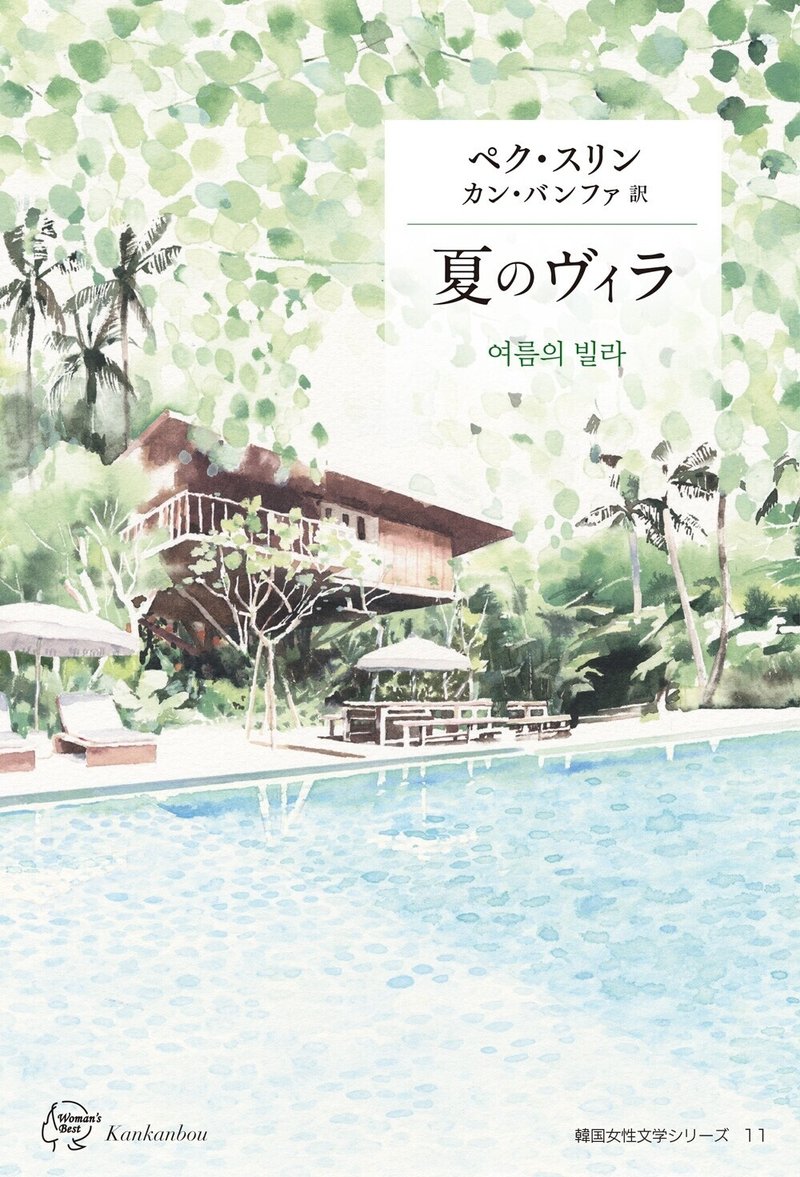
【試し読み】ペク・スリン「時間の軌跡」冒頭部分より(韓国女性文学シリーズ11『夏のヴィラ』カン・バンファ訳 収録作品)
オンニ[ここでは女性が自分より年上の親しい女性に使う呼称]に声をかけられたのは、イースター休暇が始まる前のある水曜日のことだった。オンニと私は数カ月間、語学学校の同じクラスにいた。十五人の外国人のうち、韓国人は自分たちふたりだけと知ってはいたが、それまで言葉を交えたことは一度もなかった。講義室では、オンニはいつも右端の列の二番目、私は左端の列のいちばん後ろに座っていたせいもあるだろうが、実をいうとそれだけが理由ではない。当時の私は、韓国人とばかり付き合うのなら、わざわざ三十手前で会社を辞めてパリに来る必要などないという思いから、韓国人を避けていたのだ。
オンニが話しかけてきた日は、雨がぱらついていた。あの日のことを思うと、雨の中、薄暗い講義室で〈雨の降る日 Le jour où la pluie viendra〉という曲を聴いたことを思い出す。髪はベリーショート、耳に蒼い大きな原石のイヤリングを着けた若い講師は、ホワイトボードにマーカーで「Le jour où la pluie viendra / Nous serons, toi et moi / Les plus riches du monde」という歌詞を書いた。雨の降る日、君と僕、僕たちはこの世でいちばん豊かな人になるんだ。私たちはホワイトボードに書かれた、未来時制の練習にぴったりの歌詞を一節ずつ教えてもらい、その曲を聴いた。私より若そうな講師は、クラシカルにもCDプレーヤーを持ち歩いていた。再生ボタンを押すと、CDプレーヤーから流れ出てきた男性の声がかぐわしいパンのようにふくらんで、講義室を埋めつくした。数人の学生は一緒に口ずさみながら笑った。私とオンニ、数人のアジア人を除くと、聴講者のほとんどはイタリアやスペイン、ドイツから来ていた十代後半の子たちで、彼らは箸が転げても笑うほど無邪気だった。
素晴らしい歌というわけではなかった。古いシャンソンの一つで、講師の父親がまだ幼かったころ、ラジオでよく流れていたというだけの歌。でも、バックミュージックのように聞こえていた雨音のせいだろうか。その曲を聴いた瞬間、なんだか自分が、恋しい人たちからあまりに長く、あまりに遠く離れているような気がした。きっとそのせいだろう。かばんを手に講義室を出た私に、廊下に立っていたオンニが、「韓国人でしょ? よかったら、一緒に一杯やらない?」と訊いてきたとき、いつもの私に似合わず「いいですよ」と答えたのは。オンニも私と似たような心持ちでいたのだろうか。そう尋ねることはできなかったけれど。
オンニと私は学校を出ると、めいめいに傘を差して並んで歩いた。小雨は途切れとぎれに振りつづき、夜の訪れた街は湿気の中に沈んでいた。語学学校から遠くないパンテオンの前には、レインコート姿の観光客らが立っていた。彼らを避けるように路地を突き進み、そこで見つけたカフェ兼酒場には客もまばらで、私たちは隅のテーブルに席をとった。お互いを遮っていた傘や、アンテナを張って探すべき目的地がなくなると、知らない人とふたりきりで向き合っているのが今さらのように気まずかった。落ち着かない空気の中でワインが運ばれてくると、私たちはさまざまな質問を投げ合った。オンニは三十代後半で、意外にも、大手企業の駐在員として派遣されているのだと言った。
「駐在員?」
私は驚いて問い返した。これまでの半年近いフランス生活で出会ってきた韓国人の若い女性は、留学生や留学を控えた人、駐在員、もしくはフランス人の妻だった。駐在員だと聞いて、オンニへの関心が一気に高まった。そんなふうにワインを飲みながら、私たちは二時間ほど話に花を咲かせた。お互い、フランスに来る前はどんな都市に住んでいたのか、何を勉強し、いつフランスに来たのか。私たちが急速に親しくなったのは、オンニが会社員で、私もまたフランスに来る前は会社員だったという共通点のためだけではない。ふたりとも、エリック・ロメールの『緑の光線』とフランソワーズ・サガンの小説が好きで、政治についても似たような傾向を持っていたこと、そして何より、それぞれ三十代の頭と半ばにして、新たな人生を夢見てフランスに渡ってきたということが、私たちのあいだに立ちふさがっていた壁をいとも簡単に取り払った。一重の大きな目と濃いまつげが特徴のオンニは、いかにも美人というわけではないにしろ、どこか不思議な魅力を湛えていた。声のトーンは高くても声量はなく、話すとささやいているように聞こえるのだった。おもしろい話を聞くと手を叩いて笑い、途中で口元を隠すときのオンニは慎ましやかに見えた。でも、好奇心旺盛な猫のように目を光らせて話に聞き入っているときは、そんなものとは縁遠い人のようにも見えた。その日のオンニとの会話は、長いあいだ忘れていた事実を呼び覚ました。言うなれば、ある人と交わす言葉は美しい音楽のように人の感情をくすぐり、会話を交わす者たちを一度も訪れたことのない見知らぬ世界へ導くということを。
会話を終えて外へ出ると、雨はもうやんでいた。「時々、今日みたいに遊ばない?」別れ際、オンニが地下鉄駅の前で言った。外国での暮らしが長くなるにつれ、韓国人の知り合いをつくるのは外国人の知り合いをつくるより簡単だが、好みも気も合う韓国人の友人に出会うことは、好みも気も合う外国人と出会うのと同じぐらい難しいことだと身に染みて感じていたところだったので、私は喜んでこう答えた。「ぜひ」オンニは笑って手を振り、地下鉄駅の中へ消えていった。私はバスに乗るため、道を渡った。
その後の数週間、私たちは多くの時間を共に過ごした。授業のあと、地下鉄駅まで向かう途中で道を逸れてビールを飲んだこともあれば、週末には、映画を観たり繁華街でウィンドーショッピングをしたりもした。ある日の午後、私たちはポンピドゥー・センターで企画展を見て回った。カーキ色のシャースカートにマスタード色のカーディガンを羽織ったオンニは、年より若く見えた。一緒に展示を見たあとは、チュイルリー公園まで歩いた。パリの春らしくなく、久しぶりに陽射しの気持ちいい日だった。私たちは鉄製の椅子に腰掛け、そよ風に髪をかき乱されるたびに笑った。それでも別れがたく、再び歩き出して日本料理屋で餃子とラーメンを食べ、近くの小さな酒場でビールを飲んだ。店の名前も風景もよく覚えていないが、そこでオンニが、「フランスに来て二年になるけど、こんなに気の合う友だちは本当に初めて」と言ったときの表情と言葉つきだけは、おかしなほど鮮明に思い出せる。そしてその日、オンニは、独身女性が駐在員として生きることの苦労について語った。駐在員同士で集まったり食事会をすることもあるが、そのほとんどが男性なので、顔を出すのも出さないのも微妙だとか、そういった会に夫婦で参加する人がいると、主に駐在員の奥さんと話すことになるとかいう話だった。
「変じゃない? 私は駐在員の妻じゃなくて駐在員なのに、なんで毎回そんなふうになるのよ」
オンニは酒気で赤らんだ顔を撫で下ろしながら言った。そんな話を間近に聞いているあいだは、自分にもその歯がゆさがそっくり伝わってくる気がして、私はオンニと一緒に悔しがり、憤慨した。時折会話が途絶えることがあると、私は椅子の背にもたれた。そうやって会話から一歩退いた瞬間、ふと四方からフランス語が聞こえてくると、ああ、ここはソウルではなくパリのど真ん中なのだと気づくのだった。もう終わった恋について私たちが話しはじめたのは、それからもう少し酔いが回ったころだった。
「馬鹿みたいな話、聞きたい?」
その日、オンニは駐在員としての苦労を話し終えた末に、とてもいい男で、いい夫、いい父親になるに違いなかったが、三十代半ばで駐在員を希望するオンニの気持ちだけは最後まで理解できなかったという、かつての恋人について初めて口にした。ある秋の晩、「どこまで独りよがりなんだよ」と言い捨て、オンニを漢江の土手に残してずんずん歩き去ったというその彼と、タクシーの中で泣きすぎて、どこか痛いのか、救急室へ乗せていったほうがいいかと運転手に訊かれたのだというその夜について。そして、オンニは秘密を打ち明けるように、寂しい夜は、もう別の女の夫になってしまったその彼に電話をかけて少しばかり話し、ひとりで泣くのだという話をした。
「馬鹿でしょ?」
オンニはおどけたように言ったが、その表情は寂しげだった。私は、今は既婚者となった元彼と連絡を取りつづけていると聞いてびっくりしたが、実をいうと、その瞬間、オンニがますます好きになった。オンニにもそんな愚かな面が、人間らしい面があるという事実が、私の孤独を和らげた。だから、まだ青二才だったころの自分の初恋について、包み隠さず話せた。彼は大学の同じ科の先輩で、私の初恋の人であり、十九歳から二十七歳まで付き合った唯一の恋人だった。
「気づいたら、専攻も就職先も、全てその人に相談して決めてたの」
私の後輩と浮気していたことを知り、彼に別れを告げてまず最初にしたことは、ソウル市内にあるフランス語教室に登録することだった。はた目を意識して選んだ職場を三十前に辞め、以前からの夢、フランスで美術史を学ぼうと決心したからだが、それは私にとって、生まれて初めてひとりで決めたことだった。
「そう決心した日、カップルリングを捨てて、この指輪を買ってはめたの」
私は薬指の指輪を見やった。なんの装飾もない、細い金の指輪。
「きれいね」
今になって振り返ると、そのときこそ、私たちがお互いに最も心の内を見せ合った瞬間だった。
【続きは書籍『夏のヴィラ』でお楽しみください】
------------------------------------------------------------------------
Woman's Best 14 韓国女性文学シリーズ11
「夏のヴィラ」여름의 빌라
ペク・スリン 著
カン・バンファ 訳
四六、並製、240ページ
定価:本体1,700円+税
ISBN978-4-86385-499-4 C0097
2022年3月中旬全国書店にて発売
装幀 成原亜美(成原デザイン事務所)
装画 荻原美里
過去と現在が交差し、一瞬煌めいて消える——
韓国で五つの賞に輝いた珠玉の短編集。
人と人、世界と世界の境界線を静かに描いた八つの短編を収録。
【目次】
時間の軌跡
夏のヴィラ
ひそやかな事件
大雪
まだ家には帰らない
ブラウンシュガー・キャンディ
ほんのわずかな合間に
アカシアの林、初めてのキス
著者あとがき
訳者あとがき
【著者プロフィール】
ペク・スリン(白秀麟/백수린)
1982年仁川生まれ。短編小説「噓の練習」(2011年京郷新聞新春文藝)でデビュー。2015年、2017年、2019年文学村若き作家賞、2018年文知文学賞、李海朝文学賞、2020年現代文学賞、韓国日報文学賞。著書に短編集『フォーリング・イン・ポール』『惨憺たる光』(書肆侃侃房刊)『今夜は消えないで』、中編小説『親愛なる、親愛なる』、エッセー『やさしい毎日毎日』などがある。
【訳者プロフィール】
カン・バンファ (姜芳華)
岡山県倉敷市生まれ。岡山商科大学法律学科、梨花女子大学通訳翻訳大学院卒、高麗大学文芸創作科博士課程修了。梨花女子大学通訳翻訳大学院、漢陽女子大学日本語通翻訳科、韓国文学翻訳院翻訳アカデミー日本語科、同翻訳院アトリエ日本語科などで教える。韓国文学翻訳院翻訳新人賞受賞。訳書にペク・スリン『惨憺たる光』、チョン・ユジョン『七年の夜』『種の起源』、ピョン・ヘヨン『ホール』、チョン・ミジン『みんな知ってる、みんな知らない』など。韓訳書に柳美里『JR上野駅公園口』、児童書多数。著書に『일본어 번역 스킬(日本語翻訳スキル)』がある。
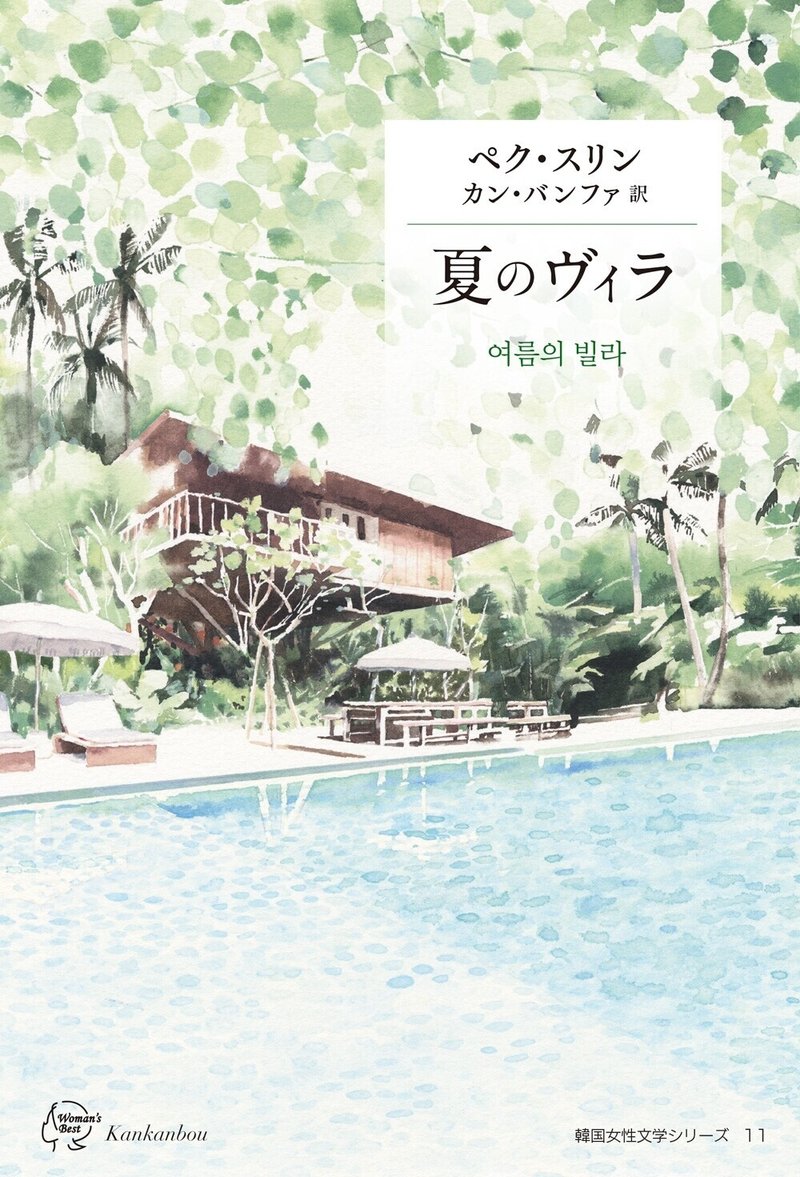
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
