
【試し読み】吉田恭子「九龍に充実するオルタナティヴなリアル──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記1」(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)
吉田恭子「九龍に充実するオルタナティヴなリアル」
(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)
*****
「国際作家工作坊」国際創作ワークショップ
先週2月17日から香港バプテスト大学に滞在している。先週から咳が止まらない。喉の腫れ用にもらった抗生物質を飲み切っても変化はなく、フランスで買ったアルファアミラーゼの錠剤とアメリカで買ったナイキル咳用シロップを持って先週の日曜日に入港。翌日学生に案内されてのキャンパスツアーでも、その次の日の学部長主催の歓迎昼食会でも、突然咳き込みだすと止まらず、あらゆる人に心配され、中国漢方の顆粒剤とインドのヨード入りチューイングタブレットをもらった。徐々に治まり、水曜夜のオープニング・イベントで壇上に座っているころには、喉に違和感がある程度で無事に朗読もできたのだが、最後に隣に座っているバーナリが朗読する番になって咳が押し寄せ、必死に腹筋を痙攣させ我慢していると涙が出てきて、それに鼻水まで加わり、壇上なので手元には原稿とペンと水しかなく、涙も鼻水も流れるままに腹筋運動をする姿を満場に晒しながら、詩と詩の合間に小出しに咳をしつつ、バーナリの朗読を聞いていた。後で参加者のみんなに、ごめんね咳き込んじゃって、と謝ると、気づいてなかったと言いはるので、みなさん人の恥は見なかったことにする大人の方々なのか、いったん詩の朗読が始まると他に何も耳に入らない方々なのかのどちらか、もしくは両方なのだろう。
おかげさまで今では一日に何度か咳払いをする程度だ。上記の薬はどれもひと通り飲んだ。いったいどれが効いたのかはよくわからない。
今回わたしが参加しているのは、香港バプテスト大学(中国語では「香港浸会大学」……ありのまますぎて改めて漢字の威力を感じる)の人文学部創作科が主催する「国際作家工作坊」国際創作ワークショップという4週間のレジデンシーだ。アイオワ大学の国際創作プログラムに触発されて始まった本プログラムも15年目である。(ちなみにアイオワの国際創作プログラムは一昨年2017年に50周年を迎え、ワークショップこと創作科の方はもうすぐ設立90年になる)作家レジデンシーは作家や詩人に滞在する場所と創作時間を与えて、レジデンシーによっては文学祭や授業参加や相互交流などが付随する。要するに積極的に缶詰環境を提供するのである。アーティストレジデンシーは世界各地にあるが、アメリカに限れば、ヤッドゥーというニューヨーク州中部の大型レジデンシーが有名で、ここでは作家や詩人は業績によりランク分けされていて、交通費を含めてすべての参加費を免除される最上位の参加者を筆頭に様々なレベルに細分化されており、中には施設の食堂やカフェで給仕として働くことで参加費が減額されるという仕組まであることでも知られている。
今年のテーマは「新しい想像力」
香港バプテスト大学の国際創作ワークショップの今年のテーマは“alternative imaginations”「新しい想像力」。オープニング・イベントでは、司会の詩人ジェイムズ・シェイがジョン・アシュベリー(1927-2017)の長編詩“Flow Chart”(1991)を引用していた。
But at times such as
these late ones, a moaning in copper beeches is heard, of regret,
not for what happened, or even for what could conceivably have
happened,but
for what never happened and which therefore exists, as dark
and transparent as a dream.
けれど昨今のような
時代には、ムラサキブナの林から嘆き声が聞こえてくる、後悔するのは、
起こってしまったことではなく、可能性として起こりえたことでさえも
なく、
決して起こらなかったがゆえに実在すること、夢のように
暗々として透き通って。
2017年に90歳で亡くなったニューヨーク派を代表する詩人アシュベリーは難解という印象が先行しているためか、日本で広く読まれていないのがもったいないのだが、詩そのものの内的な論理に支えられた瞑想的で魔法のように流れる言葉を紡ぎ、自己言及的な言葉の世界に生きる詩人たちに絶大な支持を得てきた。ここでも流石の手さばきで単なる夢こそがなによりもリアルであるという直感的感触を描き出している。夢は単に夢であると同時に夢見る者にとっては現実よりはるかに鮮やかに知覚されるまた別の(alternative)現実でもあるのだ。4週間の最後の週は “Many Worlds of Science Fiction” 「SFの多層世界」というテーマで文学祭が予定されていて、リアリズム的文学表象の見直しを促すことが今年のプログラムの一貫した姿勢だといえる。文学祭については次回で詳細をお知らせしたい。
レジデンシーにはわたしを含めて6人が参加している。キャンパスツアーで丸半日を一緒に過ごし自己紹介は済んでいたものの、あらためて5人の朗読を聞くと、ようやく本当の自己紹介を果たしたような、単なる社会的な知り合いから文学的な友人への扉が開けたような、そんな気持ちになって、壇上で必死に咳を抑えて涙と鼻水を流しながら、なんだか子どものようにわくわくして、これからの4週間に胸躍る思いがした。
サラ・リペットはロンドン拠点のグラフィックノヴェリスト。祖父母の若い頃を描いた“Stan and Nan”(2016)が英紙ガーディアンを筆頭に評価されベストセラーになった。2019年の秋にはもやもや病の闘病経験をふり返った長編“A Puff of Smoke”が出る予定(ちなみに「もやもや病」は英語でも “Moyamoya disease”だと今回学習した)。アジア滞在ははじめてだそうで、とにかく好奇心の赴くまま積極的にあちこち歩き回っている。マーラ・ゲンシェルはベルリンとシュトゥットガルト拠点の前衛詩人。彼女の詩は推敲され磨き抜かれた完成品を目指すのではなく、創作のプロセスを再現する詩の青写真のようだ。手作り本の制作など本の形をめぐる実験も行っている。バーナリ・レイ・シュクラはボンベイが拠点の英語詩人で映画監督。アマゾン配信のコメディ映画でデビュー、最近はユニークな人生を追うドキュメンタリーに興味があるようだ。ソウル大学の大学院で比較文学を研究している小説家ハン・ユジュは、トーマス・ベルンハルトやサミュエル・ベケットなどヨーロッパの前衛作家の影響を自認しているが、その小説世界は独特だ。第一長編“The Impossible Fairy Tale”(英訳2018)は小学生の日常と幻想が入り交じる残酷な世界を描くメタフィクションである。実験作家のグループRUEで活動し、ウリポプレスという文芸出版社を運営している。ニコラ・マヅィロフは今年唯一の男性参加者。マケドニアのストルミツァでバルカン紛争難民の両親のもとに生まれた。現在も北マケドニアが拠点とはいえ、常に世界中の詩祭や文学レジデンシーを転々とする生活をしていて、今回の4週間の滞在中にもフランクフルトの文学祭に飛んで行って戻ってくる予定だ。彼の詩は移動し逃亡し流浪する人々を描いている。
以上のような説明では通り一遍の紹介にしかならない。「本当の紹介」に少しでも近づけるにはやはり作品との出会いが必要なので、抜粋を翻訳紹介したい。
共通点は翻訳
イベントの後、巨大な円卓を囲んでの懇親会が終わり、それでも話し足りずマーラとニコラとわたしは大学の近くのバー、ビリー・ブーザーに飲みに行くことにした。道すがら、三人ともアイオワ大学の国際創作プログラム経験者、とりわけマーラは柴崎友香さんと同期だと判明し、共通の知り合い――ディレクターで詩人のクリス・メリル、ワークショップ出身の小説家で副ディレクターのヒュー・ファーラー、翻訳プログラムと編集担当の映画史研究者ナターシャ・ドゥロヴィコヴァ――についての話題で盛り上がり、異国で同郷の人に出会ったような気持ちになった。
この3人のもうひとつの共通点は翻訳だった。マーラはスマホのテクスト入力自動修正機能やGoogle翻訳を使った詩的実験の話をしてくれた。アメリカでスマホにドイツ語を入れると親切にも勝手に英語に「直して」くれることを逆手に取って、アイオワではAIと共作を試みたそうだ。ニコラは移動しているときは翻訳をするそうで、谷川俊太郎や大岡信の詩も英語から翻訳したとか。ニコラは2003年から2008年にかけて、“Mravka”(マケドニア語で蟻)というマケドニア唯一の俳句雑誌を主催し、スウェーデンのノーベル賞詩人トーマス・トランストロンメル(1931-2015)、ホルヘ・ルイス・ボルヘス(1899-1986)、オクタヴィオ・パス(1914-1988)、正岡子規国際俳句賞を受賞しているフランスの詩人イヴ・ボヌフォワ(1923-1916)からソビエトの映画監督アンドレイ・タルコフスキー(1932-1986)やセルゲイ・エイゼンシュテイン(1898-1948)まで、俳句に影響を受けたモダニストたちの詩論を翻訳紹介してきた。話を聞いているととにかくかたっぱしから世界中の気に入った詩を翻訳している様子である。翻訳は彼の読書・執筆生活に欠かせない営みで、出版もするが、多くは友人と分かち合うためだそうだ。詩は友情を最も重んずる文学形態だとわたしは信じているので、ニコラの翻訳哲学は詩人同士を個人的に結んでいく細い糸のような役割を演じていると感じた。それは彼が世界を旅しながら執筆を続けることと関係があるに違いない。翻訳すると非定形になってしまうが、ここでニコラの句をふたつ。
テレビが
壊れてしまい――スクリーンの中には
僕らの顔が見える
壊れたボタンが
薔薇の庭に
棘に絡まる糸
マーラもわたしも宿舎のデスクがとても気に入っている。ふたりとも10階の並びの部屋で、南向きの出窓があり、そこにちょうどぴったり嵌め込む形で小さな木製の台形デスクが設置されていて、窓の左右を覗き込むと隣りの出窓の横側がわずかに見える。右側がバーナリの窓、左側がユジュの窓。デスクからまっすぐ前を見れば、遠くに九龍半島南端の摩天楼が、雲が晴れると湾の向こうのヴィクトリアピークも見える。わたしたちは「百万弗の夜景」を裏側から遠く望み見ていることになる。
ポスト国民文学時代のアメリカ文学
近隣は低層アパートや一軒家が並ぶ高級住宅街の風情で、香港城市大学など学校も多い文教地区だ。そしてキャンパスの東を通るわずか幅5メートルほどの聯福道(レンフロー・ロード)を隔てて人民解放軍東九龍駐屯地がある。大学図書館近くの正面入口には昼夜を問わず人民兵がふたり機関銃を携えて大学に対峙している。年頃は大学生と同じぐらいに見えるが、大陸のどこからやってきたのだろうか? 鉄条網越しに見るリア充大学生の日常は彼らの目にどう映っているのか? ふたりの背後には赤い壁に簡体字のスローガンが叫んでいて、すっかり繁体字に慣れた目で見ると少しぎょっとする。道路を挟んで向かい合うふたつの漢字と一国二制度はどちらも夢じゃないリアルだ。ここで日々ソフトに銃を突きつけられ人文学を学ぶとはどういうことなのだろうか?何を自問し、何から目を背け、何に気づかないふりをすることになるのか?そしてわたしは日本で何に気づかないふりをしているのか、図書館に向かいながら考える。
この連載では、クリエイティヴ・ライティング・プログラムとその周辺について、行く先々から報告していく。行く先はアメリカとは限らないので今回みたいにアメリカ文学そのものの話にはならないかもしれない。けれどもどの場所もわたしにとってはアメリカ由来の文学生産教授法であるクリエイティヴ・ライティングが縁となって繋いでくれる場所なので、英語を執筆言語、翻訳中継言語、文学的交友言語とした現代文学のひとつの光景として読んでいただけたら、と思う。そして英語一強時代の問題も含めて、ポスト国民文学時代のアメリカ文学、英語文学、翻訳文学について考えてみたい。
よろしくおつきあいください。げほんげほん。
作品紹介
ニコラ・マヅィロフ「瞬く間に世紀は」
瞬く間に世紀は。僕が風なら
木々の皮をめくって
町外れの建物の外面(そとづら)を剥ぎとるだろう。
僕が黄金なら、穴蔵に隠されて
ぼろぼろの地面に壊れたおもちゃに混じって
父親たちは忘れ去り、
息子たちは永久に僕を忘れないだろう。
僕が犬なら、難民のことを
恐れたりはしないだろうし、僕が月なら
処刑を怖がったりはしないだろう。
僕が壁の時計なら
壁のひび割れを覆うだろう。
瞬く間に世紀は。小さな地震で僕らは
大地ではなく、空を見上げる。
窓を開けて入ってくるのは
行ったこともない場所の空気。
誰かが僕らの心を毎日傷つけるのなら、
戦争は存在しない。
瞬く間に世紀は。
ことばにする前に。
僕が死んだなら、誰もが信じてしまうだろう
僕が無言のままだと。
バーナリ・レイ・シュクラ「黄色い紙飛行機」
あの黄色い紙飛行機が
飛んでいったわたしの歌を運ぶ
にはあまり高くない
けれど月を見つけた
また丸くなりたいと願う
半月を
光を全身に映す
輝きではなく
裏側の物語を
詩人が素通りする物語を
語り始めるために
むかし白紙のページだった
あの紙飛行機が
新たな折り目を得て
飛んでいけるように
月は心浮き立って
書きつける
広げた紙に
震えて書き記し
紙飛行機は少しずつ
高度を失い
高度を失い
高度 を 失 い
高 度 を
う し な い
でも深みを得て…
月はひと休みして
夜の向こうへ
思いを馳せて
泣く
紙飛行機は
風向きの変化に飛ばされ
そうして
紙飛行機はまた舞い上がる
降下に耐えて
そして声を上げる
「新たな物語を始めるためには
誰かが終止符を打たねばならぬ。
今度は
君の裏側の番だ」
紙飛行機が
戻ってくる
今度は
黄色ではなく
ただ
読んでもらおうと。
“Apostroph.” India: RLFPA Editrions, 2017.
ハン・ユジュ「不可能な童話」抜粋
3.
その子は恵まれている。
いかに恵まれているかを話す前に、他にも子どもたちが登場するので、名前の件に触れておく必要がある。その子の名前はミア。ミンアでもミーナでもミンハでもかまわないし、アミでもユミでもユンミでもいいわけだが、彼女は自分はミアだと思っているので、とりあえずミアと呼ぶことにしよう。
ミアは恵まれている。ある日、この子を娘と見なす男ふたりのうちのひとりからドイツ製の水彩色鉛筆七十二色セットをもらった。ふたりのうちの一方はもう一方の存在にまだ気がついていないか、あるいは気がついていないふりをしていて、もう一方はもうひとりの存在に気がついているが、よくわからない理由で見て見ぬふりをしている。他の誰も知らない事実を知るとあらゆる人間関係が劇的に変化する。とはいえ、どちらもミアの父親ということになっているが、ふたりのうちのどちらか一方のみがドイツ製の水彩色鉛筆七十二色セットをあげたのだ。色鉛筆はドイツ製で中国製の安物ではないから、この子の好みと興味を満たしたし、したがって買った方の父親はもう一方の父親よりも有利になった。赤色、紫紅色、紅色、朱色、薔薇色、黄色、橙色、黄橙色、檸檬色、肌色。それから黄緑色、翡翠色、深緑色、青緑色。これほど圧倒的な色揃えを前に、恵まれたミアは周りのものはなんだって七十二色で描けると無邪気に子供らしく思い込む。……
大きくなったら万年筆を買うの、とミアは言う。万年筆で人を殺せるって知ってる?本に書いてあったの。高いところから正確な角度でペンを落とせば、尖った先が人の頭に突き刺さるんだって。加速度がつくから。探偵小説にあったの。
だがもちろんミアに人を殺すつもりはない。それどころか死や殺すという言葉の意味さえわかっていない。ミアは恵まれた子で誰かを殺すような機会どころか激情も持ちあわせない。人は憎悪のような感情がなくても人を殺すのだということをまだ知らない。高い建物から人の頭を万年筆の先で狙うよりも、尖った金属を喉に突き刺したほうがはるかに効果的だということを、もっと本を読んでいれば学んだかもしれない事実を、まだ知らない。けれども興味があるのは探偵小説ばかりだし、知らないことのほうが知っていることよりも多いので、ミアの世界は単純だ。だからこそ恵まれているのだ。ともかく、大きくなったら万年筆を買うの、と彼女は言う。響きが好きだから。まんねんひつ。
ほぼすべてを持っているミア、欲しいものは何でも持てるといつも言われてきたミアは、自分の世界を好きなように七十二色の色鉛筆で作り出せると、すでにこの世にあるもの影にもそれぞれの色を塗ることができると、影を消すことだってできると、人を殺すことだってできると思っている。殺す力があるのならば、人を救う力だって同様にあるのだ。したがって不可能なことはない。すべてを持っているミア、あるいはすべてを持つことができるミアは、なんでもできると思っている。……
マーラ・ゲンシェル「2019年度最優秀ジョーク」
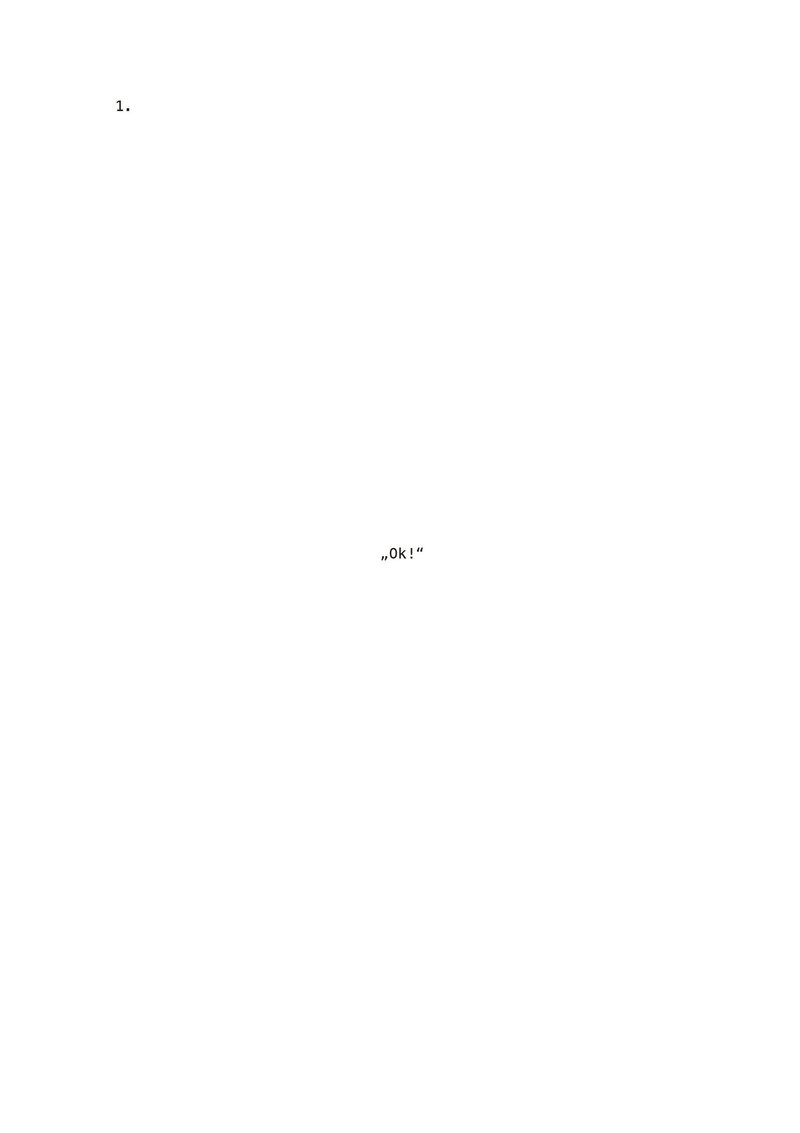
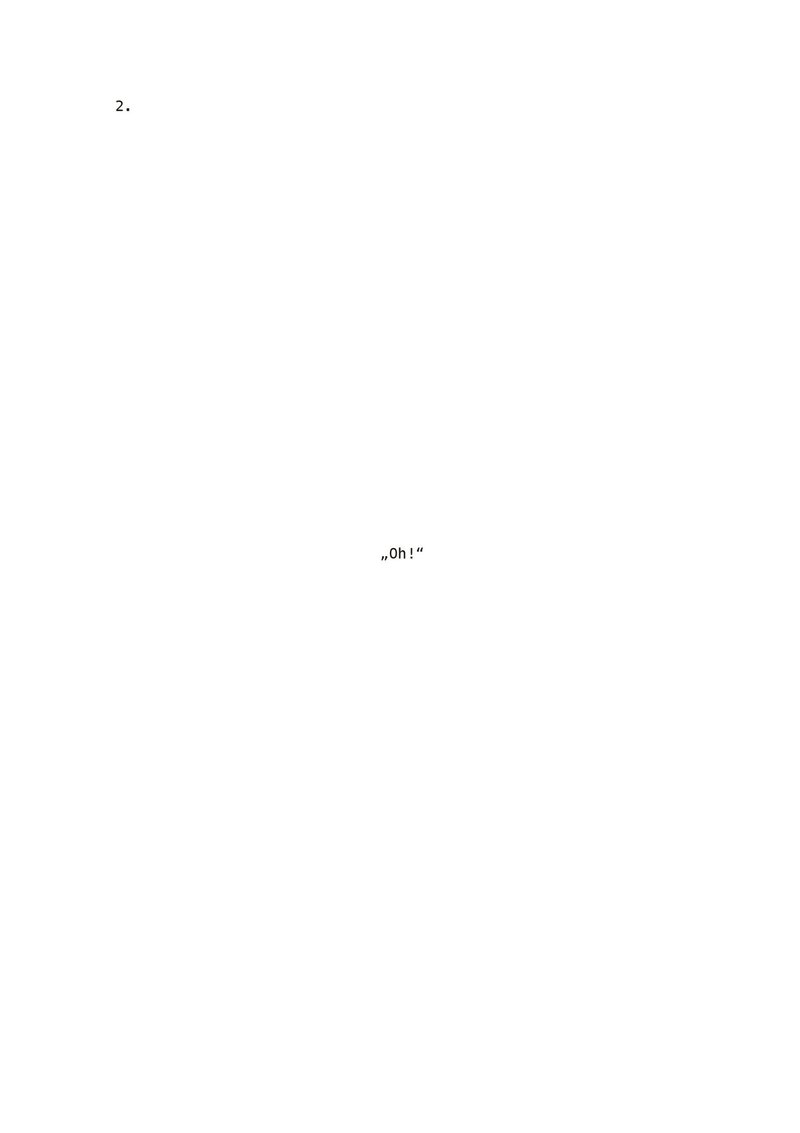


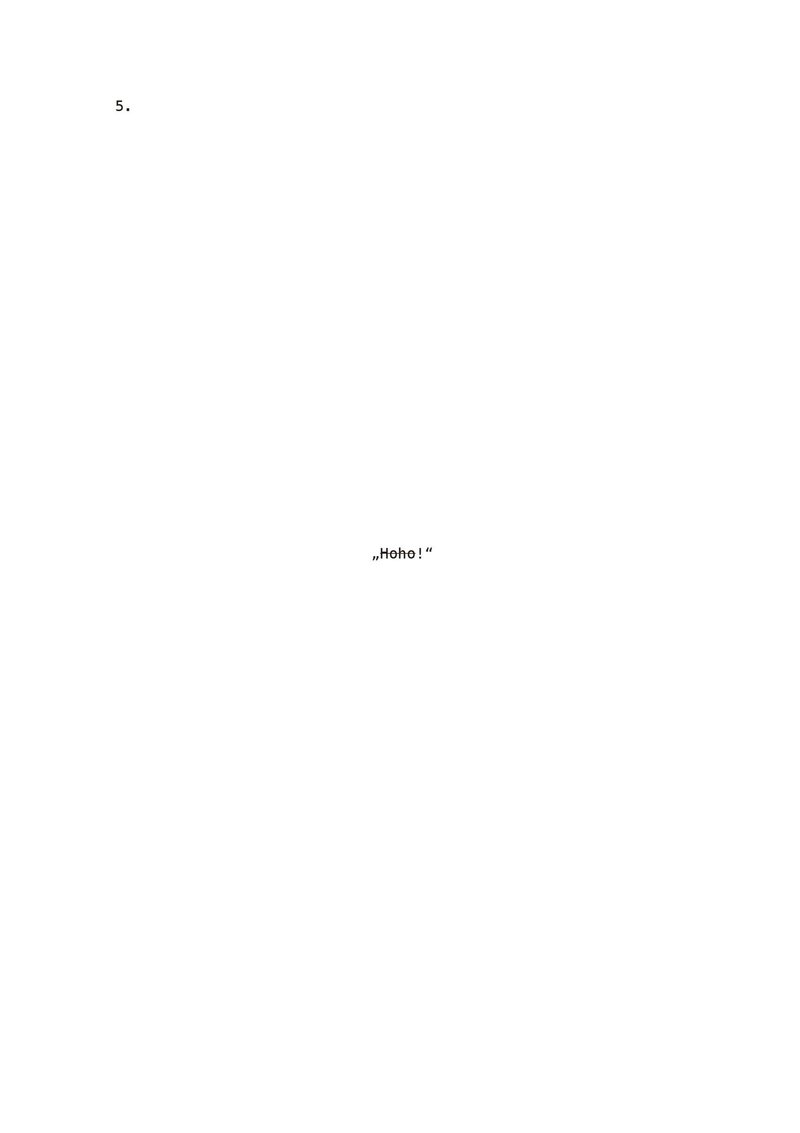
ジョークをわかってもらうためには図の解説をしたほうがよいかもしれない。
図1:スティックマンが机で車輪が五つある一本足のオフィスチェアに座り、二〇一九年度最優秀ジョークを絵に描こうとしている。
図2:どうも唯一の仕事道具の椅子の調子がわるいようだ。スティックマンは跪いて両手で椅子をひっくり返している。
図3:椅子の脚と座面がくっついていない。スティックマンは片手に座面をもう片手に車輪が五つある脚を持っている。この図は抽象的でとりわけ英語で描写するのが難しい。スティックマンはネイティヴスピーカーではないからだ。
図4:椅子の脚のアップ。と思ったら、実はスティックマンの腕と指だった!
図5:座面のアップ。それともスティックマンの口? 肛門? よくわからない。バツで消す。(ちなみにスティックマンがジョークのオチ考案に興味を失ったのは明らかだ。二〇一九年なんたらも諦めた)
サラ・リペット「煙がふわり」





読書案内
John Ashbery. “Flow Chart.” Knopf, 1991.
『ジョン・アッシュベリー詩集(アメリカ現代詩共同訳詩シリーズ)』大岡信,飯野友幸訳. 思潮社, 1993.
Mara Genschel のパフォーマンスビデオ “Mara Genschel_3 Ex-Texte”
https://vimeo.com/59395490
Sarah Lippett. “Stan and Nan.” Jonathan Cape, 2016.
Sarah Lippett のウェブサイト
http://www.crayonlegs.com/
Nikola Madzirov. “Remnants of Another Age.” Peggy Reid, et al, trans. Boa Editions, 2011.
Barnali Ray Shukla. “Apostroph.” India: RLFPA Editrions, 2017.
Han Yujoo. “The Impossible Fairy Tale.” Janet Hong, trans. Graywolf Press, 2018.
今回の執筆者
吉田恭子(よしだ・きょうこ)
1969年福岡県生まれ。立命館大学教授。英語で小説を書く傍ら、英語小説を日本語に、日本の現代詩や戯曲を英語に翻訳している。短編集『Disorientalism』(Vagabond Press、2014年)、翻訳にデイヴ・エガーズ『ザ・サークル』(早川書房、2014年)、『王様のためのホログラム』(早川書房、2016年)、野村喜和夫『Spectacle & Pigsty』(OmniDawn、2011年、Forrest Ganderとの共訳)など。
*****
この記事の収録書籍
『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』
青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税
ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行
文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。
http://www.kankanbou.com/books/essay/0431
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


