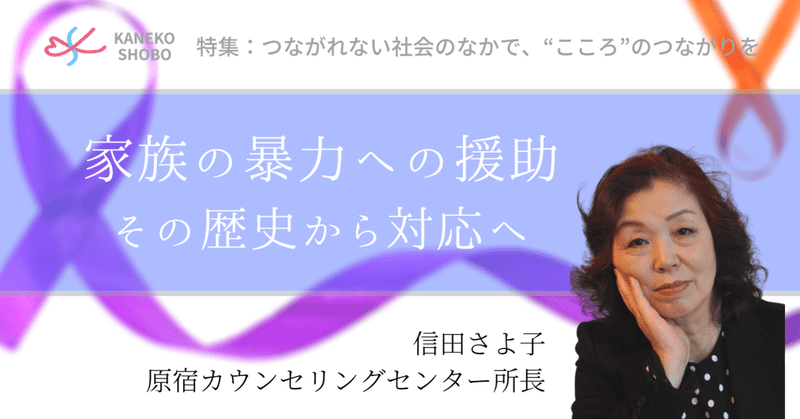
家族の暴力への援助 ~その歴史から対応へ~(信田さよ子:原宿カウンセリングセンター所長) #つながれない社会のなかでこころのつながりを
多くの国で外出しないで家にいることが一番の方策と考えられた今回、世界的な問題として浮上してきたのが、家庭内におけるDV(ドメスティックス・バイオレンス)でした。日本でその問題に早くから携わってきた信田さよ子先生に、世界での問題化に関連しての日本の対応、そして、これからの生活において忘れてはならない視点について語っていただきました。
はじめに
コロナ禍は測り知れない影響を世界中に与えるだろうが、その全貌をまだ私たちは予測すらできない時を過ごしつつある。他業種同様に、われわれ開業心理相談機関にとってもこれは大きな衝撃である。経済的なダメージは言うまでもなく、職業としての心理臨床の成立基盤が揺らいでいるのだ。三密と対人援助は切り離せるわけがないからだ。
現在DVに注目が集まっているが、こんなことはこれまでなかったので少し戸惑っている。これまで公認心理師・臨床心理士は、どちらかといえば家族の暴力の援助から距離を取ってきたことも述べておかなければならない。暴力という言葉を使用するのもためらってきたと言っていい。私のような臨床実践は同業者の中で少数派だったのである。

DVへの注目の背景
東日本大震災後も、DVの増加については半年以上経ってから少し話題になったくらいだった。災害時の性暴力については、最近初めてNHKでとりあげられたくらいだから(NHK「クローズアップ現代【性暴力を考えるvol.58】見過ごされてきた災害時の性被害」2020年2月28日)、男性が加害者であることが多い暴力に関しては、なかなかメジャーなメディアではとりあげられないことになっている。
夫が妻を殺害した事件が起きても、DVの有無に関してはほとんど触れられない。性暴力同様に、DVは男性主導の組織である主要メディアではあまり取り上げないのが通例だ。
ではコロナ禍におけるDVへの注目はなぜ起きたのだろう。ヨーロッパの都市封鎖(ロックダウン)中にDV相談が従来の130%に増加したという海外の報道を、NHKが大きく扱ったのがきっかけになったのではないだろうか(NHK「国際報道2020 世界がわかる 明日が見える 新型コロナ 外出制限長期化でDV増加」2020年4月13日)。

これはあくまで私の想像だが、感染拡大で報道現場が大混乱に陥っていたため、女性ディレクターの「ヨーロッパでのDV相談増加をとりあげましょう」という企画がすんなり通ったのではないかと思う。DV防止法が国会で成立した際も、当時複数の女性党首の存在もあり重要法案の隙を縫って可決されたという説を何度も聞かされたので、意外と信憑性があるのではないか。
非常事態だからこそ報道現場の隙をつくことができた「海外のDV増加報道」は、日本にも影響を与えた。これまで息長くDV被害者支援を続けてきたいくつもの女性団体が、日本も同様であるとしてDV相談窓口拡充の緊急対策を内閣府に要求したのだ。その結果内閣府が迅速にそれを実現したのである。驚くべき速度で「DV相談+(プラス)」が報道機関で流され、日本中に広がった(朝日新聞「社説『家にいて』DV防ぐ手立ても」4月22日、毎日新聞「新型コロナ SNSでDV相談 外出自粛で急増懸念、国がサービス開始 仙台のNPOにも切実な声/宮城」5月4日地方版など)。
電話やSNSによる相談窓口には4500件のアクセスがあったとされる。実際にかかわっている知人に聞くと、カウントされない相談を含めると9000件近いのではないかとのことだ。テレビを見ているとテロップで心のケアと並んでDV相談の電話番号が流される光景は、オーバーに言えば夢のようである。
家族の中には存在しなかった暴力
ここで少し歴史的に解説しよう。家族の暴力は多様であり複雑に絡まり合っている。誰から誰に対するものかによって、暴力と名付けられる順番があったし呼び名も異なっている。1970年代の早期から「家庭内暴力」と呼ばれたのは、子どもから親への暴力だった。おそらく80年代までは心理臨床家たちは、家族における唯一の暴力は子どもから親へのそれだと考えていただろう。だからこう呼んだのだ。
90年代に入ってから初めて子ども虐待に注目が集まるようになった。しかし主たる担い手は福祉職やソーシャルワーカー、小児科医たちであり、そこに心理臨床家は入っていなかった。95年にはドメスティック・バイオレンス(DV)という言葉が草の根的な女性支援運動の担い手だったフェミニストたちによって日本でも使用されるようになった。21世紀になると高齢者虐待として成人した息子(時には娘)から親への暴力もクローズアップされるようになった。このようにひとつの家族において、暴力と定義されるに至る順序があったこと、そこには家族における力関係(権力関係)が大きく働いていたことを忘れたくはない。極論すれば1980年代までは、親が子に行う行為はしつけ以外のなにものでもなかったし、夫が妻を蹴ったりこぶしで殴ってもそれは不思議ではない光景だったのである。

アディクションと暴力は不可分
2001年DV防止法が制定される直前に、私は「DVと虐待」(医学書院、2001)を上梓した。当時臨床心理士で家族の暴力全体にかかわることを表明した人はいなかったのではないか。もちろん同業者からの反応はほとんどなく、その本を読んでくれた人たちの多くは当事者(DV被害者)かフェミニストたち、DV被害者支援員だった。
別に私が変わり者だったわけではなく、たぶん1970年代からずっと依存症(アディクション)臨床に地道にかかわってきたことの一種の必然的帰結だったと思う。
1995年に原宿カウンセリングセンター(以下センターと略す)を開業して以来私が目指してきたのは、保険診療のシステムの外部で、非医療の立場から経済的基盤を確保してカウンセリングを実施することだった。アディクションは、他の精神障害とは一線を画すことはよく知られている。何より本人はアディクションを手放すことに抵抗し援助希求に至らないので、周囲の家族をまず援助対象としなければならない。さらに、アディクションをやめ回復を目指す当事者から学び、その知恵と経験の塊である自助グループとの付き合い・連携が必須だ。いずれも疾病本人を対象とする精神科医療システムには馴染まない。われわれのような相談機関はアディクションを専門にすると謳うことで医療機関と対等にわたりあえる、そう考えたのだ。
またアディクションにかかわっていると、女性たちが酔った夫から殴られ続け、AC(アダルト・チルドレン)と自己定義した人たちが、何十年も前の親の虐待記憶に苦しんでいるという現実に出会わざるを得ない。暴力と呼ぶしかない行為が、アルコール依存症の家族では無数に起きていたのだ。

自己救済のためであれ単なる気持ちよさからであれ、ある行為が習慣化することで結果的に自己破壊に至るドラマティックなプロセスがアディクションである。そこには必ずといっていいほど、絶望的なほどに他者を巻き込んでいく姿が見え隠れする。明暗のはっきりした暴力と愛憎劇には、ジェンダーや親子の権力関係なども織り込まれている。アディクションと暴力は、分離不可能な問題なのだ。そして、精神科医療が取りこぼさざるを得ないのも暴力である。保険診療のシステムにおいて、手間暇のかかるアディクションや暴力は対象から除外されがちなのだ。いっぽうで、カウンセリングにまつわるイメージは悩み相談や心のケアであり、おまけに高額だと一括りにされてしまう。しかし、センターはそのやさしげなイメージの向こうにあるアディクションや暴力といったハードな問題を積極的に扱うことで、なんとか25年間存続してきたのである。
司法と医療のはざまで
「暴力」とはもともとは司法の言葉である。裏側には犯罪という意味が刻印されている。加害・被害というパラダイムは警察や裁判所といった司法(フォレンジック)の世界で用いられるものだった。司法精神医学、司法心理学と銘打たなければ、精神科治療や心理臨床の世界のパラダイムには馴染まない。中でも個人心理療法を実施する立場からは、暴力という言葉を用いることは少ないだろう。言葉がなければそれは存在しないことになる。アルコール依存症という言葉ができる前は、酒好きという表現しかなかったのと同じである。
家族において、殴られる妻や親に殺される子どもはずっと以前から存在した。そのような現実を前に、暴力という言葉を使わなければ、殴られたり首を絞められたりする人たちの「被害」を看過することになる。「被害」を見過ごすことは、「加害」の容認につながるのである。
おそらく明治時代に近代医学が導入された際に、ともに人間を拘束できる刑務所と精神科病院は厳しく峻別されたのだ。中立的科学的医療と犯罪を処罰する司法との境界が、そのまま臨床心理学において「暴力」を対象とすることへのためらいにつながってきたのではないだろうか。

カテゴライズとロードマップ
ではDVの援助とは何か。センターではDVにまつわるクライエントの主訴を加害者・被害者・心配者の三つにカテゴライズしている。一般的にはDV援助=被害者支援になっているが、それは一面的だ。配偶者への行為を変えたい、妻が家を出てしまったという男性が来談すれば、DV加害者としてカウンセリングを実施する。また自分の娘が配偶者の暴力から逃れて実家に戻ったという母親が来談すれば、DV心配者としてカウンセリングを実施する。このようにDV援助とは、加害者も被害者も、そして周囲の家族(友人)も対象とするべきだろう。さらに面前DV(親のDVに曝されるという心理的虐待)の被害を受けて育った人たちのケアも含まれる。このようなカテゴライズに加え、援助機関のネットワークの知識も必須だ。
これら関係の広がりに加えて、ロードマップが必要となる。つまり時間軸の設定だ。DVについては、加害も被害も含めて長い時間軸の中で援助の見通しを持たなければならない。発見から名づけ、介入といったプロセスは一言では言い表せない。このような空間的・時間的視座を含めて、私は「DVの包括的援助」と呼んでいる。そう名付けなければならないほど、DVは虐待から分断され、心理職からも忌避され、メディアからも避けられてきた。被害者支援だけでは不十分と考えて、15年間ずっとDV加害者プログラムにかかわり続けているのも、あまりの冷遇に対する憤りからかもしれない。冒頭で述べた戸惑いもご理解いただけるのではないだろうか。

DVにまつわる誤解
大きな虐待死事件があるとメディアの取材を受けることが多い、そのたびに内心いやになるのはあまりの無知に対してだ。記者や編集者ですらこうなのだから、一般の人の知識は推して知るべしだ。
DVに関して最大の誤解は、殴られている女性は「私はDV被害者だ」と思っている、殴っている男性は「これはDVだ」と思っている、というものだ。実際は違う。当の本人たちは愛情や正義といった価値観の中で暮らしており、暴力という視点はほとんどない。正しい行為、正義の鉄槌をふるう夫、私が間違っていたからだと自分を責める妻という構図しかそこには存在しない。痛みや屈辱感はあったとしても、収容所同然の家族において正義は夫なのである。DV加害者は「どうして俺を怒らせるんだ」という常套句を述べ、妻のせいで「殴らされた」という被害者意識に満ちている。それと対照的に、DV被害者は「自分が怒らせた」「私が至らなかった」という加害者意識と自責感に満ちている。こんな逆転した構図がDV関係にある夫婦の実態なのだ。

権力という視点
コロナの自粛下で行動制限される人たちは感染防止とはいえ、行動の自由を奪われている。DVも同様で、妻の言動は夫によってすべて定義されることになる。正しい間違っている、愛情が足りない、母として妻として不適格だ、はすべて夫によって判断される。このような「状況の定義権」こそ「権力」であると言ったのはフランスの哲学者M. フーコーである。そこに「暴力」という視点の入り込む余地はない。
だからこそ、外部から介入する必要が生じる。オルタナティブな定義「それは暴力だ」をすべりこませることで状況は変わる。そこから始めなければ、ただ逃がすだけでは不十分なのだ。私はDV被害者なのだ、という当事者性をもつところからしか被害者支援は始まらない。
DV加害者プログラムも、何が暴力かという定義から始める。彼らは心底正しいことをしている、妻はすべて自分を受け入れるべきだ、という価値観をもって生きてきた。そこからどのようにして「妻も人間である」というリスペクトする関係に至るかが、加害者プログラムの根幹となる。結婚にまつわるジェンダーの視点、男性性にまつわる常識、そこには無自覚な権力性が存在すること…といった点も、DV加害者プログラムの大きな柱となる。

冷静と熱情
国難の際に、最後の砦として期待されるのが家族である。ゆりかごから墓場までを保証してくれる家族は、愛情という名で粉飾されている。2011年3月11日の東日本大震災のあとに多用されたのが「絆」であり、それの具現化が家族であった。そしてコロナ禍においても、ソーシャルディスタンスが叫ばれ、三密を避けて「ステイホーム」=おうちに居よう=家族と過ごそうが連呼されたのである。日本という国を襲った二つの大きな災禍において、家族擁護の言説のもつイデオロギー性が等しく発露しているかに見えるが、よく考えてみたい。
ここで思い出すのが、DV加害者プログラムに長年参加していたひとりの男性の言葉だ。
「Stay homeっていやな言葉ですよね。僕はパートナーにいつもStay calmだよって言ってるんですよ」。Calm=冷静でいようと彼は日々努めているのだ。カッとすることもある、でもその時はその場から離れる、反射的な言葉を返さないように3秒数える、などだ。こんな目先の対応はともすれば単なるスキルに過ぎないと思われがちだが、「我慢が肝心」といった精神論よりはるかに確実な行動変容だ。繰り返すことで習慣化し身に着けることもできる。もうひとつはカッとする背景となる無自覚にこびりついた考え(信念・認知)を洗い出すことだ。妻なら当たり前、妻だけは大丈夫といった考えがありはしないか。パートナーは対等な存在だという理念を掲げている男性ほど、一皮むくと妻に対して実に無邪気で信仰に近い菩薩幻想を抱いているものだ。過大な期待通りに妻が動かないと、勝手に被害者意識を抱いて暴力的になり責めるというのも、ありふれた姿である。
このように行動と認知の両面から取り組むことで、かろうじてCalmは保たれる。冷静と熱情の対比は、距離と密着のそれと同じではないか。つまりCalmは必ずディスタンスを伴うのだ。加害者プログラムで学んだ男性たちは、コロナ禍にあって自分たちが努力しなければ家族は崩壊してしまうかもしれないという危機感を抱いている。この危機感があるかないかによって、ウイズコロナの家族は崩壊か存続かの両極に分かれるだろう。

おわりに
アディクションの家族援助において、家族成員それぞれが共存していくためのキーワードは距離と境界だった。離れることが必要というのが長年のカウンセリングの基本だった。愛着や愛情という言葉を警戒してきたのは、距離や境界と二項対立的になりがちだったからだ。ウイズコロナの時代にあって、ディスタンスが叫ばれることに私は違和感はない。これまでの援助の延長線上に過ぎないからだ。家族の暴力を防ぐためにも、その被害を最小限にするためにも、パートナーや子どもとの距離がどれほど大切かは強調し過ぎることはない。
絆はディスタンスによって支えられ、ディスタンスによって生まれる絆もある、日々変化するコロナ感染状況の渦中で、そう再確認している。
(執筆者プロフィール)

信田さよ子(のぶた・さよこ)
原宿カウンセリングセンター所長。アルコール依存症、摂食障害、DV(ドメスティックバイオレンス)、アダルトチルドレン、児童虐待など、なかなか社会的に認識されづらかった課題について、早くから問題点を指摘し積極的に取り組んできた。『〈性〉なる家族』『母が重くてたまらない~墓守娘の嘆き』(春秋社)など、多数の著書がある。

