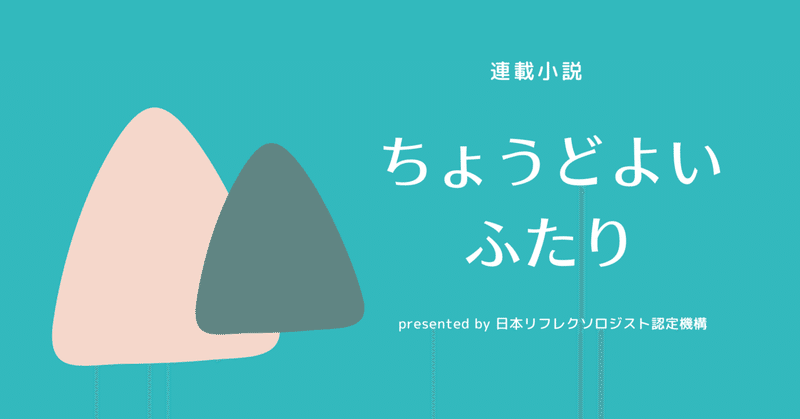
第28話 カニ尽くしと生き返り大作戦 | 2021年12月
甲本結季は果穂のリフレクソロジーのサロンで施術前にフットバスで足をあっためていた。冷え切って金属の棒のようになっていた足がお湯で溶かされていく。結季は久しぶりに自分の体を取り戻したような気持ちがした。
「生き返った」
結季が言うと、
「ゾンビみたいなこと、言わないでよ」
と、果穂が返した。
「いや、ゾンビはそんなこと言わないと思う」
思わず結季は真面目に突っ込んだ。ゾンビは生き返らないし、そもそもしゃべらない。
(でも、確かに、ゾンビみたいだったかも)
結季はここ最近の自分の生活に思いを馳せた。ここしばらくは湯を溜めるのが億劫で、毎日シャワーで済ませていた。しかも、そのことに何の疑問も抱いていなかった。シャワーで十分だと思っていたのだ。必要性を感じていなかった。
果穂のリフレクソロジーに来たのは、幸彦からのちょっと早いクリスマスプレゼントだった。恋人からのクリスマスプレゼントと言えばアクセサリーが定番だが、仕事をやめて無職になった結季にはピンとこなかった。おしゃれに興味がなくなったのだ。人に会わないし、ちゃんとする必要もないから、新しいアクセサリーも服もバッグもいらない。欲しいものもしたいことも何も思い浮かばない。
そう正直に言うと、幸彦の支払いで果穂に予約を入れてくれた。結季には思いつかなかった、気の利いたプレゼントだった。結季は幸彦を見直した。
「タオル、椅子の上に置いてあるから。あったまったら、足拭いてこっち来てね」
果穂のおっとりとした声が聞こえる。
「あったまるの、もう少しかかるかも」
そう言って、結季は目をつむった。
(幸せから離れると、何が幸せだったのかも忘れてしまうのかもしれない)
温まった血が全身をめぐる。体がほかほかして、心も優しく柔らかくなっていく。
(生き返って初めて、死んでたことに気づくんだ)
気づいてよかった。結季はゾンビから復活したことに安堵して、大きく深く息を吸った。
台の上に仰向けに寝転がると、
「アロマ、いつものやつでいい?」
と、果穂が訊いた。結季の好きな甘くて華やかな香りがふわりと漂う。香りに包まれて心が浮き立ち、胸の中が明るく照らされるようの感覚が、なつかしかった。
「世の中にいろいろな香りがあること、何だか忘れてた」
「マスクしてるからね」
果穂のあたたかな手が足をゆっくりと滑っていく。少しずつ五感が取り戻されていく。まだまだ生き返り足りなかった。まだまだ、もっともっと、人間になれる。
「クリスマスプレゼントがリフレだなんて、ゆきちゃんもやるね。わたしも男の人に営業しようかな。大切な人へのプレゼントにどうですかって」
果穂は、幸彦のことも結季のことも、ゆきちゃんと呼ぶ。発音も同じだ。だけど不思議と、どちらのことを指しているのか、結季にはすぐわかる。
「幸くんからプロポーズされちゃった」
「・・・・・・ふぇっ?」
「え? 今なんて?」
「ごめん、変な声出た」
果穂が笑う。笑いながら、ごめんごめんと謝る。
「ゆきちゃん、大人になったんだなあって思って。なんかおかしくて」
「あ、でも、プロポーズっていうか、なんか、そういうちゃんとしたやつじゃないんだけど」
結季は慌てて付け加える。自分の口が軽いせいで、幸彦が果穂に笑われるのは、さすがに申し訳なかった。
「ちゃんとしたやつじゃないって、どんな?」
「山頂で一緒にお弁当、三百回食べようって」
「わあ、何それ! すごい! いいじゃない!」
果穂がついに手を止めてゲラゲラ笑い始めた。笑いのツボに入ってしまったらしい。もう止められない。
(幸くん、ごめん)
結季は心の中で謝った。
「で、どうするの?」
「ええっと」
意外に早く矛先が自分に向いて、結季は焦った。自分からこの話題を切り出したくせに、何も考えていなかった。
「幸くんがどうこうっていうより、結婚ってなんだかまだよくわからない」
「わたしもまだわからないな」
「えっ、嘘?」
年上で既婚者で子どももいる果穂が、そんなことを言うなんて結季には予想外だった。
「今だって、結婚して本当によかったのかなあって、ときどき思うよ。戦場カメラマンとして世界中を飛び回っていた剛くんのこと、縛りつけちゃってるし」
聞き捨てならなった。施術の途中なのに、結季は体を起こした。
「そんなことないよ」
「そうかな?」
「そうだよ」
自信たっぷりに結季は言い切って、再び台の上に寝ころんだ。正直言って、果穂の夫である室田剛のことはあまり詳しく知らなかった。何度か会ったことがあるが、しっかり話したことはない。幸彦経由で話を聞くくらいだ。
でも、配偶者に縛り付けられているなんて思う人じゃないという根拠のない確信があった。きっと果穂だって、そう思ったから結婚したに違いない。
(果穂さん、疲れているのかもしれないな)
と、結季は心配になった。そして疲れていることにも気づいていない。果穂もまたゾンビになっている。
(リフレが終わったら、果穂さん生き返り大作戦、決行だ)
そう決意すると、わくわくして、エネルギーが湧いてきた。頭の中もすっきりした。
目を閉じる。心地よい刺激に身を任せながら、まずは自分をしっかり生き返らせなくては、と結季は思った。
■▢
果穂の運転でドライブに行くのは、いつぶりだろうか、と幸彦は考えた。果穂に連れ出された時はたいてい冬だった。最後にドライブしたとき、果穂はまだ結婚していなかったし、幸彦も大学生だった。そして、そのときは後ろの座席には誰もいなかった。
いま、幸彦は助手席に座っていた。後部座席には、室田剛と結季がいる。彼らの真ん中にチャイルドシートに守られた繋がいる。両側からあやされてご機嫌である。こんな配置になったのは、ナビをできるのが、幸彦だけだったからだ。カーナビはついているが、それだけでは不安らしい。結季は免許をもっていないし、室田は国際免許を持っていたが、日本の交通ルールはよくわからないと言うので危なっかしくて任せられない。
幸彦が運転するという手もあったが、全員に反対された。免許を取ってからほとんど車に乗っていないからだ。
行先は、近場の温泉宿だ。レンタカーの予約から宿まで、結季が全部手配した。
「ゆきちゃん、すごかったんだよ。どんどんわたしから希望を聞きだして、あっという間にプランを作ってくれたんだ。繋がいるから旅行なんて無理だと思ってたのに」
運転しながら果穂が言った。上機嫌だ。ゆきちゃんというのは、幸彦のことではなく、結季のことだ。小さな子がいても快適に楽しめるちょうどよいプランをオーダーメイドで設計し、果穂にプレゼンして、旅行に行く気にさせたらしい。
「温泉に入って、おいしいご飯を上げ膳据え膳してもらって、あったかい部屋の中でごろごろしながら庭からの景色を堪能できるなんて、本当最高」
果穂が言った。
「でしょー?」
「一棟貸し切りだから繋も部屋の中で走り回れるし、遊ぶスペースも用意されているみたいだし」
「今夜はカニだよ」
「そう、カニ尽くし!」
盛り上がる女性たちの側で、室田が苦笑いしている。幸彦は罪悪感を覚えた。果穂に気分転換してもらいたいから、どこか家族旅行をしたいと室田に相談されたのは、数か月前のことだった。そのとき、幸彦は登山を体験したばかりだったから、アウトドアの素晴らしさを力説したのだ。
その結果、室田はキャンプに行くことを果穂に提案し、楽しそうだけど子連れでは無理だと却下された。室田は夫としての株を下げ、果穂の閉塞感は一層強まり、試みは逆効果に終わったのだ。
「結季ちゃんのプランの立て方、勉強になるな」
室田が真面目に言った。
「自分に子どもがいるわけじゃないのに、いろいろ気を回せて偉いよ」
「わたし、そういうの、好きなのかも。相手のニーズに合わせて考えるのとか」
結季が言った。
そういえば、いつか台湾旅行に行ったときも結季が全部プランを考えてくれた。幸彦と結季とそれぞれの母親という奇妙なメンバーの旅行が心底楽しかったのは、結季の絶妙なプランのおかげだった。
「そういう仕事したら?」
「ツアーコンダクター?」
「うーん、それもだし、旅行だけじゃなく、相手の願いを叶える仕事」
ぷっと果穂が噴き出した。
「それ、ほとんどの仕事にあてはまるよ」
「確かに」
幸彦と結季が同時に言った。
「でも、なんか、そういう方向性で仕事探してみる。室田さん、ありがとう」
「いや、俺は別に何も」
晴れ晴れとした結季の声を聞きながら、幸彦は自分の仕事にも思いを馳せた。幸彦の仕事は、編集者として本を作り読者のもとへ送り届けることだ。書きたい人がいて読みたい人がいる。これも、願いを叶える仕事と言えるかもしれない。
「最近気づいたんだけど」
結季が言った。
「人って、忙しかったら、願いが思い浮かばなくなるんだと思う。願ってもいいのに、願うこと自体を忘れてしまう。だから、わたし、願うことを思い出してもらえるような、願う力を取り戻せるような、そんな仕事ができたらいいな」
「すごくいい」
室田が力強く肯定して、結季が照れたように笑った。
(そんな話、俺にはしたことないくせに)
幸彦はちょっと嫉妬した。でも、結季と室田が仲良くしゃべっているのが嬉しかった。まるで家族みたいだ、と思った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
