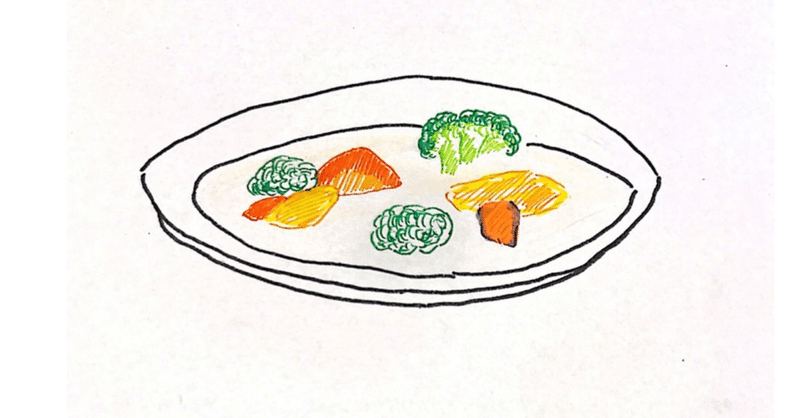
真夏のクリームシチュー(後編)【短編小説】
太陽が沈んでも外にはねっとりとした暑さの膜のようなものが残っていた。
サイドカーに乗ると地面が近くて、日中温められたコンクリートの熱が伝わってくるようだった。
「さてと、それじゃあまずはスーパーを回ってみるとするか」
「でも、シロヤマさんはスーパーには売っていないって」
「聞き込みが必要なのさ。父さんが迷子を探すときに手がかりなんてほとんどないようなものさ。まずは情報を集めないとな。その情報は『たぶん』や『かもしれない』みたいな本当に小さなものでいい。一滴の絵の具から一枚の絵画のような全貌を掴むのが腕の見せ所でもある」
陽光町には中規模の地域密着型のスーパーが二軒、コンビニだって適当に歩いていても出くわすくらいにはある。けれども、そのどこにもクリームシチューは売っていなかった。
まるで夏にはその姿が見えない魔法がかかっているみたい。
二軒目のスーパーで品出し中だった店員さんにどこかに売っていないか尋ねてみる。
「うーん。〈ゴールデン・シチュー〉なんて聞いたことがないなぁ。ここら辺であるとしたらサムエ婆のところでしょうか。小さいお店なのになんでも揃うらしいと噂ですよ」
「サムエ婆、ですか」
父さんが素っ頓狂な声で聞き返す。
無理もない。シチューのルウのありかを訊いたら、斜め上の返答だったのだもの。
「小学校の裏手にある細い道の先に食料品をを売っているお店があるんですよ。そこのおばあちゃんが、名前が寒江さんなのでね、サムエ婆の愛称で親しまれているワケなんですけれど」
「そのお店の名前は何というのですか?」
「ええと……。あれ? 何だったっけかな? あれ? ごめんなさい。ど忘れしちゃって。サムエ婆の店と呼んでいるものだから。ごめんなさい、お役に立てなくて」
「とんでもない! ありがとう。とりあえず探してみることにします」
忙しいなか私たちの奇妙なお願いに真摯に対応してくれた店員さんにお礼を言って、サイドカーは再び町を走る。
この地面の近さと顔に吹き付ける強風にも慣れてきた。
店員さんの言っていた小学校とは私も最近まで通っていた陽光小学校のことだろう。この町にある小学校はそこだけ。この町の子どもたちはみなそこで遊び、学んでいた。
小学校の裏手、大きな校舎の影に隠されるようにひっそりと存在する小道。日中でも薄暗いような不気味で、一人だったら尻込みしてしまいそうな道。
「狭い道だな。バイクはギリギリじゃないか。バイクを傷つけたくはないけど、バイクを置いておけるような場所もないしなぁ」
父はともすれば神経質なくらいに慎重にバイクを押して歩いた。
民家の庭の木が道路の上にまで覆い被さって天然のトンネルをつくっている。木葉に隠れるようにして「寒江食料品店」の看板。
お店は冷蔵庫の中にいるみたいにキンキンに冷えていて、夏だということを忘れさせた。レジの奥に座ったサムエ婆の頭の上にある小さなお店には不釣り合いなほど大きなクーラーがごうごうと冷気を吐き出している。
「こちらにシチューのルウがあるとお聞きしたのですが」
「シチューだって? この暑いなかそんなモノを求めてやって来るなんて相当な物好きだね」
「はあ。そうかもしれません」
サムエ婆の迫力に気圧されたお父さんがたじろぎながら言う。
「まったく。夏にシチューだなんて信じられないよ。暑い日にどうしてシチューのことなんて考えなくちゃいけないのさ。アタシは暑いのが大嫌いなんだ。クリームシチューは寒い日に食べるからいいんだ。そうだろう?」
おばあさんに見つめられた私はあまりの圧力に黙ってコクコクと頷いた。本当はここでシチューを食べたならおいしいだろうなと思った。
サムエ婆は「夏にシチューなんざ、サウナの中で食べてるのと変わらないさ」とかなんとか言いながら、陳列棚の向こうへ消えたと思ったらルウを手に戻って来る。「ゴールデン・シチュー」と書かれた金色の箱。
「ああ。ありがとうございます。でも、どうしてこれが?」
「ふん。どうしてかって? ここは欲しい物はなんでも揃うのさ。ただし、食べ物に限るけどね。それがたとえ、めったに流通していないような特別なものでも。欲しいものを買いに行って目当てのものを買えずにトボトボ帰ることほど虚しいこともないだろう? 長く生きていればそんなこと沢山あろうが、私はもう耐えられなくなっちまったのさ。せめてアタシの店にやってくるお客にはそんな思いはさせないようにと思ってね」
私は欲しかった漫画が売り切れていたときの帰り道を思い出す。何も持っていない手は「僕の役割はないんですね」とでも言いたげに、いつもより大げさにぷらぷらと前後する。そんな帰り道は決まっていつもより長く感じた。
もし、今の季節、炎天下を歩いて空振りだったときのことを想像するとゾッとする。私はサムエ婆が急にいい人に思えてきた。
「あの。ありがとうございました」
「……こんど、夏に食べるシチューの感想を教えておくれ」
お店を後にするときに、サムエ婆がぶっきらぼうにそう言った。
「ええ、必ず」
*
ちょうど帰宅していた母も合流して白雪堂へと戻る。
シロヤマさんは3時間前と同じ、扇風機の当たる場所でテレビを見ていた。
「おお! それは〈ゴールデン・シチュー〉ではないですか。まさか本当に手に入れてくるなんて」
「まあな。さっそくシチューをお願いできるかな」
「お任せください」
「この暑い中、シチューを食べるの?」
と小声で母。
「そういう約束になっていたの」
私と母は未だに真夏のクリームシチューに半信半疑。
シロヤマさんはさっそく厨房に入り、カチチチっと火をつけてクリームシチューの準備を始めている。
目の前に現れた白いお皿の中のクリームシチュー。
真っ赤な顔で汗をダラダラと流しながら食べたシチューはおいしかった。
3人で口を「はふはふ」させながら、「夏に食べるクリームシチューも悪くないね」と言った。
![]()
<前の話 真夏のクリームシチュー(前編)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
