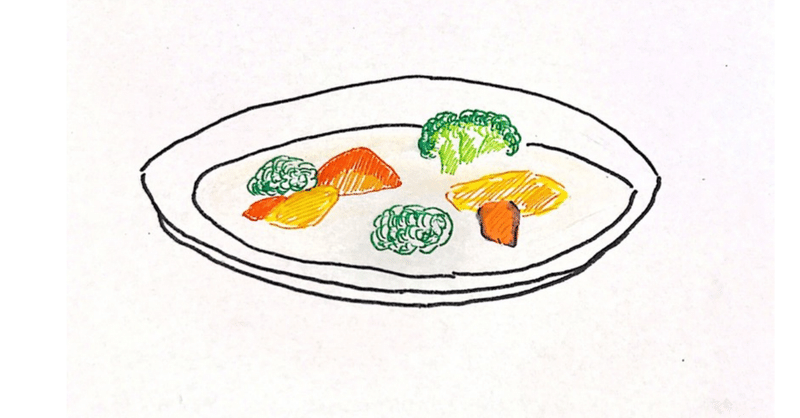
真夏のクリームシチュー(前編)【短編小説】
黒い服に黒革のリュックサック、リュックの中には黒い装丁の本が数冊。
昔から洋服や身に付けるものは黒が好きだった。
黒い色は不安なことや嫌なことを吸い込んでくれるような、そんな気がして心が安らいだ。
黒い色はまた真夏の照りつける太陽もよく吸収した。蒸し暑い夏空を行くには全くと言っていいほどむいていなかった。黒い服は夜に紛れるためにある。
暑い。私自身が小さい太陽になってしまいそう。
赤信号で自転車を停め、首筋を伝う汗を拭う。
こんな日は何か冷たいものでも食べたい。げっきょくにかき氷屋さんやアイスクリーム屋さんなんかが来てくれていれば最高だったのに。
シノノメコーポの一階には季節外れの「クリームシチューはじめました」の貼り紙。8月にクリームシチューが始まるのだとしたら、いつクリームシチューは終わったのだろう? 私の家ではだいたい5月くらいにクリームシチューやおでんとはしばしお別れする。そして、また肌寒くなった頃に満を持して帰ってくる。
つまり、クリームシチューを味わうには寒さというものが一つの重要な要素なのであって、夏に食べる気にはどうしてもなれなかった。
その夏にシチューを出すレストランの名を「白雪堂」という。
黒い暖簾に名前の通り雪のように白い文字。
店内には古いタイプの扇風機が一台。懸命にけたたましい音を立てて首を振ってはいるものの一台では荷が重そうだった。ちなみにクーラーはない。
だから白雪堂でシチューを食べる人たちはふぅふぅと額に大粒の汗を浮かべながらスプーンを口に運んでいた。
レストランから出てくる人たちは口を揃えて「夏に食べるシチューっていうのも案外いいものだね」と言い、また太陽の下へと出ていく。
そんな様子を私は日陰からたびたび目にしていた。
私は父と母との3人暮らしである。
が、父は仕事の都合上、よく家を空けることがあった。基本、食事は母と二人きりだった。
父は迷子を探すのを仕事としているらしい。ここで言う迷子とは人だけにとどまらずペット、ものまでありとあらゆる迷子を探していた。
私が「それって探偵みたいなこと?」と訊くと「探偵とは少し違うな。父さんは浮気調査も事件の推理もできない。ただ迷子を探すことにかけてはどうも才能があるみたいだ」そう言って少し考え込むような仕草をする。
「父さんの仕事に名前をつけるのは難しいなぁ。もしかしたら父さんはこの世には名前のない仕事をしているのかもしれないな」
この世には名前のない仕事をする父は一ヶ月ほど前に中東のとある国の王様の大切にしていた宝石が迷子になったから、探してくると行ったきりまだ帰ってこない。
父は今どき珍しく携帯電話を持っていなかった。「なるべく身軽でいたいからな」と時計すら身につけていない。そのためよく約束の時間に遅刻した。ポッケに必要最低限のお金の入った財布と知恵の輪だけを持っていた。父は時間を持て余すとポケットから知恵の輪を取り出してカチャカチャとやっていた。
「これはずーっと挑戦しているんだが、なかなか解けないんだ」と父のポケットには知恵の輪がもう何年も入ったままだった。
*
シノノメコーポの駐輪場に見慣れたサイドカーが居座っている。父が仕事で使っているものだった。
一匹狼を気取る父は仕事上の相棒などいないのだが、父曰く、「見つけた迷子を運ぶにはこれが一番スタイリッシュなのさ」と言うことらしい。
「スズ、ただいま」
家に帰るとやっぱり父が帰ってきており、ソファに仰向けに寝転んで顔だけをこちらに向けていた。中東帰りの父は真っ黒に日焼けしていて——ひと月ぶりということもあって——一瞬誰だかわからなかった。伸び放題のヒゲは顔の半分くらいをもじゃもじゃにしている。出発した一ヶ月前から一度も手入れをしていないように見えた。
「うん。王様からの仕事は終わったの?」
「ああ、あれな。うん、まあ解決したよ」
「そう」
せっかくお父さんが帰ってきたのだけれど、今日はお母さんが夜遅くまで帰ってこない。残念ながら久しぶりの一家団欒とはいかなそうだった。
「何か食べに行くか」
ソファから起き上がった父が呟いた。
「うん」
時刻は4時。夏の空は依然として真昼のように明るい。
普段の夕飯の時間よりもずいぶんと早かったが、私もお腹が空いていたので頷いた。何より外食というのが嬉しかった。
父は料理が下手だった。父の作る料理は大雑把な父の性格を見事に反映していて、たいていの場合、塩辛いか全く味がしないかのどちらかだった。母は「塩辛いのはどうにもならないから、せめて薄味にしてほしいわね」と言いながら父の作る薄味のチャーハンに自分で味付けをしていた。
白雪堂の店内にお客さんはおらず、店主のシロヤマさんがテーブルに座ってテレビを眺めていた。
シロヤマさんはいつでも真っ白でシミ一つないコックコートを着て、ウンと背の高いコック帽をかぶっている。厨房はとても暑いはずなのにシロヤマさんは汗一つかかないでシチューの鍋をかき回していた。
「いらっしゃいませ」
大きな音をさせながら回る扇風機にかき消されそうな声でシロヤマさんは言った。
「2人、大丈夫かい?」
「スミマセン。実は私が愛用していたシチューのルウが無いんです。〈ゴールデン・シチュー〉という商品なのですがね。これは私の知り合いの社長に無理言って作ってもらっている特別製で、ごく少数のお店にしか出回っていないのです。おそらく、普通のスーパーの棚には並んでいないでしょう。工場のマシンにトラブルがあったらしく、お昼の営業で店にあった在庫も底をついてしまいました。しかし閉店する勇気も出ず、せめてやってくるお客さんに誠心誠意、わけを説明しようと……」
しきりにペコペコと申し訳なさそうにシロヤマさんが頭を下げる。
肝心のシチューがないのにお店を開いて、こうしてやって来たお客さんひとりひとりに説明していたなんて。律儀なのか、不誠実なのか、よくわからない人だ。
壁に貼られたたくさんのメニュー名——チキン、ほうれん草、シーフード、かぼちゃ、鮭のシチュー——が扇風機に煽られて寂しげにヒラヒラと揺れている。
夏でもメニューを見て想像するぶんにはおいしそう。でもルウが無いことには何も始まらない。
ただ、何かを始めようとしている人が一人。
「ほう。つまり、シチューのルウが迷子になっているというわけですな」
お父さんはもじゃもじゃにたくわえた顎髭をつまみながら、そう言った。
普段はぐでーんとした目つきも急に鋭くなって、休日の父から仕事の父の顔つきに変わっている。
こういうところはちょっとカッコイイと思う。口には出さないけれど。
「……迷子ですか? まあ、迷子と言えば迷子かもしれませんね」
迷子なのではなく、在庫切れでしょうと心の中でツッコミを入れる。
しかし、私をおいて大人ふたりはどんどん盛り上がっていく。
「もし私たちがシチューのルウを見つけることができたらふたり分のシチューを作ってもらえますか?」
「もちろんですとも! もしそんなことがあるのなら、私の腕によりをかけて作らせていただきます」
「それじゃあ決まりだ。よし、スズミ行くぞ」
「えっ。私も?」
「当たり前だろ。シチュー食べたくないのか?」
私は別にクリームシチューじゃなくてもいい。なんならお寿司とかそばの方がいい。一番近くのコンビニでお弁当を買って家で食べてもよかった。
そんな私の気持ちなど露知らず、あっという間にサイドカーに乗せられていた。
![]()
<前の話 オドリバ・ダンサー(後編)
次の話 真夏のクリームシチュー(後編)>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
