
海外のサッカークラブをサポートするということ
その日、僕はコットブスから電車でベルリンへ向かっていた。中断が明けたばかりのドリッテリーガのコットブス対1860ミュンヘンを観て、宿へと帰るところだった。
僕と1860ミュンヘンとの付き合いはちょっとだけ奇妙な感じだ。あの日韓W杯が終わったばかりの頃、サッカーに取り憑かれた僕は深夜にテレビはかじりついてヨーロッパサッカーを観ていた。当時はまだセリエAがぎりぎり盛り上がっていた頃。
そんな時期に、ひっそりとやっていたドイツ代表の試合で、スペイン相手にとんでもないバイシクルショットを叩き込んだのが、まだ若いベンヤミン・ラウトだった。
ラウトが出会いの大きなきっかけだったけど、1860ミュンヘンの損な立ち位置も僕の負け犬根性にぴったりだったのかもしれない。「じゃない方」と呼ばれ、アカデミーの選手は次々に引き抜かれ、何十年も前のマイスターシャーレを何よりも大切にする。そしてオーナーがポンコツ。
僕と出会った直後にさっさと2部へ落ち、立派すぎるスタジアムを押し付けられても(そして手放しても)、それによって日本で試合を目にすることがほとんど不可能でも、僕の心のどこかにはゼヒツィヒがいた。
その一方で、ゼヒツィヒと共に育ってきた現地のファンとの間には超えられない壁があることも分かっている。
初めてミュンヘンへ行ったときのことだ。意気揚々とゼヒツィヒのショップへ入った僕へ、優しそうなおばちゃんが「バイエルンのショップはあっちよ」と丁寧に教えてくれた。ゼヒツィガー流の洗礼。彼らの中で、アジア人はバイエルンを観るものと相場が決まっている。
チャントを歌えばめちゃくちゃビックリされるし、ビールを飲めば「お前にはまだ早い」とおちょくられる。マフラーを巻いてスタジアムの周りを歩けば「君はフーリガンかい?」と笑われる。
彼らにとって、ゼヒツィヒを応援する日本人なんて、想像しうる世界の範囲外の産物でしかないのだろう。
そうは言っても、彼ら自身だって一歩社会に出れば、はるか昔に強かっただけの3部のチームを応援する変わり者だ。「結局ゼヒツィガーには変なヤツしかいない」という事実が、ミュンヘンに行くたびにちょっとした疎外感を覚える僕の、唯一の処方箋になっている。
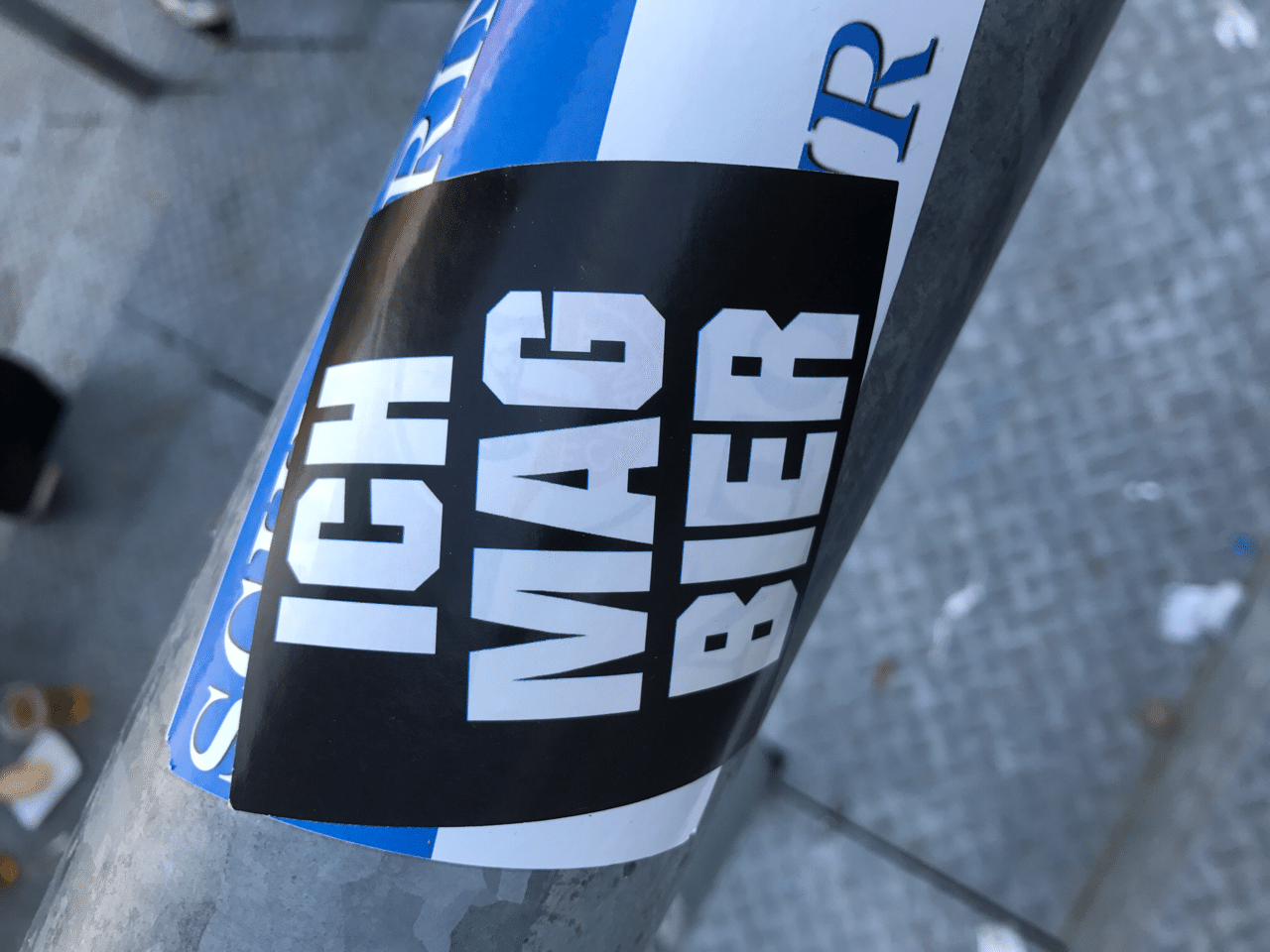
コットブスからの帰りの電車は、コットブスに3-1で勝って満足げな、そして社会的にアウトなヤツらの臭いで充満していた。そしてあのチャントが聞こえてくる。
「ベニー・ラウト、ベニー・ラウト、ベニー・ラウト・・・」
僕も歌う。そして電車の机を叩く。野郎どもが飛び跳ね、電車が左右に揺れる。
ゼヒツィヒは彼らのクラブだ。それでも僕の心のどこかにはいつも引っかかっていて、結局何だかんだ気になっている、それくらいの距離感で応援している。応援って一体何なんだろうか。
海外のサッカークラブを応援している方も、同じような想いをしているのでしょうか。ぜひ教えてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
