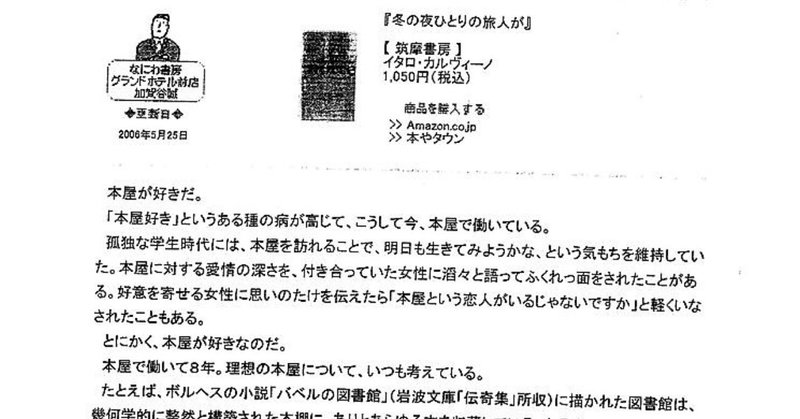
2006年の本屋のカガヤ
本屋が好きだ。
「本屋好き」というある種の病が高じて、こうして今、本屋で働いている。
孤独な学生時代には、本屋を訪れることで、明日も生きてみようかな、という気もちを維持していた。本屋に対する愛情の深さを、付き合っていた女性に滔々と語ってふくれっ面をされたことがある。好意を寄せる女性に思いのたけを伝えたら「本屋という恋人がいるじゃないですか」と軽くいなされたこともある。
とにかく、本屋が好きなのだ。
本屋で働いて8年。理想の本屋について、いつも考えている。
たとえば、ボルヘスの小説「バベルの図書館」(岩波文庫『伝奇集』所収)に描かれた図書館は、幾何学的に整然と構築された本棚に、ありとあらゆる本を収蔵している。ある本の、一文字ちがいの異本にいたるまで。探す手間暇を度外視すれば(この図書館では、一冊の本を探すことが「旅行」と呼ばれる)、図書館としては理想的であろう。だが、完璧な「品揃え:にもかかわらず、本屋としては、なにか物足りない気がする。
本屋には、色気が必要だと思う。読者を誘惑する色気が。
ぼくが理想とする本屋は、イタロ・カルヴィーノの小説「冬の夜ひとりの旅人が」にヒントがある。
これは、ふしぎな構造をもった小説だ。小説の冒頭部分のみで中断する10個の断片と、それらの断片の続きを求める「男性読者」と「女性読者」の探索行とが交互に並ぶ。二人は続きを探すのだが、見つかるのはいつも関係のない別な断片だ。この断片を、われわれ読者もいっしょに読むことになる。さらにこの断片の「作者」や「翻訳者」「編集者」「偽作者」までも登場し、SF的な設定やミステリ的な筋立ても導入されながら、「読む」ことの意味が問いつめられる。メタフィクションと呼んでしまえば、何やら頭でっかちな難しい作品に思われるかもしれないが、全編ユーモアにいろどられている。本を介して近づきあった「男性読者」と「女性読者」が、たがいの身体を「読む」などという場面も登場する。物語はいくどもいくども中断されるが、先を読み進めずにはいられない、魅力あふれる傑作だ。
さて、この小説の冒頭に、本屋で一冊の本を買うまでの様子がユーモラスに描かれている。目当ての本があるのだが、それにたどりつくまでに、「あいにくあなたの人生は今あなたが生きているものでしかないので仕方ないがあなたがもっといくつもの人生を生きることができたら喜んで読むかもしれない本」や「みんなが読んでいるのであなたも読んでしまったような気になっているような本」や「読んだふりをずっとしてきたが今本当に読んでみる気になった本」などの大軍が待ち伏せし、誘惑する。一冊の本を買い、それを読むことはもちろん楽しいが、本屋を訪れる楽しみは、さまざまな本から誘惑されることにもあるのではないだろうか? 学生時代のぼくは、そんな誘惑に生かされていたのだと思う。そして今も。
陳列の仕方やPOPの文句などなどによって本の魅力を引き出して、色気のある、誘惑に満ちた本屋をつくりたい。その誘惑が、読書への誘惑であると同時に、生きることへの誘惑でもあるような。
「冬の夜ひとりの旅人が」は、本好きのぼくに「読む」ことの快楽を再認識させながら、本屋好きの書店員としてのぼくをも大いに刺激する作品なのであった。
【以上は、書店員だった2006年に依頼を受けて書き、某サイトに掲載された文章だ。現在は消滅してしまったのでテキスト部分を再録した。】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
