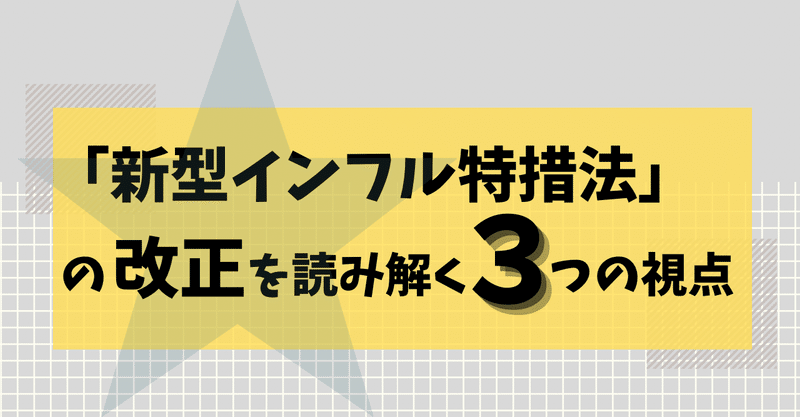
新型インフル特措法等の改正を読み解く3つの視点
【新型インフル特措法改正で何が変わるのか】
去る1月8日、緊急事態宣言が発令された。筆者は、昨春に改正された新型インフルエンザ特措法(以下「特措法」という)による緊急事態宣言には法的な不備が多すぎるため、弁護士やジャーナリストら有志で慎重な運用を求める声明を発出したところである。
1月18日から開会される国会では、政府から現状のコロナ禍に対応して特措法及び関連法制の改正法案が提出される見込みとなっているが、今般明らかになったこの改正法案の方向性(「新型インフル特措法改正の方向性」、「感染症法改正の方向性」)が、法的にひどい。
ひどさを端的に理解するポイントは3つだ。
①「平時」と「有事=緊急事態」の“間”にグレーゾーンとして新設する「予防的措置」によってなし崩し的に緊急事態と同じ(かそれより悪質な)状態を政府が自由に作れること
②補償が政府に裁量がある政策補償(=“施し”)であって我々の請求権とはなっていないこと
③自宅・宿泊療養や調査に応じない場合の入院勧告や罰則の適用が、医療のひっ迫を逆に悪化させること
である。①②が特措法改正に関して、③が感染症法改正に関する論点だ。以下に少し詳しく見て行こう。
【「平時」と「有事」の境界線を失くし、いつでも「緊急事態」状態を作れる「予防的措置」の新設】
今回の特措法改正で、感染まん延防止に関する措置を講じなければ緊急事態措置を実施することが回避できない事態(≒このままだとヤバい)が発生した場合、政府対策本部長(菅総理大臣)の判断で、「予防的措置」を実施することが可能になるという。簡単にいえば、いわゆる「平時」と「有事=緊急事態」の間に、“準”緊急事態的な措置を講ずるグレーゾーンを新設するということだ。
しかし、何のことはない、「予防的措置」と言いながら、内実は緊急事態措置とほぼ同様の措置がとれるのである。つまり、営業時間の変更等はもちろんのこと、いわゆる緊急事態宣言による「施設の使用制限」(特措法45条2項)や休業要請等々が可能だ。また、今回の改正で、緊急事態宣言と同等に「要請」➡「命令」の発出+立入検査&公表が可能で、これに違反した場合は過料という罰則の適用があるというフルパッケージだ。緊急事態とまったく同等のオプションで人々の行動制限を調達できる建付けになっている。
この点、政府からは「営業時間の変更だけしかしない」といった「商売文句」での矮小化された説明がなされる可能性があるが、中身をシビアに精査しよう。
しかも、予防的措置の決定には緊急事態宣言の際に要求される国会報告すら必要なく、我々国民の代表者たる国会関与なしの政府の判断のみで措置を決定できてしまう。そもそも緊急事態宣言においても国会「承認」ではなく「報告」であることすら問題であるのに、さらに後退して、国会関与自体が落とされるとすれば、緊急事態への入り口に我々国民が関与できないこととなり、国民➡国会➡内閣と一直線に繋がっている“民主的正当性”という手綱が切れてしまう。さらに、緊急事態宣言は2年以内という期間制限が存在したが、予防的措置には期間制限が存在しない。ディストピア的に描くと、一切の国民の関与なく予防的措置を永久的に継続することも可能なのだ。
なぜこのような措置を新設するかといえば、よりラフに、そして総理のフリーハンドで緊急事態宣言と同様の措置をとるために「予防的措置」を新設するというのが政策的意図ではないか。
いわば緊急事態宣言の密輸入だが、緊急事態宣言よりも「タチが悪い」と断言しよう。
【日本社会に欠如する「緊急事態」という「人権感覚」】
さらに、少し抽象的だが法的には絶対に見過ごせない話をすれば、そもそも「緊急事態」という法状況は、立憲的秩序を一旦停止するという「ぬきさしならない」状態であり、立憲民主主義社会からすれば原則「最も望ましくない」事態であることを抑えてほしい。国家を維持し、ひいては市民社会を防衛するため、私たちが普段当たり前のように生活している「法の支配」や「法治主義」で光が照らされている日常を意図的に「停電」させるという逆説的で諸刃の状況である。
現行法上、日本での緊急事態宣言下の私権制限は、法的根拠を有する強制的措置によることなく、従うか従わないかは「任意=わたしたち次第」の「要請」という行政指導ベースで行われている。これにより、店を自粛した責任は政治権力ではなく任意に従った店側に存在するという歪な構造が生まれた。同時に、緊急事態法制が非常に「弱い」建付けになっていることによって、法的な拘束力による明白な線引きよりも、相互監視と同調圧力(≒自粛警察)というなんとなくの「肌感覚」で行動変容が調達された。そのせいか、「マスクが店頭からなくなる」という実生活上の不安感とは全く異なる、緊急事態宣言下という異常事態に突入していくという“法的恐怖”ともいうべきある種の「人権感覚」が芽生えていない。これは、戦後我々日本人が「人権」や「自由」「平和」、そして「議会制民主主義」や「法の支配」を“キレイゴト”として奉じていただけで、これらの価値を死守し立て直し続けるための実践を怠ってきたことのツケであると言わざるを得ない。
本来、緊急事態に突入することは法的に絶望的な高さの壁が存在するはずで、この境界線は絶対に明確でなければならない。雑な例えをすればこの世とあの世を隔てるくらいの差があり、緊急事態を出したり出さなかったりということはこの世とあの世を行き来することの異常さと通底する。だからこそこの境界線を乗り越える政治判断や市民の受け止めも必然的に「抜き差しならない」ものになるのである。我々が「法」を共通のルールや言語とする社会を生きているのであれば。
法的には「平時」(白)と「有事」(黒)しか存在しないにもかかわらず、今回、その中二階のような「予防的措置」(グレー)を創設するということは、まさに絶対に明確にすべきである平時と有事の境界線を溶解させるものだ。これは、日本社会の自由への意思や人権感覚の欠如及び統治システムへの「不感症」がそのまま投影されているといっても過言ではないだろう。
「予防的措置」によって事実上緊急事態を恒常化させるとすれば、もはや「緊急事態」が「緊急」事態ではなく「日常」と化し、近代立憲民主主義社会の原則と例外が逆転する。強調してきたとおり、平時と有事との線引きは、「人権」や「法の支配」という近代市民社会の文法である「法」にとって致命的に重要な分水嶺なのである。この防波堤が決壊すれば、日常は「緊急事態だけ」の濁流に飲み込まれてしまうのだ。このことの異常性を読者の方に理解していただけることを信じている。
【我々に請求権がない“施し”としての「補償」】
次に、「自粛と補償はセット」などと言われる「補償」の問題がある。
予防的措置が緊急事態宣言よりも「タチが悪い」として、気になるのは補償の豊かさだ。結論からいって、補償については何らの変更がない。
そもそも、「補償」といっても、現在支給されているような「協力金」の類は、いわゆる「政策補償」であり、行政が支払いを義務付けられているものではなく行政側の裁量で出すか出さないかを決定できる、いわば「施し」に近い。本来は、公共の福祉のための特別な犠牲に対して「損失補償」をすることを行政に義務付ける「義務的補償」の規定を法定すべきである。義務的補償は政策補償とは異なり、我々に請求権があることを意味する。つまり、政府が「●●給付金」を創設するか否かにかかわらず、請求権を有しているということだ。特措法では「財政的措置」(70条)の規定は存在するものの、損失補償の規定は存在せず、今回の法改正でも議論の対象にはなっていない。早急に損失補償規定を法定すべきではないか。
【「病床のひっ迫」をさらに悪化させる「入院勧告」】
さらに驚くべき政策の「ちぐはぐさ」を露呈しているのが、感染症法の改正による入院勧告だ。今回の政府提案によれば、自宅・宿泊療養の協力要請を規定し、これに応じない場合には入院勧告がなされ、入院勧告に従わない場合は罰則が適用されることによって入院への実効性が担保されている形だ。これは明らかにおかしい。
何らかの法の制定や改正で誰かの自由や権利を制限する場合、その制限の目的とそれを実現する手段の関連性が吟味される。
今回の感染症法改正の目的は、新型コロナウイルス感染拡大と医療崩壊の防止なはずである。しかし、そもそも病床がひっ迫しているという前提から出発しながら、今回の法改正のように自宅・宿泊療養で「足りる」人を、罰則をちらつかせてまで事実上強制的に入院させることは入院の必要性のない人たちを大量に病院に送り込むことにつながり、あまりに倒錯している。
医療崩壊を防止するという目的にとって今回の入院勧告という手段が合理的関連性や実質的関連性を有しているどころか、もはや有害である。驚くべきことに目的を害する手段をとろうとしているのだ。
したがって、おそらく目的・手段の実質的関連性も合理的関連性もない今回の改正は、法的に移動の自由を制限することを正当化しないし、政策的にも医療崩壊を促進する可能性があり、妥当ではない。
また、感染者や患者について、積極的疫学調査に対する虚偽答弁や調査拒否に罰則が設けられる。調査事項としては、性別、年齢、連絡先、居住地、症状、経過などから始まり、行動歴等の行動に関する情報や予防接種などの過去の状況に関する情報など、個人にとってかなりセンセィティブな情報を強制的に徴収することとなる。この点も、行動歴や病歴などの高度なプライバシー情報を事実上強制取得するほどの立法事実(その法改正の必要性を支える根拠となる事実)の精査を含めた合憲性の検討がなされたのだろうか。罰則によるプライバシー開破の強制は、検査自体への拒否・隠蔽感情を高め、結局のところ感染拡大防止という目的の達成を阻害してしまう手段になりかねない。
しかも、上記改正感染症法の措置は特措法とは関係ないため、緊急事態宣言とは関係ない。すなわち、「有事」でもないにもかかわらず、「平時」からこのような取り扱いが行われるということなのだ。「平時」の人権制約としてはあまりに法的に雑な議論ではないだろうか。
【法はいつでも「必要」に対するブレーキ】
本稿の結論としては、「予防的措置」は新設せず、「平時」と「有事(緊急事態)」を厳に切り分けたまま、緊急事態宣言につき「要請」等の市民が任意に従うか否かにかからしめる措置ではなく、統治権力が責任を負う形での命令等に一本化すべきであると考える。命令であれば、行政手続法2条の「不利益処分」に該当し、告知・聴聞や理由提示等の事前の手続も厳格化する。その上で、政策補償(施し)ではなく、損失補償を法定すべきである。当然、発令には国会「報告」ではなく国会「承認」を要求すべきだ。
感染症法の改正も、感染拡大と医療崩壊を防止するという目的に照らして真に実効的な手段を再度検討すべきである。一部指摘されているが、入院が必要とされている「中等症」の基準が存在しないこと等、並行してやるべき事項はたくさんあるはずだ。
コロナ禍において、あらゆる「必要性」が前面に出てしまって、それが法的に許容されるかという「許容性」が吹き飛ぶ。しかし、法は権力が何かをする権限を与える(授権)のと同時に、それを制限する性質を持つ。したがって、必要に対するブレーキになりがちである。
コロナ対策は当然せねばならないが、全体主義的な「空気」によって緻密な法的検証がなされることなく物事が決まっていく日本社会の「空気の支配」「空気治主義」には強い危機感を覚える。コロナ禍で法的議論を真正面からすると「今はそんなことをしている場合か」という声に、日本の「法」すなわち「自由」の意識の脆弱性を感じざるを得ない。野党、法律家団体、マスコミも、コロナ禍で「反対」することへの「きまずさ」から、緊急事態法制については声が小さい。政治家たちは、会食のルールは国対委員長間で合意しても、選挙目線から「反対」と映ることを気にしてこのように大問題を抱える法案に真っ向から反対しない。いつもあれだけ反対ばかりしているのに。また、憲法改正についての緊急事態条項にあれだけ批判的だった学者や専門家たちが鳴りを潜めているのは、一体どういう理屈なのか。
「コオロギは鳴き続けたり嵐の夜」
戦時中に日本が全体主義に突き進む中、孤独に抵抗を続けた信濃毎日新聞の記者であった桐生悠々の句である。法律家こそ、このコオロギとして、「空気」という「嵐」にかき消されそうになっても、鳴き続けなければならないだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
