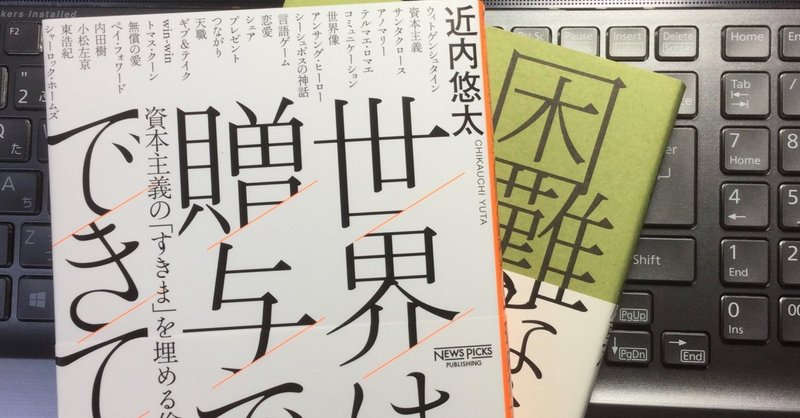
『世界は贈与でできている』読後雑記
「#キナリ読書フェス」をきっかけに、近内悠太著『世界は贈与でできている』を読んだ。フェス向けの文章は前回アップしたが、そちらに入れなかったことを残しておく。
実は、いちばん心に響いたのは「あとがき」のこの記載だった。
「今、いろいろな文章を書いてみているんです。でも、文章を書くと、ああ、自分はからっぽなんだなって思い知らされるんです」
これだけの本を書いておきながらそうなのか。この言葉に対する加藤典洋氏の応答も秀逸で、たぶんずっと忘れない気がする。
声に出したり、文字を書くたびに、私もからっぽになる感覚があるが、そこに気づくところが始まりなのかもしれないな。
さて、本書は内田樹氏の著書をきっかけに着想を得たことが書かれている。私の本棚には内田氏の本がたくさん積んであり(読んだとは言っていない)、「贈与」や「祈り」、「呪い」と言った言葉は馴染み深い。若い人の感覚で新しい言葉で語られる贈与論は新鮮であった。
それよりも、逆説的にハッとさせられたほうが多かった。若者の感覚はかなり違う、便利な世の中を当たり前に感じているのだと。
「#キナリ読書フェス」でたくさんの感想がnoteにあげられている。自分がすでにたくさんの贈与を受けてきた存在であること、世の中は贈与にあふれていることについて、大きな気づきを得たという内容が多い。
しかし、「贈与」と言う言葉の定義はしていないまでも、その感覚は「当たり前なんじゃないの?」という世代が、私以上の世代には間違いなくいる(いた)と思う(その分「呪い」の制約も多い世代だが)。不便な時代に助け合って生きていた世代では、「有り難い」感覚は当たり前のことだった。
生まれたときから便利な世の中に暮らしている若者にとっては、便利であることが当たり前なのだ。蛇口をひねればお湯は出るし、おなかがすいたらコンビニに行けばいいし、電話もテレビもパソコンも持ち歩いているようなもんだし。
生まれたときから存在したものに対して、有り難いという感覚はなかなか出てこないのだろう。
そんな彼らにとっては、この本はパラダイム変換にも似た視点を与えているのかもしれない。
著者の問題意識も、まさにそこにあるのだろう。
著者の近内氏の名は初めて知った。私の買った本で7刷だった。今の時代に必要な本だと思うし、こういう本が売れるのは嬉しい。
新味があろうとなかろうと、繰り返し確認しておくことが必要な命題というのはあります(内田樹「日本辺境論」)
内田樹自身が『日本辺境論』の前書きで語っている。これは全くそのとおりなのだ。著者はそのことをよくわかった上で、今の言葉にして訴えざるを得ないのだ。なぜなら、知ってしまったから。
だから、若い人がそのことを理解した上で問題意識を持っていることが頼もしいし、そういう論者を私は応援したい。新しい人が新しい言葉で、時代に即した形で大事な論議をしていくことはとても重要なことだ。
なお、本書では、内田樹の論を有益としつつ「勇み足」と評している。しかし、私はここで引用された内田の表現については「贈与されても反対給付義務を感じない人」が増えてしまうことの恐ろしさを示唆していると理解していた。
同じことを、本書の帯にも名前がある山口周氏が、本書の紹介記事で次のように述べている。
大衆とは「贈与されたことへの後ろめたさ」を感じなくなった人なのである。(山口周氏、プレジデントオンライン;下リンク)
副題の「資本主義の隙間を埋める」の部分はもうちょっと論議が深まればいいなぁと、この部分はこれからの著者の奮闘を大いに期待したいです。
本書を読んだ人に、次にオススメするとしたら。やはりこれだろうな。
内田樹『困難な成熟』
本書の参考文献で、サンタクロースの話題の元ネタでもある。贈与論だけでなく、責任とは、働くとは、大人になるとはどういうことなのか、といった根源的な問いに真摯に思考を重ねる。「これから大人になってゆく少年少女青年達に」書かれた本であり、分厚いけど読みやすい。
