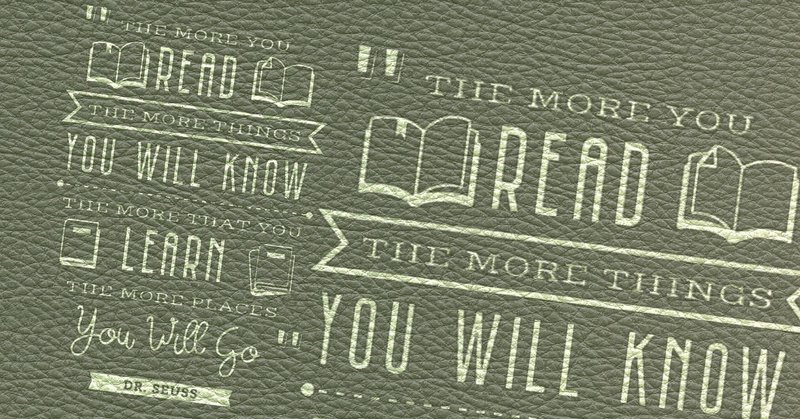
「問う」こと、その根源を問う~『問い続ける技術』
予防医学の研究者である著者が、様々な職業/業界における知のトップランナー達との対談を通して、彼らの問い、考える力を紐解いていく本。
各対談は、対談者が自身の専門領域や課題認識について話し、著者がそれとなくファシリテートする形式を取る。対談者がなぜそれを考えるに至ったのか、幼少期の原体験を振り返ったり、日々の習慣を深掘ったりしながら、彼らの思考様式に漸近していく。
本書では、それら各対談や対談者の思考の共有項を括ったり、それらを汎化/体系化させて「問いを立てる仕方/能力」を形作る手続きも特に取ってはいない。
その意味で、本書は問いを立てる力を養うために読む本としては入門書にも決定版にもなりはしない。
類書だと、王道のクリティカルシンキング系や『Q思考』等の方がおすすめであろう。
ただ、本書自体が全編を通じて発する「”問う力それ自体”はどこから来るか」という”問い”と、それへの回答となりうる一流の思考人たちの個別具体的な生のエピソードは、世にある類書が教えてくれる「問いの仕方」よりも、よりプリミティブで深遠な知の形式/生成の一端を垣間見せてくれる。
それらのあり方や伝え方が、属人的で非体系的であり、なんなら物心ついた時には天才だったといった元も子もない話ですらある(本書の対談1人目の物理学者長沼伸一郎とか)ことは、オブラートに包まれていない”知のリアル”を手触り感を持って感じさせてくれるし、ゆえに、読み物としてもとても面白く読める。
いま、なにかを「問う」ことはとても難しい。
近代以降の自然科学の発展により、人類は”説明的”に世の中の現象を捉えることに、顕著に慣れきってしまっている。
この世に生を受けた瞬間、乳児は等しく、自他やあらゆる事どもが何一つ分節されていない「一」または「無」としての魔術的な世界を見る。その後、言葉や経験が少しずつ増やしていく分別と、義務教育により詰め込まれる「世の中の全てに法則があって、いかなる物事にも合理的な解釈が可能である」という科学的な"経験"の体系によって、我々は説明可能な世界に無自覚に這い出している。
比較的昔の人々は、自分たちが「ある」ということ、あらゆる個物が「そうある」ということの一つ一つを驚嘆の目で見つめていただろう。古代の人々は、夜空の星々を見上げ、その正確無比な運動の「なぜ」を問うた。そして中世の人たちは、自然のあまりの完全性に恐れをなし、そこに神を発見することで問うことをやめ、それにより1,000年にも及ぶ知の暗黒の時代を作り出した。
それを乗り越え、主権を奪還した理性が科学を生み、しかしその科学の趨勢の結果として我々の脳内に落とし込まれた観念としてだけのなんとなくの説明可能性は、世の中の不思議を問うこと、その意欲を大きく削いでいるのではないか。市井の知にとっての第二の暗黒時代が、ここに姿を表す。
人類に分かっていることが増えてきた、という単純な話ではない。解明される現象が増えれば増えるほどに、同時に分からないこと、問わねばならぬことの広々とした深淵が、一層意識される。むしろ、現代が近代を乗り越える過程で見えてきたのは、自然の認識や真理への到達には限界があるということではなかったか。この、比較的最近になって分かってきた事柄について、大半の市民はアクセス手段を持たない。世界は依然として、なんとなく説明可能であり、なんとなく自分が問わずとも明らかなものである。科学の専門分化も相まって、非専門家が「問うても仕方がない」という空気は、いつにもまして支配的である。
そんな時代に、そんな空気を吸いながら生きる我々にとって、それでも問い続ける人々の背中を見据えることには、大きな意義がある。「問い続ける力がどこから来るか」という前述の問いが照射し、我々に垣間見せるものこそが、本書の一番の価値なのではないだろうか。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
