
虹のかけら ~短編小説~ 橙の葡萄酒2
食べ終わった後、ソファでしばらくいっしょに映画を見たり、彼が作ったゲームや昔撮ったスペイン旅行の写真を見せてもらった。
やがてわたしはお風呂に入り、目を大きく見せるための化粧を落として床に就いた。彼もベッドにするりと入ってきた。わたしには少し大きいシングルベッドに彼が寝そべると、もう少しで足がはみ出しそうな程だった。足を持て余している、彼はそういった。
「おやすみなさい」
暗がりの中そういうと、彼も彼の星の言葉でおやすみなさい、と返してくれた。
暗闇でも分かるほど彼からは太陽の匂いがする。そっと首に手を回して頚椎の数を数えると、何度数えても八つあった。

翌朝、コーヒーとバターの温かい香りで目が覚めると、彼は約束通りフレンチトーストを作っていた。オレンジのマーマレードとラズベリーのジャムの小瓶がテーブルの上に乗っている。これ、どうしたの、と尋ねると、スーツケースに入れてきたのだという。旅先で出会った人々のために、彼はスーツケースに、自分の星からのお土産を幾つか入れてきていた。
「コーヒーも持ってきたのですよ」
といって、香ばしく熱く淹れられたコーヒーは、確かに普段飲んでいるインスタントのコーヒーとは香りの深みが違った。テーブルの彼のスマートフォンからは英語のニュースが流れている。内容は一貫して、世界的な流行病についてのことだった。わたしは顔を洗って席に着いた。
彼は、なんて上手にものを食べるのだろう、と器用にナイフとフォークを使って、きつね色のフレンチトーストを口に運ぶ様を見て、そう思った。ただ、食べることは異常に早かった。わたしが半分も食べ終わらない内に、彼は食パン二枚をぺろりと平らげていた。
「今日は仕事のために、ミリオンダラー・ホテルに行きますよ」
「ミリオンダラー・ホテル?」
それは、彼が見つけたエンジニア専用のコワーキングスペースだった。設備も機械も全て整っていて、希望者は宿泊もできる。かつては、この病が広まる前は、京都に訪れた世界中のエンジニアがよくここに泊まっていたという。利便性も良く、河原町通りのビルの最上階にあった。
「だから今日は夜の十時頃に帰ると思います」
「じゃあ、帰る前に連絡してね、鍵は一つしかないから」
「わかりました、帰る前に連絡します」
しかしその日彼が帰ってきたのは夜の十時半を過ぎた頃で、事前に連絡もなかった。仕事に没頭していたのだという。帰ってくるなり、お腹が空いたといい、買って来た餃子定食を開けビールを飲み始めた。また別の日は、今日は早く帰れそうだと直前にメッセージが来て、帰ってくるなり親子丼を作り始めた。午後の八時だった。
そうして話したいことを話したい時に話す。ある時は、わたしがお風呂に入っていた時に、いきなり脱衣所から、この音楽がすてきなので聴いてみてください、と声をかけられた。
そういう日が十日以上続いて、さすがに、わたしにもわたしのリズムがある、と伝えた。彼はしばらく考えた後わたしに詫びて、二、三日ミリオンダラー・ホテルに泊まるといった。
「ミファさん、ちょっと一人でゆっくりしてくださいね」
さらりとそういった彼は特に寂しくも何ともなさそうだった。スーツケースだけわたしの部屋において、パソコンとティーシャツと歯ブラシをリュックサックに詰め、彼はふらりと出て行った。
スーツケースだけ残されたわたしの部屋は、急に奇妙な静けさに包まれた。空間にぽっかり穴が空いた様な感じだった。一人でこの部屋にいることは慣れているはずだ。今までだってずっと一人で過ごしてきたし、人を部屋に上げたこともほとんどなかったのだから。
室内が無音になったので、外からの音がよく聞こえた。サイレンの音、誰かが唱えている読経と木魚の音、赤ちゃんの泣き声。けれど、やはり奇妙な静けさだった。いつもより生き物の存在が薄くなっているようだった。それはこの部屋が沈黙しているせいだろうか。それとも世界中が、今沈黙しているせいだろうか。気づくと、頬に温かいものがつたって落ちていった。
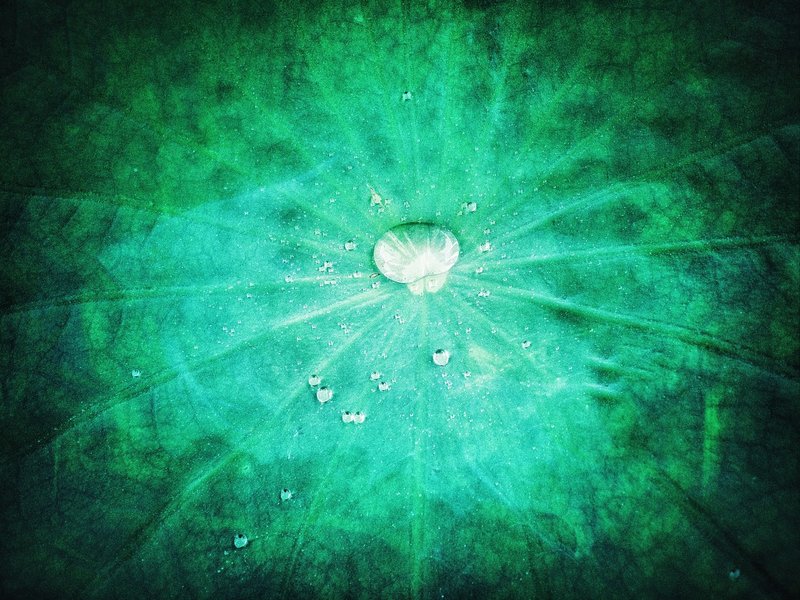
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
