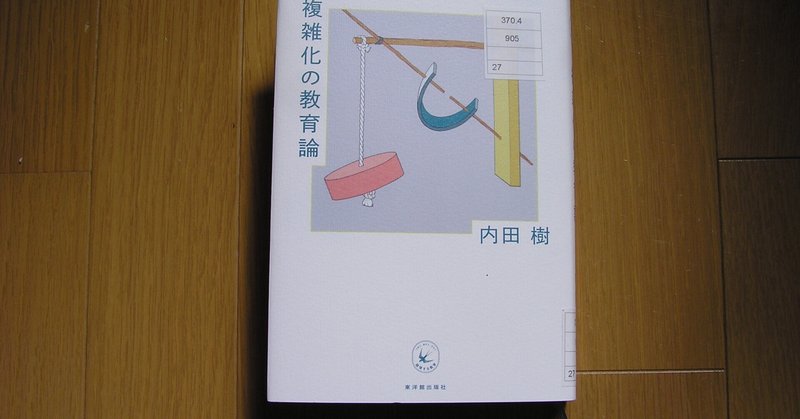
なぜ、日本の学校はこんなにも悲惨なことになってしまったのか?
昨日、教員の側から現在の学校がとても息苦しい場所になってしまっていることを「覚醒剤に依存することによってしか、校長という責務を果たせない」という状況について書いた。この例は全く氷山の一角に過ぎず、本当にたくさんの教職員が「抗うつ剤」や「睡眠導入剤」を医者から処方されているのだと思う。闇ルートから「覚醒剤」を入手してなんとか職務をこなしている教員も相当数いるのではないかと推測する。当然、「覚醒剤」や「麻薬」は麻薬等取締法に違反することは、使っている本人がよくわかっているので、自分から「わたしは覚醒剤や麻薬のお世話になっております。」などと告白する教員がいるわけがない。昨日の新聞記事の兵庫県の校長のように売人がパクられて、その携帯の履歴から逮捕されることはとてもまれなことだ。それを「教員の麻薬汚染が広がっている」などと言い募るのは、週刊誌やTVのワイドショーのコメンテーターの常套句でしかない。彼らが罪深いのは、自分もしんどいこの日本の状況の中でいきていることを隠して、おもてづらだけで正論を吐いていることだ。
前置きはこのくらいにして、今回は、どうして学校がこのように「息苦しい」空間になってしまったのかについて考えてみたい。「学校というのは、状況が最後にやって来る場所だ」と言われるが、そうすると私たちが生活しているこの「ニッポン」という空間がどうしようもないくらい「息苦しい」ということになりはしないだろうか?
今回は、内田樹さんの近著『複雑化の教育論』から、その理由を探ってみたい。
格付け機関化する学校の弊害
内田樹 『複雑化の教育論』p59~p67
いま日本に不登校が20万人いると報道されています。この子たちの何割かは、進化しよう変化しようとしているのだけれど、学校に行くとそれができないということで立ち止まっているんじやないかと思うんです。複雑化するという生物の自然過程が学校という人為的な制度によって阻まれている。学校に行くと生きる力が衰弱するということを直感するから、命を守るために学校に行かないことを選択した。そういう選択をした子どもたちって結構いると思うんですよね。だから、それを「脱落した」というように見てはいけないと思うんです。ノーマルな成熟のプロセスから脱落したんじやなくて、むしろその子たちの方が生物として自然に生きているのかも知れない。
その20万人の不登校の子たちをどうやってこれから学校規戻すのか。これは今日出して頂いた中にあった質問なんです。どうやって学校に戻すか。それは学校が子どもの成熟と、複雑化を支援する場であればいいと僕は思います。そのことを嫌う子どもはいないと思うんです。
でもいまの学校はそうではない。文科省はたぶんそんなことに何の興味も持っていない。文科省は国民の市民的成熟などまったく望んでいないように見えます。むしろ幼児のままでいて欲しいとさえ思っている。いまの文科省が学校教育を通じて子どもたちに教え込もうとしているのは、上位者の言うことに絶対抗命しないイエスマンシップです。上位者に言われたことはすべてそのまま実行する。どれほど無意味なタスクであっても、「これに何の意味があるんですか?」というような問いを発しない無意味耐性を身につけること、これを文科省は最優先に、あらゆる領域で追求しています。
無意味なタスクを教員にも子どもたちにも命じて、それをすれば褒賞を与え、しないと処罰する。
それを繰り返していると、国民は「この仕事にはどういう意味かあるのか?」ということを問う習慣そのものを失います。ふつう「意味がない仕事」をしていると、だんだん生きる力が減殺してきますから、自分でもわかるはずなんです。「アラーム」が鳴るから。そんな仕事はもう止めろ、って。でも、その無意味なタスクをやらないと罰される。仕方がないから我慢してやる。それが続く。アラームが鳴り続ける。うるさいからスイッチをオフにする。そうやって「無意味耐性が強い子ども」が作り上げられる。
タスクそのものは何でもいいんです。格付けのためのただのツールですから。無意味なタスクをどれくらい手際よくこなすかを査定している。「穴を掘って、掘り出した土でまたその穴を埋めなさい」というような無意味なタスクであっても、格付けツールとしては十分に使える。(筆者注 教員に課せられる「官製研修」がこれに当たる。文科省から研究指定校に指定されると教員の疲労度は各段に上がる。日常的に行われている半官半民の(実は強制されている)「小(中)学校教育研究会」の研究授業というのもこれにあたるし、年に一回、県教委の出先機関である教育事務所から指導主事がやってきて、授業を見せなければならないのも「学校訪問研修」という名のビッグイベントである。とても「無意味な仕事 ブルシットジョブ」の最たるものである)仕事を終えるまでの所要時間でも、掻きだした土の量でも、穴の深さでも、スコップの使い方の手際よさでも、何でも格付けに使おうと思えば使えます。タスクそのものは何でもいいんです。問題は客観的で数値的な格付けなんです。その格付けに基づいて子どもたちに褒賞と処罰を与える。そして、それこそが社会的なフェアネスであると子どもたちに信じ込ませることが重要なんです。
(筆者注 なぜ、学校は荒れるのか?)
学校教育が格付け機関であるということになると、学校の空気はますます忌まわしいものになります。格付けというのは、ゼロサムの競争だからです。自分の格付けが上げるということは、誰かの格付けが下がるということです。そして、自分の格付けを上げることよりも他人の格付けを下げることの方が簡単でかつ費用対効果がよい。そのことに子どもたちはすぐに気づきます。自分の学習努力は自分にしか関係しないけれど、学習妨害は自分以外の全員に影響を与えることができる。
最も効果的な学習妨害は自分たちがしている勉強は「ほんとうは意味がない」ということを周りの子どもに知らせることですね。みんな内心はそう思っているわけですから、これは説得力がある。「こんな勉強に何の意味があるんだよ」と言われて効果的な反論ができる子どもはいません。
学級崩壊というのは子どもたちを偏差値至上主義イデオロギーに染め上げたことの自明の結論なんです。集団全体の学習意欲が減退して、勉強しなくなると、わずかな学習努力で偏差値が跳ね上がるから。「最少の学習努力で最高の偏差値を得るためにはどうしたらよいか?」を問えば、「周りの人間の学習を妨害する」というのが「正解」なんです。子どもたちを同学齢集団内部で相対的な優劣を競わせていると、学習意欲が減退する。そんなの当たり前のことなんです。
「お気楽な学校」が必要
今日頂いた中に面白い質問がありまして、それは「内田先生が校長先生になったらどうしたいですか?」というものでした。僕が校長先生になったら、やることは一つですね。それは「職場を明るくする」ということです。
まず、教員たちの仕事をできるだけ減らす。教え方についてはできるだけ自由裁量に委ねる。好きにやっていいですよと、教員にフリーハンドを与える。どんな教材を使って、どんな方法でやっても、結構です。もし何か問題が起きたら私か責任をとりますと約束する。それだけで、職場はずいぶん明るくなると思いますよ。「好きにやってください。何か問題が起きたら、私か責任をとります」と断言するのが、現場の人たちのパフォーマンスを上げるには最適の方法なんです。
現場ではいったい何をする気なのか、それはどういう成果を上げているのか、逐一報告しろという上司がいますよね。「ほう・れん・そう」とかいうやつ。これ、一番仕事がやりにくいやり方ですね。現場の問題について上司が適切なアドバイスをしてくれると期待できたら、「ほう・れん・そう」なんてことを上が言わなくても、自分から進んで仔細に報告し、相談しに来ますよ。命令しないと報告にも連絡にも相談にも来ないのは、そんなことをしても「役に立たない」と思われているからです。何かまずいことが起きた場合でも、そういう上司は「オレは知らないからね。お前、責任とれよ」と言って押し付けるに決まっている。そんなこと言われたら不愉快だから、実際に何か問題が起きても、ぐずぐず先延ばしにして、報告や相談に問題は責任をとるかとらないかというレベルの話じゃなくて、どうすれば現場の教員のパフォーマンスを向上できるか、なんです。どうすれば教員たちが自分の能力の限界を超えて能力を発揮してくれるか、自分に割り振られているジョブの範囲を超えてオーバーアチーブしてくれるか、それを考えるのが管理者の仕事です。
そのためには上司は「お前が責任とれよ」ではなくて、「私か責任をとる」と言い切った方が有効なんです。原理の問題じゃなくて、程度の問題として。「責任は私がとるいと断言した方が、づ責任をとらなどと言い張るよりも、責任をとらなければならないような事態が出来する可能性は少なくなる。でも、考えてみたら当然ですよね。「お前が責任とれよ」と言われて突き放されたら、緊張して、硬直化して、失敗するリスクは高まる。それよりは肩の荷をおるしてあげて、自由にやらせた方が失敗するリスクは少ない。
効率的な組織マネージメントはどういうものかを純粋にプラグマティックに考えたら、「できるだけタスクを減らす。現場の自由裁量権を大きくする。責任は上がとる」という仕組みが一番合理的なんです。
あと僕が校長になったら、とにかくよく一緒に遊ぶようにすると思いますね。一緒にスキー行ったり、温泉行ったり、麻雀やったり。むかしの終身雇用の企業では、そうでしたよね。疑似家族的なつながりを作る。「そういうのは鬱陶しくて我慢がならない」という人はいます。もちろん、そういう人には無理強いはしません。でも、教育というのは集団で行う営みですから、お互いに「人間を知っておく」というのはたいせっなことだと思うんです。この人にはどれくらいのことまで話して平気か、この人にはどれくらいのことまでは頼んでも平気かということは一人一人違います。
だから、一緒に旅行する。旅行というのは必ずトラブルが起きるからです。列車が遅れるとか、が遅れるとか、旅館の部屋割りがうまくゆかないとか、食事がまずいとか、飲み過ぎてげろ吐くやっがいるとか……必ず何か起きる。そういう時に正味の人間の社会的能力がわかります。「誰のせいだ」というようなことをいつまでもうるさく言い立てる人もいるし、頭を切り替えて、いま手持ちにあるリソースで何かできるか、次善の策は何かということに集中できる人もいる。トラブルの時にこそ社会性の違い、特に復元力の差が際立ちます。というのは、社会的能力というのは何かがうまくゆかなくなった時に復元する力のことだからです。 コミュニケーション能力というのは、言いたいことをうまく相手に伝える能力のことではありません。コミュニケーションが途絶して、言葉がうまく通じなくなった状況から、コミュニケーションを再開させる能力のことです。交渉能力というのは、押したり引いたりして自己利益を確保する技術のことではなく、交渉の余地が
ないような緊張関係をとにかく緩和して、対話的環境に持ち込む能力のことです。ほんとうに重要な能力というのは、すでにあるものの上に何かを加算する力ではなくて、マイナスからプラスに転じる力のことです。
そういう力は定型的な仕方では考課できない。だから、トラブルが起きた場合でも、本業に大きな影響が出ない局面で、「トラブルが起きた時にこの人はどうふるまうか」を観察することが有益なのです。起居をともにして、いろいろなトラブルを経験すると、その人が一緒に仕事をした時に、どれくらい頼りになる人か、どれくらい頼りにならない人かはわかりますから。
僕が校長になったらすることは、それくらいですね。とにかく現場の先生方に自由にやってもらう。だって、自分が現場の教師だと想像した時に、上司に一番言って欲しい台詞は「好きにやりなさい。責任はオレがとる」ですからね。自分か上司から言って欲しい台詞を言えばいい。
僕が校長先生になったら、何よりも「お気楽な学校」を作ります。そのためには教育委員会とも文科省とも、場合によっては教育にうるさく口を突っ込んでくる政治家や保護者とも戦わなければいけない。結構ハードな戦いになると思います。でも、学校は査定や格付けの機関ではなくて、子どもたちの市民的成熟を支援するために存在するのだという大筋のことについては、少なくとも保護者は話せばわかってくれると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
