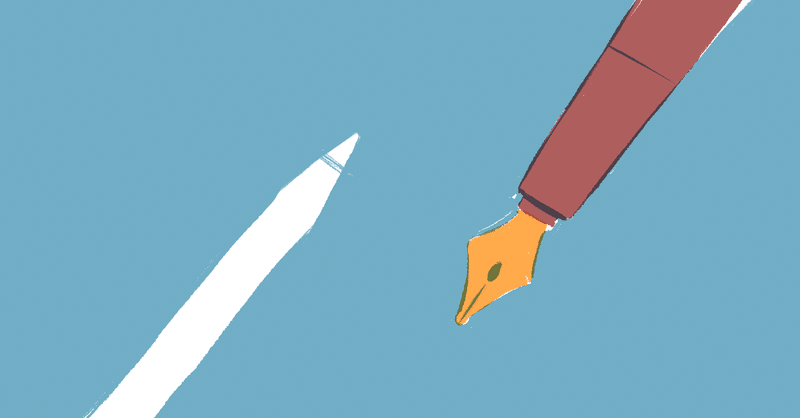
書く動機
話すことが苦手だった。自分の思いをすらすらと口に出せる人がうらやましかった。日常会話は、ふつうは自然に流れていくだけのなんてことないものだろうけれど、私にとっては常に厄介な即興劇で、余計なことを言うのが怖くて、考えすぎて、話すタイミングを逃して、そんなことばかり。ああ言えばよかった、この気持ちは伝えたかった。そんな言葉が、もどかしさ、悔しさと一緒に心にたまっていった。
だから、私には書くことが必要だった。文章を書くのは好きだった。夜遅くまで起きて、自分の内面とじっくり向き合いながら、何時間もかけて言葉を紡いだ。とにかく、時間がかかった。あの時は確かに夢中で、没頭していて、楽しかった。
とはいえ、常に自分の言葉ばかり見つめていたわけではない。高三の時、選択科目で文芸批評の授業があった。友達、というほどではない、そこでしか会わない人たちと文学を通じて交流するのが楽しかった。そこで積極的にしゃべることも、私はあまり得意ではなかったけれど、それでも楽しかった。友達、というほどではない、たった週一回のつながりだったけれど、私はその空間を共有していた人たちの名前をしっかり覚えていて、それぞれの言葉に表れた人柄、良いところも知った気になっていた。あの時間は私にとってすごく大切なもので、あの場所が、本当に大好きだった。一年で授業が終わって、もうこのメンバーで集まることもないのかと思うととても寂しくて、そんなことを言うようなキャラでもなかったから、また、言葉を心にしまう羽目になった。
高校生の頃は、確か、忘れられたくないと強く思っていた。自分は、友達でもちょっと関わっただけの他人でも、言葉を交わしてああいいなと思えたつながりは忘れないでいられる自信があったから、でも向こうは違うんだろうなと、そのアンバランスさが嫌だった、ような気がする。……ちょっと、正直今はよくわからない。作家になりたい、という夢があったけれど、それも純粋に好きなことを仕事にしたいというよりはなんとかして自分の名前と言葉を残したい、死んでも忘れられない人になりたいという気持ちが強かった、確か。……今は、そんな願望はない。こんな風に自分が変わってしまうことが怖かった。私は、他でもない自分自身に忘れられてしまうことが、一番怖かった。過去の自分の悩みや怒り、心にたまった複雑な気持ちを、くだらないことだったと笑い飛ばすような大人にだけはなりたくないと思った。その方が気楽で生きやすくなるとしても。
そんなことを思い出しながら、久しぶりに高校生の時に書いた脚本を読み返してみた。書いた時のことを忘れたわけではないし、確かに自分の文章なのだけれど、他人の言葉に触れているような感覚になった。言葉が嫌いな登場人物の台詞が印象的だった。
「言葉なんて、みんなのものでしょ? 私は、私でしかないのに、言葉を使って生きなきゃいけないなんて、そんなの……」
「仕方ないよ。『変』とか『おかしい』とか『気持ち悪い』とか『異常』だとか、誰が作ったか知らないけど、そんな言葉がさ、生まれる前からあるんだよ。そりゃ使うよね、普通の子たちのためにある言葉だもん。普通は使うよね……」
些細な言葉に傷つきよく悩んでいて、言葉なんてなかったらよかったのにと憎みながら、それでも必死に言葉で表現しようともがいていたあの頃の自分の切実さが表れた言葉。こういうものは、きっと、今の自分からは生まれてこない。ああ、なんかいいなあ、と素直に思えた。言葉にして残しておいてよかった。
大学でも文芸批評がしたいと思い、選択基礎演習をとった。自分の作品について、「会話がとても自然に書けている」と言ってもらえたのがとても嬉しかった。思えば、高校生の頃は会話を書くのにかなり苦労していた。どうしても説明的で現実にありそうにない会話になってしまって、自分の下手さによく落ち込んでいた。時間をかけて向き合ってたくさん書いていくうちにしっかり成長していたんだなあと実感できて、嬉しかった。「自分はこういう風には書けない」という言い方をしてもらったのも印象的だった。自分の文章にはあまり自信がなかったけれど、自分の文章は自分だけのもので、他の人の文章もその人にしか書けないもので、それは、それだけで凄いことだと思えた。
作品、批評の言葉、話し方から、それまで様々な生き方をしてきたそれぞれの人柄、個性が伝わってきて、毎回、ああ良いな、と思えた。たくさんの素敵な言葉に出会えた。できることならその全てを覚えておきたいと思った。だからできるだけ書き留めた。全てというのは無理があるけれど。
色々な人と関わって、色々な言葉に刺激を受けた、その時々の自分を言葉にして、しばらくたって再会すれば、きっとまた面白い。タイムカプセルのような宝物が増えていく。これからもずっと、書くことを続けていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
