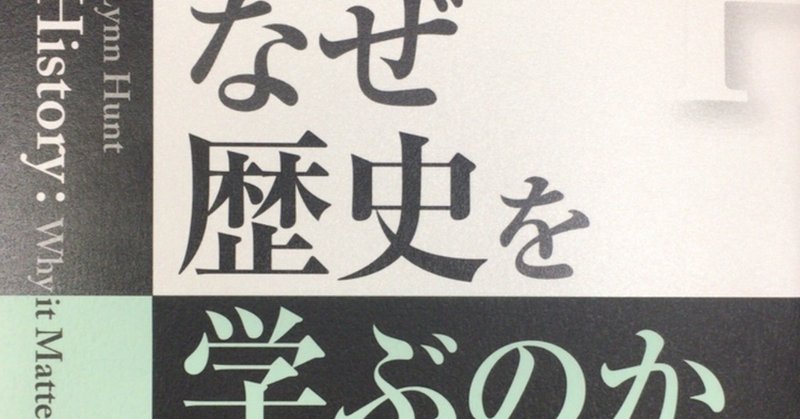
「21世紀版『歴史とは何か』(E・H・カー)」なる本が出版されていたので読んでみた
「"歴史学"の入門書でお薦めの本はありますか?」
後輩さんからこのような質問を投げかけられるたびに、私は「少し分かりにくい所もあるだろうけど……」と注意書きを付せて、E・H・カーの『歴史とは何か』(清水幾太郎訳、岩波新書、1962年)を薦めてきた。
なぜこの本を薦めるのかといえば、理由は単純で、私が幾人もの教授、講師、先輩方に「読むべし!」と薦められてきたからである。内容的な面を考えれば、「歴史」(及び歴史学)の入門書としては、事前に抑えておかなければならない基礎知識が多すぎるため、まだ大学で学び始めたばかりの後輩さんには積極的に薦めることができないでいた。
「『歴史とは何か』の代わりとなる歴史学の入門書はないかなー」
私は本屋に足を運ぶたびに、上記の悩みを頭の片隅に留めながら、棚に並ぶ本を眺めていた。
すると先日、ある本の帯に面白い一文を見出し、「おお!」と思わず手に取った。
その一文とは、
「欧米の歴史学界を牽引してきた著者による、『歴史とは何か』(E・H・カー)の21世紀版。」
である。
帯が巻かれた本のタイトルは、『なぜ歴史を学ぶのか』。出版元は、『歴史とは何か』と同じ「岩波書店」である。
「岩波書店が「21世紀版」として売り出しているのか。なるほど」と頷きながら、次に著者のリン・ハントの略歴を確認する。
「1945年生まれ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校名誉教授。著書に『人権を創造する』(松浦義弘訳、岩波書店)、『フランス革命の政治文化』(松浦訳)、『フランス革命と家族ロマンス』(西川長夫ほか訳、以上、平凡社)、『グローバル時代の歴史学』(長谷川貴彦訳)、編著に『文化の新しい歴史学』(筒井清忠訳、以上、岩波書店)など多数。」(以上、引用)
「……この本、期待できるかもしれない」
私は二三分のうちに購入を決意し、会計場へ。
期待を胸に膨らませながら、家路についた。
**********************************
今回は、リン・ハント著、長谷川貴彦訳『なぜ歴史を学ぶのか』(岩波書店、2019)について、その中身を7つのポイントに分けて紹介したいと思う。(以下で示される引用文は、すべて『なぜ歴史を学ぶのか』からのものである。)
①インターネット時代、ソーシャル・メディアの発達を踏まえた考察
E・H・カーが『歴史とは何か』の元となった講演を行ったのは1961年。当時はまだインターネットという概念は世に存在していなかったため、当然ながら本の中で言及されることもなかった。一方で、『なぜ歴史を学ぶのか』においては、当然インターネット社会の現状をきちんと反映させた上で、さらに「SNSの普及」などの「ソーシャル・メディアの発達」について注目し、議論を展開している。
「歴史についてのあからさまな嘘は、ソーシャル・メディアの影響によって、より一般的な現象となっている。インターネットが、歴史的嘘が増殖するのを可能としている。というのも、インターネット上では、事実上、事前の検閲なしに、そして一切の制裁もなく、誰でも、どのような名前でも、そしてどのような内容でも投稿することが可能だからだ。きわめて異様な主張が広範囲に流通し、ただ流通しているという理由で一定の信用を獲得している。こうした状況において、歴史的真実を主張することは、市民として勇気が要ることだが、必要な行為となっている。」(P4)
かつての「歴史」というのは、一部の権力者や知識人の手によって編み出され、提示"される"ものであった。常に「受け身」である。しかし、現代社会においては、誰もがインターネット上に、「歴史」に纏わる自身の考えを発表したり、他人の「歴史」に纏わる意見に対して賛同や批判を示すことができるようになっている。そこにはほとんどの場合、「学術的な検証」が加えられることはない。このことは、日頃Twitterを見ていて、「ユダヤ人虐殺はなかった」というツイートが目に入るときがあることからも、容易に察することができる。
私たちは「受信者」「発信者」という二つの立場から、「歴史」と向き合っていかなければならない。
②「歴史」を巡る日本の事例に言及
『なぜ歴史を学ぶのか』においては、「歴史」が争点となっている政治的事象が数多く紹介されている。残念なことに、日本はその「政治的事象」の実例の一つを提供している。その実例とは、「教科書」の記述を巡る議論(=「教科書論争」)である。
「歴史教科書は、常に改訂され続けている。しかし、そのことは教科書をさらに論争的なものにしているにすぎない。二〇一五年の日本で、ひとりの東京都知事候補が主張したのは、「敗戦国としての私たちは、勝者によって強制された歴史のみを教えている」ということであった。彼は続けて言う。「再び独立国家となるには、私たちに押しつけられた歴史を乗り越えてゆかねばならない」と。彼の主張によれば、日本は第二次世界大戦において侵略者ではなく、一九三七年の中国の南京における悪名高き虐殺事件にも関与していないことになる。日本軍兵士のために朝鮮半島の女性を強制的に「慰安婦」(性奴隷)にしてはいなかった。この論争は、新しいものではない。一〇年前の二〇〇五年には、中国と韓国のデモ参加者が日本の「新しい歴史教科書をつくる会」による教科書の書き換えに抗議している。日本の第二次世界大戦における過失を矮小化していると主張し、デモ参加者は日本の国旗を焼却し、日本製品の不買を求めたのだった。」(P11)
③ランケを出発点に「歴史学の歩み」(歴史学史)を振り返る。
『なぜ歴史を学ぶのか』には、著者による「読書案内」の頁が設けられているのだが、その冒頭に以下のような指摘がある。
「多くの歴史系学科では、ひとつの学問分野としての歴史哲学や史学史といった科目は必修とはしなくなっている。歴史家は、みずからの研究領域に専念して、地理的ならびに時代的なものでおよそ定義される独自の分野の議論にほとんどの関心を集中するようになっている。」(P109)
自分の学生生活を振り返ってみると、明治以降の日本の歴史学の歩みについては、ある程度学ぶことができたとは思うが、西洋の歴史学史までと言われると、恥ずかしながら「基礎の基礎」レベルにしか把握できていない現状がある。
このようなお粗末な状況を改善する上で、『なぜ歴史を学ぶのか』は便利な一冊であると言える。近代歴史学の創設者の一人であるレオポルド・フォン・ランケを出発点に、E・H・カー、ディペーシュ・チャクラバルティ、パルタ・チャタジーなど、「西洋中心の近代歴史学」から「脱・西洋中心の現代歴史学」にいたるまでの歩みが描出されており、大変参考になった。
(以下の文章は、ランケの歴史学における姿勢を示した文章。「西洋中心」という偏りをもった初期の歴史学の中にも、学ぶべき精神は存在することが分かる。)
「歴史学の創設者のひとりであるレオポルド・フォン・ランケは一八二四年に、未来の世代に教訓を垂れるために過去を断罪する目的で歴史を書いているわけではない、という有名な言葉を残した。彼は「あるがままの事実」を語ろうと欲したにすぎないのだ。研究者のなかには、歴史家は過去を完璧には再構成できないと論じて、ランケの素朴と思われる見解をもって彼を批判するものもいたが、私たちが過去を知りうるのは、痕跡、すなわち時代を超えて私たちのもとに伝わってくる断片を通じてのみである。私たちはあるがままの事実を知ることはできないのだ。しかし、こうした批判は誤謬である。ランケは自分の視点の不完全性を告白している。つまり「歴史家の意図は、その視点に依存している」ことを認めていたのだ。しかし、彼は依然として歴史の読者を説得して、視座を拡大させることを望んでいた。」(P40)
④戦前期の日本における歴史学の成立過程・機能を指摘
西洋で確立された近代歴史学の解説に加えて、『なぜ歴史を学ぶのか』においては、明治期に整備されていった日本の歴史学の歩みについても詳述されている。
「一八八七年に東京大学が史学科を設立したときは、ヨーロッパ史だけを教授していた。その最初の教授は、ベルリンから来たドイツ人の歴史家、ルートヴィッヒ・リースであった。彼はランケの弟子で、英国国制史の専門家であった。のちに史学科が拡張されて、日本史や「東洋史」を含むようになったが、「西洋史」はドイツ、英国、フランス史から構成されていた。というのも、それらの国は歴史実践と近代国民国家の発展のモデルと考えられていたからだった。」(P47)
また、「ランケ⇒リース」の流れで日本に持ち込まれた「歴史学」の手法が、どう日本の近代化において役立てられたのかについても記述がある。(個人的な感想として、「辻善之助」の名前が挙げられていたことには、少し驚いた。)
「日本の歴史家は、ランケの手続きを用いて、日本のナショナリズムを昂揚するひとつの方法として天皇制の伝統を支持した。彼らは、ヨーロッパ的な文明の観念を独自の目的に適用したのである。一八六九年に明治天皇は、日本が文明を代表するような「文明と野蛮を明確に区別する歴史」を依頼した。二〇世紀前半の日本の指導的な歴史家である辻善之助は、日本は儒教や仏教などの外国の要素を吸収したが、独自の形態でそれらを受け入れたのだ、と一九五〇年に論じた。その結果、「東洋文化の本質は、日本だけに含まれている」としたのである。」(P49)
⑤マイノリティと歴史学の関係性を分析
西洋で成立した歴史学には、様々な「外部」、言い換えると「マイノリティ」が設定されていた。本書では、その中でも「東洋」と「女性」に注目して、議論が展開されている。特に注目すべきは、「歴史学という専門職における女性」に注目した文章で、いかに「歴史学」という学問が「男性中心」でまわってきたのかが、一女性として長年歴史学と向き合ってきた著者(リン・ハント)の実体験も踏まえた上で、浮き彫りにされている。
「合衆国での歴史学という専門職における女性の地位は、実際は一九五〇年代や六〇年代に低下していたし、多くの総合大学の歴史学科は一九七〇年代にいたるまで女性の雇用することに抵抗した。一九七四年に、私がカリフォルニア大学バークレー校の助教授に任命されたとき、サーモン(引用者註:ミシガン大学で最初に女性に認められた学士号を取得した女性)が最初の学位を獲得してから五〇年あまりがたっていたが、歴史学科に採用された女性としては、四人目にすぎなかった。」(P64)
⑥「歴史」そのものの分析
『なぜ歴史を学ぶのか』における「歴史」の捉え方については、主として「歴史的真実の二層構造」を理解しておく必要がある。
「歴史的真実は二層構造になっている。第一の段階では事実が問題となり、第二の段階では解釈が問題となる。議論する目的でそれらを分離することは可能だが、現実の歴史実践のなかでは、ふたつは相互に結びついている。事実というものは、意味を与える解釈に組み込まなければ、動き出すものではない。そして解釈のもつ影響力は、事実に意味を与える力を基盤としている。」(P27)
宮沢賢治を例に、事実と解釈について考えてみたい。「宮沢賢治は『銀河鉄道の夜』を執筆した」というのは、疑いようのない「事実」である。そこには議論の余地はない。次に「なぜ宮沢賢治は『銀河鉄道の夜』を執筆したのか」という段に入ると、そこには様々な「解釈」が生じる。これらの「解釈」は、すべて「宮沢賢治は『銀河鉄道の夜』を執筆した」という「事実」を前提としてのみ成立している。これが「歴史的真実の二層構造」である。
テレビのコメントやSNSのツイートなどを見ていると、時折この二層構造がごちゃまぜになっている事態に遭遇することがある。「南京大虐殺はあった」という「事実」と、「南京大虐殺では○○人の方が殺された」という「解釈」を十把一絡げに「否定」する姿勢には、注意の目を向けなければならない。
⑦「アカデミックな歴史」と「通俗的な歴史」の緊張関係を分析
2018年11月に刊行された百田尚樹『日本国紀』(幻冬舎)は、ウィキペディアやNAVERまとめなどからの転用疑惑が指摘され、大変な騒ぎとなった。
一方で、一程度の読者が『日本国紀』を手にして読んだ事実を考えるとき、「アカデミックな歴史」に携わる学者は、ただただ研究に没頭するだけでなく、できるだけ多くの人が手に取れるような「入門書」「研究書」の作成にもチャレンジすることが求められていると言える。
「アカデミックな歴史と通俗的な歴史の緊張関係は、一八〇〇年代に歴史学の専門職が誕生して以来、多様な形態をとってきた。ウォルター・スコットのベストセラー小説のように通俗的歴史や歴史小説は、一七八九年のフランス革命後の数十年に歴史叙述に対する広範な読者層を引きつけてきた。逆説的なことだが、フランスの革命家たちは、封建制という過去との断絶への強い意志をもって、過去に対する研究を促していった。そうした研究は、あまり馴染みがないもので、既成の歴史とは異なるものに思われたのは間違いなかろう。しかし、その後に歴史が大学を基盤として専門職となるにしたがい、アカデミックな歴史家は通俗的な歴史について、史料的には不十分であり、歴史研究上の議論からすれば独自性がなく、そこから学んでいないものとして扱い始めた。
しかし同時に、自然科学をモデルとした専門家の増大は、アカデミックな歴史叙述をかつてないほど難解で、仲間内の少数の研究者にのみ理解可能なものとしていった。」(P100)
**********************************
以上、『なぜ歴史を学ぶのか』の中身を「7つのポイント」に分けて紹介しました。
分かりにくい記述が多々あったと思いますので、ぜひ実際に手に取って中身を確認して頂ければと思います。
今後私は、『なぜ歴史を学ぶのか』を「歴史学の入門書」として後輩さんに薦めていくつもりです。
「後輩さんが読了後、どんな反応を示すのか」――今から楽しみにしています。
今回は「「21世紀版『歴史とは何か』(E・H・カー)」なる本が出版されていたので読んでみた」をお読み頂き、ありがとうございました。
※※サポートのお願い※※
noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。「本ノ猪」をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
