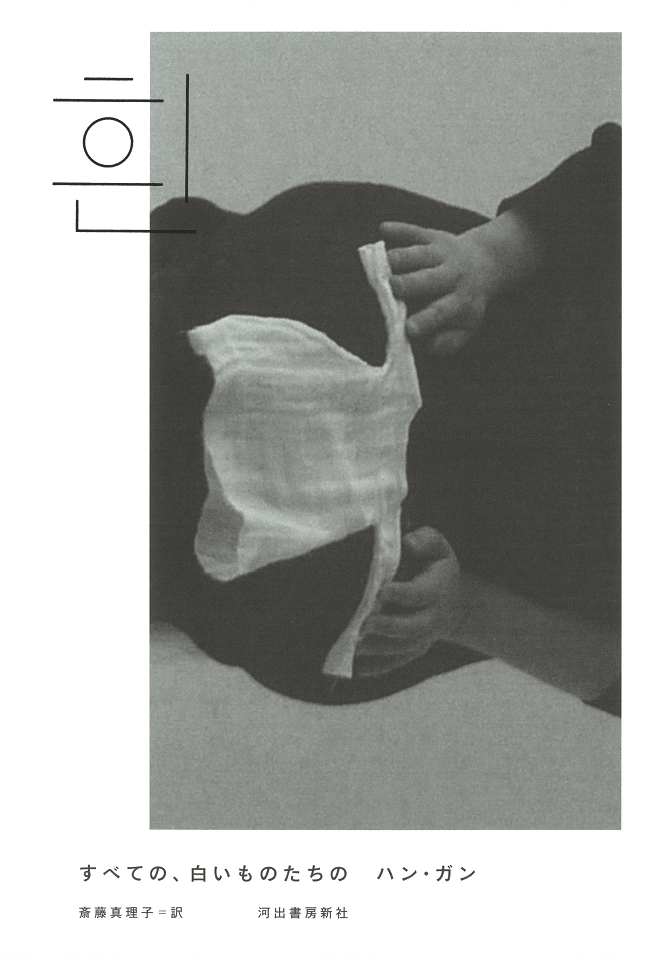リレーエッセイ「わたしの2選」/『雪の階』『すべての、白いものたちの』(紹介する人: 下田明子)
翻訳者の下田明子です。お勧めしたい本は山のようにあるのですが、中でも最近、まったく違った方向からわたしの心に飛びこんできた2冊をご紹介したいと思います。純粋に本を読む喜びを思い出させてくれた大切な2冊です。
『雪の階』
数年前、ふらっと立ち寄った近所の書店で、こちらをまっすぐ見つめてくる1冊の本に会った。その視線に吸い寄せられるようにして手に取り、そのままレジへ向かっていた。よく行く書店だが、こんな経験は初めてだ。この話を人にすると、「へえ、それどういう本なの」と聞かれることが多いが、ひと言で答えられたためしがない。帯には「ミステリーロマン」と銘打ってあり、たしかに人が死んでその事件を解決するという形式はミステリーといえるかもしれないが、読んでいる間も読み終わってからもそう感じたことはないように思う。
奥泉光『雪の階』(2018, 中央公論新社)
二・二六事件前夜の昭和初頭、伯爵令嬢の笹宮惟佐子は親友の心中事件に疑問を感じ、秘密を探るうち国の運命を左右するような事件にかかわるようになる。そのあたりまでは、華族のお嬢様の冒険譚といった雰囲気だったのが、読み進めるうち次第に大きな政治の話にふくらんでいく物語の筆運びが絶妙で、息が詰まるような思いで六百ページ弱を読み切った。やがて太平洋戦争へと突き進んでいく昭和十年代の空気が色濃く描かれ、わたしが子どもの頃から感じていた「あの戦争はなぜ起こったのか」という疑問への答えにつながるヒントが隠されているような気がする。
ただ、わかりやすい作品ではない。筋も複雑だし、たくさんの謎や伏線が縦横無尽に張りめぐらされている。謎は読むたびにむしろ深まっていき、その最たるものは主人公である惟佐子のキャラクターだろう。容貌についての具体的な記述はほとんどないが、「のっぺりとしていながら何ともいえぬ陰花の色香を放つ顔立ち(15ページ)」だという。なんともこちらの想像力をかき立てる表現ではないか。惟佐子以外の人々は、姿かたちがわりとくっきりしている。惟佐子の「おあいてさん」で、もう一人の主人公ともいうべき千代子は、その頃の言葉で言えば「職業婦人」で、仕事に打ち込みつつ昔ながらの価値観に縛られて思い悩む姿も、ごく平凡で善良な人となりも、目の前に立ち現れてくるようだ。新聞記者との恋の行方が気になって、思わず感情移入してしまったりもする。他の登場人物にしても、世間に認められたくて懸命に策略をめぐらす伯爵、あわよくば若い華族の令嬢と親密な関係を結ぼうと群がってくる男性たちなど、その姿がありありと浮かぶ人ばかり。それなのに、惟佐子に関してだけは終始、紗を通して遠くから眺めているような不思議な感覚を覚えるのだ。
心のうちをほとんど人に見せない惟佐子の印象は、物語の中盤以降にくるくると変わっていき、同じ人を描いているのかと思うくらいだ。周囲にいる人たちと同じく自分も彼女の変化に驚き、次にどんな顔を見せてくれるのかとひそかに期待したりもした。また、次々に移り変わる視点も物語の謎めいた雰囲気を強めている。惟佐子の目を通して見ていたはずの人物が突然こちらに向かって自分の思いを語りかけてきたり、客観的に描かれていた情景が千代子の視点からのものにすり替わっていたり。おかげで読んでいるこちらの立ち位置はとても不安定になるが、それでもその不安定さこそがこの作品の魅力になっているから不思議だ。全体を通して感じる不穏な空気、たいへんなことがすぐそこまでやってきているという予感、それはもしかしたら、この時代を生きた人々の多くが抱いていた感情と似ているのかもしれない。そして、その予感どおり物語が悲劇的な結末へと一気に向かうスピード感あふれる展開に、呼吸が苦しくなるほど圧倒された。
この本を読んでわたしが知識や教訓を得たかと聞かれれば、それはないと答えるだろう。感動したという言葉も当てはまらないような気がする。どんな本か、どこがいいのか、ひと言で言えないのはそのせいかもしれない。でも読んでいる間はただただ物語の世界に入りこんで自由に漂い、読んだ後はずっとその世界を思い出して幸せな気持ちに浸っている。それは、大人になってからいつの間にか忘れていた純粋な読書の喜びだと思う。そう気づいてとても嬉しかった。だから、あのときの書店での出会いに、わたしは今でも感謝している。
『すべての、白いものたちの』
次に紹介するのはまったく趣の違うこの作品だが、どうしてこれを読むことになったのか、不思議なことにそのいきさつをよく覚えていない。誰かからの勧めだったのか、書評欄で見たのか、とにかく気づいたらこの本がここにあった、という感じだ。
ハン・ガン著/斎藤 真理子 訳『すべての、白いものたちの』(2018, 河出書房新社)
詩のような本だった。寂しくて、清冽で、心の深いところに直接語りかけてくるような。題名どおり、登場するのはさまざまな「白いものたち」だ。「おくるみ」では生まれたばかりの赤ん坊を亡くす母親の様子が描かれ、わたしはのっけから打ちのめされてしまった。若い母親の底知れぬ悲しみと、それを聞かされて育った「彼女」の苦しみとに。それはずっと後、最終章まで続く白いものたちをめぐる語りの背骨になっているようだ。最後に近いエピソードでは、死んだ我が子をおくるみにくるんで山に埋めたという父親の話も加わり、悲しみは重層的になっていく。癒えることがなく、両親を通して「彼女」の中にも深く植えつけられた悲しみは、くり返される「しなないで しなないでおねがい」という祈りになって物語の底を流れる。
ソウルの凍てついた冬を過ごす間も、第二次世界大戦で破壊されたというワルシャワ(とは書かれていないが)の街の歴史を思うときも、彼女の頭からは生と死をめぐる思いが離れず、白いものたちはすべてその思いを表現するためのもののように思える。
「彼女」(著者自身か)は自分が生きていることに罪の意識を覚えていたのだろうか。この世に存在して、息をして、さまざまなものを見たり聞いたり感じたりすることに、後ろめたさを感じていたのだろうか。
たとえそうだとしても、彼女が慰めを見出したことをわたしは願わずにいられない。希望は「レースのカーテン」の一節にある。きれいに洗った白い枕カバーとふとんカバーに包まれる「彼女」はこんなふうに思う。
そこに彼女の肌が触れるとき、純綿の白い布は語りかけてくるかのよう。あなたは大切な人であり、あなたは清潔な眠りに守られるべきで、あなたが生きていることは恥ではないと。そして眠りと目覚めのあわいで、純綿のベッドカバーと素肌がさわさわと触れ合うとき、彼女はふしぎな慰めに包まれる。(「すべての、白いものたちの」89ページ)
悲しみを抱えて生きていくこと。戻らない時間を思いながら生きていくこと。この1年あまり、激変した世界で暮らしながら、わたしの中にもいろいろな思いが浮かんでは消えていった。そして、奇しくも世界が変わる直前に読んだ『すべての、白いものたちの』を、変わった後の世界で読み返してみたら、悲しみも痛みも前よりもっと強く深く突き刺さってくるのに驚いた。それはおそらく、わたし自身が変わったしるしなのだろう。自分や社会が変われば、同じ本を読んでも受け取るものは変わる。とてもおもしろいことだと思う。だから何か月後か何年後かはわからないけれど、もう一度読み返したときに自分がこの本をどう感じるのか、それが今から楽しみでもある。
■執筆者プロフィール 下田明子(しもだあきこ)
英日翻訳者。訳書に『300点の写真とイラストで大図解 世界史』(ジェレミー・ブラック著・ニュートン・プレス社)、共訳書に『若い読者のためのアメリカ史』(ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン著・すばる舎)、『パスタ』(クーネマン社)、『エコ・デザイン・ハンドブック』(アラステア・ファード=ルーク著・六耀社)がある。翻訳は苦しいけれど楽しい仕事。おばあさんになっても続けたい。今一番したいことは海外旅行だけれど、まだ当分は無理かなと思うので、当面は旅番組を観ながら、ガイドブックをめくりながら旅の計画を練る日々が続く。
よろしければサポートお願いします! 翻訳や言葉に関するコンテンツをお届けしていきます。