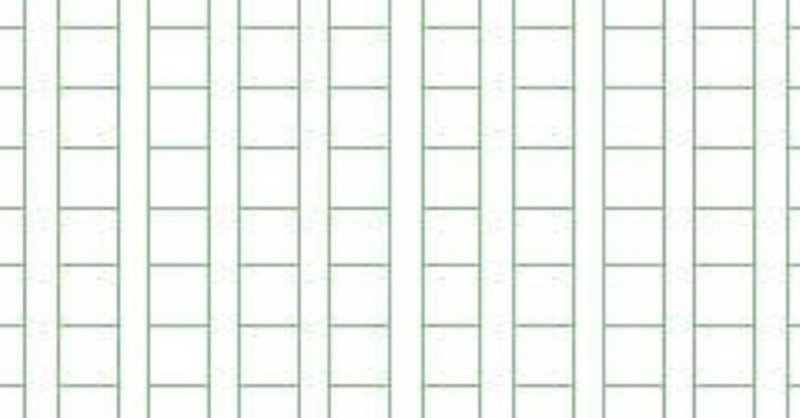
「この世界の片隅に」を毎年観る
【ネタバレは極力ありませんが多少内容に触れていますのでご注意ください】
映画「この世界の片隅に」は何度観ても傑作だ。縁あって原画展なども見に行っていたのでハードルも上がっていたのだが軽々と越えていった。
6年の歳月をかけ、4000万円近い資金をクラウドファンディングで集め、こうの史代さんの原作を「マイマイ新子と千年の魔法」の片渕須直さんが監督したアニメーション映画である。
舞台は戦時中の広島県呉市。若くして呉市に嫁いだ少女「すずさん」と「すずさん」の日常(戦争とはまったく関係がないと思えるほどの普遍的な日常)が、日本が終戦に向かう中でどう変化をしていくのかという物語である、というのが当たり障りのないあらすじかと思う。
しかし、この映画を語るにあたって、本当は戦争というものを避けては通れないはずなのであるが、避けて語れる気にさせるところに「この世界の片隅に」の魅力の源がある。この映画から戦争というファクターをまるっと抜いても十分に意味のある映画であろうと思えるからだ。
絵を描くことだけが得意だった呑気な少女が好きではないがいい人そうな男と結婚して嫁いだ先の家とはそりゃいろいろあって昔好きだった男もそりゃいてそれでも生活するってことは自分のせいでいろいろあるからいつの間にか夫やその家が彼女の唯一の居場所になっていく。そんな物語がとても丁寧に描かれる。美しいアニメーションと実力派声優たち(主演の「のん」は出色の出来である)によって尊いものとして描かれる。
そしてふと気がつくのである。映画を観ている最中に「ああ、これが戦時中の設定でなければいいのに」と思ってしまった自分に気がつくのである。そして観る者にそう思わせた頃、戦争の足音がいよいよ物語を侵食しはじめる。前述の戦争以外の物語が求めるであろう「起承転結」を容赦なく突然に所かまわず壊しはじめる。
「この世界の片隅に」が優れているのは先の戦争やそれ関わる人の物語を描くのではなく、戦争のせいで成立しなかった個人の人生の物語を描いているからだ。
別に人に誇れるような物語じゃないかもしれない。笑い飛ばせるような悩みしかないかもしれない。揶揄されるような小さな努力しかできていないかもしれない。それでも、一人ひとりの物語はその人で完結しなければならないのだ。自ら選んだ「起承転結」でなければならないのだ。それが許されないことへの怒りが主人公「すずさん」を変えていく。
ネタバレになるため多くは書けないが、絵を描くことだけが得意だった呑気な「青春映画の主人公」だった少女が、一端の「戦争映画の主人公」になっていかざるをえないのである。
このコントラストがあまりにも強烈なため、観客は涙する余裕もない。もっと涙する余裕を与える作り方もできただろうけれど、この映画はそれをしない。涙することがあるとすれば、すべてを観終わった後に自分の生活を見回してそこに「すずさん」を重ねたときだろうと思う。
「この世界の片隅に」は軍港である呉市を舞台としているから、作中には登場人物たちが丘の上から戦艦やら巡視艇やらを眺めるシーンが幾度となくあるが、子供のために景色として写生をしていたり、「あれはなに?」「あれは大和で武蔵」とまるで遠くに見える山の名前でも言うように会話をしたりしている。そんな自分たちの後ろに建つ家には炊き立てのご飯や干しっぱなしにした布団、面倒くさい小姑なんかがいる。丘の向こうもこっちも、どっちも「この世界」なのである。
同じ意味で、戦時中も今もどっちもこの世界であり、そしてそんな無数の「片隅」が集まってこの世界なのである。その素晴らしさと恐ろしさを知った上で、では、どう生きるか。そう問うてくる映画であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
