
「気高さ」に触れるとき
「自己肯定の鬼」というタイトルで臆面もなく投稿するほど、私は自己肯定感が強い。
だが、そんな鬼にも死角はある。
「どうあがいても今生では手が届きそうもないな」という善き属性がある。今生は「こんじょう」と読むのじゃよ、若いの……。
それは、「気高さ」という美徳だ。
こればかりは、今生どころか、3回生まれ変わっても無理そうだ。
SARSから世界を救った医師
「気高さ」とは、どんな属性だろう。
今、真っ先に浮かぶのは、新型コロナウイルスとの戦いの最前線にいる医療関係者だ。
その姿を思い浮かべるとき、私はカルロ・ウルバニという一人の医師の生涯を思い出す。少しWikipediaから引きます。
国境なき医師団イタリア支部の会長を務め、1999年に同組織がノーベル平和賞を受賞した際には、授賞式に参加する代表団の一人であった。アンコーナ大学で医学博士号を取得した後、世界保健機関に採用され、ベトナムのハノイで主に寄生虫感染症の対策に取り組むことになる。
2003年2月の後半、中国からの旅行者を治療したベトナムの医療従事者の間で急速に重度化する肺炎が見られた。彼は、この症候群を従来にないものと判断し、SARSという新病だと認定した。さらに、これが飛沫感染によるものと判断し、病棟の隔離処置を行った。この前後に彼はSARSに感染したものと思われる。同年3月11日にタイのバンコクを会議出席のため訪れた際に発症し、同地で46歳でこの世を去った。
彼の警告により、世界保健機構は各国への警報を発することができ、ベトナムにおいてはSARSの大規模な流行を防ぐことができた。
NHKの特集番組を元にした本があるはずだが、引っ越しの混乱で発見できない。再読しようにも、Amazonでは古本が高騰している……。
NHKさん! 今こそ重版&再放送を!
詳細はWikipediaと本に譲りますが、ウルバニ氏はSARSと戦ってパンデミックを防ぎ、自身も感染して命を落とした医師だ。
死の直前の行動への批判はあろうが、私はその人間らしい振る舞いも含め、その生き方に心を揺さぶられる。
新型コロナウイルスが猛威を振るう今、世界には「名も知れぬウルバニたち」が医療の最前線で戦っているだろう。実際、医療関係者の感染のニュースを耳にすることは増えている。
今日(4月10日)は、今や戦場と化したニューヨークで治療と情報発信を続けていた日本人医師・宮下氏の感染という胸が痛むニュースが伝わってきた。
本来、こうしたことが起きないよう万全の態勢がとられるべきであり、簡単に美談にしてしまってはいけないとは思う。
それでも、医療リソースが枯渇するなか、使命感を持って持ち場を守る方々には「頭が下がる」という言葉しか出てこない。
「気高さ」を教えてくれた少女
さて、毎度で恐縮だが、私は「ヒルビリー」だったので、育ちがあまりよくない。
動物園以下と言ったら動物に失礼みたいな中学校なんて、「気高さ」とは無縁と思うかもしれない。
だが、そうでもなかった。
むしろ、そんな中で出会ったからこそ「気高さ」の記憶は鮮明だ。
忘れられない思い出が2つある。
1つは2年生のクラスメートだった、ある女の子のエピソード。
ここでは「田村良子さん」としておこう。『寄生獣』っぽいが、穏やかで、真面目な、なぜかちょっとスラブ系の美人さんであった。
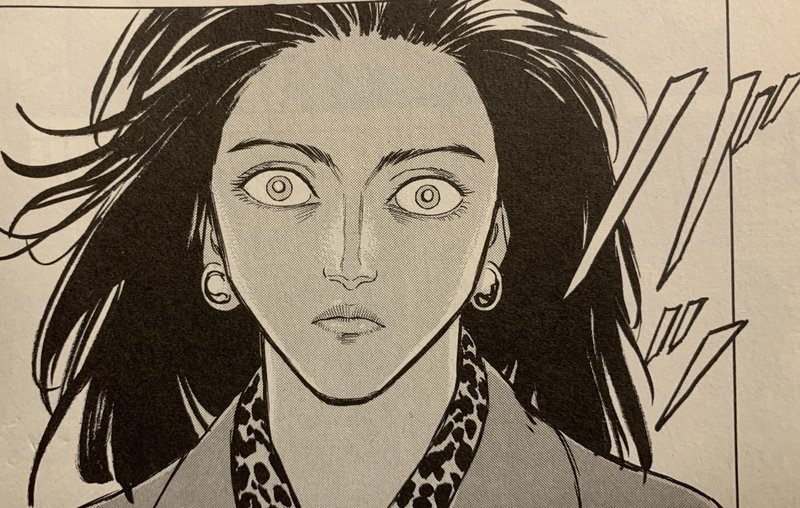
(違う違う、そうじゃない)
田村さんは「超」がつく優等生だった。定期テストはほぼ常に学年トップ。
ちなみに高井さんはそのころ学年100位くらいをウロウロしていた。市内屈指の底辺校だったので、3桁はかなりしょっぱい。
田村さんは数学が得意でほぼ毎テスト、満点をとっていた。
そのうち数学教師がコンプリート阻止のため「対田村」の超難題を1問だけテストに混ぜるようになった。大人げないぞ、S光(〇〇みつ、と読む珍しい苗字でした)。
ところが田村さんはそれもヒョイっと解いて100点を取る。
テストを返すとき、S光は「田村さん、100点!」と読み上げた後、リアルに「くそぉおおお!!」と叫んでいた。
大人げないとかいうレベルじゃないぞ、S光。
そんな「対田村攻略戦」が3度も続いた。
アホだ。
アホな教師による、アホな中学にふさわしくない、アホな試みだ。
その試みも失敗に終わり、3連敗したS光がついに白旗をあげた。
3度目の「田村さん、100点! くそぉおおおお!!」の後、S光は「参りました!!!」と叫び、生徒にこう呼びかけた。
「みなさん! これから田村さんを、敬意をこめて『おりょうさん』と呼びましょう! それでは一緒に! せーの!」
「おりょうさん!」
ちゃんとクラスみんなで唱和した。
昭和だなぁ……って、すいません、筆が滑りました。
ここまでは前振りである。
そんな田村さんがあるテストで、いつものように100点を取った。
私はたまたま田村さんの隣の席で、一緒に答え合わせをやっていた。
すると田村さんが「あ……」と小さな声を漏らした。
「私、ここ、間違えてる」
それは単純な計算ミスで、おそらく教師は「田村さんがこんなところで間違えるはずが無い」と勢いでマルをつけてしまったのであろう。
「お。得したね」
点が上がる方向の採点ミスは大歓迎という主義の高井少年(今もそうだ)は当然のように気高くない言葉を返した。
しかし、田村さんは違った。
「うーん。こういうのは気分が良くない」
そう言うと、「やめときなよ! もったいないよ!」と引き留める高井少年を振り切り、S光に申し出て減点してもらった。
その時、彼女がこぼした言葉はよく覚えている。
「前に同じような採点ミスで『ま、いいか』って黙ってたんだ。でも、後から『採点ミスでトップとった』って言われた。そういうのは嫌だから」
その定期テストで、田村さんは自己申告の減点をモノともせずに学年トップの座を守ったのだった。
「なんという男前な女や!」
この出来事に深く感銘を受け、一緒に学級委員(更生のけじめ的な気分でやったんだよな……)などやるうちに仲良くなって、「この人、なんだか自分とは別世界の人だ!」という言動にたびたび触れた。
ポニーテールが似合うスラブ系の美人さんの優等生は、県内トップクラスの名門高校に進み、出遅れ受験生だった高井さんは2番手グループがせいぜいで高校からは進路が分かれてしまった。
その後、田村さんは医大に進み、医師になったと知った。
違和感なさすぎだ。
立派な、もしかしたら立派過ぎて自分自身が大変になっちゃうタイプのお医者さんになっているんじゃないかと勝手に心配してしまうほど、立派なお医者さんになっているに違いない。
これが私が生身の人間に「気高さ」を感じた、おそらく初めての体験だった。
心優しきマイク・タイソン
もう一つ、中学時代の気高き友人のエピソードを。こちらは男子だ。
プライバシー保護のため「前ピ」というニックネームで通す。「前〇」という苗字になぜ「ピ」がついたかは知らない。
前ピは、普通に不良というか、ヤンキーっぽい少年だった。タバコを吸ったり、バイクを乗り回したりはしていた。
でも、マンガのキャラみたいな「弱きを助け、強きをくじく」タイプの心優しいヤンキーだった。
身長は低めだが、ケンカは滅法強かった。マイク・タイソンみたいな体型で、パンチもハートも強い。ギターもちょっとうまかった。
おまけに、ちょっと『スタンド・バイ・ミー』のクリスみたいに、ふとした表情と背中に哀愁があった。
男が惚れる男だ。かっこよかったなぁ、前ピ。
そんな前ピを含む中坊男子数人で、ある日、大須観音近くのスケートリンクに行った。その筋では全国的に有名な、ここである。ちょっと引用。
アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさん、バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さんをはじめ、村上佳菜子さん、宇野昌磨さんら世界の檜舞台で活躍するアスリートたちのホームリンクとしても知られ、東海地方のアイスホッケー選手の育成にも力を入れています。
みんなで楽しくスケートして、帰りに大須の商店街のゲームセンターに寄った。
これが間違いだった。
今はどうか知らないが、当時の大須の商店街は超がつくデンジャラスゾーンだった。
「圏外」から調子こいた中坊が行けば、そこそこの確率で地元勢にカツアゲされるか、タコ殴りにされる。
だから普段は寄り付かなかったのだが、そのときは6~7人と人数がそろっていたのと、スケートで盛り上がった余勢もあって、ゲーセンに繰り出してしまったのだった。
案の定、1時間も経たないうちに、地元のヤンキーにつかまった。
相手はたったの2人。だが、1人は見るからにカタギではなかった。
身長はそれほどでもないのだが、体格は前ピよりも「マイク・タイソン度」が5割増しぐらい高かった。
しかも顔はガッツ石松。
以降、「ガッツ」と表記します。歳は2つくらい上だったんじゃないだろうか。
「ちょっと顔貸せ。タイマンしようぜ」
高井さん御一行の中でも貧弱な一人ががっちり肩を組まれ、「人質」状態でゲーセンから連れ出された。
道中、私は前ピが持っていた自前のスケートシューズに目をつけ、「それで後ろからぶん殴って逃げようぜ」とささやいた。
前ピが「やめといた方がいい。こいつらマジでヤバい」と止めた。
連れていかれたのは商店街の人の流れから外れた空き地だった。ガッツが愛用しているタイマン闘技場のようだ。
「誰でもいいから、1人出ろ」
ガッツがそう告げると、前ピがスッと進み出た。
確かに、その日のメンバーで一番ケンカが強いのは前ピだった。
でも、相手が相手、下手したら病院送りだ。
それでも躊躇なく前に出る。
それが前ピという男だった。
ガッツと前ピのタイマンは、ありがちな取っ組み合いのグダグダなケンカではなく、ラピュタの「親方vsドーラの息子」みたいなパンチの交換で始まった。
最初にガッツの拳が前ピの顔をとらえた。
やはり只者じゃない。一発で気絶モノのパンチだった。
その一撃を持ちこたえて、前ピが強烈な一発を返した。
よろめいたガッツの顔に驚きの表情と笑みが浮かんだ。
相手が予想より強くて、嬉しくなったのだろう。アタマおかしい。
ガッツがまた重い1発を繰り出す。前ピが返す。
数発のやり取りの後、私は思った。
体格は一回り負けているが、ガッツより前ピの方が強いんじゃないか?
ガッツの立ち直りが悪くなり、次第に前ピが連続してパンチを決めだした。
(これ、勝つぞ、前ピ!)
そう思った時、ガッツが叫んだ。
「うおおお! 〇〇〇〇、ナメンなよ!」
「〇〇〇〇」には、ある固有名詞が入る。〇〇連合、みたいな。諸般の事情で伏せますが、聞いた瞬間「フカシだろ?」と思った。
前ピの手が止まった。ガッツが反攻に出た。
おいおいおい。
負けそうになったからって、それはないだろうが。
アタマに来た私が一歩前に出ると、すかさずガッツの連れのスネ夫みたいなヒョロヒョロ君に遮られた。
「動くな」
その手には、刃をむき出しにしたジャックナイフが握られていた。
ナイフなんてそう簡単に人を刺したり切ったりできるものじゃない。あれは使う方も怖いものだ。
だが、スネ夫の目は「オレは刺せる」と言っていた。
前ピはいつのまにか土下座させられ、顔を何度も蹴り上げられていた。
顔が跳ね上がり、下を向くと地面に血が滴った。
しばらくして我々は解放された。
別れ際にガッツが「お前、すげえから、また遊びに来いよ」と前ピに声をかけていた。何言ってんだ、コイツ。
みんな前ピに申し訳なくて、私はナイフにビビった自分が情けなくて、誰もが口を閉ざして地下鉄の駅に向かった。
すると前ピが、傷だらけの顔を歪めるように笑って、こう言った。
「アイツ、めっちゃ、強かったわ」
違うだろ。前ピの方が強かったよ。
でも、相手がヤバいヤツだったから、厄介なことにならないようにタコ殴りにされる役回りを引き受けたんじゃないか。
後日、前ピの判断が正しかったことが分かった。
ガッツは、たどれば「ホンチャン」までつながる準々構成員みたいなヤツだった。フカシじゃなかったのだ。
本格的なもめ事に発展していたら、みんな無事では済まなかっただろう。
私は、たかだか14歳の少年の勇気と判断力に救われた。
「高井くん、ちょっと教えてもらえますか」
高校、大学でも、私は多くの良き友人に恵まれた。
だが、「気高さ」という視点で記憶に残るような出来事や人物はスッと思い浮かばない。
これはそういう人がいなかったからではなくて、私がぼんやりと呑気な生活を送っていたからだろう。
高校時代なら、このnoteに書いたバスケ部の先輩からかけられた言葉が、それに近い。未読でしたらどうぞ。
本物の気高き人に会ったのは、新聞記者になってからだ。
入社3年目までに、私はSさんという大先輩と同じ部署で働く機会を得た。
Sさんはその道の屈指の論客だった。一行たりとも、いや、一文字たりとも無駄のない密度で超骨太のコラムを書く。
ある著名な経済人から「Sさんのコラムは別格だ。2度、3度と吟味して読んですべて切り抜いている」と聞いて、「自分は凄い人と一緒に仕事をしているんだ」と実感したものだ。
時は1995年。入社して数か月経った頃のことだった。
私は本社ビルから出ようと勝手口に向かっていた。重いガラスドアを押し開いて出入りする昭和な造りだった。
勝手口に向かう通路で、距離にして7~8メートル先に、Sさんの後ろ姿が見えた。ひょろりとした体型と独特の髪型ですぐSさんだと気づいた。
先にドアにたどり着いたSさんは、グイっと扉を押し開けて半身を外に出すと、軽く後ろを振り返った。
目が合ったので、私は会釈した。
すると、Sさんがドアを開けて私が来るのを待ってくれた。
慌てて勝手口まで小走りで駆け付けた。
私が「ありがとうございます」と頭を下げると、Sさんが言った。
「高井くん、記者は面白いかい?」
ビックリした。
私とSさんは別の記者クラブに席があり、話したことは無かった。顔を合わせたことすら数度しかなかったはずだ。なのに、新人の私の名前を憶えていて、声をかけてくださるとは。ドアまで開けて待ってくれて。
少し会話を交わすと、Sさんは「うんうん」と渋い笑顔で頷き、「それじゃ」とヒラヒラと肩越しに手を振って立ち去っていった。
夏の日差しの中、ひたすらカッコいい後ろ姿は、今でも瞼に焼き付いている。
翌年、そのSさんと同じクラブに席を置くことになった。
2年生なんて短い原稿をなんとか書ける程度のヒヨッコもヒヨッコだ。
そんな尻の青い高井記者が夜、自席で原稿を書いていると、Sさんがタバコを燻らせながら近づいてきた。Sさんは超ヘビーな愛煙家だった。
私の隣に立ち、Sさんが言った。
「忙しいところ申し訳ないが、高井くん、ちょっと教えてもらえますか」
耳を疑った。Sさんに「教える」なんて。
「私に分かることでしたら……」
Sさんはある非常にテクニカルな疑問を私にぶつけた。超マニアックなテーマで、たまたま私は最新情報を仕入れたばかりだった。
私が最近の取材の内容を簡単に話すと、いつものように眉間に皴を寄せながら、Sさんはメモをとりつつ話を聞いてくれた。
一通り説明して、コピーを取ろうと取材先の名刺を取り出すと、Sさんがスッと手を出して、
「ありがとう、自分でコピーしますから」
と私の手から名刺を抜き取り、コピー機から戻ってきて、
「本当に助かりました。ありがとう」
とお礼を繰り返した。
四半世紀前の新聞社なんて旧陸軍みたいな組織で、入社が1年違うと「おい、お前!」の世界だった。今はかなりマシ。まだまだ年功序列ですが。
そんな「文化」のなかで、Sさんは親子ほど年の差がある私に、対等に接してくれた。
その後、何度か仕事のやり取りや酒席でご一緒したが、ただの一度も「先輩風」を吹かすようなことはなかった。
私が取材した話を面白がって聞いてくださって、「それはこういう視点で考えると興味深いよ」とアドバイスを授けてくれた。
「記者は、新人であろうとベテランであろうと対等のプロであり、それ以前に対等の人間なのだ」
Sさんの振る舞いから、私はそんなメタメッセージを受け取った。
もう第一線は退かれているが、心から尊敬できる先輩だった。
「紛争地の看護師」の矜持
その後、取材で「この人は」という人達に何人もお会いしたが、ここではペンネーム「高井浩章さん」の活動で知り合った方を。
「国境なき医師団」で活動されている白川優子さん。
詳しくは上記のnote、いや、ご著書の『紛争地の看護師』をぜひご一読ください。
白川さんとはこのインタビューを御縁にお友達になった。
普段はチャーミングなホンワカとしたお人柄で、「この人が本当にシリアやイエメンの戦地を潜り抜けてきたのだろうか」とギャップに驚かされる。
なのだが。
やはり、そこは「紛争地の看護師」。
詳細は伏せますが、最近もある出来事についてポロリと漏らした本音から「ああ、この人は、自分とは全く別の種類の人間だな」と再認識した。
世の中には、見知らぬ誰かのために自分の命を懸けられる人がいるのだ。
愉快だけど、すごい人です。ホントに、かなり愉快ですけどね。
精神的な貴族
「気高さ」について、つらつらと書いてきた。
最後に、このテーマについての私の理想像を描いた『マースター・キートン』のエピソードをご紹介しよう。
「貴婦人との旅」は、列車で乗り合わせた老婦人とキートンの邂逅を描く短編だ。
実は数奇な運命を背負う女性は、事情を明かさず、それどころか嘘を交えて、キートンに次々と面倒を押し付ける。

キートンは、その嘘を見抜きながら、それでも窮状にある女性を助ける。
だが、ついにキートンの堪忍袋の緒が切れる。
「あなたの方こそ、嘘ばかりついています!」
「ただの一度も私に感謝の言葉を言ってくれませんでしたね」
立ち去ろうとするキートンを呼び止めて、老婦人は指輪を渡す。
その指輪は後日、東西ドイツの分裂で引き裂かれた、とある貴族の悲劇にまつわる秘宝だと判明する。
物語は老婦人との別れの場面の回想で終わる。
「あなたは今時、珍しい青年ね。礼儀正しくてとても優しい」
「あなたみたいな人を、本当の貴族というのよ。」
「本当の貴族」。
出自ではなく、精神性による貴族。
自分もそんな人間になれればな、とは思う。
でも、この歳になれば、無理なのも分かっている。
私という人間は、そういう風にできていない。
人それぞれ、向き不向きがあります。
だからこそ、「気高さ」に触れたときの感動が大きいのだろう。
あらためて。
今も世界中でコロナ禍と戦う、すべての医療従事者、生活インフラを守ってくれている気高き人たちに感謝の意を表して、本稿を閉じます。

=========
ご愛読ありがとうございます。
ツイッターやってます。フォローはこちらから。
異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。
無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。
