
[願・日本語化] Punk or Esoteric音楽・未邦訳文献9冊
調べ物をする上で洋書を無視するわけにはいかない。しかし、母語でない言語だけに読むのは大変な苦労が伴う。データ重視の筆者は、どうしてもトピック単位で読んでしまうため、全体の流れを意識して読むことに長けていない。情けないことに、手元にある時間こそ長いが、いまだに内容を把握しているのか自信のない本だらけである。今回はそんな筆者が頑張って読んでみたはいいが、やっぱり自信がないので正規に邦訳されてほしいを本を挙げた記事である。遡ればキリがないため、21世紀以降に出版されたもの中心です。ヘッダーのTiny Timは特に意味はありません。

Ripped, Torn and Cut: Pop, Politics and Punk Fanzines from 1976 (2018 Manchester Univ Pr)
ファンジンは音楽やファッションと並ぶパンク発のカルチャーだ。そのオリジンと称される『Sniffin' Glue』が作られた76年からの数年間に絞って、ファンジン文化を追いかけたのが本書である。『Sniffin' Glue』創刊者マーク・ペリーはもちろん、当時の発信者たちから得たインタビューをもとに、短命だがアティチュードとしてのパンクに突き動かされた人々の情動を辿っている。
「女性によるパンク」を標榜した『JOLT』にはじまり、ゴスや2トーンなど同じ時間の別の都市で生まれていたシーンがファンジン越しに描かれ、パンク直後に訪れた思想と創造の多様化がいかに豊潤であったか。中でもインダストリアル・ミュージック・シーンのZINEネットワーク(Throbbing Gristleいうところの情報戦)は、有名なCome Organisationによる『KATA』「以外」にも言及しており、資料的価値も高い。
書名はサイモン・レイノルズが2005年に発表した『Rip It Up and Start Again』(『ポストパンク・ジェネレーション』 2010 シンコーミュージック)を意識しているとしか思えない。2019年に再刷、Kindle版も発売中。
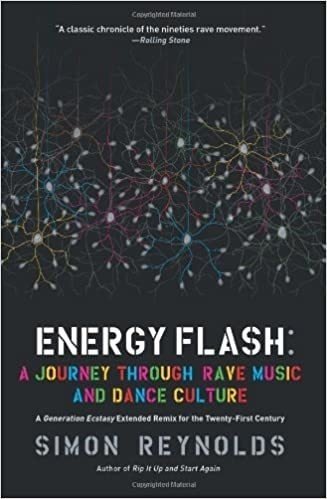
Simon Reynolds / Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture
(1998 Faber & Faber)
そのサイモン・レイノルズがUKレイヴ・カルチャー経由でダンス・ミュージックのシーンを研究した一冊。ポストパンク育ちのレイノルズは、マンチェスターから発火してイビサで大輪の花を咲かすレイヴこそ、60年代サイケデリックやポストパンクに連なる何度目かの音楽革命であると同時にDIY最前線であったと主張する。そのサンプルがサッチャー政権下で濫造・放棄されたビル群を会場にした違法レイヴや、ベッドルームの片隅に置かれたAMIGAで作られたダンス・ミュージックだ。
いわゆる現場主義の声と差異があるとの評価を下されているようだが、事象と同時代の社会的背景を鮮やかに結び付けるレイノルズの論考は、筆者のようにリサーチ目的で手に取る人間にとって大変読みやすい。画像は2012年再版のもの。

David Keenan / England's Hidden Reverse
(2003 SAF Publishing)
Nurse With Wound、Current 93、COILは互いの創作に出入りすることでも知られているが、この三角関係を巨視的に見てみると、一つのシーンとさえ呼べる輪が出来上がっていた。Throbbing Gristleが解体され、ポスト・インダストリアルと称されるアーティストたちが現れた80年代前半から始まり、レイヴ~テクノによるDIYネットワークが芽吹いていた90年代にひっそりと、しかし確固たる基盤を作り上げていたエソテリック・アートの水脈を追いかけた意欲的一冊である。パンク、インダストリアル、ケイオスマジック(オカルティズム)、エクスタシー、これらの単語に一つでも興味があるなら必読の書。少々、というか多分にCurrent 93とCOILびいきが目立ち、取材対象に偏りがあるのは事実だが、2000年代前半の時点でここまで書けたのは大業というほかない。2016年に改訂版と銘打って再版されたが、未収録(追加)インタビューを丸々掲載しただけの小冊子が「限定的に」付けられただけなのは少し残念。
今年中には出版される(いつまで言うのか)筆者のNWWヒストリーでも、多分に参考した一冊だ。

Justin Martell / Eternal Troubadour: The Improbable Life Of Tiny Tim (2014 Jawbone Press)
読書中①。68年のファースト・アルバム『God Bless Tiny Tim』は全米7位の売上を記録し、The Beatlesが同年に出したクリスマス用ソノシートに登場したことでも知られるアウトサイダー、Tiny Timの生涯を綴った評伝。ウクレレとファルセット、そして少しショッキングな見た目ばかり取り沙汰されるTinyだが、彼の影響力はオーバーまたはアンダーグラウンド問わずしてバカにできないものがある。音楽面では主なレパートリーだった50年代以前のポップスを歌うことでトラッド再評価の種をまいたし、熱狂的ファンはジャック・ニコルソンのジョーカー(『バットマン』)は、『Blood Harvest』(87)のTimが元ネタだと主張し続けている。思想家としてはチャールズ・マンソン、デヴィット・チベット(Current 93)、ボイド・ライスまで魅了した異端的キリスト教信者として名高く、ボイドはTimをアントン・ラヴェイに並ぶ「本物」と称える。
本書ではTimがスターダムへ昇りつめる道程はもちろんのこと、ヴィッキ夫人との確執など、私生活含めての凋落を客観的に記録している。今年にはドキュメンタリー映画も上映予定(ナレーションはアル・ヤンコヴィック)。
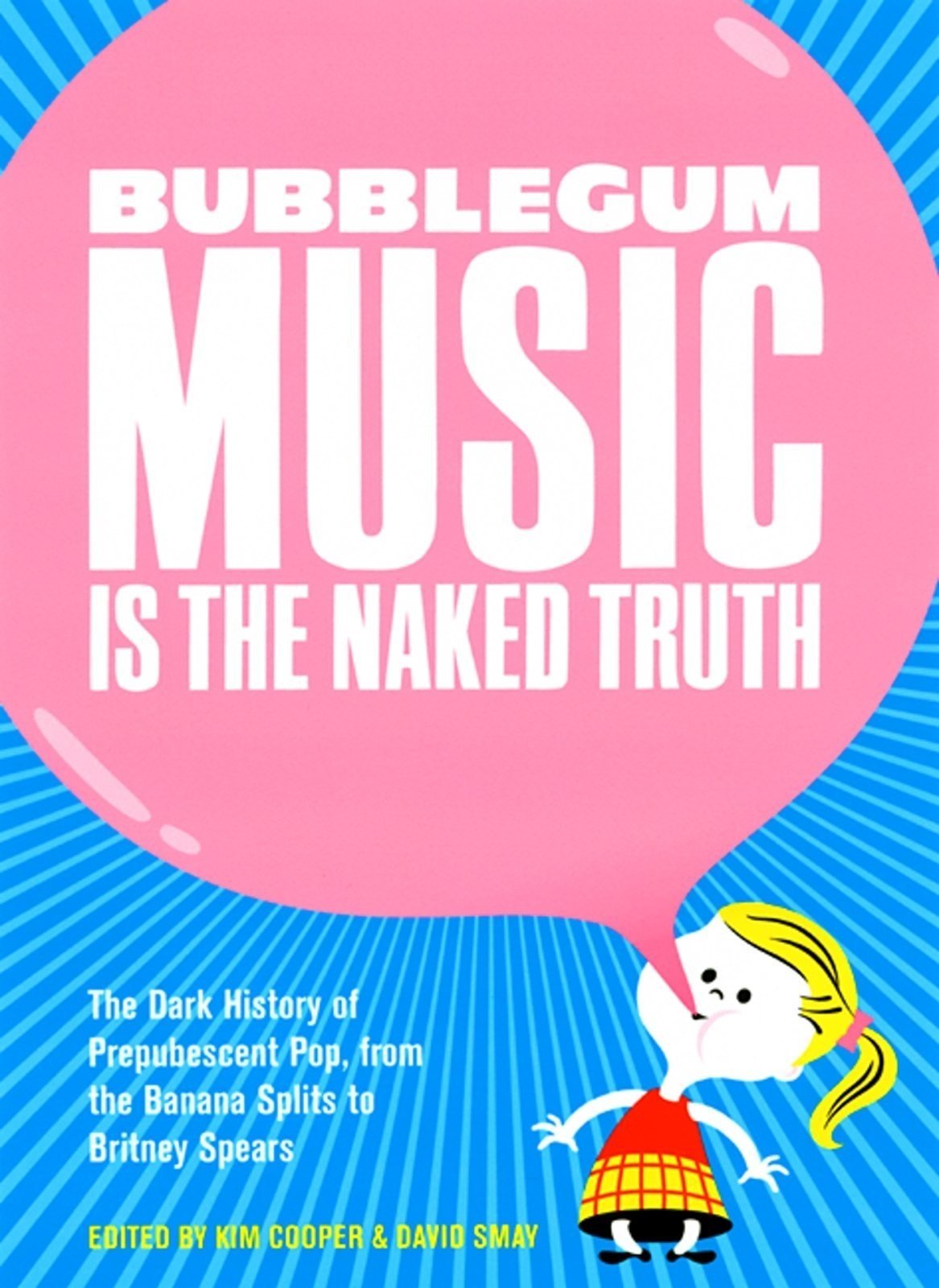
Kim Cooper, David Smay / Bubblegum Music is the Naked Truth: The Dark History of Prepubescent Pop, from the Banana Splits to Britney Spears
(2001 Feral House)
『RE/Search Magazine』以降のトラッシュ・カルチャー出版社代表格であるFeral House(89年設立)は、ここ日本でもSteven Blush による『American Hardcore: A Tribal History』や、Michael Moynihan『Lord of Chaos』が出版されている(それぞれ『アメリカン・ハードコア』、『ブラック・メタルの血塗られた歴史』としてメディア総合研究所から出版)。
本書は90年代にモンドの文脈で再発見もされた、60年代のコマーシャルなポップス、「バブルガム・ポップ」をフィーチャーした一冊。The MonkeesからOhio Express、The Partridge Family、Archiesなどのフィクション発のグループを取り上げ、それらが「プロデュースされた」商品であることを改めて明らかにする。「神はテレビとポップスの7インチに宿る」とはThe Partridge Family Temple創始者Shaun Partridgeの言だが、正にそれを裏付ける米国の(アシッドな)実利主義教本と呼べる・・・のか?

Lisa Christal Carver / Drugs Are Nice: A Post-Punk Memoir
(2005 Soft Skull Press)
パンクバンドPsycho Dramaを皮切りに、ジャン・ルイス・コステスやボイド・ライスとのパートナー生活、漫画家Dame Darcyとの『The JayWallker』や、個人による『Rollerderby』といったファンジン出版など、ライオット・ガール・ムーヴメントのワイルドサイドを生きたSuckdogことLisa Carverの自伝。健全とはいえない家庭から距離をとりながら、またしても健全とは言い難い環境でアートに触れた彼女が見てきた光景が綴られる。Suckdogとしての破天荒な表現は、肉体的にも精神的にも受けてきた搾取の反射であることを見過ごしてはならない。2017年に発表された新たな自伝『Suckdog: A Ruckus』も興味深い。
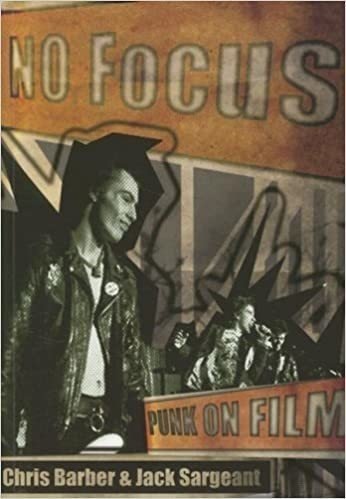
Jack Sargeant / No Focus : Punk on Film
(HEADPRESS 2006)
※未読!
犯罪心理学やアンダーグラウンド芸術分野のノンフィクション作家であるJack Sargeantは、カルト殺人事件に関する論考を集めた『Death Cult』への寄稿から、コージー・ファニ・トゥッティやデヴィット・チベットを招いたパフォーマンスのキュレーションなど、過去のアーカイヴを中心に多方面で活躍している。彼の仕事でもっとも知られているのは映画評論で、パンク・ムーヴメントを描いたフィルムについて複数の作家が論じた本書にも寄稿している。低予算フィルムの美学から、デレク・ジャーマンが当時のパンク・シーンに与えた衝撃まで書かれているようだ。
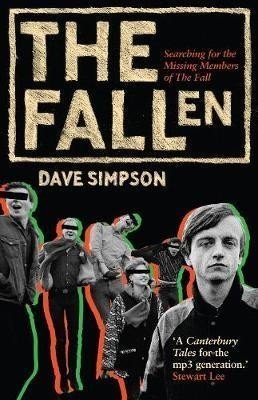
Dave Simpson / The Fallen: Life in and Out of Britain's Most Insane Group (2009 Canongate Books)
日本におけるThe Fallの認識といえば、Joy Divisionと同郷のベテラン・ポストパンクバンド程度のものだろう。しかし、UK本国および周辺のヨーロッパ諸国での人気はすさまじく、ことフロントマン、マーク・E・スミスは「詩人」として絶大な人気を誇っている。書店ではディランらと同じように専用のコーナーが作られているほどで、筆者が昨年ダブリンを訪れた時も、書店にはインタビュー集が平積みされていた。
スミスの世界観を解読することは難しく、当時の英国北部という環境を共有し、そのうえ大量の文学と哲学書に精通していなければならない。そんな複雑で捻くれた男を中心に動いていたThe Fallを、本書は40名以上におよぶ元メンバー(スミス曰く「役立たず」または「下等な存在」)の証言から辿っている。バンドのサウンドの模索から、スミスのパラノイア的オブセッション、そしてバンドの特色とさえ呼べた恐怖政治レベルの威圧をのぞき見れる痛快な一冊。なお、スミスは本書に対して一言「燃やしてやった」と愛のある(?)コメントを送っている。

Boyd Rice / The Last Testament of Anton Szandor LaVey
(2019 自費出版)
読書中②。Church of Satan(悪魔教会)司祭アントン・サンダー・ラヴェイの生涯と、彼が地上地下問わずカルチャーに与えた影響を振り返る一冊(サミー・デイヴィスJr.もメンバーだったとは知りませんでした)。ベトナム反戦運動の波が大きくなる直前の66年に灯されたトーチ、既存の(キリスト教的)価値観からの抜け道を照らす役割を担ったサタニズムと、それを唱えた男(獣)がいかに、恐怖と憧れの対象となったかが描かれる。エド・ゲインがホラー映画に与えた影響など、モンド愛好家にもたまらないチャプターだらけだ。書き手はラヴェイに「息子」と称され、次期司祭候補にも名が挙がっていたボイド・ライスである。
最後に、日々あらゆる言葉、あらゆる歴史、あらゆる人に触れる機会を身近にしてくれている翻訳者のみなさまへ感謝を申し上げます。同時に、日本における翻訳業の社会的地位向上を求めます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
