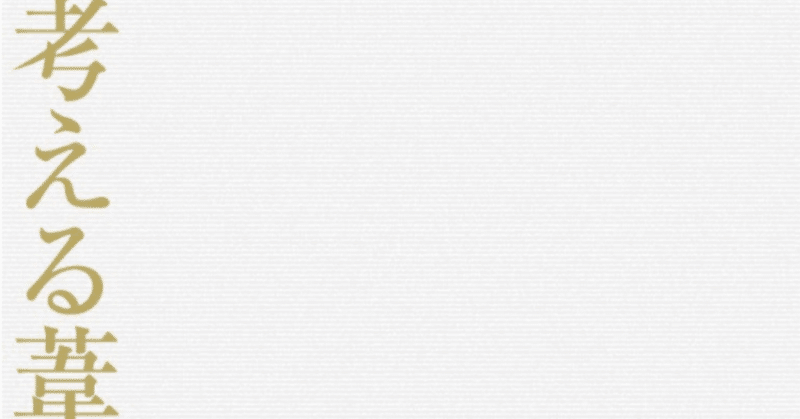
考える葦|I-13|「稔りの飽和」の静かな重みーー古井由吉『ゆらぐ玉の緒』
平野啓一郎の論考集『考える葦』(2018年9月発売 / キノブックス)より、『ゆらぐ玉の緒』(著:古井由吉)を公開しています。古井由吉さんのご冥福をお祈り申し上げます。
主に、2014年〜2018年(それより古いものも)、第4期にあたる『透明な迷宮」『マチネの終わりに』『ある男』が書かれた時期の批評・エッセイを集めた論考集。平野啓一郎の思考の軌跡が読める一冊です。
(2018年9月発売 / キノブックス)
Ⅰ : 文学・思想
Ⅱ: 自作及び文壇・出版業界への言及
Ⅲ:美術、音楽、デザイン、映画その他
Ⅳ:時事問題とエッセイ
所謂「体内時計」の研究は、随分と進んでいるようで、東京大学の上田泰己氏の説明によると、人体の各器官には「時計細胞」があり、それらに二十四時間という周期的時間を刻ませているのが、現在、二十個確認されている「時計遺伝子」なのだそうである。この時計遺伝子は、朝、昼、晩と三つのグループに分けられ、タンパク質の信号を介して相互に八時間毎にスイッチングしつつ、二十四時間周期の時計を形成している。そして、これら個々の臓器の時計細胞を、脳の視交叉上核が統御するという仕組みらしい。人間の肉体は、誕生に始まり、成長から老いを経てやがて死に至る直線的な時間に運ばれている一方で、朝夕を知り、また季節を知る円環的な時間にも属している。
後者は、時間性というより、さしずめ、時計性とでも呼んだ方が良さそうである。というのも、時計の正確さは、組織化された共同性を担保するもので、これは社会的な時計に於いてもーー人と人――、時計細胞であってもーー細胞と細胞ーー、同様だろう。同時に、その均質性は、正常さの拠り所でもある。
再び上田氏の説明を借りるなら、体内時計の正確さは、地球の自転/公転によってもたらされる外部環境の反復的な時間に、予測的に対応するために備わったものらしく、その調整には、日照の感受が大きく関係しているという。今では、睡眠の規則性のようなわかりやすい事例のみならず、一日の中で、血中のコレステロール値やアドレナリン値が最大になる時間帯だとか、脳溢血を起こしやすい時間帯などが判明しているそうである。
日本ではあまり広まっていないが、医療の分野では、正常細胞とがん細胞とがそれぞれに活発な 時間帯のギャップに注目し、抗がん剤の投与の時間をコントロールすることで、正常細胞に及ぼす 副作用を抑制しつつ、効果的にがん細胞を殺傷させる「クロノテラピー」なる治療法もあると知った。
古井由吉氏の新作『ゆらぐ玉の緒』を読みながら、そんな生物学の最新の知見が、何度か脳裡を掠めた。
凡そ、古井氏の文体ほど、科学的な論文から遠いものもなく、古今東西を貫く文学的な教養――とりわけ、詩についての深い理解――は圧倒的だが、だからこそと言うべきか、その人間の把握は 極めて正確で、冒頭のような生物としてのヒトに関する最新の認識に遙かに先んじて、むしろ例証をさえ与えている観がある。古井文学のファンに、若い読者が少なからず見受けられるのも尤もである。
古井氏が、日本の近代文学の歴史に末永く名前を残すことは確実だが、教科書的には、そこに、「〈内向の世代〉を代表する小説家」という肩書きが付されることは、やはり避けられないのかもしれない。この世代論的な呼称は、色々と考えてみて、結局あまりうまくないように思われるが、いずれにせよ、古井氏の小説を読んでつくづく感じさせられるのは、人間は、彼らの先行世代が考えていたような政治理論のためには、あまりに複雑すぎる生き物だ、ということである。そして、古井氏の意図はともかく、その事実の剔出こそは、翻って最も核心を突いた文学者による政治的見解たり得るだろう。
私は以前、河出書房新社の『古井由吉自撰作品』に寄せた「個体、存在、『身理』」という小文の中で、古井氏の方法を、心理主義ならぬ「身理主義」と評したことがある。
「『怖いから鳥肌が立つ』のではなく『鳥肌が立つから怖い』のだと、その因果関係を転倒させたのがジェームズ=ランゲ説だが、古井氏は『鳥肌』を『怖い』という感情に短絡させることもなければ、そもそもそんな手っ取り早い慣用句で済ませることもない。その水も漏らさぬ緻密な言葉の網の目は、個体の外部の事象に独自に反応し、内部に直接働きかける、身体としては十分に理に適った活動の存在を、鮮 やかに掬い上げる。」
本書でも、作者と虚構を挟みつつ重なる主人公は、まるでしばしば引用される古の歌人たちのように、自然の様々な現象に感応する。しかし、彼が住むのは、同時に「どこに居ようと騒音は避けられない」都市であり、「四角四面のコンクリートの箱」である。両者は、初期から中期にかけて の古井氏の作品に見られた一種の対置を解かれて、今やより複雑で、遍在的な混淆に至っている。
主人公の知覚と感覚は、あらゆる外的事象に対して敏感だが、とりわけ、音に対する反応には、音楽的な教養が豊かといった意味とはまた次元の異なる作者の資質が見えている。
生物学者が、細胞レヴェル、或いは分子レヴェルで観察しているミクロな次元も、また、その時計性に於いて呼応し合う、地球の自転/公転や太陽の燃焼といったマクロの次元も、身体感覚的には、所詮、無音である。それが生の根本条件であるにも拘らず、感覚器にとっては死のような、或いは無のような静けさである。
地球の気候変動も無音だとするならば、やがては手術を促すこととなる「悪い物」としての「腫れ物」の出現と成長もまた無音である。
その狭間に、存在の音が雑多に満ちている。
しかし、作者が経験した最も激しい音は、死そのもののような東京大空襲時の空爆の音であり、生が宛ら細胞レヴェルの活動を映したかのように澄んだのは、死へと急接近してゆく「敵の爆撃機の編隊がひとしきり上空を低く掠めて通り過ぎた後の、つぎの編隊の接近を待つ間の静まり」であったのかもしれない。生と死は、実際、この時ほとんど交換可能なまでに切迫していて、「孤帆一片」の中では、端的に「死んでいたかも知れぬ子供の年」と記している。
古い柱時計の記憶が、そこに幻聴のように差し挟まれる「時の刻み」は、時計の象徴性が際立つ本連作の白眉だが、そこでは、「ひろがる」という、古井文学では常に特別な響きを持つ動詞が、三度、用いられている。
最初は、「中年に深く入」って、夕暮れ時の秋の雲を眺めつつ、心中にひろがる「老い」。二つ目は、慈圓の歌に見る「野辺よりも、眺める心よりもはるか遠くへ、無限の境まで」ひろがる「秋より外の秋」。最後はやはり、その歌を論じてこう説く。
「あまりゆく心とはそのことか。この目で眺める秋を超えて、果てしもない秋の中へ、心があまってひろがり出て行ったのを、本人はすこしも知らず、しかし老年に至って、いつだか無限の境まで抜けた心を、置き残された身体がひそかに慕って、声も立てずに泣く、そんなこともあるのかもしれない。」
無音の、恐ろしく複雑な生物学的基礎に立つ人間は、心拍を備え、声を発し、「時空のはるけさ」と向き合う。「ひろがり」には源があり、果てがある。凝縮があり、拡散がある。「内向」性が「外向」性の極限と、一種、神秘主義的に直結する。この三様の「ひろがり」の表現には、古井文学の存在論的な形式が、非常に明瞭に表れている。
「ひろがる」とは、単なる延長ではなく、全方位的なものである。だからこそ、これと背中合わせに、やはり古井文学に頻出する「いつ、どこに」という方向感覚の喪失がある。
このゲシュタルト崩壊的な現象は、本書でも、「ゆらぐ玉の緒」や「孤帆一片」等の作品で見ることが出来るが、これは日常的な時空間の限定から放たれて、むしろ、いつでもあり得、どこでもあり得るという遍在性の開示と取ることができよう。それは無論、常にありがたがられるばかりではなく、時に恐怖の再来となる。殊に東日本大震災以来、空襲体験の記憶が古井氏の作品に濃厚に現れるようになったのは周知の通りである。
「ゆらぐ玉の緒」には、
「住むという言葉は重い、生きるというよりも重い、」とあり、更に「世にあるのは、住むことにほかならない。食べるのも、住むうちのことだ。男女の同棲も、男の通うのも、住むのひと言であらわされた。」
と続く。
東日本大震災直後に対談した折(「震災後の文学の言葉」・拙著『「生命力」の行方』収録)、古井氏は、「小説は一体、何から始まって何で終わるべきなのか。本の一ページを開いて、最後のページを閉じるまでに何が起きるべきなのか。」という私の問いかけに対して、
「追いつめられると、時間と空間に関する考察しかなくなってしまうでしょう。すると、小説にとってストーリーは何なのかということになる。」
と答えている。
ここに「考察」主体の複雑にして精妙な作中人物を置く時、「住む」という言葉は、本作のみならず、古井文学の全体を照射する一つの光源とも感じられる。そしてその光は、「その日暮らし」 の二度目の頸椎狭窄手術のあとの心境に差し込んでいる。
「家の内の、変哲もない日常の空間が、間取りやら家具の位置やらが、妙にくっきりと目に映る。そこに移る一日の光と陰とがすでに懐かしいように感じられる。この空間も時間も所詮、いつ失せるとも知れぬはかないものであるにしても、眺める自分にくらべればはるかに永遠らしい相を見せる。」
この「永遠らしい相」は、主人公を始めとする個々の登場人物たちにも仄めいている。彼らは決して、近代小説的な典型的な性格を与えられているわけではないが、しかし、彼らが経験している生は、総体としては、この世界に「住む」ことの典型を縹緲と眺めさせる。例によって、本作でも、一人称単数の人称代名詞「私」の極端な省略が見られ、固有名詞の省略にも、独自の判断が働いている。例えば、ボードレールや芥川龍之介といった固有名詞が目につく一方で、重要な箇所での和 歌の引用で、作者名がぼかされていることもあり、また「奈倉」と呼ばれている人物もいれば、社会的属性だけで指し示されている人物もいる。「人と人との間の、見境がとかくつかなくなって」というのは、本作の読書体験を通じてもしばしば起こることで、読者はその都度、道に迷った作中人物さながら、唐突にはたと立ち止まる。作中の誰というより、作者の内なる多声に幻惑されているようであり、またそれが自身の内なる多声と呼び交わす。いや、むしろ自他を超えた過去から現 在に至る無数の声か。「人違い」は、本連作中でも私の最も好きな作品の一つである。
全体としては、「その日暮らし」で触れられた「邯鄲の夢」の「終りが始めにかさなり、はてしもない反復の気味をふくみはしないか。」という解釈に示唆されるかのように、「腫れ物」を巡って、最後に手術をする病院が、序章のような「後の花」に続く「道に鳴きつと」の母親の死の夜伽の記 憶を再現する、円環的な結構を備えている。しかし無論、老いの直進性は、或いは時空間感覚の変容という大きな主題を通じて、或いは、不穏な「睡気」の兆しの反復のような細部によって、巨細に描かれている。
「私」という一人称代名詞の例外的な導入の仕方や、各篇のタイトルの付け方、その始末の付け方などに、これまでにない直截さを感じるところがあり、それは不思議な明るさを帯びているようにも思われたが、「文章のほうは書く者の苦労も知らぬげに、むしろ淡白のようになる。」という一文には息を吞み、また静かに長く吐いた。
全篇を読了して、私はやはり、作中に引用されたフリードリッヒ・ヘッベルの詩の一節を振り返った。
「――乱さぬがよい。この自然の祝日を。これは自然が手づからおこなふ刈り入れにほかならない。」
季節が幾度も繰り返す実りの最中にまっすぐに落下する果実の音。――読者が本書から聴き取るのもまた、そうした「稔りの飽和」の静かな重みではあるまいか。
(「新潮」2017年5月号)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
