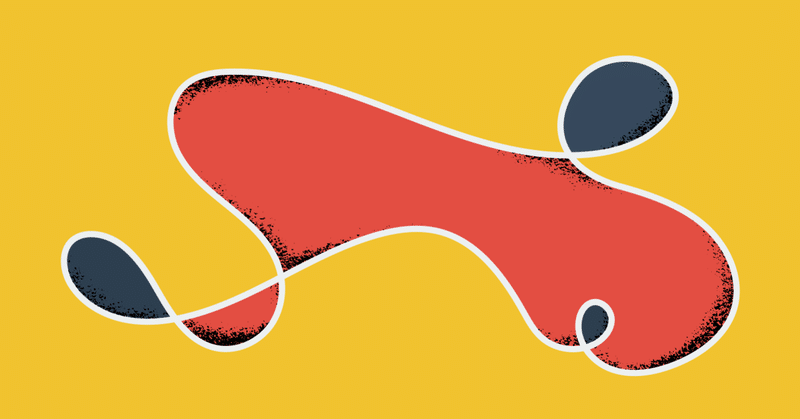
本を贈られるということは手紙をもらうことに似ている
私が初めて人から贈られた本は『星の王子さま』(サン=デグジュペリ著)だった。
中学三年生のときで、とってもかわいらしい名前の友人からだった。
そこまでは覚えているのだけれど、どういうきっかけでもらったのか、実は思い出せない。
私が読んだことがない、と言って、じゃああげるよ、と言われたのだったか。
とにかくその子が持っていた物をもらった。新品ではなくて彼女の本棚にあったものだ。
特別なものを贈られたような気持ちだったことは覚えている。
その特別な『星の王子さま』は、今も実家の本棚にたたずんでいる。
今度帰省したときに持って帰ってこようと考えているが、先日文庫版を購入した。
同じ本を所有することに抵抗はない。
なにせ『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著)を表題とした文庫を三冊、本棚の整理中に発見したくらいだ。
(それらはおもしろがった私により隣同士に並べられた。)
次に本を贈られたのはつい、何年か前のことだ。
とあることのお詫び、という形でいただいたのは『刺繍する少女』(小川洋子著)だった。
それもまた『星の王子さま』と同じく、その人の本棚からやってきた。
気を遣わせてしまって申し訳ない気持ちもあったけれど、私のために本を選んでくれたということへの喜びの方が大きい。
この記事を読んでいただけるかはわからないけれど改めて、ありがとうございました。
そして贈られた、というのとは少し違うのだが、ご自身の本棚から小説本を紹介してくれた人がいる。
廃盤になっていたものを、日本の古本屋さんで発見、購入した。
『パロール・ジュレと紙屑の都』(吉田篤弘著)である。
コンセプトが私を思わせる、というお言葉に舞い上がるまま手元に置いた。
人から本を贈られるということは、手紙をもらうことのような気がしている。
『星の王子さま』は何度か読み返すほど読んでいるが、あとの二作はまだ途中だったりする。
パロール・ジュレはハードカバーなので家で腰を据えて、『刺繍する少女』はふすま地のブックカバーをかけられて出先でページを開かれる。
読むのも遅いし、読み始めるのも遅いしで読了がいつになるやらわかったものではないのだが、常にかたわらにあるので、いつかは終わりがくるだろう。
まだ受け取りきれていない二冊の手紙を読み終えたら、実家から連れてくるだろう『星の王子さま』と一緒に並べておくと決めている。
サポートいただきましたら、ちょっと良いものを食べたり本を買ったりします。
