
【ATOY 2020】年間ベストアルバムと振り返り
今年も2020年の年間ベストアルバムを決めました!
毎年「これだって感じのベスト作るぞ!」とか気込むものの、結局日々の生活と新譜の荒波に飲まれて1枚をじっくり聴かないでノリで選んじゃうみたいになりがちなのが年間ベスト。今年もその傾向が強かったのかな〜どうでしょう。
今年は国内のアルバム9枚+国外の音楽9枚の計18枚という構成です。
1枚1枚順番に紹介するというよりは、2020年の自分の音楽的興味を、個人的に面白い・関連があると思った曲を絡めながら纏めた備忘録って感じです。
読んでいて「そんなムードねえよ!」的なこと思わせてしまったらすみません!
一先ずリストからいきましょ〜
〜年間ベストアルバム2020(18作品)〜
〜国内作品(9枚)〜
■ BBHF 『BBHF1-南下する青年-』
■
ROTH BART BARON『極彩色の祝祭』
■
TAMTAM『We Are the Sun!』
■
Mom『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』
■
yonige『健全な社会』
■
Kamui『YC2』
■
環ROY『Anyways』
■
Moment Joon『Passport & Garcon』
■
中田裕二『PORTAS』
〜国外作品(9枚)〜
■ HAIM『Women In Music Pt. Ⅲ』
■ Soccer Mommy『color theory』
■ Tom Misch&Yussef Dayes『What Kinda Music』
■ Mura Masa『R.Y.C』
■ Phoebe Bridgers『Punisher』
■ Zack Villere『Cardboard City』
■ Omega Sapien『Garlic』
■ Yves Jarvis 『Sundry Rock Song Stock』
■ Khotin『Finds You Well』
●演奏と編集の両方を活かした作品たち
1年間の自分の音楽的嗜好がどんな風だったか振り返るのが楽しくて毎年年間ベストを作っていますが、結構年ごとのムードが反映されているんですよね。
2018年は宇多田ヒカルや中村佳穂、ceroなどのクロスリズムやポリリズムを活かした作品、2019年はFear Gortaや100gecsなどジャンルをごちゃ混ぜにしたようなキメラ的構造を持った作品に興味が向きました。
では2020年の私はどういう作品に興味が向いたのか。その一つに「演奏」と「編集(ポストプロダクション)」の両方を活かした音楽作品たちでした。
「一聴するとシンプルな楽曲だけど、ちゃんと聴くと様々テクスチャーを持った音や、演奏としては違和感のあるアレンジがある」みたいな、そんな作品。
なんかザックリした表現しかできませんが要は楽曲構造でなく細かいサウンドデザインにやっと興味が出てきた、って感じです。ではではいきましょ〜
1.HAIM『Women In Music Pt. Ⅲ』

ロサンゼルス出身の三姉妹によるバンドの3枚目のアルバム。もう自分にとって間違いなく2020年を代表する1枚でしたね。LPも持ってるくらい大好きな1枚。
本作の素晴らしいところはやはり「バンド演奏とDTM以降の音楽編集の融合」と言ったところでしょうか。本作を気に入ったきっかけの1つにもなった2曲目の『The Steps』のイントロのドラムの音像を聴いてみてください。
1拍目のバスドラムと3拍目のバスドラムの音像を明確に使い分けており、おそらく前者は乾いた軽めの生音、後者は重みのある打ち込みの音像になっています。
これがかなり独特な違和感を演出しており、クラシックな曲構成の中の一つの大きなフックになっています。初めて聴いたときはぶっ飛んだな〜。
他にも2ステップを取り入れた『I Know Alone』なんかも面白いです。ブリッジ・コーラス・アウトロでそれぞれ違ったスネアの音色を使い分けていたり、ヴォーカルのピッチや音色をコロコロ変えたりするなど、音源を細かく編集しているのが伝わります。
また今作は5曲目『Gasoline』の弾いている指先が伝わってくるようなギターのタッチング音や、4曲目『Up From A Dream』間奏の気持ち悪くなるギリギリを目指したキンキンとしたギター(違うテイクを左右に重ねているようにも聞こえる)など、生音ならではの生々しい質感もしっかり残しており、演奏と編集の両方を大切にしている印象を受けました。
この徹底的に作り込まれたサウンドデザインは、何度聴いても新しい発見に満ちていて聴いていて本当に飽きません。しかもこれだけの仕掛けがありながら、ポップソング、アンセミックなロックソングとしてしっかり王道として聴こえるのがすごい。というかむしろこれだけ更新されたサウンドの上でクラシックな歌を鳴らすからこそ、自信満ち溢れた印象を受けるのかもしれません。オーセンティックでフレッシュな傑作でした。プロデューサーのRostam Batmanglij恐るべし。。。
2.Soccer Mommy『color theory』

ナッシュビル出身のSSWの2枚目のアルバム。プロデューサーはGabe Wax。
リスナーや批評サイトでも好評だった前作はそんなにハマらずでしたが、今作は気に入ってよく聴いていました。
2曲目『circle the drain』が音楽批評メディアPitchfork誌の記事でThe Matrix(Avril Lavigneの初期作品などに携わったプロデューサーチーム)の諸作品と比較されていた通り、90〜00年代のヒットチューン的な煌びやかなソングライティングと、ロードムービーを想起させるようなローファイで冷たい音像がマッチしたのが本作の大きな特徴です。
一聴するとギターの重なりの美しい本作(特に6曲目!)ですが、1曲ごとにドラムの音色を小まめに使い分けており(一曲の中でも変化のある曲もありました)、どうしても埋もれがちなインディーロックのドラムの存在感という問題を見事にクリアしています。LP欲しい〜。
打ち込みを導入した楽曲はSSWやバンド作品にも多く見受けられますが、最終曲『gray light』は2:30〜にあるスクラッチ音を起点に大胆に音像が変化して曲の印象をガラっと変えており、音楽編集以降ならではの曲展開だと思います。
余談ですがこの90sのUSインディーと00sUSエモ・ポップス、ベッドルームポップを混ぜたような本作のムードは大きな発明だと思っていて、国内外問わず2021年のバンド・SSWシーンにも波及し始めています。日本でもDYGLの新曲がそんな雰囲気で、今後ますますこの作品が多くのミュージシャンに影響を与える気がしてます。
3.Phoebe Bridgers『Punisher』

カリフォルニア出身のSSWの2枚目のアルバム。
前作ではSSWらしい比較的にシンプルなインディフォークという印象で、正直にいうと良くも悪くも眠くなる作品だったんですが、今作はサウンドデザインの幅がかなり広がっていて本当によかったです。あと全曲メロディが泣けます。
アップテンポかつトランペットを使った開放的でドラマチックなインディーロックソングである『Kyoto』やハウスの様なシンプルな4つ打ちのバスと、篭った様な低めのアルペジオの上で展開されるアコースティックソング『Garden Song』など、序盤を一聴しただけで前作から大きな成長を遂げたのがわかります。
また最近ようやく音源のMIX(というかポストプロダクション)に興味が湧き始めているんですが、そういった観点から聴いてもすごく面白い作品だなと感じました。Mike Mogisという人がエンジニアみたいですね。前作に比べて音のレイヤーが多い本作は(楽曲の多くに流れる不穏なシンセなど)、作品全体が意図的に中低音域の多い、滲ませた様な独特な音像になっています。まるで水彩画の様な、または夢の中にいる様な感じ(ドリームポップから聴こえるそれとは全く別の浮遊感です)。それによって幅広いアレンジの本作に、統一感と独特の世界観を生んでいます。
「滲んだ音像ってなんだよそれよく分かんねえよ、、」って思う人もいると思いますが、同じく2020年リリースのTaylor Swift『folklore』は近い音楽性でありながら音の輪郭のはっきりした音像が特徴でもあったので比較して聴いてもいいかなって思います。人それぞれだけど僕は全然違うなと思ったのでぜひ!
ポストプロダクションの観点から言えば9曲目『ICU』も最高でした。迫ってくるこれまた輪郭が掴めないタムが壮大なイントロから、00:40〜に聴こえるビットクラッシュ(ピッチも変えてますね)させた様なギターフレーズで一回フックを持たせ、今までになく輪郭のあるバシッとした音像のスネアとハットを近くで鳴らして、、とシンプルなメロディの本曲の印象を大きく変えています。
まあ細かいことを抜きにしても全曲自然と涙が出ちゃう様な傑作でした。
4.Tom Misch&Yussef Dayes『What Kinda Music』

今度はジャズ・ソウル系の作品の中でも紹介します。南ロンドン出身のSSWのTom MischとジャズドラマーのYussef Dayesのユニットアルバム。
Tom Mischといえば2018年の『Geography』が印象的でしたが、その頃の自分といえば所謂「洗練されたチルいダンスミュージック」に若干飽きていた時期で、作品自体もあまり真剣に聴いてなかったんです。
ただ先行配信された本作10曲目『Kyiv』を聴いてその変貌ぶりに驚きました。
Chorusがかったドリーミーで漂うようなブルージーなギターフレーズに、J Dillaとは逆を行く様な、性急で工夫の凝らされたYussef Dayesのドラミングに、新しい何かを模索している予感がしました。(ちょっとだけtoeらしさも感じます。)
そんな期待を軽々超えた今作は、「演奏」と「編集」、「チル」と「ノットチル」の折衷感に満ちたアルバムでした。(作品の詳細は柳樂光隆による素晴らしいインタビュー記事があるのでそちらを是非読んでもらいたいです。)
本作はいわば「Tom Micshのダークサイドが発揮された実験的作品」でしょうか。
ダンスを誘発する様なビートは少なく、開幕1曲目『What Kinda Music』の不穏なギターフレーズはどことなくRadio Headを想起させます。また作品に次節現れるシンセのフレーズはIDM(Intelligent Dance Music)の浮遊感を思わせる瞬間もあります。
その浮遊感のある上物にYussef Dayesのタイトなドラミングが加わることでジャムセッション的な緊張感を与え、唯一無二性な仕上がりになっていると思います。またジャムセッションが中心の本作ですが、曲によってはYussefの叩いたドラムフレーズをTomが持ち帰ってビートを組んだり、Overdriveを掛けてパンチを持たせるなど「プレイヤー同士による即興演奏性」と「ポストプロダクションによる編集性」を兼ね備えた作品であるとも思います。ドラムの音はマジで必聴。
この特徴でいえば同じく2020年作のKassa Overall『I THINK I'M GOOD』も超良かったんですが、Tom Mischの新たな1面が見られた本作を選びました。
5.Mura Masa『R.Y.C』

2020年はギターロックも熱かったですよね〜しかもプロデューサー界隈から。
イギリス王室属領・チャンネル諸島出身のプロデューサー、Mura Masaの2枚目のアルバム。なんかセレクトが2枚目ばっかですね。
『Raw Youth Collage(生の青春のコラージュ)』と題された本作は、ギターを大胆導入したいわば「プロデューサーサイドによるギターロック作品」です。
この異色とも言える本作ですが、乾いた生々しいギターとグリッドぴったりなバツっとした打ち込みや、ボーカルに掛けられたオートチューンが、ギターロック特有のメランコリックさをモダナイズしていてとても新鮮でした。
本作を聴いているとギターロックばかり聴いていた若い頃の自分を思い出してしまうというか、そういう意味ではタイトルにもある「青春のコラージュ」というワードがバッチリハマっています。過ぎ去った青春へも捧げているというか、若くして有名プロデューサーとなったMura Masaを思うと少し物悲しい作品という気もします。ファッションメディアWWDのインタビューによるとそんなことも無いらしいですが、、、、、
ギターばかりが取りざたされる本作ですが、『 I Don't Think I Can Do This Again (with Clairo) 』『 Live Like We're Dancing (with Georgia) 』などはしっかりポストEDM的なカタルシスを持ち合わせているのもとても良いです。(こうした曲の中にも少し粗い演奏のギターやドラムを仕込み、ノスタルジックさを演出しています。)
本作が「バンド演奏とDTM以降の音楽編集が融合した作品」と言われると少し違う気がしますが、(全編アンプは使ってないみたいですしね、、)とても折衷感のある「DAW以降のギターロックアルバム」であると思ったのでセレクトしました。
このように「演奏」と「編集」を併せ持った作品が多かったのが2020年で面白かったことの一つだったかと思いますが、国内にもそうしたことにトライした人たちがいるので、この流れでそちらを紹介しましょう。
6.BBHF 『BBHF1-南下する青年-』

日本は北海道出身の4人組ロックバンドの2枚目のアルバム。
北から南を目指す一人の青年の物語がテーマの2枚組のコンセプトアルバムで、曲が進むにつれサウンドも冷たいものから暖かいものへ変わるというギミック。
非常に多くのジャンルをレファレンスに持っていることがわかるのが本作の特徴ですが、「日本国内におけるバンドサウンドを更新したアルバム」の一つと言っても過言では無いくらい非常に音もいい作品です。
何を持って音が良いとするかって人によりますよね。本作は強いて言うなら「クリアで整頓された美しさ」があると思います。特に先行曲『僕らの生活』は真ん中に配置したギターの周りを派手にPANを振った強靭な音のドラムやベースが目まぐるしく耳を刺激してきて、モダナズされたギターロックという点でも代表的な一曲だと思います。『流氷』『クレヨンミサイル』『Siva』等、大げさとも取れる様なポストプロダクションの施されたマッチョな音像も聴いていてとても面白いです。US・UKの現行ポップスを聴いていないと作り出せない様なビートを主軸に置いたミックスのバランスも最高で、ここまでパワフルな音像に終始したバンド作品は今までに国内には無かったのではないでしょうか。(本人たちによるものの他にTHE 1975の作品も手がけるマイククロッシーによるものもあります。)
サンプリングや打ち込み、ビードチェンジなど、編集によって構築されたバンドサウンドは機械的というよりはかなり肉体的な印象で、HAIM『Women In Music Pt. Ⅲ』を彷彿とさせる瞬間も沢山ありました。
また本作は共同プロデューサーとして岩井郁人(ex.FOLKS)を招いて制作されたという点もとても興味深いですよね。インタビューによると彼の弾いた鍵盤のコードを基にして制作された曲もある様で、同じメンバーによる制作されるのが基本のバンド作品でいわばコライトをしているんです。ここまでプロデューサーが制作に踏み込むことも結構珍しい気がします。この柔軟なバンドの姿勢が本作のクオリティの高さに反映されているでは無いかと思います。
このあまりにも綺麗で隙のない音作りやヴォーカルの尾崎雄貴による物語チックな詩は、好みの分かれるところであると思います。ただ「好みを超えた良さ」は確実にあるのが本作ですので未聴の方は是非聴いてみて欲しいです。
7.ROTH BART BARON『極彩色の祝祭』
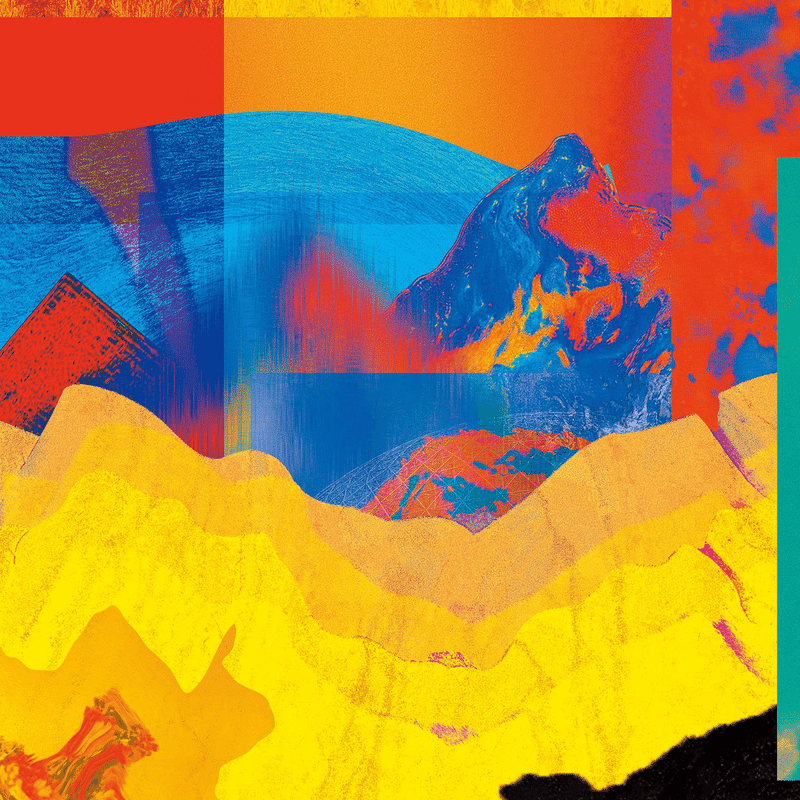
シンガーソングライターの三船雅也が2008年に結成したインディーフォークバンドによる4枚目のアルバム。デビューあたりから名前はなんとなく知っていましたが、グッとビートを意識した音づくりにシフトしたブレイクスルー的な前々作『HEX』をきっかけにちゃんと聴く様になりました。『JUMP』の出音は何度聴いても最高なんですよね〜
そんな『HEX』からの取り組みの集大成とも言えるのが本作『極彩色の祝祭』で一曲目『Voice(s)』で導入されたデジタルクワイアや変調したボーカル(ほぼ全てのパートが編集された自分の声だそうです。)や『極彩|IGL(S)』で聴こえるチープなクラップ音や、『NEVER FORGET』で聴こえる耳を引き裂いてくるよな歪んだシンセの音(シンセベースかな?)や打ち込みなど、たくさんの音が重ねられておりエディット感の強いバンドサウンドが印象的です。と同時に、COVD-19の影響も受けながらもバンドセッションを中心とした制作だったようで、『ひかりの螺旋』のドラムや豊艶なストリングスでは生音演奏の良さも感じられます。また『King』の2:20〜で聴こえるクラップは『極彩|IGL(S)』や『000Big Bird000』のそれとは対照的に(恐らくですが)マイクレコーディングを幾重にも重ねており、曲によって『人力』と『機材』を細かく使い分けている点も面白かったです。
もう一つ本作は今までにも増してヴォーカルのエモーショナルな歌声やメロディも印象的で、迫ってくるような熱量が感じられます。それに拍車をかけるようにストリングスやホーンの響が彼の歌声と重なり合って、生を肯定させてくれる気持ちになります。Phoebe Bridgers『Punisher』もそうですが、全曲自分の涙腺を刺激してくるようなメロディなんですよね、、、、、
アルバムの曲数や並び順のバランスもとても良く、(楽曲の幅も結構広いですしね)39分というサイズ感もあってインディーフォークアルバムにある冗長感がないものいいですよね。
クラウドファンディングを活用した独特なバンド形態や取り組みもとても面白くて、とても先進的な取り組みも多いバンドですので今後の活動にも要注目です。
8.TAMTAM『We Are the Sun!』
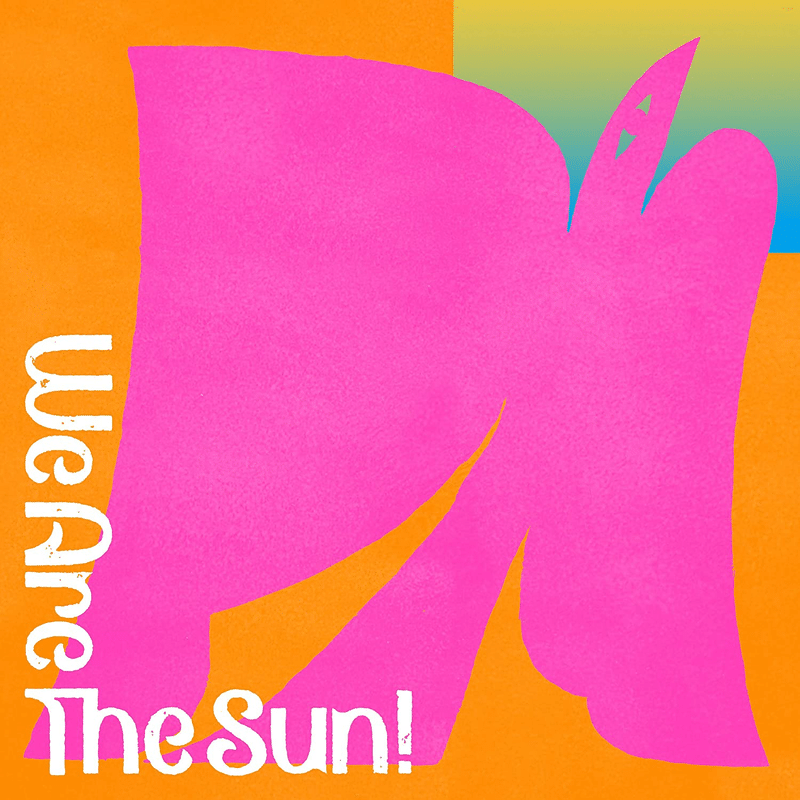
2008年に早稲田大学の音楽サークル・中南米研究会のメンバーで結成し日本の東京を拠点に活動するバンドの5枚目のフルアルバム。元々はダブやレゲエを全面に出したサウンドだったのがメジャーデビューを機にギターロックを取り入れ、Pヴァイン移籍以降は現行R&Bにサウンドの中心に据えているという、結構色々やってきたバンドなんです。
最新作『We Are the Sun!』は前作『Modernluv』の路線の延長でありながら、演奏にさらに磨きが掛かった最高傑作であると同時に、ブラックミュージックをルーツに持ったバンドが増えてきた2010年以降の日本のバンド作品の中で屈指のクオリティだと思います。
一番のサウンドリファレンスとしてまず挙がるのはThe Internet『Hive Mind』でしょうか。お風呂感の強い(?)リバーブがかったコーラスやペナっとしたChorusギター音、そしてどことなく湿度の高い夏を思わせるようなサウンドデザインということで強く影響を受けているのではないかと思います。
しかし『Hive Mind』をただ模倣するだけでなく、ルーツであるレゲエの要素を上手く取り入れた『Summer Ghost』やお祭り的なムードのフック部分やパーカッションが印象的な『Sun Child』、ネオシティポップのようなキャッチーさのある『Flamingos』など、自分たちのエッセンスを海外のR&Bシーンのサウンドと上手く掛け合わせています。
音像の面にしても演奏感はしっかり残しながら、(打ち込みと生の丁度中間のような)存在感のあるバツっとしたスネアや左右に飛び散るパーカッションは、現行のネオソウルやR&Bのトラックやクラブミュージックと並べて聴いても負けないような立体感とハリのある音像で、めちゃくちゃ聴き心地がいいです。
またヴォーカルKuroのフロウや詩もポイントです。一曲目『Work song』の「最後に見た顔/よりマシに見えそう」「今週はずっと/(ウ)かんでいる気分でさ」という部分では、一般的にはしない言葉の区切り方や言葉の輪郭を濁らせるようなフロウを使うことで、一瞬日本語で歌っている事を忘れさせるほどスムースに感じさせます。これが顕著なのが『Aloma(Joy Of Life)』でしょう。一聴すると気持ちいい演奏とヴォーカリゼーションによって詩に比重を置いているように感ぜさせませんが、「やってられない日々/でもやっていく/やってやるんじゃない/やっていく/やっていくには?」「嘘か真かのニュースを口ん中でミックスしても無味乾燥/人生はハードモード」「真実と向き合うとmama/全然やってられないよ/だけど目はそむけないと決めた」など、Kuroが感じた日常と社会との付き合い方や葛藤ををかなりストレートに表現しており、スムースなBGMとして聴き逃せないパンチラインが沢山あります。実際本作品の詩は去年の混沌とした状況の中でとても励みになりました。Kuroはソロワークスもとても面白いので要チェックです。(特にこの曲で蹴っているバースはやばい)
9.yonige『健全な社会』

2013年に結成した2人組バンドの5枚目のアルバム(フルレングスとしては2枚目)。この作品、聴いたことある人は意外と少ないんじゃないかな。
自分は「あ、これは今後も聴く縁ないな。」って思うミュージシャンって結構いまして、yonigeもそういうポジションに位置付けてしまっていました。
ただ本作の先行曲『健全な朝』を聴いて一気に印象が変わりました。BPM 100〜110くらいのミドルテンポとドラムとベースにグッとフォーカスされたミックス、ロングトーンで詰めこみすぎないメロディーと牛丸ありさの淡々とした歌唱、全てが丁度いい具合のギターロックソングでした。去年はことあるごとによく聴いていたな〜。このアッパーともダウナーともつかない絶妙な温度感は、中盤で挿入される立体的な楽器の配置がいい『intro』も含めて雰囲気が統一されています。またyonigeは恋愛的な詩が多かった印象でしたが、一転して日常を俯瞰したような内省的な曲が多く、今までの作品と圧倒的に聴き心地が違います。また『あかるいみらい』の2:05〜で聴こえるハンドクラップと下敷きを弾いたような音(なんの音なんだろう、、)が特徴的な間奏部分も意外で、こんなことするバンドなんだと驚きました。
オフィシャルのインタビューによると、削ぎ落とされたシンプルでタフなサウンドは、プロデューサーとして参加したASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文の影響が大きいようです(『11月24日』『健全な朝』の2曲をプロデュース)。またサポートギタリストが導入したDAWも本作が今までと違うことに制作に大きく影響していると思います。
欲を言えば録音やミックスを統一して欲しかったな〜とは思いつつ(「intro」〜「往生際」の音像の落差はかなり違和感ありました)、偏見を持たずにいろんなミュージシャンにトライしたいなと思えるいい作品だったのでセレクトしました。これからが楽しみなバンドですね。
10.中田裕二『PORTAS』
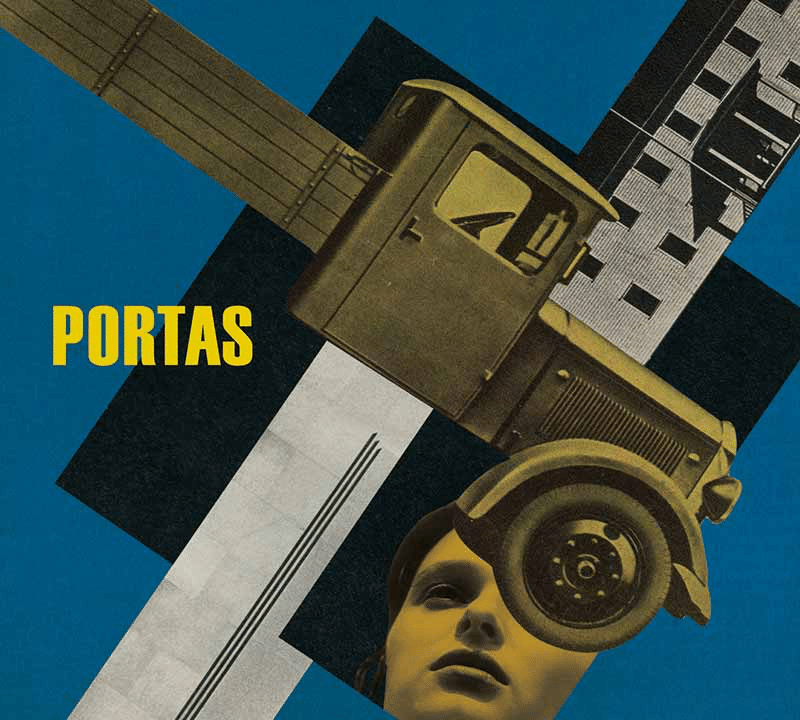
熊本出身で元椿屋四重奏のフロントマン、中田裕二の10枚目のアルバム。「ポストプロダクションを活かしたバンド作品」としてはこの作品も外せません。
実は2020年、中田裕二は『DOUBLE STANDERD』というもう1枚アルバムをリリースしています。(そっちの方も本当にいい作品で選ぶの大変だった。。。)
本作はその延長上な雰囲気がありながらより全体のバランスのとれた作品になっており、ソロ活動10年の成熟加減が伺えます。
この作品を一言で表すなら「宅録的密室感を漂わせたアコースティック歌謡ソウル作品」と言った感じです。
もちろんドラマタイアップもできるようなJ-POPのど真ん中を行くようなメロディセンスを持ち合わせながらも、アレンジは非常に密室感があり、Leon BridgesやKhruangbinを想起させるようなマットでくすんだ音像が全編通して覆っています。これがインディーSSWにも、所謂チャートインするようなSSWにもない絶妙なバランスになっていて、中田裕二の近作の大きな特徴でもあります。
こういうマットで密室的な質感といえば、ロサンゼルスのラテンソウルバンド、Chicano Batmanの新譜も思わせますね。こっちの方がより凶悪な音像ですが。いい作品。
この密室的な音像の背景には、本作品の3分の1の楽曲がリモートレコーディング、また中田裕二によるセルフプロデュースということが大きく影響しています。
アコースティックギターのフレーズとシンセの音色が不思議な聴き心地を与えるミドルソウル『プネウマ』や、抑制の効いたミュートギターが特徴的なAORソング『Predawn』も一聴するとバンド演奏のようですが、どこかDAWで組み上げたようなカチッとしたグリッド感があり、ニューウェーブテクノ歌謡とでもいうようなジャンルの折衷感が強い『Back To Myself』に至っては全てのサウンドを中田が演奏・打ち込み・録音・プログラミングをしています。
また『Back To Myself』はサビ前のギター・シンセフレーズがとても印象的で、セルフプロデュース独特のいなたさを感じてなんとも滋味深いので特にオススメです。(Origami Production界隈が関わったらスムースになりすぎそう。。)
聴くほどに旨味が増すような本作品は、煌びやかでキャッチーなネオシティポップ作品とは一線を画す渋さがあり、オルタナティブな魅力を放っているのではないでしょうか。あとなんとなく15年後の藤井風を観ているような気分になります。
●生活を彩ってくれたグッドバイブスな作品たち
ということで「演奏」と「編集」の観点を中心にプロダクションの優れたバンド・SSW作品を書いてきたわけですが、次はなんとなくうまくまとめられなかったものの、沢山聴いていたお気に入りの3作品を挙げていきます。
11.Zack Villere『Cardboard City』
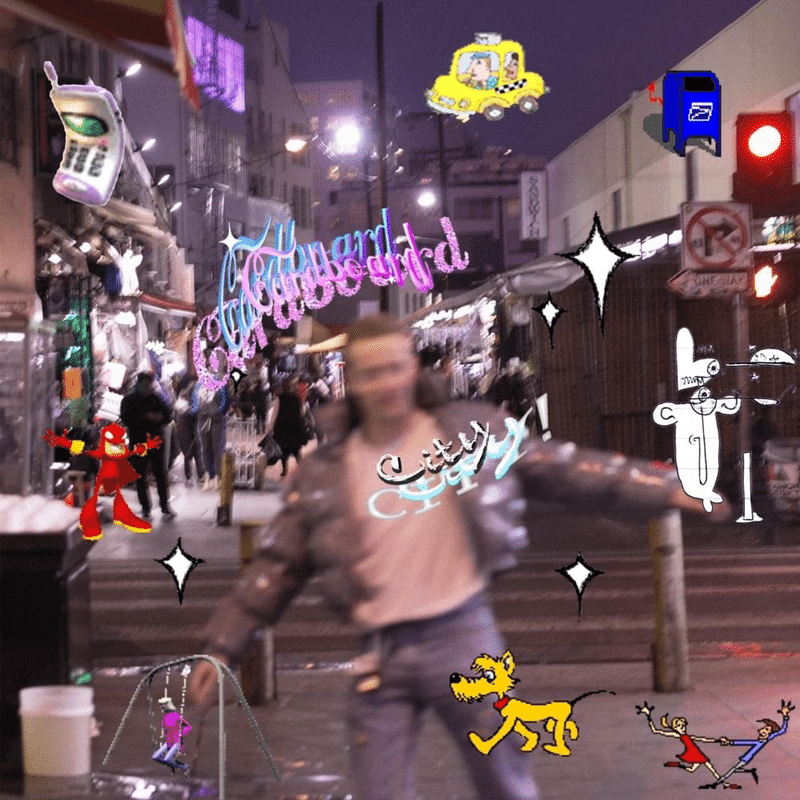
米南部ルイジアナ州出身のSSWの2枚目のアルバム。所謂ベッドルームポップの系譜にあたる、緩くてチープなサウンドデザインが特徴の楽曲を作ってきた彼でしたが、今作はどうやら少し変化の兆しが感じられるような作品でした。
前作『Little World』ではピッチを変化させたようなボーカルや、アメリカのカートゥーン作品を想起させるような奇妙で過激な音使いが印象的で、アルバムに至る先行シングル群はそれらにトラップやドラムンベース的なダンスミュージックのマナーを取り入れた比較的エッジーな音楽性でした。
てっきり本作もその延長上にある過激な音楽性になるだろうと期待していましたが、美しいメロディーとともにピアノの弾き語りから展開される1曲目『Superhero Strength』やアルペジオギターとファズギターの上でまったりと歌われるバラード曲『Knockout』からもわかるように、ソングライティングが中心に据えられた作品となっています。思えば奇抜な音作りが中心だったZackですが、作るメロディーはどれも本当に美しいんですよね。本作はギターや過剰な音色のシンセ、騒がしく挿入されるサンプリングを避け、一貫してピアノがフィーチャーされていますが、これは歌に回帰したZackには必要不可欠なものだったのだと思います。先行シングル『Sore Throat』はそんな彼の変化を代表するような優しい歌メロが素晴らしい一曲で、2020年一番好きなメロディーでした。ボーカルピッチの代わりに包み込むようなコーラス、アルバムの節々に現れるハミングのような柔らかいシンセの音色は、前作より優しく人間味を感じられ、彼の心の柔らかい部分に触れたようなトキメキと癒しのあるアルバムです。ヴィヴィッドな音楽性を好むリスナーには肩透かしを食らわせるような作品でしたが(結構期待されてる感じだったしね)、そういった音楽を追うのに疲れたとき、この作品を聞き直して彼の美しいメロディーに耳を傾けるのもいいのかもしれませんね。
12.Yves Jarvis 『Sundry Rock Song Stock』
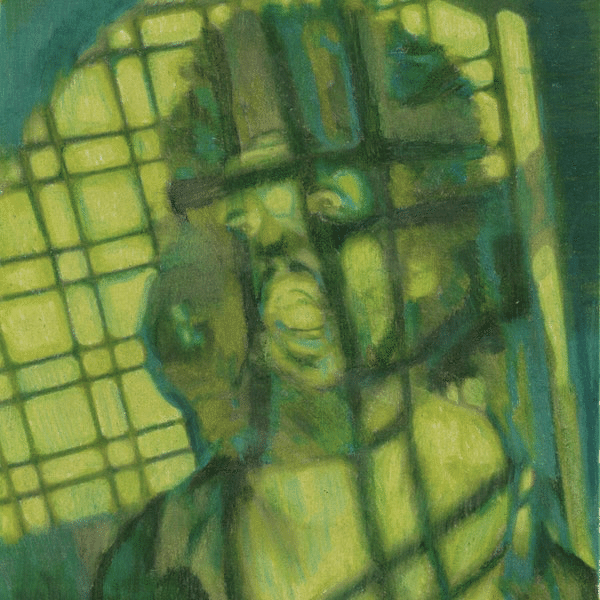
カナダはモントリオールを拠点とするミュージシャン、プロデューサー、そして作曲家Jean-Sebastian AudetのソロプロジェクトYves Jarvisの3枚目のアルバム。これは2020年聴いてきた作品の中でも結構異色というか、唯一無二の感触を持ったアルバムでした。
前作はアンビエントR&B・ベッドルーム的な音楽性にアーシーで異国的な響きのある音が掛け合わさったカオティックな作品でしたが、今作は曲数も絞り、R&Bっぽいリズムや音色は控えめでよりサイケデリックで異国感を感じられる統一感のある仕上がりになっています。ジャンルに明るくない自分が言うのもアレですが、なんとなくMPB(ブラジルのポピュラーミュージックのことを指す言葉)のような色気がありました。マルコス・ヴァーリみたいなね。
様々なジャンルが混在している本作ですが、一曲目『Epitome』に聴こえる森の中を彷徨っているような怪しげなコーラスや、ホセ・ゴンザレスのような綺麗でフォーキーなメロディラインがグッドな『For Props』など、サイケデリックな陶酔感と、草原をかける電車に揺られているようなノスタルジックさを全編通して感じられます。また前作は割とミステリアスで得体の知れなさが音にも現れていた印象でしたが、今作で彼の人間味に触れたような暖かさがあって、そこが割と好きなポイントでした。
録音は非常にナチュラルでローファイ、近年のヒップホップ以降のポップミュージック作品のような角張った質感はなく、終始川の流れに身をまかせているような柔らかい音像が特徴です。この音作りが「サイケデリックさ」と「ノスタルジック」さの同居に起因しているのかもしれませんね。2020年のリラックス枠でした。
ちなみにタイトルの「Sundry」って「雑多」って意味らしいです。へえ〜
13.Khotin『Finds You Well』

カナダはエドモントンのプロデューサー、Dylan Khotin-Footeによるソロ・プロジェクトKhotinの新譜です。おそらく4枚目なのかな?
2020年の後半は目新しいサウンドを求めて海外の新譜を聴き漁り、飽きたら日本語ラップを聴くみたいな、耳に常に刺激を与えるような不健康な期間があったんですね。海外の新譜も日本語ラップも攻めた作品が多くてめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そういうことをやっていると心身ともにダウナーな気分になってくるわけです。要は聴き疲れですね。何のために音楽を聴いているのかマジで本末転倒です。
そんな時期に出会ったのがこのアルバム『Finds You Well』です。「声」のないインストアルバムの良さに改めて気付かせてくれたようなアルバムでした。大好きなBoards Of Canadaを彷彿とさせるようなアンビエントなシンセの音像に、ミドルテンポのローファイハウスでとにかく耳が癒される。リズムや上物の音色が本当にセンスの塊といった感じでひたすらに気持ちがいいんです。
このアルバムを聴くと、楽曲を色々な角度で聴けるようになったとはいえ、結局「声」に音楽を聴くアンテナの大部分が引っ張られてしまっているなと痛感させられました。「声」の入っていない楽曲を聴きながら散歩していると、そこに空いたスペースに自分の思考や周りの景色を取り込みながら音楽を聴くことが出来て、それがすごく自分の中で新鮮な体験だったんですよね。当たり前なのかも何ですけど。そこに気づいた瞬間感極まってしまって、以降すっかり愛聴するようになりました。インストアルバムは良い。
そんなこんなで事あるごとに聴いてはリラックスされてくれそうな末長く付き合っていけるような作品です。疲れたら聴いてみてください。あと前作も超チルでオススメです。
次は刺激強めなヒップホップ作品を紹介していきます〜残り5作品。
●ジャンルを打ち破っていくヒップホップ作品たち
2020年はヒップホップも面白い作品が沢山リリースされましたよね。特に日本や韓国などのアジアのオルタナティヴヒップホップシーンがとても面白かった印象です。現在のヒップホップシーンはジャンル横断がもはや当たり前というか、その中でいかに個性を見出していくかというある種のインフレ状態のようにも思えます。特に、各メディアやリスナーに絶賛だった(sic)boy&KM『CHAOS TAPE』はそんなオルタナティブな音楽性を持つヒップホップ作品の代表格だったと思います。エモロックやミクスチャーロック、アニメソングにトラップのマナーを取り込んだKMの独特なトラックに(sic)boyのメロディアスなフロウが最高な、これも好み云々抜きに「いい作品」でした。
ただ本作は敢えて選ばずに、まだまだ評価と知名度が追いついていないように思える面白いヒップホップ作品を年間ベストに選びました。もちろん、単純にたくさん聴いた大好きな作品たちです。まずは2020年の真打からいきましょう。
14. Moment Joon『Passport & Garcon』
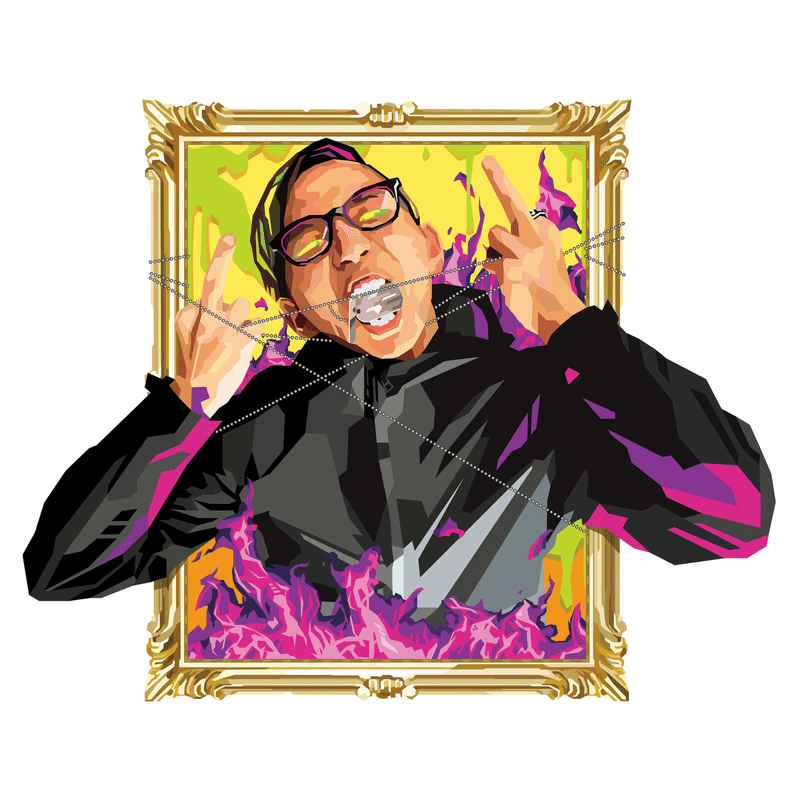
韓国出身で大阪在住のラッパーMoment Joonの1枚目のアルバムで、彼が日本で暮らす中での差別や葛藤が悲痛に、時にユーモラスに描かれた自伝的なコンセプトアルバム。2020年末には客演や新曲を加えたDX版されましたね。やっぱりこれは2020年の国内ヒップホップシーンでは見逃せない作品でした。決してオルタナティヴな音楽性を持つ作品ではありませんが。
本作品はどうしてもMoment Joonの心情がこれでもかと吐露されるリリックの内容に注目が集まりがちですが、実はサウンド的にもかなり面白い作品に仕上がっています。その中でも特筆すべきは数多くのビートチェンジです。
例えばMomentが兵役を終え日本へ帰国することからはじまる1曲目『KIX /Limo』では物語に呼応して3回ものビートチェンジが行われます。「通れなかったら/帰れなかったら/もし君のそばにいられなくなってしまったら」という心の声を歌ったフックの途中を無理やり遮るようにバッサリをビートが切られ、パスポートの確認という”現実”に一気に引き戻されます。そこから弱いドラムを経て帰国、そこからMomentのボースティングに呼応するようにマッチョなビートにチェンジします。
また「在日韓国人に差別的な日本人」にMoment自身がなりきり偏見や陰謀論を語るユーモラスかつ衝撃的なTrap曲『KIMUCHI DE BINTA』ではフックの「真っ赤なキムチでビンタ」という強烈なフレーズの前後にビートが無くなり「説明しても無理/チョンである罪/違うといっても聞こえないふり」というMomentの悲しみが吐露されます。トラップ・ミュージックの気持ち良さの一つでもあるビルドアップ的な構造を壊して差し込まれるこのリリックはより悲痛に響き、ユーモラスで開きなおり的な楽曲により立体的な印象を与えています。
ラッパーによっては既存曲やフリーのビートを使うことも多く、ある種ビートに対するこだわりがないように思うことさえあります。(そこにはLEXのように「どんなビートであっても自分は乗りこなせる」と言った自信の裏返しでもあるようにも感じますが。)
対照的に(本作における)Momentはビートメイカーや客演者向けにアルバムの脚本などを記した企画書を作るほど、リリックのみならずビートや楽曲に対するこだわりもかなり強いではないかと思います。その強いこだわりがNoahの作るビートに深く浸透しているような印象を受け、まるで本人の強い意志でビートをある種支配するような狂気さえも感じるほどです。端正でフリーキーさにかけるトラックやミックスには少々不満はありつつも、楽曲一つ一つに多くの仕掛けがありそれだけでも楽しめるアルバムになっていると思います。一度聴いた人も是非ビートに焦点を当てて聴いてみてください。
15.Mom『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』

「クラフトヒップホップ」を自称するSSW・ラッパーMomの3枚目のアルバム。
それまでMacに付属されたフリーの音楽制作ソフトGaregebandを使ってトラックを制作していましたが今作からは有料ソフトLogicを導入しており、前2作のローファイでキッチュな音像から一転クリアで華やかなトラックが多く、複雑な曲構成も含めクオリティが格段に上がっている印象があります。
様々なテクスチャーの音が各所に組み込まれた奇怪なトラックはSpank RockやJpegmafiaなどボルチモアのエクスペリメンタルヒップホップやZack VillereやStill Woozyのような遊び心の溢れたベッドルームポップの影響を感じさせます。
その上、小沢健二を想起させるメロディラインやたまなどから影響を受けたフォーク的な節回しを意識的に取り入れることで他のヒップホップ作品に類を見ない、独自性の高い作品になっていると思います。沢山の自作曲からセルフサンプリングして作られた各曲は、Moment Joon『Passport & Garcon』と同じく多くビートチェンジやコラージュあり非常に刺激的です。この展開の多い作り込まれた楽曲はやはりセルフメイクであることが大きく起因しているのではないでしょうか。 またアルバムを通してSFなどの映画からインスパイアされたディストピア的な近未来と現実の社会を重ねたかのような先鋭的な詩を聴くことができます。彼のファニーな歌声はそのゾッとするようなニヒルな詩世界を、一層引き立てています。
キャリア最大のヒット曲でもある『Boyfriend』は現在の今や食傷気味なローファイやヒップホップのテクスチャーを取り入れたJ-popのパイオニア的な楽曲であったと思います。故に「ポップすぎてヒップホップじゃない」という思いを引きずった人(あるいはそういった曲を期待するファン)も少なからずいるのではないでしょうか。そんな人たちはこの高い作家性と野心を持った本作を聴けば、彼が今目指しているオルタナティブな音楽性を感じられるのではないでしょうか。
やっぱセルフプロデュースのトラックは独特でいいですね・・2020年はセルフプロデュースのヒップホップ作品で面白いのが多かったんので、いくつか紹介しましょう。
16.環ROY『Anyways』

宮城県仙台市出身のラッパーの6枚目のアルバム。それまで多くのビートメイカーと組んでいた彼ですが、本作はトラックメイクから全て彼だけで作られた完全セルフプロデュース作品です。
「大きな変化ですよ。ベースの入れ方がわからないところからビートを作るんですから。コードの1番下から入れないといけないとか初歩的なことを理解するのも遅かったですからね。」とTurnでのインタビューで話していた通りほぼ1から、音楽理論や編曲技術を独学で学びながら制作されたそうです。凄い熱意だ。。
その苦悩が実ったのか、本作は彼の音楽的嗜好がこれまでになく表出したような楽曲が並び、ジャンルレスな現在のヒップホップシーンに追随するような作品になっています。『I Know』のようなサンプリングベースのシンプルなループトラックから、初期のようなアグレッシブなフロウに呼応するように複雑で性急なリズムが展開される『能』や「枝で箸を作っていたのかだいぶ前の人たち/俺も敢えて作って見たら何かわかるMy箸」と本作のテーマにも繋がる詩でJpegmafiaさながらの崩壊的な曲展開になる『life』、ピッチ変化させたボーカルにインダストリアルなリズムが混ざる『Rothko』など様々です。そんな多彩で折衷的な音楽性は円熟したキャリアの中でも特にデビューアルバムのようなフレッシュさを感じられるような勢いのある作品になっていると思います。これからが一層楽しみなミュージシャンですね。
ベストには入れ損ねましたが上記にあげたような実験的なビート作品の中でも特に紹介したかったのは、熊本県出身ビートメイカーJunes Kの2020年作『SILENT RUNNING』で、これもめちゃくちゃ良かったですね〜環ROYハマったらこっちもどうぞ。
あと個人的にオススメしたいFox4gの2020年作『Attitude』もセルフメイクトラックが光る渋く鮮烈な作品なのでこの流れでぜひ。てかこの作品群だけでも記事にまとめたいですね。
17.Kamui『YC2』
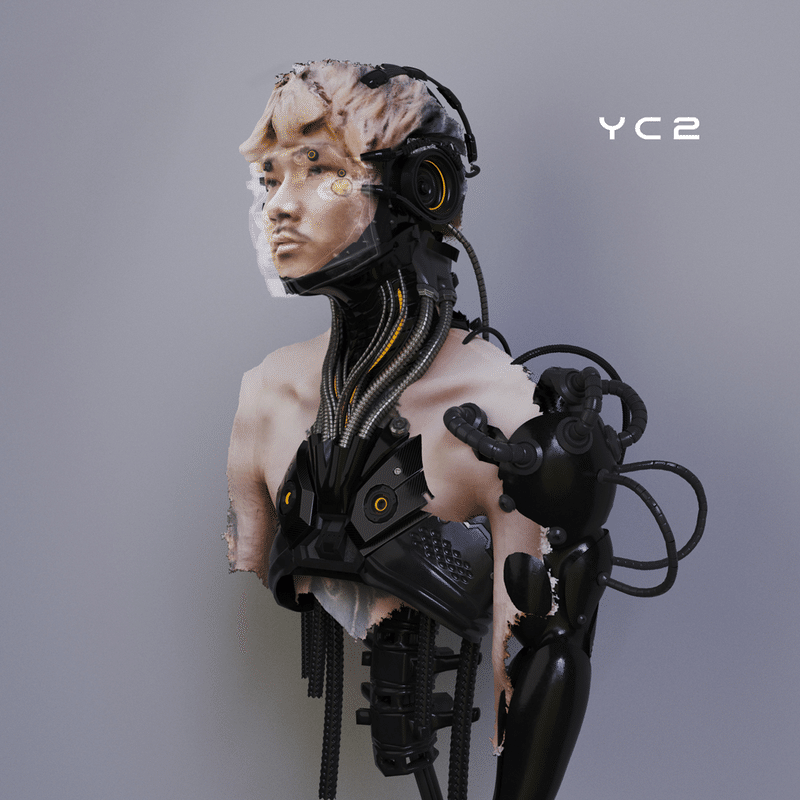
名古屋出身で東京を拠点として活動するラッパー・ビートメイカーの4枚目のアルバム。タイトルの『YC2』は彼の処女作『Yandel City』の略称であり本作はその続編にあたります。意外と沢山作品を出しているんですよね。
本作は近未来の日本を舞台としたSF×ヒップホップなコンセプチュアルな作品で、SFの世界観を表現したようなダークなトラックとKamuiのパンクから影響を受けたヒリヒリとしたフロウは、他のヒップホップ作品では味わえないような斬新で異質な聴きごたえがあります。
サウンドや詩からマトリックスやAKIRAなどのSF映画からのサンプリングを感じられるのに加え、ヴァーチャル世界の主人公として自身を作品の中に落とし込む手法としてなんとボーカロイドを数曲導入しています。特にアルバムの中盤曲『Everything Is Dancing』はボーカロイドのフックとKamuiのシンギングラップを交差させることで仮想空間から現実世界へと作品の舞台をスイッチさせる役割を担っています。
また多彩なフロウも聴きどころで、ダークで機械的なハウスに音として気持ちいいギリギリの情報量を3ヴァース分スキルフルにラップするセルフプロデュース曲『Tesla X』やコード感の不安定なエクスペリメンタルなトラックの上で自身のラップをカットアップしたようなポストプロダクションが印象的な『Kopy Cat』、リアムギャラガーのような気だるさがロックバラード的な響きを与えるマンブルシンギングラップ曲『You’ll Never Know』など客演なしとは思えないほどのバリエーションがあります。本当に毎作毎作1stアルバムのそうな熱量がありますよね。
本作のテーマが「選択によって未来を変えられるか」ということにあるように作品の後半は元恋人の死や、地元のしがらみからの脱出、自身を過小評価する音楽シーンといった現実世界の自身の人生についてリリカルな詩とともに振り返ります。そしてメランコリックなコード感と暴力的なベース音に乗せてエモなシンギングラップ〜リリカルなブーンバップへとフロウを巧みに変幻させていく終盤のハイライト『疾風』では「この世界の色を変えたい/できないなんて思ったこと一度もねえ」と締めくくります。
SFという表層を纏いながらも自身の実存を強く訴えかける作品構成は、聴き手を引き離すようなインパクトを与える反面、聴き手の孤独や葛藤に寄り添い強く背中を押してくれるような印象を受けます。ボーカロイドを起用した作品のギミックや彼のクセのある独特なフロウや歌唱は賛否両論があるとは思いますが、もっと広く聴かれるべき独自性の高い作品だと思ったので選びました。正直めちゃくちゃ聴きました。みんなKamuiを聴いてくれ〜
18.Omega Sapien『Garlic』
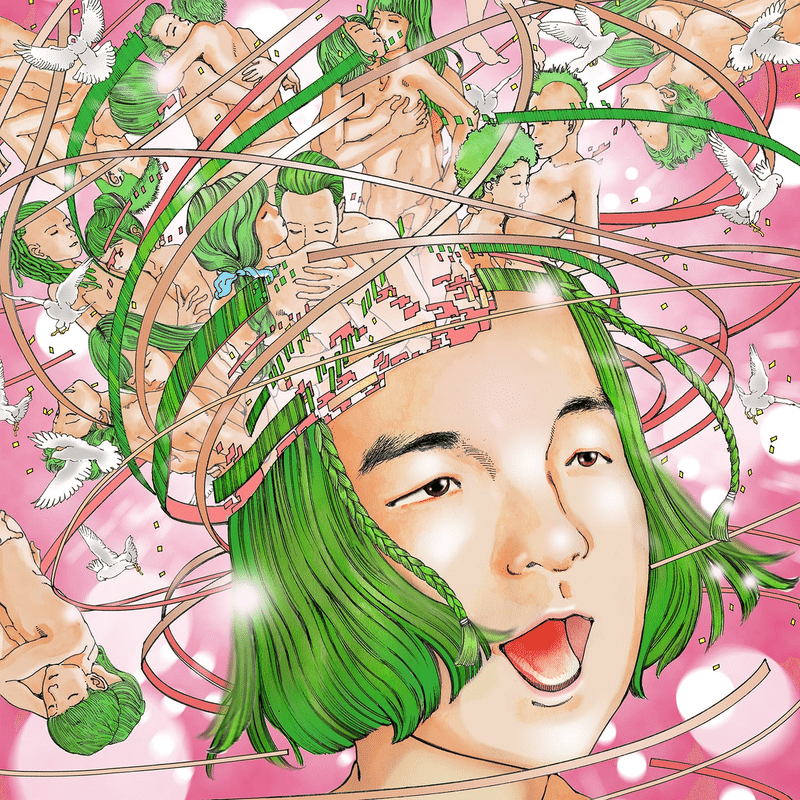
韓国出身でオルタナティブ・Kポップバンド「Balming Tiger」のメンバーとしても活躍するラッパーのソロアルバム。おそらくこれが1作目かな?本作も2020年を代表するオルタナティブヒップホップ作品だったと思います。
全7曲で収録時間は22分という非常にコンパクトなフォーマットですが1曲1曲のインパクトは絶大。歪んだシンセフレーズと4つ打ちのキックからフックのドロップ感がカタルシスを生む1曲目『i p t i m e』やヴァースの緩やかな展開から一気にハッピー・ハードコアのような性急なビート上でOmega Sapienが何者からか全力で逃げているような焦燥感あるフックを放つ『Ah!Ego』など一曲の中で喜怒哀楽がコロコロとスイッチしていくような楽曲は、まるで遊園地のアトラクションを乗り回しているような過剰なスリルと快感を味わえます。
本作のレファレンスとして思い浮かぶのはやはりエレクトロミュージックとヒップホップを融合させたKanye Westの傑作『Yeezus』でしょうか。
しかしジャケットにも現れているように本作の方がより明るく煌びやか印象があり、これはバブルガム・ベースやハイパーポップのようなインターネット発の音楽からの影響と、Omega Sapien自身のコミカルな声質とフロウが寄与していると思います。開き直った明るさというか、ちょっと怖くなるくらい明るい。
こういう風にラップとトラックが互いに見せ場を作ってカタルシスを生むような作品はとても希少ですよね。この作品をきっかけに「韓国のヒップホップ」追わねば、、という気持ちになりました。そのくらい刺激的な1枚。
最後まで読んでいただきありがとうございます!沢山迷ったけど見返すと結構自分らしいセレクトになったのではないかと思っています。以上が2020年選んだ年間ベストアルバム18枚でした。今年はどんなアルバムを選ぼうかな〜今から楽しみです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
