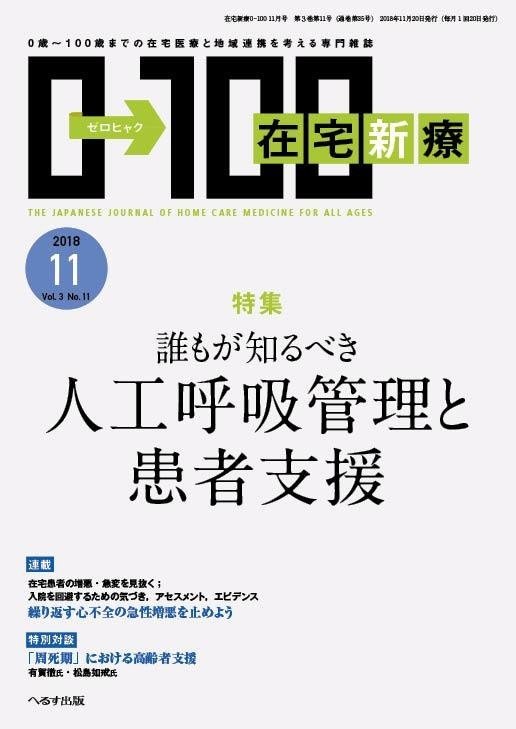【第7回】トップダウンではなくフラットな、型の固定されないしなやかな仕組みが、これからの在宅医療のど真ん中
個別性の宝庫である在宅医療の世界には、患者の個性と同じように、ケアする側も多彩で無数の悩みをかかえています。悩みにも個別性があり、一方で普遍性・共通性もあるようです。多くの先輩たちは、そうした悩みにどのように向き合い、目の前の壁をどのように越えてきたのでしょうか。また、自分と同世代の人たちは、今どんな悩みに直面しているのでしょうか。多くの患者と、もっと多くの医療従事者とつながってこられた秋山正子さんをホストに、よりよいケアを見つめ直すカフェとして誌上展開してきた本連載、noteにて再オープンです(連載期間:2016年1月~2018年12月)
【ホスト】秋山 正子
株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長、暮らしの保健室室長、認定NPO法人maggie’stokyo共同代表
【ゲスト】佐々木 淳(ささき じゅん)
医療法人社団悠翔会理事長・診療部長
―――――――――――――――――――――――
【対談前の思い・テーマ】
①在宅医療で医師が何をやるか、最初はまったくわかりませんでした。アルバイト先のクリニックで始めた在宅医療を医師としてどう位置づければよいのか、よくわかりませんでした。かかわるうち、答えを教えてくれたのは患者さんたち。今でも印象に残っています。
②一緒にかかわる看護師には、医師の足りないところを助けてほしいです。医師は、医学モデルで考えてしまいがちです。患者とのかかわり、家族とのかかわりで見逃してしまう部分をサポートしてもらったり、地域での情報共有を担ってもらえると、とても助かります。
「総合的に診る」医師に育ってもらうには
秋山 筑波大学ご出身ですが、大学に残らずに三井記念病院に。
佐々木 もともと全身を診られる医師になりたいと思っていたのですが、僕らの世代ではまだ総合診療という研修のコースがなかったのです。 かといって、大学病院にそのまま残ると臓器を決めないとならないから、「民間の病院の内科で、循環器も呼吸器も消化器も全部診られるところを探そう」と思ったのです。それに当てはまる病院が当時は3つあって、そのなかから三井記念病院を選びました。
秋山 最初から全体を診たいと思われたのはどうしてですか。
佐々木 もともと『ブラック・ジャック』という漫画に憧れて医師になったクチですが、あまり協調性がないし、でも1人でオペはできないということを知って、1人で全部診られるとなると外科ではなく内科なのかなと。
秋山 三井記念病院での勤務中から、在宅に出られていましたか。佐々木 そうではないんです。三井記念病院に勤めている途中から、東京大学の大学院に行くようになったのですが、慣れない基礎研究があまりに合わなくて(笑)。それで大学院の研究活動はいったんストップしたのですが、大学病院での臨床は続けていました。ただ給料は出ないので生活のためにアルバイトを。アルバイト先のフジモト新宿クリニックが在宅もやっていたんです。
秋山 週に何日かだけ。
佐々木 ええ。ただ、別に在宅をやりたくて行ったわけではなく、たまたま藤本進先生が在宅医療をやっていたという感じです。在宅医療のコンセプトをまったく理解しておらず、「へぇー、家に行くんだ!」みたいな認識でした。だから患者宅に行っても、何をやっていいかわからなかった。ゴールが見えないというか、病院だったら何か管理目標や、治癒という目標があるけれど、在宅の場合は生活している人たちの生活をみに行ってるわけで、医師としてどういう立ち位置に自分を位置づけたらいいかがよくわからなかったのです。
秋山 そのころ、四谷でたぶん会ったことがあるはずなんですよ。
佐々木 会ってたんですね。当時の患者にも何人か印象に残っている人がいて、ある人はALSの女性でしたが、レスピレータが着いていて、「人工呼吸器なんて、苦しそうだな」と僕は思うわけです。「苦しくないですか」と聞くと、彼女は「苦しくない」と。ところがあるとき、「とっても苦しい」と彼女が言うのです。「何が苦しい?」と聞いたら、「花粉症で鼻水が止まらない」って。 僕はすごく驚いて、「レスピレータなんか着いてたら、花粉症なんて超ささいな問題じゃないのかな」と。だから、花粉症で「困った」の前に、レスピレータのほうが苦しくはないのか、少し聞きにくかったけど率直に聞いてみたんです。すると彼女は「人工呼吸器はもはや着いていることも気にならない。外出もできるし、家族との時間もあるし、私、そんなに不幸じゃないです」みたいなことを書いてくれて、僕にとっては衝撃でした。器械がないと生きていけない状況で、自分は不幸じゃないと言い切れる。「これは何だ?」って。
そのときに健康や幸せの価値観は多様なのだと思ったし、障害とともに生きることを僕らが不幸と思っていたら、きっと患者は皆、不幸に生きていくのだろうと思った。「病気があっても不幸じゃない」と思える状況が、生活によって生まれるのかと、当時はそれを表現するボキャブラリーがなかったですけど、それって素晴らしいと思ったことを覚えています。そうした経験をするうちに、自分でやってみてもいいかなと考え始めました。
秋山 実際に始めてみてどうでしたか。在宅医療はプライマリ・ケアでもあり、全体を診る医師でもあると思いますけど…。
佐々木 全体を診られる医師になりたいと思っていましたから、在宅医療を地域で始めるうえで、3つのことを心がけました。1つ目は、「〇〇の領域は苦手だから病院に行ってもらおう」とはせず、僕は「全般を診ますよ」と伝えました。2つ目は「求めがあれば必ず24時間往診しますよ」ということ。3つ目が、その人の人生観を大切にしたいということ。この3点を「地域の人たちとのお約束」として掲げてスタートしました。
秋山 そうやって始められてから、診療所を拡大していくのが非常に速いし、人集めも上手だと外から見て思うのですが、そこの経営的な工夫はありますか。
佐々木 在宅の場合は、必ずしも病気を治しに行っているわけではないので、その人たちのニーズをしっかりキャッチしてそれに応えていく。それは個人単位でも大事だし、地域単位でもそうです。例えばこの地域は在宅医が何人かいるけど、電話しにくいとか、夜なかなか来てくれないとか、精神科が少し弱いというのがあれば、そこに行く。 僕らは、「ここが患者さんが多そうだから診療所を出そう」という方法は、実はこれまで1回もとっていないのです。地域の事業者や行政の人が「出して」と言ってきてくれたときに、「この人たち、信用できそうだな」「方向性が近そうだな」と思ったら出すようにしてきています。
また、出すにあたっては、ポンとは出さず、どんな診療所がいいのかを時間をかけて検討する。出すと決めてから、オープンするまでに1年くらい時間がかかるので、その間に地域のケアマネジャーたちとワークショップや勉強会を開いたりします。2カ月に1回ずつ勉強会をすると、「作るぞ」と決めてからだいたい5~6回できて、7回目でワークショップとクリニックのお披露目みたいな感じになります。
もともと千代田区から半径16kmで回っているから、東京23区内はカバーできる条件が整っている。だから、スタート前から診察自体はもうできるんです。診療所ができる前から集患はできるイメージですから、スタートした段階で居宅の患者が50~60人いて、常勤の院長が1人いるんだけど、あと20~30人患者が増えたら、2人目の常勤の先生を入れるという感じで始めていくんです。
ただ来てもらう医師が一番肝要なところで、「患者や地域のニーズに応えるために僕らはそこに行くんだ」というコンセプトが共有できない人が行くと、困ったことが起こる場合があるので、「医師が確保できたら出しますね」という感じです。
秋山 地域のケアマネジャーや訪問看護師など、医師以外の医療・介護の連携やコンセプトの共有はうまくいくとしても、医師自体が「総合的に診る」「生活をみる」というふうに変わってくるのには、時間がかかると思うのです。
佐々木 そうなんですよ。
秋山 そこが一番大変なんじゃないかなと思っていて。
佐々木 僕の結論としては、若い医師は育てられますが、40歳を過ぎてくると自分の価値観があるので変えられないと考えています。だから自分と同世代を採用する場合は、あらかじめ方向性が近かったり、共有できている人を採るしかない。そうじゃない人は比較的若い段階で採って、一緒に勉強していくという感じですかね。
秋山 今、クリニックは何カ所ですか。
佐々木 11カ所で、12カ所目を準備中です。
秋山 それだけの数になると情報の共有や方向性を合わせる工夫など、大変な面もありますか。
佐々木 一番大事なのは採用の段階です。方向性が合わない人が来てしまうと、いくら教育・研修をしても変えられないので。方向性が合っている人という前提で採用しています。 教育・研修は、「在宅医療をやったことがある人」を含めて、実際に僕らの診療に同行してもらい、サービス担当者会議、退院前共同指導の実際も見てもらいます。在宅医療の経験がない人は、2~3カ月同行訪問したあとに、1人で患者を少しずつもち始めてもらいます。いきなり多くにはせず、数人ずつ、時間をかけて丁寧に勉強しながらやってもらって、1年ほどで稼働率7割くらいになってもらっています。
教育・研修といっても、こちらから教えてあげるというより、何を勉強しなくてはいけないのかを、定期的な面談などで気づいてもらって、自主的に勉強してもらえるように心がけています。学会や外のクリニックを見学に行ったり、そういった部分は惜しまずに投資するように、看護師も含めて取り組んでいます。
秋山 実際に働いている人の「やりたいこと」「課題の吸い上げ」にも、工夫されていますか。
佐々木 小さい診療所がパラパラあって、みんな遠隔での連絡なので、それぞれのクリニックごとの問題を抽出するのも時間とエネルギーがかかります。全部で12人いる院長が、月に1回は集まって院長会を開くようにしていて、それぞれのよかったこととトラブルを共有します。よい取り組みは皆でシェアするし、「これはこうやったらうまくいった」というのも皆でシェアして、それを積み重ねていく。普通の診療所がやることを、われわれの法人はおよそ10倍のスピードで経験していけることになるので、それは僕らの成長の種の1つだと思います。 そのシェアの場には、地域で連携している医師にも参加してもらえるようにしています。そのほか地域に16ある連携先のクリニックの医師とも、月に1回カンファレンスをやったり、年2回の全体ミーティングでワークショップを開催したり。
秋山 利用している患者の満足度調査のようなこともしていますか。
佐々木 全体評価を毎年やっていて、13項目の質問につき、患者・家族、地域の事業者、施設運営者に回答をお願いしています。病院の平均在院日数のような指標はないし、患者ごとに満足の指標が違うから、これをどうスコア化するかはけっこう難しい。毎年、外の事業者、患者に、トータルで5,000通くらい送って、回収率は7割ほどです。それから内部評価もあって、各ドクターについて、それぞれかかわる診療チームのスタッフが評価をする。全体評価は年1回、内部評価は年2回やって、それで医師は通信簿がもらえるという感じです。どこがダメというより、「どこに伸びしろがあるよ」と伝えて勉強してもらう仕組みですね。自分の通信簿が一番よいだろうと思っていたのですが、僕より成績がいい医師がいるんです(笑)。最初見たときはショックでしたけど、最近は、「まあそんなもんだよね」みたいな(笑)。

佐々木 ある程度の年齢になると、自分の価値観はなかなか変えられない。 方向性を共有できる人材に出会うための採用は、じつに大切です。
フラットに、自然と強みを生かし合うチームを
佐々木 一緒に勉強していくといっても、つきっきりで教えるわけにはいかないので、結局教えてもらうのは、ケアマネジャーや訪問看護師。怒られながら成長していく。僕も秋山さんに怒られたことがあって(笑)、覚えてます。ある施設での医療を連携させてもらったときに、「先生はなんでも1人でやろうとするのね」と諭してもらいました。
秋山 すみません(笑)。
佐々木 いえ、こちらこそ。「すみません、勉強不足でした」って(笑)。
秋山 あのときお伝えしたかったのは、「振ってもらえるように訪問看護師の側もスタンバイしているので、すり合わせをしてもらえたら…」というニュアンスなんです。
佐々木 僕らもまだまだ未熟だったというか、僕が「やりたい」と見切り発車した診療所だから、勉強しながらやっていたのが実情です。当時、まだ20代だった若手院長と「ちょっと一緒に勉強しなきゃね」と反省しました。
秋山 介護施設のケアスタッフにもさまざまな人がいて、不安の強い人もいます。介護のプロではあるけれど医療のことはわからない場合も少なくないので、そういう人向けには「よく使う薬剤の勉強会」とか、「緊急電話を入れる際の、5W1H」とか、施設のスタッフの底上げにつながるような介入も検討しながらかかわったりするんですね。
そうやってかかわって、少しずつ改善してもらおうとしていたとしても、医師とそのすり合わせができていないと、結局「医師に頼りっきりの環境」になってしまって、ケアの人たちを育てる環境にはならないんじゃないかしら。だから、佐々木先生たちが、施設からの要請にしっかりと応えて、出番がどんどん来ているのは「よい面ばかりではないかも…」と、「全部1人でやるんですね」と言ったわけです(笑)。そういうことはどこでも起こっているから、すり合わせがきっと必要。
佐々木 おそらく秋山さんの言葉どおり、当時の僕らは1人で全部やろうと思っていたんだと思います。訪問看護師やケアマネジャーとは、明確に役割分担しながら連携してはいたけれど、「地域全体を面で支える」といった視点はまったくありませんでした。とくに施設の場合はチームを育てることが、いわば1つのゴールだけど、当時はそういう考えはぜんぜんなかったですね。目の前の患者の問題を解決していこう、ということだけで。 それを秋山さんにも叱られたし、僕自身も多職種連携の勉強会などいろいろな場でもお叱りを受けて、そんなこんなで12年かけて少しずつ勉強してきたという感じです。ただ、まだまだ体系的に在宅医療ができているわけではないので、教えてもらいながら。
秋山 今や在宅はもうチームが当然というか、多職種が一緒にやって当たり前の領域ですね。
佐々木 地域の皆で頑張ろうと思えば、結局、自分たち医師が出しゃばらないほうがよいなというシーンがけっこうあります。 「安心できる生活」を地域で叶えるには、患者のニーズも大事ですが、チーム全体をきちんと機能していく形にする必要がある。そうすると、「病気で弱っていく・もうすぐ死んでしまう」この人を安心してみていけるヘルパーが必要で、つまり僕らが支援するのは患者・家族だけではなくて、「ヘルパーのエンパワメント」「福祉系のケアマネジャーにも伝わる情報提供」などを通して、地域でイメージを共有して、この人たちがドキドキしないで支援ができるように支えることですよね。
「患者のニーズ」と僕らは言ってきたけど、在宅でかかわるのは、患者だけではなくて家族もそうだし、もう少し広い視野で支えるコミュニティ全体が患者だと、今は定義を変えています。そうするとかかわり方も変わってくる。
また、以前英国の澤憲明先生が「shared leadership」という言葉とともに、「かかわる誰もがリーダーシップがとれる・誰がリーダーシップをとってもいい」という状況が多職種チームとしての理想ではないかと教えてくれました。それぞれの専門性と立ち位置と患者との距離感のなかで、お互いにリスペクトし合って、誰でもリーダーになれる。僕もそれが一番いいかなと思う。ついつい出しゃばり癖が出ますけれど、そこは抑えつつ。
秋山 医師のなかでは、佐々木先生は横並びでかかわってくださる先生だと思いますよ。「叱られた」という話ばかりじゃなく(笑)、看護師と横並びで連携されてきて、今どんなことを考えてらっしゃいますか。
佐々木 僕らは、診療同行の看護師には、「医師の足りないところを埋めてもらおう」と考えています。僕らはついつい医学モデルで考える癖があるから。あとは、患者の家族の不安な目の動きを見逃さないように、看護師に診察に参加してもらっていますし、多職種連携で情報共有が重要なんだけど、医師が直接電話をかけると恐縮する人も多いので、看護師同士で情報を共有してもらうなど調整役としても活躍してもらっています。 また、地域において、在宅医療を支える側の主役は訪問看護師がよいと僕は思っています。ただ、訪問看護師も人それぞれで、病院に入院させたくなってしまう人もいますので、それぞれのスタンスに合わせながら一緒に勉強しています。
在宅医療で、日本みたいに「医師が月に2回行け」といった制度の国はないですよね。フランスなど、基本は看護師がガンガン行って、時々医師が呼ばれるパターンが一般的で、医師が主力で、在宅医療は医師主導でやるというスタイルは国際的に見ても微妙かな…。ただ現状は、訪問看護の供給量・絶対数が少ない。そういう意味でも、もう少し訪問看護が増えてもいいと思っています。
秋山 若い先生方は、訪問看護師とのかかわりで苦労をされていたりしますか。
佐々木 最近の若い医師たちは、僕らよりも多職種連携をちゃんと勉強してきている人のほうが多いし、訪問診療に同行してみると、とてもフラットにコミュニケーションができるんですよね。職種間の障壁をぜんぜん感じさせないコミュニケーション能力が、若い人たちにはある。むしろ僕らは、そこから学んだほうがいいんじゃないかと思いますね。30代前半より下の若い人たちは、自然な連携がとれている感じがします。だからあと10年もすれば、地域医療の様相は相当に変わっているんじゃないかな。コミュニケーションの難しさをあまり苦労とは捉えないのかなと思いますね。
秋山 SNSなどのツールの関連もあるのかしら。
佐々木 どうでしょうね。フェイスブックとかで、普段からフラットに多職種がつながっているのはあるし、仕事でも、トップに医師がいて、看護師がいて、ケアがいてという雰囲気では、今はぜんぜんないですね。個人ベースで職種に関係なく友達で、それぞれが今はフラットにつながっているから、それが地域でも自然な姿で現れていて、「看護師だから」みたいなのはない。そういう意味では、SNSはすごく意味があるかなと思いますね。 最近になって、僕ら医師は「生活を支える」なんて言い始めたけれど、そもそもそんなトレーニングは受けていないし、価値観は理解できるけどスキルはもっていないですね。もちろん「ここは僕がやるしかない!」という場面では精いっぱい取り組みますが、それぞれ得意分野があるから、フラットさを生かしつつ、役割分担が自然とできるようなチームをそれぞれの地域ごとにつくっていくことのほうが重要です。
だからクリニックごとにケアカフェやカンファレンスをやったり、皆で顔の見える関係を超えて、お互いの仕事のスタンスとか、何が得意かとか、まず「理解する」ことが大事かなと。
秋山 それは今や、患者・家族についても同じかもしれませんね。あおいけあの加藤忠相さんをはじめとして、当事者、つまり医療でいう患者・家族力をどう引き出すか。こちらから何か働きかけをするとか「介護する」とかではなくて、「相手の力を引き出そう」という方向に進んできています。
佐々木 僕の元同級生の丹野智文さんの講演で「ベストサポートを求めているわけではない、僕らが求めているのはパートナーなんだ」という言葉を聞いて、グサッと。その人の生活だから、かかわるわれわれも「よりよいケア」とか「支援する・穴を埋める」というのではなくて、その人が強みを生かしながら、その場所でちゃんと生きる目的・生きがいをもって生活できる状況を作っていくことがとても大事で。それはいろいろな人がこれまで発信してきたような、「強みを伸ばす」とか「本人にとっても、介護者にとっても快適な領域を広げる」といったことかと思います。 本人の強みをより高めれば、その人の弱点は多少あっても、「だから何?」という状況になっていくけど、現状は弱点にフォーカスして、弱点を埋めることに専念してしまっているところがあるので、そこは意識を変えていく必要があるし、専門職の間で勉強会をやっているだけでは足りないのではないかな、と思っているところです。(了)
§ § §
対談をおえて
佐々木 在宅医療を始めたばかりのころ、「自分の正義」を振りかざして突き進んでいた気がします。しかし、それが本当に患者さんのため、地域のために一 番よいのか? 多くの人に示唆をいただき、理解を深め、方向性を変えてきました。秋山さんにはチームで仕事をすることの大切さ、そして訪問看護の力を教えていただいたように感じます。暮らしの保健室やマギーズ東京など、一人ひとりの人生に真摯に向き合い、大胆にチャレンジを続ける秋山さんの姿勢から、常に多くの刺激をいただいています。同じ地域で協働させてもらえる幸運に感謝しかありません。
秋山 もともと全身を診られる内科医を目指したことが出発点。バイトに行った先で偶然出会った在宅医療へ触れることにつながったエピソードは、とても興味深いものでした。そこから、地域全体を面で支えるチームを作り上げるという視点まであっという間に到達され、在宅に興味をもつ医師やそのほかのメンバーを育てる仕組みを組み立てていくところはさすがです。社会的処方を大きく拡大して、農業とのコラボレーションを試みようとしていることも伺い、今後の動向からますます目が離せないと感じました。超多忙ななか、対談のために時間を割いていただきありがたく思います。
―――――――――――――――――――――――

【ゲストプロフィール】
1998年筑波大学医学専門学群卒業。社会福祉法人三井記念病院内科/消化器内科、東京大学医学部附属病院消化器内科等を経て、2006年に最初の在宅療養支援診療所(MRCビルクリニック)を開設。2008年 医療法人社団悠翔会に法人化、理事長就任。
現在、首都圏を中心に全15クリニックで、約5,000名の在宅患者さんへ24時間対応の在宅総合診療を展開している。
【出版】
『これからの医療と介護のカタチ 超高齢社会を明るい未来にする10の提言』(日本医療企画、2016)、『在宅医療 多職種連携ハンドブック』(法研、2016)、『在宅医療カレッジー地域共生社会を支える多職種の学び21講』(医学書院、2018)等。

【ホストプロフィール】
2016年10月maggie’stokyoをオープン、センター長就任。事例検討に重きをおいた、暮らしの保健室での月1回の勉強会も継続、2020年ついに100回を超えた。2019年第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
―――――――――――――――――――――――
※本記事は、
『在宅新療0-100(ゼロヒャク)』2018年11月号
「特集:誰もが知るべき 人工呼吸管理と患者支援」
内の連載記事を再掲したものです。
『在宅新療0-100』は、0歳~100歳までの在宅医療と地域連携を考える専門雑誌として、2016年に創刊しました。誌名のとおり、0歳の子どもから100歳を超える高齢者、障害や疾病をもち困難をかかえるすべての方への在宅医療を考えることのできる雑誌であることを基本方針に据えた雑誌です。すべての方のさまざまな生活の場に応じて、日々の暮らしを支える医療、看護、ケア、さらに地域包括ケアシステムと多職種連携までを考える小誌は、2016年から2019年まで刊行され、現在は休刊中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?