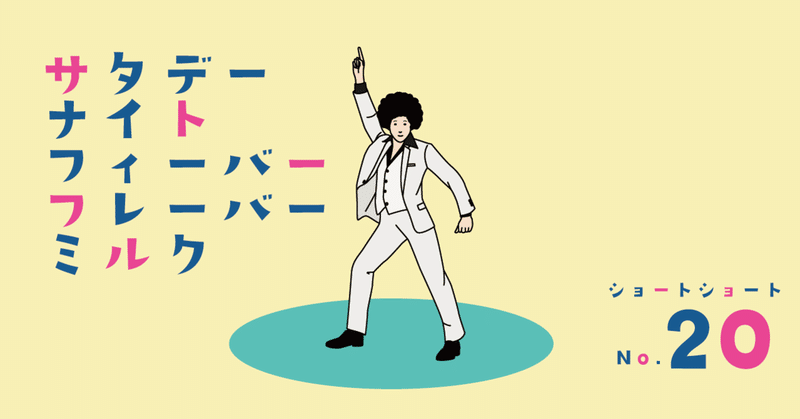
ショートショート サタデーナイトフィーバーフレーバーミルク
入り口の扉は分厚くて重たそうだった。怖い顔のボーイが立っていた。動悸で胸が破れそうだった。
「こんばんは。」と笑顔を作ってボーイに挨拶した。すぐに後悔した。いかにも、田舎娘みたいだ。恥ずかしくて息がつまった。ボーイは会釈だけして、扉を開けてくれた。「ありがとう」と小さく答えた。ボーイがちょっと笑った。
入るなり、音楽と熱気に圧倒された。
胸に抱えていたハンドバックを落としそうになって、慌てて気を取り直した。星空よりも綺麗なキラキラが、部屋じゅうをぐるぐる回っている。背中が誰かとぶつかった「ごめんなさい」と謝った。ぶつかった人はさっきのボーイと同じような顔をして去っていった。香水の匂いが残った。見たことがないくらいおしゃれな人だった。
私、変なのかもしれない。精いっぱいおしゃれしたつもりだったけど、余計に恥ずかしく思えた。せめて香水くらいしてくるべきだった。お母さんの。でも、たくさんありすぎてどれをつけるべきかもわからなかったし、私なんかがつけるのも恥ずかしく思えた。でも、そうだな、つけてくるべきだった、立って見ていると邪魔になりそうなので、壁側に寄った。椅子があったので、座った。キラキラはここまで届いていなかった。少し落ち着いた。
部屋の真ん中、一番キラキラが集まっているところに、一人で踊っている男の人がいた。真っ白なスーツが素敵だった。部屋中の人が踊っていたけど、本当に『踊っている』のはあの人だけだと思った。音楽も、あの人のためだけに流れているみたいだった。くるりと体を回転させた。部屋じゅうから歓声があがった。私も思わず立ち上がった。
「何をお飲みになりますか」
声をかけられた。驚いて声が出た。振り向くと男の人がたっていた。そういえば椅子と一緒に細長い机がある。何か頼まないといけないんだ。「ええと……。」あわててメニューを探した。
「ソルティドッグを2つ。」
後ろから声がしてもう一度振り向くと踊っていた人だった。思っていたより大きい。私に覆い被さるくらい。体から湯気が出ているみたいだった。
「君は踊らないの?」
男の人は当然のように私の隣に座った。びっくりして席をひとつ開けようとしたら、腕首をつかまれた。驚いた。慌てて手をひっこめようとすると、「ごめんね」と言って離してくれた。ちょっと悲しそうな顔になった。
今度こそ胸が破れる。そう思った。
「ソルティドッグです。」
机の上におもちゃみたいな綺麗な飲み物が滑ってやってきた。本当に滑ってやってきた。三角の、薄いグラスに入っていた。ここでは飲み物までキラキラしてる。
男の人がちょっと笑った。不思議だ。あんなに大きくなっていた音楽がもう聞こえなくなっていた。私が顔を見ると、満面の笑顔で「嬉しそうだから。」といった。それから、さっきのグラスをつまんであっという間に飲み干した。もう一方のグラスを指さした。大きな手だった。「俺の、おごり。」
びっくりした。もうずっとびっくりしっぱなしだ。断ると、またこの人を悲しい顔にさせると思った。『ソルティドッグ』ってなんだろう。私はグラスをつまんだ。男の人のまねをして飲み干した。しょっぱかった。頭がぐらんと揺れるのがわかった。
「チェイサーを。」男の人が、机の向こうに言った。私の方をみて、「そんな急に飲んじゃだめだよ。」と言った。すぐに『チェイサー』が机を滑ってでてきた。恐る恐る飲んだら、お水だった。男の人がずっとこっちを見ていて、恥ずかしかった。
「君は、踊らないの?」また男の人がいった。いろんなことが起こりすぎて、もう何で息がつまりそうなのか分からない。声を必死で絞り出して答えた。「踊り方なんて知らないから。」
「大丈夫。」男の人が笑った。「好きに体を動かせばいいんだ。」
「…恥ずかしい。」
「気にすることなんてないさ、他人のことなんて。」
うまく返事ができなかった。私は、男のひとの顔を見た。この人は、ずっとこっちを見ていた。
「それに、俺と一緒に踊れば、誰も君のことを笑いやしないさ。さっき、ずっと見てただろう?」
私はきっと、真っ赤になっていたと思う。顔が蒸発してしまうかと思った。男の人が声をあげて笑った。
「踊ろう。楽しいよ。もし君がよければだけど。」
男の人が立ち上がった。私に手を差し出した。
私は手を取った。立ち上がった。
二人で部屋の真ん中に走った。音楽が急に大きくなった。みんなが道を開けた。キラキラが私に降り注いだ。男の人が何か叫ぶと、みんなが歓声をあげた。
リズムに合わせて体をゆらした。心臓が、いっしょに鳴った。キラキラが口に飛び込んできた。右手の先にはあの人がいた。ステップを踏んだ。手をひらひらした。腕と足が、ばらばらになるみたいだった。
※
「これなに?」
冷蔵庫に顔を突っ込んだまま、夫が言った。タッパーに入った白い塊を私に見せた。
「サタデーナイトフィーバーフレーバーミルク。」
私は言った。夫が変な顔をした。タッパーのふたを開けて匂いをかいだ。
「チーズ?」
「『サタデーナイトフィーバーフレーバーミルク』。田舎娘の牛乳を瓶に入れて一晩中踊るとできるの。」
「マクドナルドにあるのは『サタデーナイトフィーバーフレーバーミルクバーガー』?」
「『ダブルサタデーナイトフィーバーフレーバーミルクバーガー』。」
「うまいね。」夫が塊を少し摘んだ。「お酒いれた?」
「いれてないよ。瓶を消毒するのに少し使ったかも。」
「うまいよ。なんだろう。踊りたくなる。」
「『踊ろう。楽しいよ。もし君がよければだけど。』」
私が手を差し出すと、夫が軽くキスをした。私は笑った。だいぶ太っちゃったけど、この人は今でも一番キラキラしてる。
それから私たちは一晩中踊った。音楽にのって。笑って、騒いで、疲れて、チーズになるまで。
ショートショートNo.20
よろしければ、こちらもどうぞ
