文壇ゴシップニュース 第6号 シンクレア・ルイスの顔面を侮辱したヘミングウェイ──私小説としての『河を渡って木立の中へ』──
まずは、次の文章を読んでもらいたい。
二人は、三つ目のテーブルにいる男のほうを見た。イタチのがっかりしたところを、うんと拡大したような不思議な顔をした男だ。安物の望遠鏡で月世界の山の景色を見たときのように汚い痘痕づらは、ゲッペルスの顔に似ている、と大佐は思った。もしヘル・ゲッペルスが、火に包まれた飛行機にのっていて、火のつく前に機体から脱出できなかったら、あんな顔になるだろう。
その顔が、抜け目のない詮索好きな視線に答えるように、絶えず、あちこちのぞいている。その顔の上に、人類とはいささかの関係もなさそうなまっ黒な髪がある。この男は、一度頭の皮を剥がれて、そのあとへこの髪を植えつけたように見える。じつに面白い、と大佐は思った。ひょっとすると、あいつは、おれと同国人かもしれぬぞ。そうだ、きっとそうだ。(大久保康雄訳)
これは、アーネスト・ヘミングウェイの小説、『河を渡って木立の中へ』の中にある文章で、ゲッペルスに似ていると書かれている男のモデルはシンクレア・ルイスである。場所はヴェニスにあるハリーズ・バーで、今でも開店しているようだ。
シンクレア・ルイスは、アメリカ人で初めてノーベル文学賞を受賞した作家だが、現在の評価・知名度は共にかなり下落していて、よく『石油!』を書いたアプトン・シンクレアと混同される。映画好きなら、『エルマー・ガントリー』、『孔雀夫人』の原作者といえば、少しは伝わるだろうか。
また、上でに出てくる大佐とは、この小説の主人公であるリチャード・キャントウェルで、一緒にいるのは、恋人の伯爵令嬢レナータである。リチャードは50歳、レナータは19歳という超年の差恋愛だが、レナータにもモデルがいる。それは、アドリアーナ・イヴァンチックというイタリア人で、ヘミングウェイが1949年に妻メアリーと一緒にイタリア旅行した際、出会ったのだった(『河を渡って木立の中へ』もその時に執筆され、ヴェニスが主な舞台となっている。)。
ヘミングウェイはこの少女にぞっこんとなり、その後、キューバの自宅にも招いている。小説では大佐とレナータは熱愛状態にあるが、これはヘミングウェイの妄想で、実際はアドリアーナ及びイヴァンチック家のガードが固く、ものにできなかった。ヘミングウェイと彼の二度目の妻ポーリーンとの間にできた息子、グレゴリー・ヘミングウェイによる回想記『パパ』では、二人の関係が次のように描かれている。
そして、パパとアドリアーナはお喋りをつづけた。時にはイタリア語、時には英語を使ったが、お喋りの内容は空疎きわまるものだった。ただそこからははっきり、パパが恋をしているとだけは察せられた。たぶん娘のほうはパパの熱心さをうれしがっていたのだろう。いや、たぶん退屈して、ただ礼儀から応じていたのかもしれない。あるいは若い娘が自分に惚れた老人を面白がる程度に楽しんでいただけかもしれないが、とにかく彼女がパパに恋をしていないのは明らかだった。しかしごく優しくて、気もくばり、決して自分の深い感情は表に出さなかった。決して彼を傷つけたりしなかった。(加島祥造訳)
グレゴリーは父がアドリアーナを過大評価していたという風にその本の中で書いていて、事実ヘミングウェイは出版社の反対を押し切ってまで芸術家志望のアドリアーナに、『河を渡って木立の中へ』と『老人と海』のカバーを描かせている(無論、今は使われていない)。まさに「恋は盲目」を地でいっているが、スケールは違えど、男なら一度や二度ぐらい惚れた女の能力を見誤るという経験をしているのではないだろうか。
『河を渡って木立の中へ』は、訳者の大久保康雄曰く、総ページ数の3分の2が大佐とレナータとの会話に使われており、それまでのヘミングウェイの小説違い、「行動」がほとんどない。しかも、会話というよりかは、大佐による戦争体験をテーマにした独演会に近く、それを19歳のイタリア人少女がうんうんと聴き続けるのだから、ありえないにもほどがある(そもそも、なぜレナータという少女が大佐に惚れているのか小説を読んだ限りではさっぱりわからないのだが、現実をもとにした妄想だと知れば納得できる)。一応、大佐は時折「退屈じゃないか」と尋ね、その度にレナータは「退屈じゃない」と答えるのだが、グレゴリーの「ごく優しくて、気もくばり、決して自分の深い感情は表に出さなかった」というアドリアーナについての文を見てからそれらの会話に戻ると多少味わいが出てくる。対照的なのが、三度目の妻であったマーサをモデルにしたキャラクターで、こちらはかなり批判的に描かれている。
『河を渡って木立の中へ』はヘミングウェイ10年ぶりの長編小説で期待も大きかったが、発表当時から失敗作と認定された。さすがにヘミングウェイもこの小説の弱点が「自己陶酔」にあることは理解していたようだが、それでも書き上げたのは、佐伯彰一が『書いた、恋した、生きた──ヘミングウェイ伝』で指摘するように、「作者自身の、カタルシスのため」ということだろう。ちなみに、小説家のジョン・オハラだけがこの失敗作を賞賛したのだが、それはかつてヘミングウェイがオハラの『サマラでの約束』を褒めたからで、ヘミングウェイ自身、「ああいうアイリッシュ系の人間というのは、時には友情に忠実すぎて判断力を失ってしまうことがあるんだ」とグレゴリーに語っているのは面白い。
ヘミングウェイはかなりの読書家だったが(ただし、本人はそう思われるのを嫌っていた)、小説を読む際の基準は、ボクシングの如く「自分はこいつをノックアウトできるか」というものだった。そして、相手に対する嫉妬心やライバル心を、自身の小説やエッセイで爆発させることが多々あった。何しろ、世話になったシャーウッド・アンダソーンとガートルード・スタインを風刺した小説『春の奔流』を書いたり、『移動祝祭日』でフィッツジェラルドがペニスの大きさに悩んでいたことを暴露したり、トマス・ウルフはシベリアか刑務所にでも送られていれば本物の作家になれたと『アフリカの緑の丘』で書いたりするぐらいなのだから。また、ジェームズ・ジョーンズやノーメン・メイラーといった当時の若手作家にも警戒を怠らなかった。
そうしたことを踏まえると、冒頭の描写もシンクレア・ルイスを葬り去るためのものに見えてくる。ルイスをモデルにした人物に名前はなく、終始「痘痕づら」としか呼ばれないが、彼が作家であることは明かされている。そして、「あの男の才能はもう涸渇している」とか「凡庸な作家」といった辛辣な表現が容赦なく繰り出される。『河を渡って木立の中へ』は、前述したように、大佐とレナータの恋愛と会話が大半を占める小説で、そこにルイスをモデルにした人物が直接絡むことはなく、彼が登場しなければならない必然性がまったく存在しないのだ(あるとしたら、当時たまたまルイスがイタリアにいたということぐらい)。だから、なおさらルイスを潰すためのものとしか思えない。グレゴリーによれば、ヘミングウェイは、ルイスがノーベル文学賞を受賞したことについて、スウェーデン・アカデミーが「あんな恐ろしい顔付の作家である以上、よほど苦しんだにちがいない、だから作品にも高貴な高揚性があるはずだと思ったからだろうよ」と揶揄していたという。
ヘミングウェイがルイスを侮辱したことについて、ランダムハウスの創設者ベネット・サーフは、自伝『アト・ランダム』の中で次のように述べている。
一九四九年のクリスマスのすぐ前、つまりレッド・ルイス(筆者注:シンクレア・ルイスのあだ名)が彼の最後の旅行に出発してからまだあまりたっていないときに、フィリスと私は、ニューヨークに近いコネティカット州スタンフォードにあるハーバート・メイズの家でもよおされたパーティーに出かけた。”ハーブ”はそのころグッド・ハウスキーピング誌の編集長をしていたが、同時にまたコスモポリタン誌のためにも材料集めをしていた。そこで彼はヘミングウェイの新しい小説『河を渡って木立の中へ』を、コスモポリタン誌に連載することを計画し、彼がそれまでに受けとった原稿を私に見せてくれた。この小説の初めのほうに、ヴェネチアのハリーズ・バーでの一場面があって、そこに一人の人物が登場してくるのだが、それはまごう方なくレッド・ルイスで、主として彼の顔の状態を中心にして、読むにたえないようなきたない言葉で人物描写がしてあった。レッドは久しい以前から、一種の皮膚病におかされ、それがとくに彼の容貌をみにくいものにしていた。彼はそのことをひじょうに気にしていたので、万一にも彼がその部分を読んだならば、手がつけられないほど怒り狂ったにちがいない。私は彼がそれを読んだかどうか知らないが──ルイスの伝記を書いたマーク・ショーラーによれば、幸いにも彼はそれを読まなかったらしい──しかし、私でさえ、それを読んだときには激怒したのを憶えている。(木下秀夫訳)
シンクレア・ルイスはアル中で、それが原因で『河を渡って木立の中へ』が出版された翌年、ローマで客死した。1940年代からは作品の質や売上にムラがあり、『夫婦物語』や『血の宣言』をのぞけば、概して低調な作家生活を送っていて、死後すぐに出版された『World So Wide』も酷評を受けた。サーフは「あまりにも長く書きつづけすぎた作家の好適な例」とまで言っている。つまり、ヘミングウェイは引退寸前のボクサーをボコボコにしたようなもので、そのやり方は威張れるようなものではないだろう。
参考文献
『ヘミングウェイ全集 第3巻』(『アフリカの緑の丘』を収録)
『ヘミングウェイ全種 第7巻』(『河を渡って木立の中へ』を収録)
グレゴリー・ヘミングウェイ『パパ』
ポール・ジョンソン『インテレクチュアルズ』
佐伯彰一『書いた、恋した、生きた──ヘミングウェイ伝』
A・E・ホッチナー『パパ・ヘミングウェイ』
ベネット・サーフ『アト・ランダム』

グレゴリーは、シンクレア・ルイスついて、「この作家の顔は赤くてシミだらけで、死人の顔そのままであり、ぼくら子供はすっかり怖がった。ぼくは紹介された時に恐怖の気持を抑えられず、思わず表情に見せた。それを見たせいではないだろうが、彼はあまり長く滞在せずに立ち去った」と『パパ』の中で書いている。
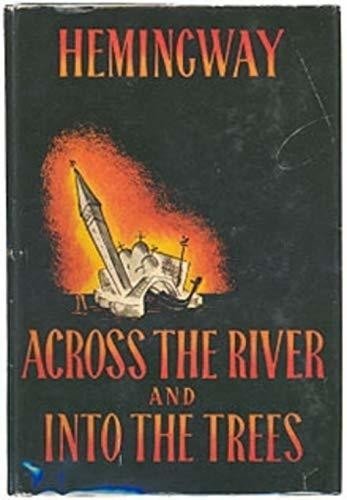
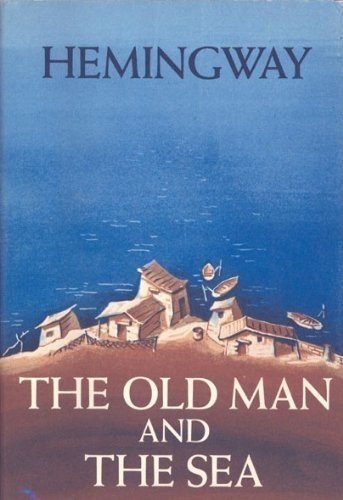
アドリアーナ・イヴァンチックが描いた『河を渡って木立の中へ』と『老人と海』のカバー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
