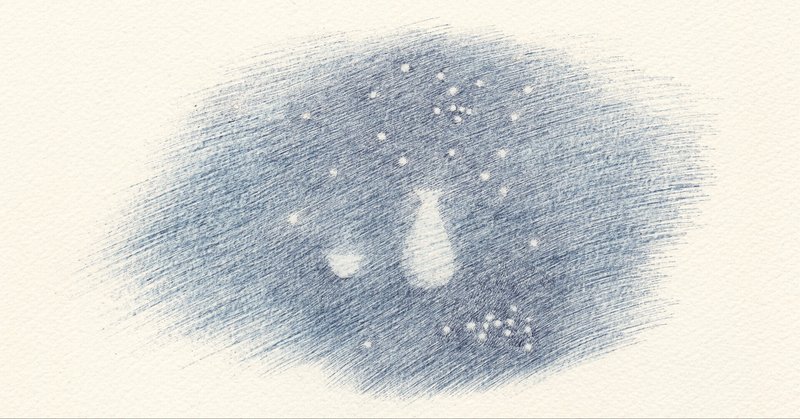
vol.43 立冬「昭和歌謡」11/7~21
朝の開店準備は、まずは入口のドアを開け放ち、箒で店内の掃き掃除を始める。ヒヤッとするような冷たい空気は、身が引き締まるようで気持ちいいなどと言っていられるのも今のうち。掃除をする間、ドアを開けたままにするほんの数十分ですら躊躇するような寒さは、もういつやって来てもおかしくはない。今年は寒さが厳しくなるのだろうか、それとも暖冬か。雪はどうだろうと冬の天気予報をこれほど気にするようになったのは、三春で暮らすようになってからかもしれない。
祖母が健在だった頃は、雨が降ろうが寒さが厳しい冬の日だろうが、朝はまず窓を開けて空気を入れ替えるようにしながら箒でリビングの掃き掃除をしていた。
「おばあちゃん、寒いのに何で窓を開けるの?」などと子どもの頃は文句をよく言っていたっけ。祖母にはあれこれと躾けられたわけではないけれど、あの習慣がいつの間にか身についている。寒いのは重々承知でそうしているのは、真新しい空気を店内にスーッと送り込むことで、なんとなく清々しい一日を始められるような気がしているからだ。
ドアを開けていると、表の通りからは有線の音楽が聞こえてくる。それはインストゥルメンタルやジャズ、クラシックなどではなく、主に演歌や昭和歌謡。口ずさめる曲がいくつかある。いや、いくつもある。懐かしいメロディーを聞いていると、知らぬ間に曲にのって箒を動かすテンポが合っていく。 森進一の「冬のリビエラ」、和田アキ子の「あの鐘を鳴らすのはあなた」他にも山口百恵や岩崎宏美、ザ・ピーナツに河島英五…etc 特にファンだったわけでもないというのに、小学生の頃に聞いていた曲は、今でも歌詞まで覚えているのだから自分でもびっくりしてしまう。苦手だなと思っていた演歌ですら、鼻歌交じりで口ずさんでいるのだ。
演歌が苦手だと思ってしまったのは、父の晩酌の時間が原因だ。私がまだ子どものときは、たいてい夕飯は兄と祖母の三人で食卓を囲み、私たちが食べ終わる頃に仕事上がりの父の晩酌が始まるという具合だった。私がグズグズと食べ続けていると、お酒で機嫌が良くなった父が、歌を唄い始めることがあった。それは民謡の日もあれば演歌の日もあって、決して上手くはないその歌を、大きな声で歌っている父のことが、子どもながらに恥ずかしくてちょっと嫌だった。母は笑ってやり過ごしていたけれど、私は笑えるような心境にはどうにもなれず、早々にリビングへ退散するか、眉間にしわを寄せながら仕方なく父の歌を聞いていた。今でも特に耳に残っているのは、いくつかの民謡と千昌夫の「星影のワルツ」だ。どれも歌詞の意味などわからないというのに、何度も聞かされたそれらの歌は好き嫌いに関わらず、子どもの耳にスルスルと染み込んでいたようだ。
ある朝、いつものように掃除をしていると、「星影のワルツ」が表の通りから不意打ちのように聞こえてきた。何年も耳にすることもなかったその歌によって、香りを嗅いで記憶の蓋が開くように、幼いころの食卓の景色が思い起こされた。お酒が飲めない母が父だけに作る酒の肴や、むせるような熱燗の匂い、テレビを見て笑う家族の声。
空を見上げれば、星が瞬いているようで朝からどこか切ない気分に包まれる。曲ひとつでこんなにも鮮明に細々したことを思い出せるというのに、肝心の父の記憶は今、おぼろげなものとなってしまった。どうにもできない寂しさを抱えながらせっせと箒を動かし、曲に合わせてフルコーラスを口ずさむ。すると、沈んだ気持ちは埃を掃き出すように次第に消えてなだらかになっていく。いつからだろう。寒くなると熱燗を嗜むようになった頃からだろうか。演歌への苦手意識も今では不思議となくなっている。
