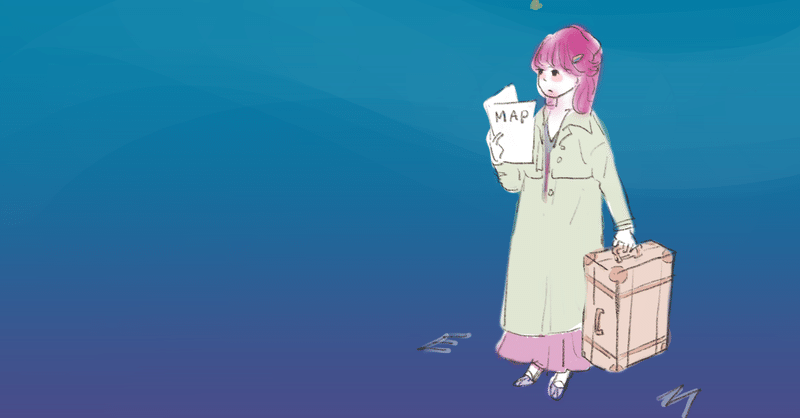
夜明け頃には ep.1
土屋桜子の廊下を歩く足取りは緩やかだった。初めてクラスの担任を任されることになり、長年の夢が叶った喜びで、自然と胸は弾んだ。
それでも、緊張も多分にあった。
(私のような若輩者に、担任が務まるだろうか。子どもたちと上手くやっていけるだろうか)
桜子が着任した学校は、都内の公立中学校。ビルが立ち並び、都会のど真ん中で、自然が少ない。校庭も狭い方で、横に幅を取れないから上に積み上げました、と言いたげな校舎は、五階建て。さらに屋上つきで、地下にも一階分のスペースを有する。
生徒は多くない。少子化の影響で、一学年、七十人に満たない。三十人程度のクラスを二つしか作れず、つまり担任は六人しかいない。
桜子は、その栄えある一人に抜擢されたのである。大学を卒業して間もないにもかかわらず。
「土屋先生は、あのN大学の卒業生ですから、非常に期待しております」
桜子は、教頭先生が自分の自己紹介の後で言った言葉を思い出す。プレッシャーにしかならなかった。N大学は全国でも最難関と言われる所だが、そこに行ったからって、誰もが優秀とは限らない。机に向かった勉強ができても、先生という職業は知識だけで何とかなるものではない。
期待される分だけ、不安を覚えた。
しかし、先程も述べたように、教師は長年の夢だった。教師になれた喜びはひとしおで、これから始まる学校生活は楽しみでもあった。
教室の前まで来た。中から生徒たちの話し声が聞こえる。元気な子たちだろう。笑顔で騒いでいる姿を思い浮かべ、目尻を下げた。
深呼吸をし、よし、と呟いてから、教室のドアを開けた。昔から変わらぬ、横に開閉されるドア。
上から黒板消しが落ちてくる、ということはなかった。ドラマや小説で見たことのある光景が浮かんだが、現実にはお目にかかれなかった。今どき、それは古いのだろうか、と桜子は思った。
教室のざわめきは収まっていた。自分に視線が集中しているのが分かる。黒い名簿を抱えながら歩いて、教壇の前で彼らの方を向いた。何人かの生徒と目が合う。笑顔で見つめ返し、そのまま教室一帯を見回す。
生徒の数が少ないこともあり、自分の学生時代に比べると、スペースに余裕があるように感じた。窓から降り注ぐ日差しも心地よい。
「起立」
声が上擦らないように、号令をかけた。
「気を付け」
真面目にすぐ応じる人も、だるそうにやる人もいて、その速度はばらつきがあったが、それが微笑ましかった。
「礼」
「おはようございます」
さすがに三十人ともなれば、その挨拶は感動的だった。「おはようございます」と少し遅らして言いながら、桜子はその感動に浸った。
「着席」
がたがたとイスを動かしながら、それぞれが席に着く。学生時代、席に着く瞬間に、イスを引いて、しりもちをつかせる悪戯をする男子がいた。座る生徒たちを眺めて、それを思い出した。
「はじめまして」
緊張はあるが、生徒たちを前にして気分は高揚した。言葉も、すらすらと出てくる。
「このクラスの担任を務めることになりました、土屋桜子です」
と言って、黒板の方を向いた。白いチョークを一つ手に取り、縦書きで「土屋桜子」と書く。書き終えて、前を向いた。
「みなさん、三年生ということで、受験生ですが、受験勉強のサポートをしていきたいと思うので、気軽に、何でも相談に来てください」
教壇の上に置いた名簿を手に取る。「それでは、出席を取りますね」と言って、名簿を開いた。三十人の名前が上から順に並んでいる。
そこで桜子は、しまった、と心の中で叫んだ。ふりがなを確認していなかった。読み間違えたらどうしよう、と不安になる。
「浅井将太君」
「はい」
「大越光希君」
「はい」
「柿沼奏多君」
「はい」
思ったより、大丈夫そうだ。桜子は胸をなでおろす。
「片桐陸翔君」
「はい」
その後も順調に進み、男子も終盤に差し掛かった。
「長潟真一君」
「はーい」
間延びした返事が返ってきた。面倒くさそうに、イスに深く腰掛けている。
「ちゃんと返事しなさいよ」
どこからか女子の咎める声が聞こえた。その方と思われる方に目をやると、黒髪のショートカットの女の子が目に入った。かわいらしい顔付きで、体型は華奢で小柄だが、その発言と表情から真面目さが窺える。
男子が終わって、女子に入る。ここまで、順調に来ている。
「井上月子さん」
「はい」
「金山節子さん」
「はい」
次の名前を呼ぶ前に、さっきの女の子が目に入った。次は、彼女か。言い訳をするわけではないけど、彼女自身に集中を何割か持って行かれてしまったため、読み間違えてしまった。
「川島セイメイさん」
教室に笑い声が起こった。すぐに、間違えたのだと気付く。名簿に目を落とし、名前をよく見直す。「川島世明」と記されていた。
間違えたのは分かったが、じゃあ何て読むのか、思いつかなかった。
すると、その彼女は毅然とした態度で、「ヨアケです」と言った。そうか、世明でヨアケと読むのか。何となく、いい響きだと感じた。
「ごめんなさい、世明さんね。もう覚えました」
それが、世明と桜子の初めて会った日のことだった。
桜子がいなくなった後の教室は、再びざわめきを取り戻した。あちこちに数人ずつの塊ができていた。
「何か、楽そうだね。今度の担任」
塊の一つにいる竹花梨沙子が言った。顔には化粧が施されていて、髪も茶色く染まっている。いかにも、最近の若者を体現した感じだ。
「だね。若いし」
近くで、足を組んで座っている沼津亮子が同調した。自分で短くしているスカートから白い足が露わになっているが、気にする様子はない。
「しかも、国語の先生らしいよ。睡眠時間で決まりだね」
井上月子が笑顔とともにそう言った。本来の形状が分からなくなるぐらい、目にアイシャドーを塗っている。
「マジ? よかったー。国語、眠すぎるんだよね。去年、さんざん怒られたし」
「ああ、やばかったよね、ムラタ。いかつい顔して、耳元で怒鳴ってさ。耳がいかれるっつの」
「あの授業、どう頑張っても寝るんだけど。読んでるだけとか、マジ無理」
「ね。……それよりさ、昨日のドラマ見た?」
三人の話は笑い声を挟みながら、様々な方向に進行した。周りの人に聞こえるぐらいの声で、抑える気がさらさらない。教室の騒がしさの要因の大部分が、彼女らによって、と言っても過言ではない。
全くうるさいなあ。
彼女らのうるささに辟易しているのは、川島世明。先程、桜子に名前を読み間違えられた少女だ。参考書とノートを机の上に出して、受験勉強にいそしんでいる。彼女は学年で三本指に入る学力の持ち主だ。
それにしても、と世明は思う。あの、私をセイメイさんとか言った担任は――まあ、私が名前を間違えられるのは初めてじゃないからいいけど、みんな揃って「セイメイ」って、安倍晴明じゃないんだから――大丈夫かしら。早速、舐められてるけど。亮子の言うとおり、あんなに若いのに担任って、そんなに優秀なのかな。
土屋――桜子か。世明は前方の黒板に残っている名前を見て、確認する。大きさも丁度よくて、字はきれいだ。
その日は授業がなく、午前中で下校となった。帰りの挨拶をするとき、梨沙子たちがぺちゃくちゃと喋っていたけど、早くも学級崩壊の兆しだわ、と世明は嘆いた。
私が何とかしなくちゃ。
翌日は一年向けのオリエンテーションが行われた。簡単な委員会紹介と、部活紹介。進行役は生徒会で、その中には世明の姿もあった。世明は、生徒会副会長を務めている。
委員会は昨年度までの委員長が話したが、今年度で代わるから、そんなに熱は入っていない。そもそも、委員会に全力を注いでいる人は少数だ。
一年生は時折、笑うことはあっても、基本的に大人しく耳を傾けていた。最初は健気なものだ。この前まで小学生だったから、中学校の雰囲気に圧倒されているのだろう。でも、かわいく見えるのも今のうち。そのうち、慣れてくると、かわいげのないやつが増えてくる。
全ての委員会と部活が紹介し終えると、生徒会が一年の前で一列に並んだ。三年生四人、二年生二人の計六人。もうすぐ、役割が終わる。世明は、胸に寂しさを覚えつつも、笑顔で一礼をして、オリエンテーションを終えた。
不思議な造りだなあ、校内を歩きながら、桜子は思う。五階建てにしたのはいいけど、一階ごとの面積はそんなに広くないから、結局、普通の公立中学校と同じぐらいしかキャパはない。
第一、体育館が三階をほぼ占領しているのは奇妙だ。エレベーターを取り付けてないから、下級生は毎日、体育館の横を通る。一年生が五階で、二年生が四階だ。子供たちは元気があるからいいけど、先生方は一苦労だ。まあ、運動になると言えばなるけど。
地下には技術室と理科室がある。どちらも、日当たりがないけど、何となくイメージと合っているから(決して、技術や理科が暗いというわけではなく)、この配置は適格だったと勝手に思う。
三年生は二階に教室がある。先輩だから、一番楽できるというわけだ。職員室は一階にある。
プールは見晴らしのいい屋上にある。厳重なフェンスで囲まれているため、危険はないが、学校をフルに使っているなあ、という窮屈感を覚えないでもない。
桜子は、自分の教室の戸締まりをしてから、隣の図書室を覗いてみた。学生時代、勉強に図書館を活用してきた桜子にとって、図書館は馴染み深い場所だった。もちろん、この学校の図書館とは初対面もいい所だが、その雰囲気を好んでいた。
中には、一人しかいなかった。机に参考書を並べて、ノートにかじりつくようにして、シャープペンシルを持っている手を動かしている少女がいた。世明だった。桜子は、その姿がかつての自分と重なり、一瞬で好印象を抱いた。
「川島さん」
邪魔しちゃ悪いと思ったが、声をかけずにいられなかった。
すると、世明は笑顔で迎えてくれた。「あ、先生。今、一段落ついた所なんですよ。話し相手になってくれませんか」窓から注ぐ日差しと重なって、余計にその笑顔が眩しく見えた。出会ってから初めて見る笑顔だったが、陽だまりみたいな明るさだった。
桜子は向かいの席に腰掛けて、「受験勉強?」と聞いた。
「はい」
「偉いですね、早めのスタートで」
「そんなことないですよ」世明は表情を変えずにそう言った。「どうせ、家でやってるんですよ、みんな。私は家が狭いし、汚いからここでやってるけど、だからってみんなよりやってるわけじゃないんです」謙遜ではなく、本気でそう思っているようだった。
飽くなき向上心の持ち主なのだなあ、と桜子は感心する。中学生なのに、立派なものだ。
「私も学生の頃は、図書館で勉強してましたよ」
「そうなんですか」
世明は興味なさそうに呟く。
「他にこれといった趣味もなくてね、暇があると、じゃあ勉強しようってなって、本当に勉強ばっかりしてました」
「先生、大学はどちらでした?」
「N大学だけど」
世明は、あっと一言漏らして、「私、そこに行きたいと思ってるんです」と続けた。
「本当? 中学生で大学のこと考えてるの」
実を言うと、桜子も同じタイミングで考えていた。明確な目標があると、やる気も違うだろうと思っていた。
「川島さんなら行けますよ。こんなに頑張ってるんだもの」
と桜子が言っても、世明は表情を明るくせず、「まあ、まだ先の話なんで、何とも言えないです」と言った。
「そうだ」
桜子は昨日の出来事を思い出す。「ごめんね、名前、間違えて」
「いいですよ、別に」
世明は、何だそんなことか、という顔で返す。「初めてじゃないですし」
「世明って、珍しい名前ですよね。……あ、言い訳じゃないけど」
桜子は慌てて取り繕った。
「いえ、先生の言うとおりですよ。今まで、同じ名前の人に会ったことはおろか、テレビで見たこともありません」
先生みたいな普通の名前がよかったです、と最後に付け加えた。あんまり褒められてないなあ、と感じずつも、桜子は笑顔で返した。
「世を明るくして欲しい、っていう親の願いが込められているんです」
聞かぬ先から、世明が桜子に名前の由来を教えた。桜子は感心した。
「素晴らしい名前ですね。それに――」
桜子は、今日のオリエンテーションの光景を思い出した。「現実に実行してるじゃない。生徒会なんでしょう」
「まあ、副会長でしたけど。それに、世の中よりもずっと小さい学校ですし」
世明は相変わらず、褒めても照れなかった。満足しにくい性格らしい。褒められるのが嫌いなのかな、とも思う。
「でも、すごいことですよ」
と言ってから、桜子は時計を見た。「あ、そろそろ帰らないと。最終下校の時刻になりますよ」
「あ、本当ですね」
世明は立ち上がると勉強道具を鞄に入れて、「さようなら」とスタスタと歩き出した。が、ドアの前で立ち止まって、桜子の方を振り向いた。
「先生は、どうして先生になられたんですか?」
世明は、真面目な表情でそう尋ねた。桜子は、ふふ、と小さく笑って、「それは明日にでも、ゆっくり教えてあげますよ。今日は帰りなさい」と答えた。
「そうですか」世明は納得し、改めて「さようなら」と言った。
「さようなら」
桜子はそれを見送った。微笑を表情に残していた。
ああ、やっぱり、学校とはいい場所だなあ。心が満たされるのを感じながら、桜子も図書室を後にした。
はあ。世明は、歩きながらため息をついた。結局、一番聞きたいことを聞けなかったなあ。忠告もできなかったし。まあ、明日でいいか。
人通りの多い街中を抜けていき、世明は家路をひた歩く。
翌日の二時間目、桜子の初授業は、自分のクラスだった。忘れ物がないか何度も確認して、少し早めに職員室を出た。昔から、時間をきっちりと守らないと気が済まない性分だった。
チャイムが鳴るまで廊下で待機し、通り過ぎていく生徒たちを眺めていた。水族館みたいで、見ていて飽きなかった。通りがかる度に、おはようございます、とちゃんと挨拶していく人もいれば、こっちが言ってから、っす、とだけ言う男子がいたりして、様々だった。
チャイムと同時に教室に入ると、生徒たちが、波が引いていくように席についた。
「号令」
と言うと、日直の大越光希が「起立」と声を出す。合わせて、生徒たちが立ち上がり、礼をし、また座る。
「今日は」教壇の横に出て、ゆっくり歩きながら今日の予定を告げる。「みなさんのことをよく知りたいので、順番に自己紹介してもらいます」
あちこちから、色んな感情の声が上がる。そのほとんどが歓声。男子の中では、誰か時間稼げよ、とでも言っているのであろう。
「出席番号順に、名前と部活、あとは出身校でも、血液型でも、誕生日でも、何でもいいから、教えてください」
左の方に顔を向け、「では、浅井君から」と指名する。浅井は大儀そうに立ち上がって、自己紹介を始める。
「浅井将太です。部活は……」
自己紹介は、たまに起こる笑いが教室の雰囲気を作って、進んでいく。和やかだ、と桜子は感じた。時折、質問や感想を挟みつつも、なるべく彼らの自主性に任せた。彼らの中の面白さは、彼らにしか演出できないものがある。
ところが、長潟の順番になって、その雰囲気が少し落ち着いた。見えないけど、それは感じられた。
「長潟真一です」
それだけをぶっきらぼうに言って、すぐに座ってしまった。笑いが起こるかと思ったが、教室はしんとしている。
「あれ、それだけ?」
桜子が尋ねると、「何でもいいって、言ったじゃないっすか」と無愛想な返事。
「先生、あいつ放っといていいです。いつも、あんなんですから」
世明が呆れたように言った。そういえば、初日も長潟を叱っていた。
「は、何様? お前なんかに気安く、あいつ、とか言われたくねえから」
長潟が言い返した。ポケットに両手を入れて、首を後ろに反らしながら。
「私も、お前なんか、って言われたくないけど。何で、そんなにツンツンしてんの? かっこいいと思ってんの?」
世明も負けていない。
「うるせえ、ごみ。耳障りかつ目障りだから、消えてくれる?」
「長潟君」
ここで桜子が割って入った。腕組みをして、長潟を真っ直ぐに見据えている。
「言葉遣いに気を付けましょう」
長潟は何も言わずに、不機嫌そうに下を向いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
