
白・黒・黄色 : 肌色と外見。明治の文豪たちは...... artとnature。アジア人の未来
少し前にアメリカの友人に頼まれて、彼が制作した音楽家のインタビュー・ページを、Wikipediaの外部リンクに追加しました。わたしがWikipediaの編集に関わっているのを知って頼んできたのです。
その友人はクラシック音楽専門のFM局でブロードキャスターをしていた人で、自分の番組で世界中の様々な音楽家にインタビューをしてきました。その音源をいま、時間をかけて文字化し、自分のサイトで公開しています。
今回頼まれたのは、アメリカのカウンター・テナーの歌手、デレク・リー・レイギン(1958年〜)でした。該当ページに行ってみると、レイギン氏はアフリカ系だとわかりました。カウンター・テナーでアフリカ系、ということで、アメリカのクラシック界にそういう人は多くいるのか、友人に質問してみました。彼の答えは、クラシック音楽界、中でもオペラの世界にはアフリカ系アメリカ人は、それなりの数いるということでした。が、作曲家や指揮者となると数は少ないそうです(女性も同様)。
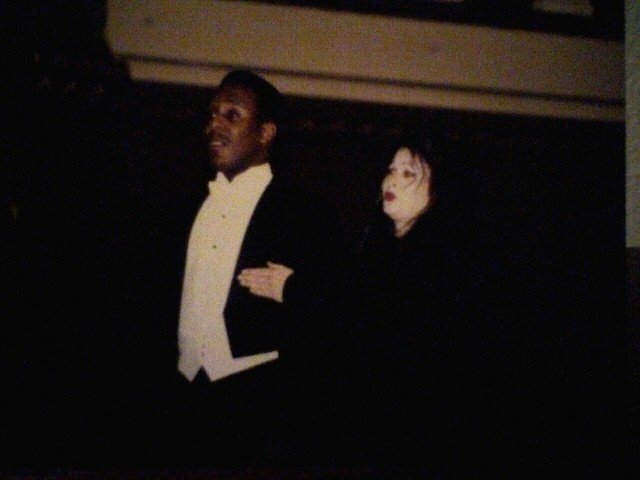
その友人はデレク・リー・レイギンを含めた、"men and women of color*"の音楽家のリストを、膨大な全体リストから抽出して別途つくっていました。それは一般に彼らが紹介される機会が少ないからのようで、彼は特別リストをつくるだけでなく、そのリストの存在をいくつかの(ブラックコミュニティやそれ以外の)団体に知らせてもいました。昔の音楽家も含まれているので、アフリカ系の人にとっても、もう過去の人となり忘れられている可能性があるのかもしれません。
*このcolorという表現については、「もしこの用語が不適切であるなら、指摘してほしい」という但し書きがありました。
そんな話のつづきから、アメリカのマイノリティの話になりました。スティーヴ・ライヒという作曲家がいますが、彼はユダヤ系です。アメリカにおいて、ユダヤ人はマイノリティなのかどうなのか、聞いてみました。友人によると、クラシック音楽界についていうと、彼らは非常にたくさんいる、したがってマイノリティではない。しかし一般社会ではそうだ、と。彼らは何千年もの間、世界の国々や集団から迫害されてきた、とのこと。いまのアメリカでもユダヤ人に居て欲しくないと思っている人や集団はあって、それを止める方法はなかなかないそう。
*スティーヴ・ライヒはユダヤ人とエルサレムをめぐるオペラ(ミュージック・ヴィデオ・シアター『THE CAVE』)を作っています。この作品を中心とするライヒのインタビューの日本語訳がこちらにあります。
そこでさらに、日頃から感じていたユダヤ人についての疑問を確認してみました。ユダヤ人かどうかというのは、(わたしの理解では)信じている宗教の話であって、血筋や遺伝子の話ではないでしょうと。年配の方々がよく言うような身体的な特徴(鼻が大きいとか)とは無縁であるはずと。
彼の回答は、そうだ、純粋に宗教の話であると。ただそれは家族から家族へと受け継がれていくものでもある。人口として数が少なく、長い間迫害されてきたため、ユダヤ人は家系(their line)への強いこだわりがあり、それをなんとか保持しようとしている。だから現在の家族だけでなく、その子どもや孫にもそれを伝えようとする、ユダヤ人としての生き方、あり方を教えるのだ、ということでした。
なるほど。少し理解が進みました。
差別や迫害というものが、ある集団の結束を強め、維持していこうという力になる、そのような方向に働くことがあるということでしょうか。そこには自然発生的なユダヤ人という「人種」があるわけではない。
このマイノリティに付きものである「人種」という視点、これを「」付きでわたしは書きます。白人、黒人、黄色人….この分類を、「人種」という言葉で一般社会はつかってきました。しかし現在の科学では、「人種」というものは存在しない、人類はすべてホモ・サピエンス・サピエンス(ヒト)で一つの種類に集約される、すべての人間は同種である、と言われています。
*ウィキペディア日本語版「人種」の項目では、注釈として「なお、今日ではヒトの分類は科学的な妥当性は認められず、社会の作り出した文化的概念とみなされている。」とありました。これを認めない人もあり得ますが。
科学でそう証明されていても、人間はまだ(21世紀の人間でさえ)、それを真に(少なくとも心情的には)理解できていないように見えます。
人はささいな違いというものを非常に意識し、あるいは重視し、ときにその違いのために対象を恐れもします。違いがあると居心地が悪いので、それを排除しようとするという傾向も見られます。それは動物一般がもっている習性、あるいは本能なのかもしれませんが。自分の身を守るという警戒心から発生するもの。
日本在住の作家、バイエ・マクニールさんは、日本に住むアフリカ系の人々の記事を東洋経済オンラインで掲載しています。マクニールさんによると、電車でアフリカ系の人が席にすわっていると、日本人の多くはその隣りに座ろうとしない、と書いていました。最近では日本でもアフリカ系の人はそれほど珍しくないですし、音楽や映画、ファッションの世界では間接的であったとしても、日常的に触れる機会があります。それでも、日本人の中に、近寄ることへの抵抗感がまだあるということでしょうか。
これはもしかしたら差別以前のものかもしれませんが、、、いや、やはり差別なのかもしれません。ただアフリカ系の人々と接したことがない、という経験のなさを単純に「悪いこと」と責めるのも難しい気がします。
この肌の色の違いというのは、人間の本質にはまったく関わらないものなのですが、外見、ビジュアル的な印象が、人に及ぼす影響というのはとても大きいことがわかります。
最近『「肌色」の憂鬱:近代日本の人種体験』(眞嶋亜有著、中公叢書、2014年)という本を買いました。
この本は、海外(欧米)に留学や仕事で住んだことのある日本人が、そこで感じた「肌の色など自分の容姿」によって生じた自己嫌悪感について、あるいは実際に現地の人から受けた差別行為について、多くの記録(小説やエッセイ、文壇史、解説書など)から事例をあげて記しています。
たとえば夏目漱石(1867〜1916年)。漱石がイギリスに留学していたことはよく知られていますが、そこで自らの日本人としての容姿を恥じ、落ち込んでいたことを、わたしは知りませんでした。1902年に帰国し、東京帝国大学の英文科の講師になった際は、当時の知識人にとって「最高の出世」だったため、意気揚々としていたようですが。いかにも外国帰りの「ハイカラーの洋服にカイゼル髭」「よく磨いた先の尖ったかかとの高い靴」で、「リズムをとるような歩き方」をして、学生たちからキザなスノッブ、などと言われていたみたいです( 金子健二『人間漱石』)。それはイギリス生活の中で、「西洋人」と自分の外見の差を痛いほど感じて、劣等感に苛まされていたことの裏返しのように見えます。
『「肌色」の憂鬱』では、ロンドン時代の漱石の心理として、以下のような文章を例にあげています。
何となく自分が肩身の狭い心持ちがする。向ふから人間並外れた低い奴が来た。占めたと思つてすれ違つてみると自分より二寸許り高い。此度は向ふから妙な顔色をした一寸法師が来たなと思ふと、是即ち乃公自身の影が姿見に写つたのである。(夏目漱石『倫敦消息』)
ユーモアらしきものも感じられる文章ではあるけれど、自分の外観に対する劣等感や、アジア人一般についての(今の時代の感覚からすれば)差別的とも見える記述には、あの漱石がと、驚くところもあります。
さらに、ロンドンで英文学を研究している自分は、所詮「ポツトデの田舎者のアンポンタン」に過ぎず、「山家猿」のような「チンチクリン」の小柄さで、「土気色」の顔色をしているために、西洋人から馬鹿にされるのは当然だと感じる。
ヨーロッパでこのように感じて落ち込んでいた日本の知識人は、漱石だけでなく、他にもたくさんいました。カトリックの奨学生としてフランスに渡った遠藤周作(1923〜1996年)も、人種的な差異を強烈に体験した一人で、帰国後、しつこいほどにそのことを題材にして小説に書いていたようです。
遠藤周作はカトリック教徒だったため、フランスでは洗礼名のポールと呼ばれていたとあり、当時の日本人としては179cmと背も高く、フランス語もできたのでフランス人との交流も多く、結婚を約束したフランス人女性もいたようでした。それでも自分、もしくは日本人の肌の色に対する劣等意識は強く、フランスから船で帰国するときの心情を以下のように記しています。
欧州からの帰路、紅海を渡り、アラビア砂漠の一角にたち、この欧州と東洋を切る一点の上で、ぼくは非常なくるしさを覚えた。もはや白人の世界はここで終わりとなる。白き色のもつ明晰さ、非情さから黄色人の混とんとした色、濁った色、境界なき色の世界に帰らねばならぬ。だが、自分の肌色は黄色であって決して白色ではない。ならば、この黄色を白き世界と混同せず対立させることからすべてははじまるとぼくは考えた。(遠藤周作「基督教と日本文学」)
遠藤周作は生きていれば今年100歳、昔の人とはいえ、それほど遠い時代の人ではない、のに、「この黄色を白き世界と混同せず対立させることからすべてははじまる」とは! 『白い人』『黄色い人』など、人種的差異をテーマにした小説をいくつも書いたのは、このときの心情によるものなのでしょう。
遠藤周作はリヨンに滞在していたときに、市電やレストランで、フランス人が自分の近くにすわろうとしない、人からジロジロ見られる、子どもに「支那人」と言われる、「黄色人は黒人のように醜い」「とにかく野蛮だ」などと囁かれるといった嫌な経験をしています。この時代のフランス、中でもリヨンのような中央から少し離れた街ではこのような差別があったようです。
夏目漱石や遠藤周作が、当時のヨーロッパで差別的な扱いを受けたことは、容易に想像がつきます。しかし、こういった知性の高い人々が、その差別をある意味、当然として受け入れていたことは少し不思議にも思えます。さらに自ら進んで、劣等意識を強調するような発言や記述をしていることにも。
肌の色が黄色いことが、背が低く、体格が小柄なことが、これほどまでに当時の日本人の精神状態に影響を及ぼしたことに、やはり驚きがあります。自ら劣等意識を引き寄せ過ぎてはいないか、とも。
そう時代の違わない、イギリス人のチャーリー・チャップリンやフランス人のモーリス・ラヴェルも、160cmそこそこの小男でした。肌色は白かったかもしれませんが。彼らにも劣等意識はあったのか。
人間が外観によって大きな影響を受けるのは、動物としての警戒心と、社会的な差別構造の反映と、両方の理由が混ざり合っているとも考えられます。
インターネットの発達や、海外旅行、人の移動・移住、ワールドスポーツ、海外からのコンサート、国際コンペティション、語学教育などでグローバル化が進んだ現在、直接・間接的に外国人との接触は増えました。それにともない、漱石時代の「人種」的劣等感は、どう軽減していったのか。
特に若い世代の間では、西洋劣等感は限りなく小さなものになっている、と見えないこともありません。それでも足が長い、顔が小さい、色が白いなどの特徴は「日本人離れ」している、と言われ、ほめ言葉の一種ととれるし、美白、目が大きく鼻が高く見える化粧、美容整形、金髪ややわらかな茶色の髪色などを「単なるファッション志向」であり好みの問題でしかない、と捉えてもいいものか。そこは単純ではないかもしれません。
先日、YouTubeで韓国出身のチョ・ソンジンさん(1994年〜)のリサイタルを見ました。どこだったか、ヨーロッパの音楽祭への参加出演(2019年)だったと思います。彼は2015年にショパン・コンクールで優勝し、その後ヨーロッパを拠点に、ドイツグラモフォンのアーティストとして活動しています。いわば韓国の、あるいはアジアの、ではなく、普通にグローバルなクラシック音楽界の一演奏家として、そのステージに立っていました。
そしてその演奏も、そのように(国籍や民族と関係なく)、一ピアニストとして普遍的なものに聞こえました。モーツァルト、シューベルト、ベルク、リストなど(古典、ロマン派、近・現代のドイツ・オーストリア系の作品)を弾いたのですが、集中力の高い、心動かされる演奏でした。そして舞台での振る舞いも、あるいは服装も、特別なことは何もしていませんが、演奏と同じようにその場に馴染んでいました。(西洋人化したアジア人という風でもなく、かといって韓国ローカルという見え方でもなく、一人の音楽家が、そこにいたという感じ)
そのチョ・ソンジンさんの演奏を見て、聴いていて感じたのは、ここに音楽を通して、無理なく異種(異文化)の世界を越境している人がいる、ということでした。生まれは朝鮮半島、今は音楽人(西洋音楽人)であるといった。ある種の音楽移民です。そこには夏目漱石や遠藤周作が感じた、「超えられない一線」のようなものは見つけられませんでした。
肌の色、背の高さ、体格といった外見が無化された世界が、すでに存在しているのではないか? 音楽とかスポーツとか、アート(natureに対しての人工)の領域では、nature(生まれもった体格や外見)は、人間社会全体から見たら、ごく小さな要素になっているのでは?
昔は(時代を遡れば遡るほど)、人間世界の大きな部分はnatureによって支配されていました。産業革命などテクノロジーの発明、進化によって、人間はnatureをかなりの部分、コントロールできるようになってきました。natureが支配していた時代には、「人種」というものがあると信じられ、黒人、白人などを分類する学説が17、18世紀に生まれ、カントのような18世紀の哲学者も、著書の中でこの区分を明確に指摘しています。
アフリカの黒人は、本性上、子供っぽさを超えるいかなる感情も持っていない。(中略)それほどこの二つの人種(註:白人と黒人)の間の差異は本質的で、心の能力に関しても肌色の差異と同じほど大きいように思われる。
しかし現在のように、ここまでアート(人工)がnatureの領域に侵入、支配するようになった時代には、科学的になんの根拠もない「人種の分類」に大きな意味を持たせることは、根本的に難しいように思います。人々の感覚も大勢はそれに従っていくはずです。
人が、外見につよく支配されてしまうのは、案外、「人間のnature」に対する感受性の片寄りや、社会的な先入観が作用しているのかもしれません。
もしかしたら「ユダヤ人は鼻が大きい」説がまことしやかに語られていたのも、人を分類するには外見的要素が重要(違う種は外見も違うはず)という、nature視点偏重の、過去の思想からきているのかもしれません。
Title photo: Cross Duck (CC BY-NC-ND 2.0)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
