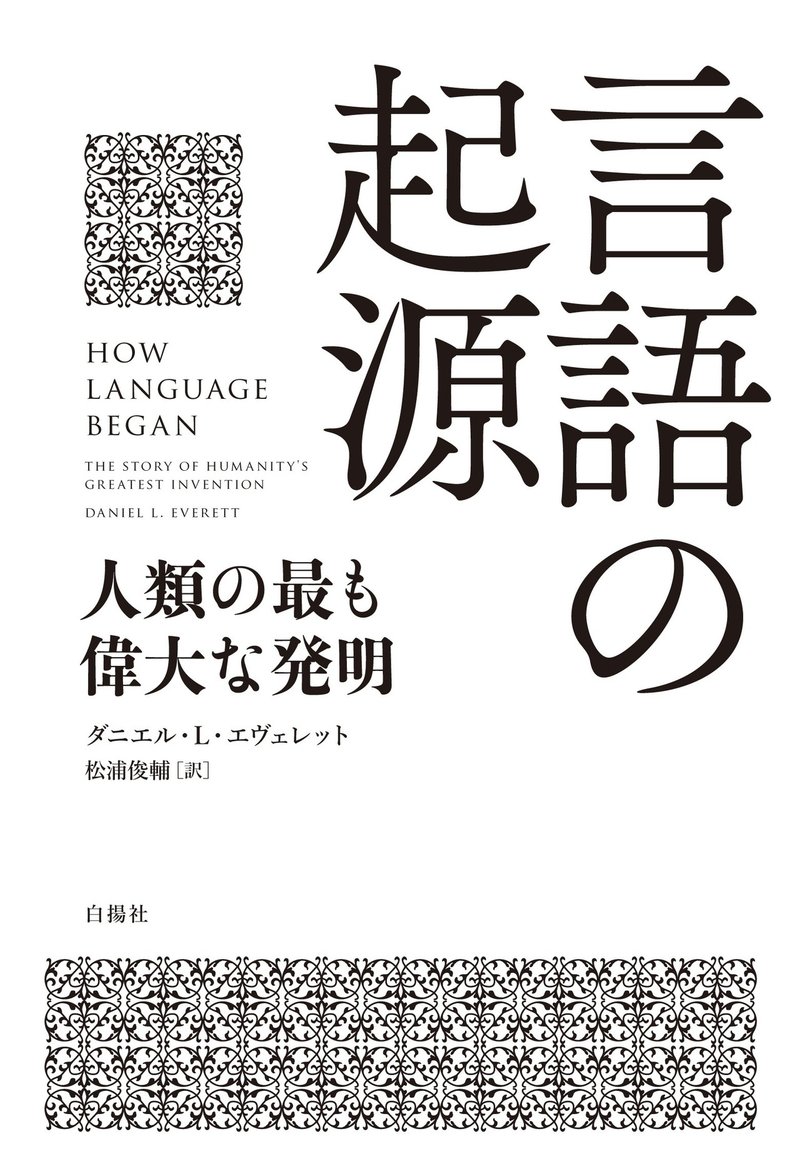言葉はなぜ、生まれたのか? 『言語の起源』試し読み
人類史上最も偉大な発明である「言語」——その起源をめぐっては、これまで様々な議論が交わされてきました。言語はいつ、使われはじめたのか? 人は言語をどのように獲得したのか? そもそも、他の動物のコミュニケーションと人間の言語は何が違うのか? 言語とは何なのか?
ノーム・チョムスキーが提唱した生成文法への反証であるとされた「ピダハン語」の研究で一躍有名となった、異端の言語学者ダニエル・L・エヴェレットが、言語学のみならず、人類学、考古学、脳科学などの知見をもとに、上記の問い答えを出す力作から「はじめに」をお届けします。
■ ■ ■
はじめに
はじめに言葉があった。
──『ヨハネによる福音書』(1-1)
いやいや、そんなことはなかった。
──ダニエル・エヴェレット
一九九一年のある蒸し暑い朝、ブラジルのアマゾン熱帯雨林を流れるキティア川沿いの集落でのことだ。最寄りの町から単発のプロペラ機で三二〇キロほど飛んだところにあるその場所で、私は、長年の野外活動のあとが肌に刻み込まれた二人の痩せた男、サバタウンとビードゥーにマイク付きヘッドフォンを取りつけていた。いつものこの時間なら、二人は、毒矢を入れた矢筒と二・五メートルほどの吹き矢を携えてジャングルに入り、ペッカリー、シカ、サルなど、自分たちのエデンの園に昔から暮らす獲物を狩っているはずだった。だが今日の二人は、私が録音機器の操作と音量の調整に手こずっているのを横目に、会話を交わすことになっていた。
二人に会話を始めてもらう前に、二人の言葉であるバナワ語とポルトガル語のちゃんぽんで、私の希望をもう一度説明した。「二人で話してくれ。話題は何でもいい。話を聞かせ合ってほしい。集落を訪れるアメリカ人やブラジル人のこと。何でもいいよ」。この場を用意するために、私は二人をなだめすかし、お金も払っていた。なぜなら、言語学の野外研究者にとって何にも代えがたい宝、──つまり自然な会話(二人以上でなされる自発的で双方向のコミュニケーション)を求めていたからだ。過去の失敗の経験から、自然な会話を録音するのが至難の業なのはよくわかっていた。録音機器を持った研究者の存在が仇となり、出てくる言葉を汚染してしまう。その影響はあまりに深刻なので、ネイティブスピーカーであれば誰も本物の会話とは思わないような、堅苦しくて不自然なやりとりしか生まれないのが常なのだ(想像していただきたい。誰かがあなたを友人の前に座らせて、ヘッドセットを装着させ、合図を出してこう言うのだ──さあ、何かしゃべって!)。
しかし今回は、採録した会話の音質を確認しながら興奮を抑えることができなかった。会話はこう始まる。
サバタウン ビードゥー、ビードゥー! 今日はしゃべるぞ。
ビードゥー うーん。
サバタウン 俺たちの言葉でしゃべるぞ。
ビードゥー うーん。
サバタウン ダニエルは俺たちの言葉が大好きなんだ。
ビードゥー ああ、知ってる。
サバタウン 俺からしゃべるぞ。それからおまえが、あのジャガーの話をしろよ。
ビードゥー ああ。
サバタウン 昔はどんなふうだったか思い出してみよう。
ビードゥー ああ、思い出すよ。
サバタウン ずっと昔、白人たちがやってきた。ずっと昔、白人たちが俺たちの集落にやってきたな。
ビードゥー 知ってる、そいつら。
サバタウン 奴らは俺たちを見つけた。俺たちは奴らと働くことになる。
ビードゥー ああ、知ってるよ、そいつら。
二人の会話は、ごく自然に話題を変えながら一時間近く続いた。
わが家から何千キロと離れた地で、だらだらと汗をかき、血を吸うハエやハチを叩いては追い払うという状況にあって、四五分後にサバタウンとビードゥーが語り終えたとき、私はほとんど泣き出さんばかりだった。そして、宝物のような会話を提供してくれた二人に熱烈な感謝の言葉を述べた。二人はにこりと笑うと、毒の吹き矢を携えて狩りに出かけていった。そこからは私の作業である。一人で録音を書き起こし(ほんの小さな言葉の違いもすべて発音通り書き留めた)、翻訳し、分析するのだ。集中して仕事をすること数日、データはどうにか「見られる」ものになった。そこで、イギリスのマンチェスター大学からアマゾンに同行していた大学院生に、録音、ノート、まだ残っている大量の分析作業を引き継いでもらうことにした。
一日の終わりには、研究チーム(私と三人の学生)で集まって、バナワ族から買いつけておいた豆、米、ペッカリーの肉という夕食を楽しんだ。食後はのんびりと、ジャングルの暑さや見たこともない虫などについてみなで語らった。だが会話の中心はやはり、例のサバタウンとビードゥーの録音会話であり、私たちがどれほど二人に感謝しているかということだった。会話の中に会話があり、会話についての会話をしていた。
つるべ落としのようなアマゾンの日没の後には、バナワ族の訪問を受けた。それが先方の習わしなのだ。私たち四人は、クールエイド〔粉末ジュース〕とコーヒーを用意して、訪問者のために甘いビスケットの袋を開けてあげた。最初に挨拶をする相手は、バナワの女性たちだ。バナワでは男女が厳格に隔てられている。その文化を踏まえ、女性たちへの挨拶や給仕の大半は研究チームにいる女子学生が行なった。ほどなく男性たちが座ることを許可され、私たちは追加のコーヒーとクールエイド、ビスケットを供した。飲み食いをしながら、私たちは男性たちとおしゃべりをした。西洋の家族や住居に関するあちらからの質問に私たちが回答するのが、主なやりとりだった。世界中で日常的に見られるように、私たちとバナワ族もまた会話を通じて関係を築き、友情を育んだのである。
この種の自然な会話は、言語学者、心理学者、社会学者、人類学者、哲学者にとって重要だが、それは、自然な会話が、他のどんな言語的表現もなしえないような形で、複数の要素が統合された全体としての言語を体現しているからだ。会話が言語研究の先端にあり、洞察の元になるが、それはとりわけ、会話の意味や形式が潜在的には定まっていないからに他ならない。会話はまた、実際に伝えたいことよりもつねに言葉足らずで、言外の前提を何らかの方法で解釈することを聞き手に任せる。つまり意味をはっきりさせるのに必ずしも十分ではないわけだが、この「非明示性(underdeterminacy)」ゆえに、会話は、言語の本質を理解するために欠かすことができない。そして非明示性は、これまでずっと言語の一部であり続けてきた。
非明示性の例は、先の会話のサバタウンの二番目の発言に見られる。そこでサバタウンはビードゥーに「俺たちの言葉でしゃべるぞ」と言っている。だが文字通りに受け取れば、これはちょっと奇妙だ。二人はすでに自分たちの言葉で話しているのだから。二人のポルトガル語の知識は初歩的で、主に物々交換する際の使用に限定されているので、実のところ二人がポルトガル語で自然な会話を成り立たせるのは難しい。サバタウンの発言は、そこでは述べられていないことを前提としている。サバタウンはあの発言によって、この会話内でポルトガル語を一言たりとも使うつもりがないことを私に間接的に知らせようとしたのだ。なぜなら二人は、自分たちがバナワ語でどう会話をするのかを見たいという私の希望を知っており、また私を助けたいとも思っていたからだ。こうしたことはどれも会話内では明示されておらず、言葉面だけを見るのでは不十分だ。だが、文脈から暗黙のうちに表れている。
同様に「昔はどんなふうだったか思い出してみよう」という呼びかけでは、前提として、二人が思い出そうとしている物事のおおまかな範囲が共有されている。では、その発言から導ける話題とは何か。儀式のことか。狩猟のことか。他者との関係か。それはどれくらい前のことなのか。アメリカ人がやって来る前か。ブラジル人がやって来る前か。それとも百世代前のことか。サバタウンとビードゥーは二人とも(あるいはバナワ族の誰もが)そこで何が話されるかを知っているが、外部の文化から来た者には最初のうちは見当がつかない。
サバタウンとビードゥーを含めてバナワ語を話せる人間は現在、約八〇人いる。科学者たちはこの言語を調査することで、人類の言語や認知能力、アマゾンについて、文化について、数多くのことを学んできた。もっと具体的に言えば、珍しい音声構造と文法、矢に塗る毒の材料と作り方、アマゾンで見られる動植物の分類、アマゾンに暮らす他の集団との言語上の関係などだ。この種の知見は、バナワ族をはじめとするさまざまな集団──固有の生活環境で数千年にわたって生きる術を磨いてきた人たち──の知識構造、価値観、言語のありよう、社会組織を分析することで自然に得られる。
コミュニティというものは、それがバナワであろうとフランスや中国やボツワナであろうと、どれも例外なく、言語を通じて構成員間の社会的つながりを築き上げる。実のところ、人類の会話の歴史は非常に長い。地球上で見られるあらゆる言語に関して、その思考表現の非明示性、社会的つながり、文法的制限、意味志向性の起源は、初期のヒト族であるホモ・エレクトゥス、もしかするとそれ以前までさかのぼることができるのだ。ホモ・エレクトゥス文化の痕跡、たとえば道具、住居、集落の空間構成、水平線の向こうにあるかもしれない土地への旅といったものから推定すると、ホモ属は約六万世代、おそらく一五〇万年以上にわたって話をしてきたようだ。そう考えると、人類は千年を千回以上繰り返すほどの長きにわたって言葉を磨いてきたわけだから、きっと言語に非常に習熟しているはずだ。また、自らの認知および知覚の制限、可聴範囲、発声器官、脳の構造にうまく適合するように言語を発展させてきたとも考えられる。非明示性とは、あらゆる会話のあらゆる発話、あらゆる小説のあらゆる一節、あらゆるスピーチのあらゆるくだりに「空白の点」、つまり話されることない暗黙の知識、価値、役割、感情が含まれていることを意味する──私が「ダークマター」と呼ぶ、言葉で特定されていない内容のことだ。言語を全面的に理解するには、共有され、内在化された一連の価値基準、社会構造、知識の関連が欠かせない。これらの共有された文化的、心理的要素を通じて、言語は伝えられる内容にフィルターをかけ、聞き手を解釈に導くのである。人は、言語が話される際の文脈と文化を利用して、その言葉を解釈する。と同時に、伝えられている意味を十分に読み取るために、ジェスチャーとイントネーションも利用している。
初期のホモ属は、ゼロから言語を構築するという長くて骨の折れる道に足を踏み出すことになったが、他の人類と同様、自分たちの頭にあることを余すところなく話すことはまずなかっただろう。それは言語の基本設計の特徴に反しているからだ。一方で、そうした原初のヒト族は、音声やジェスチャーをただ無作為に捻り出していたわけではない。そうではなくて、これならば相手が理解してくれると考えた手段を用いて意思表示をしていたはずだ。また、聞き手が「ギャップを埋める」、つまり不足を補うことができ、文化と世界に関する知識を結びつけて何が言われているかを解釈できると考えていた。
今挙げたことを考慮すれば、理解すべきことを記したリストの先頭に「会話」を持ってこない限り、言語の起源に関して有意義な議論ができない理由がわかるだろう。言語のあらゆる要素は、脳や身体の各部位がそうであったように、自身が会話や社会生活に参画できるよう進化してきた。言語は、最初の一人が初めて語や文を口にしたときに完全な形で始まったのではない。言語とは、その源泉であり目標でもある会話が生まれたときになってはじめて、本格的に開始されたものなのだ。言語は生活を変える。言語は社会を築き上げ、われわれの最も強い願望、最も基本的な考え、感情の動き、人生哲学を表現する。だがつまるところ、すべての言語は意思疎通にこそ奉仕するものだ。だとすれば、まずは会話ありきであり、文法やストーリーといった言語の他の要素はあくまで二の次である。
他方、こうした主張は言語進化に関する好奇心をそそる問いを提起する──すなわち、最初に話したのは誰かということだ。過去二世紀にわたり、南アフリカやジャワや北京からネアンデル谷やオルドバイ渓谷に至るまで、数多くの人類の祖先の候補が提案されてきた。そればかりでなく、研究者たちは新たなヒト族の種もいくつか提案しており、進化のパズルに混乱をもたらしている。こうしたいまだ真偽のはっきりしない各種提案の泥沼にはまるのを避けるため、本書で議論するのは、言語を獲得していた三つの種、ホモ・エレクトゥス、ホモ・ネアンデルターレンシス、ホモ・サピエンスにとどめることにする。
ホモ・エレクトゥスが言語を持っていたと主張する言語学者はほとんどいない。実際、多くの研究者がそれを否定している。人類が最初に話したのがいつなのかについては、今のところ意見の一致は見られていない。だが、人類進化や用いられる手法、人類の身体および認知能力の進化の大筋については、ある程度のコンセンサスが得られているようだ。チャールズ・ダーウィンは自著『人間の由来』の中で、人類が誕生したのは類人猿が多くいるアフリカではないかと述べ、人類と類人猿は近縁であり、共通の祖先を持っていることも(正しく)推論してもいる。こうした未来を先取りした主張をダーウィンが書き残したのは、初期ヒト族の存在が大々的に明らかになる前のことだった(ヒト族とは、ホモ属の他、アウストラロピテクス・アファレンシスなどのホモ属の祖先も含む分類のこと。人類とその近縁をまとめたもう一つの分類がヒト科だ。このグループには、ヒト、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、そしてそれらの共通の祖先が含まれる)。人類進化の物語には、ホモ・エレクトゥスから分岐した人類たち──その末裔がわれわれ現生人類となる──が登場する。そんな登場人物たちの関係を理解し、実際に話せたかどうかを知るには、こうした種族についてすでに判明していることがらをあらためて学ばなくてはならない。
ホモ属にはどれだけの種があったかというのも議論の的だが、言語進化におけるヒト族の移動の重要性について考える前には、やはりすべてのヒト族の潜在的な認知能力を、脳の容量、道具一式、あるいはその旅に基づいて理解しなければならない。その際、生理学的な側面または文化的な側面、あるいはその両方に注目することができるが、興味深いエビデンスは文化の方から得られる。
シンボル(象徴記号)は、人類を言語獲得への道に導く発明だった(シンボルとは、たとえば「いぬ」という音を用いてイヌ科のあの動物を指示するように、ほぼ恣意的な形象を特定の意味へと結びつけるもの)。そのような理由から、われわれはシンボルがどう誕生したかばかりではなく、それがどうやってコミュニティ全体に採用され、いかに編成されていったのかを理解しなければならない。私がここで退ける説は、人類言語の起源に関して現在最も影響力のある説明だと言っていいだろう。すなわち、言語とは、およそ五~一〇万年前に起きた、たった一度の遺伝子変異の結果であり、その変異によって、ホモ・サピエンスは複雑な文を組み立てられるようになった、という主張だ。この一連の主張は、「普遍文法」と呼ばれる。だが、人類の生物学的・文化的進化に関する形跡を入念に調べていくと、それとはまったく異なる仮説が浮かび上がってくる──すなわち、言語起源の記号進展理論(sign progression theory)だ。この言い回しの意味は単純で、言語は指標記号〔インデックス〕(足跡が動物を指すように、物理的につながりのあるものを表す事項)、類像記号〔アイコン〕(実在の人物の肖像画のように、表そうとする事物と物理的に似ている事物)、それから最後に象徴記号〔シンボル〕(ほとんど恣意的な、慣習的な意味の表し方)の創造へと、徐々に現れてきたということを意味している。
シンボルはいずれ他のシンボルと組み合わされて文法を生み出し、単純なシンボルから複雑なシンボルが構築されていく。こうした記号の進展が言語進化のある段階に達すると、ジェスチャーとイントネーションが文法と意味に統合され、一人前の言語が形成されることになる。なお、この統合によって、一方が話す情報が他方に伝達され、それと同時に強調もされる。無視されがちではあるが、このことは言語の起源における非常に重要なステップだ。
言語進化の問題は非常に難しいためやむをえないことではあるが、最初にそれを解明しようとした人たちの手並みは、予想されるように、かなり粗末なものだった。たとえば、理論の説明はデータや知識ではなく、憶測に頼っていた。有名なところでは、すべての言語の起源はヘブライ語だという説がある。だがこうした主張がなされたのは、ヘブライ語が神の言語だと信じられていたからにすぎない。このヘブライ語起源説をはじめとして、これまでに憶測に基づいた数多くの主張が破棄されてきたが、中には優れた洞察の萌芽を含んでいるものもあり、そうしたものが、回り道をしながらではあるが、今日の言語の起源の理解へとつながっている。
しかし、当時の研究すべてに深刻な欠陥が伴っており、憶測だらけで根拠が欠落しているという状態に、多くの科学者が苛立っていた。そのためパリ言語学会などは、一八六六年、言語の起源を扱った論文は今後いっさい受理しないと宣言したほどだ。
喜ばしいことに、その方針はすでに撤回されている。今日の研究は、一九~二〇世紀に比べると憶測がいくぶん少なくなり、ときには堅固なエビデンスにしっかりと依拠している場合もある。二一世紀になって、科学者は、難しいこととはいえ、言語の起源というパズルのごく小さなピースでも十分に集められるようになり、人類の言語がいかに生まれたかについて、合理的なアイデアを提出できるようになったのだ。
もちろん、それで言語の起源に関する謎がすべて解決されたわけではない。多くの研究者が指摘しているとおり、未解決の大きな謎の一つが「言語の断絶(ギャップ)」と呼ばれるものだ。人類とそれ以外の生き物の間には、広くて深い言語のギャップがある。言い換えれば、動物界のコミュニケーションのシステムは、人類の言語とは異なっている。人類の言語だけがシンボルを持っている。また高度に構成的であり、ストーリーを段落に、段落を文に、文を句に、句を語にというように、意味を持つより小さな部分へと分解できるのも人類の言語だけだ。このとき各構成要素は、それが集まって作られるさらに大きな構成要素の意味形成に寄与している。言語の裂け目が存在する理由を、たんに人類が他のどんな動物とも異なる特別な存在だからと考える人もいる。その一方で、人類の言語の独自性は神によって設計されたものだと信じている人もいる。
しかし、それよりも可能性が高いのは、言語のギャップはほんのわずかずつ、言い換えれば、文化によって促進されたホメオパシー的な変化〔全体から見ればごく微小の要素から生じる変化〕により形成されたという説だろう。そう、人類の言語は他の動物のコミュニケーションシステムと劇的に異なってはいるが、「言語の閾値」を超えるための認知的、文化的な一歩は、多くの人が考えているよりも小さいのだ。各種エビデンスは、人類が「突然の跳躍」によって独自の言語的特徴を得たわけではなかったこと、現代人類に先行する種(ホモ属、あるいはそれ以前のアウストラロピテクス属に分類されるもの)がゆっくりと着実に発展して言語を手に入れたことを示している。こうした初期ヒト族のゆっくりとした歩みは、最終的に人類の言語と動物のコミュニケーションの間に大きな進化的溝をもたらすに至った。結果として人類は社会の複雑さと文化を発展させ、また他の生き物よりも生理学や神経学の面で優越した存在に変貌していった。
人類の言語は、かくして慎ましく始まる。それは、初期のヒト科が持っていた、他の動物とは異なる──そしてガラガラヘビのものよりは効果的な──コミュニケーションシステムとして始まったのである。
ところで、もしバナワ語を話せる最後の八〇人が突如として死に絶え、その骨が一〇万年後まで見つからなかったとしたら、いったいどうなるだろう。実際には、バナワ語の文法書や辞書が出版され、研究論文も残されているが、今はそのことも忘れておこう。残されたバナワの物質的産物は、それを残した人々にシンボルを用いた思考や言語を使う能力があったことの証拠になるだろうか。たとえ証拠になったとしても、ネアンデルタール人やホモ・エレクトゥスに関して見つかっているものよりも、その数はさらに少なくなるに違いない。バナワの芸術品(ネックレス、編みかごのデザイン、彫刻)や道具(弓、やじり、矢柄、毒、編みかご)は生分解されてしまう。最古の文化が出現してから現在までに八〇~一五〇万年が経過しているが、バナワの物的産物はそれよりもはるかに短い時間で跡形もなく消え去ることだろう。もちろん、地面の痕跡から、この部族がある大きさの集落や住居などに暮らしていたと判断できることはあるかもしれない。だがそれでも、そうした遺物から言語の有無を推定するのは難しいし、多くの古代狩猟採集民にも同じことが言える。今日アマゾンに暮らす集団が十分に発達した言語と豊かな文化を持っているのは周知の事実だ。それを考えれば、先史時代の記録に言語や文化に関する証拠が欠けていることをもって、古代の人類集団がそのために必要な認知的特質を欠いていたと結論するのは早計だろう。実のところ、注意深く調べてみると、初期ホモ属は実際に文化を持っていたし、しゃべりもしたという証拠が見つかるのだ。
言語の起源の謎を解く最初の一歩は、言語を使う人類の唯一の生き残りであるわれわれホモ・サピエンス──作家のトム・ウルフはそれをホモ・ロクワクス、すなわち「話す人」と呼んだ──の特質と進化を考察することから踏み出される。言語進化の道筋を見極めるための視点には、以下のようなユニークなものがある。
第一の視点は、人類の言語が、動物のコミュニケーションという、もっと大きな現象に端を発しているとする。コミュニケーションとは、ある存在から他の存在への(普通は意図的な)情報の伝達にすぎず、それ以上のものではない。フェロモンを使ったアリのコミュニケーションだろうと、サバンナモンキーの鳴き声、イヌの尻尾の位置や動き、あるいはイソップの童話だろうと、本を書いたり読んだりすることだろうと、同じことが言える。だが、言語はたんなる情報伝達ではない。
言語の進化についての第二の視点は、生物学と文化の両面から俯瞰して調べることだ。脳、発声器官、手などの身体の動きは、文化と協働して、言語の進化にどう影響を与え、それを促進したのか? 「生物学か文化か」というように、どちらか一方だけに着目し、他方を除外する学説はあまりに多い。
最後の視点は非常に重要であり、一部の読者にとっては奇妙に思えるかもしれない。それは、言語学の野外研究者と同じように言語進化を見るというもので、ここからは二つの根本的な問いが導かれる。すなわち、今日話されている各地の言語は互いにどれほど似通っているのか。そして、現代の言語の多様性から最初の言語について何がわかるのか。ここで見た三つの視点は、人類の最初の言語が歩んだ道を記す進化の里程標となる出来事を見通せるようになるうえで有益になることだろう。
答えておくべき問いはまだ他にもある。ジェスチャーは言語にとって決定的に重要なものなのか? 答えはイエスだ。言語には現代人と同じ発声器官が必要なのか? 答えはノーだ。複雑な文法構造は言語に不可欠なものなのか? 答えはノーだ。ただ、そうした構造はさまざまな理由から、現代の言語の多くに見つけることができる。他の社会よりコミュニケーションが少ない、あるいは言語によるコミュニケーションが弱い社会は存在するか? どうやら答えはイエスのようだ。ホモ・エレクトゥスは言語を持っていた可能性があるが、それでも寡黙を良しとしていたかもしれない。
最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。