
人間が作った世界で、動物はどのように変わったのか?『家畜化という進化』試し読み
オオカミをイヌに、イノシシをブタに変えた「家畜化」。人間の作った世界で、動物は野生の祖先からどのように変わったのか?
イヌ、ネコ、ブタ、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ラクダ、トナカイ、ウマ、モルモット、マウスやラット――家畜化された動物には奇妙な共通点が。私たち人間にも、同じ特徴があるといいます。ということは……
家畜化を通して動物とヒトの進化を読み解く意欲作『家畜化という進化』から「はじめに」をお届けします。
■ ■ ■
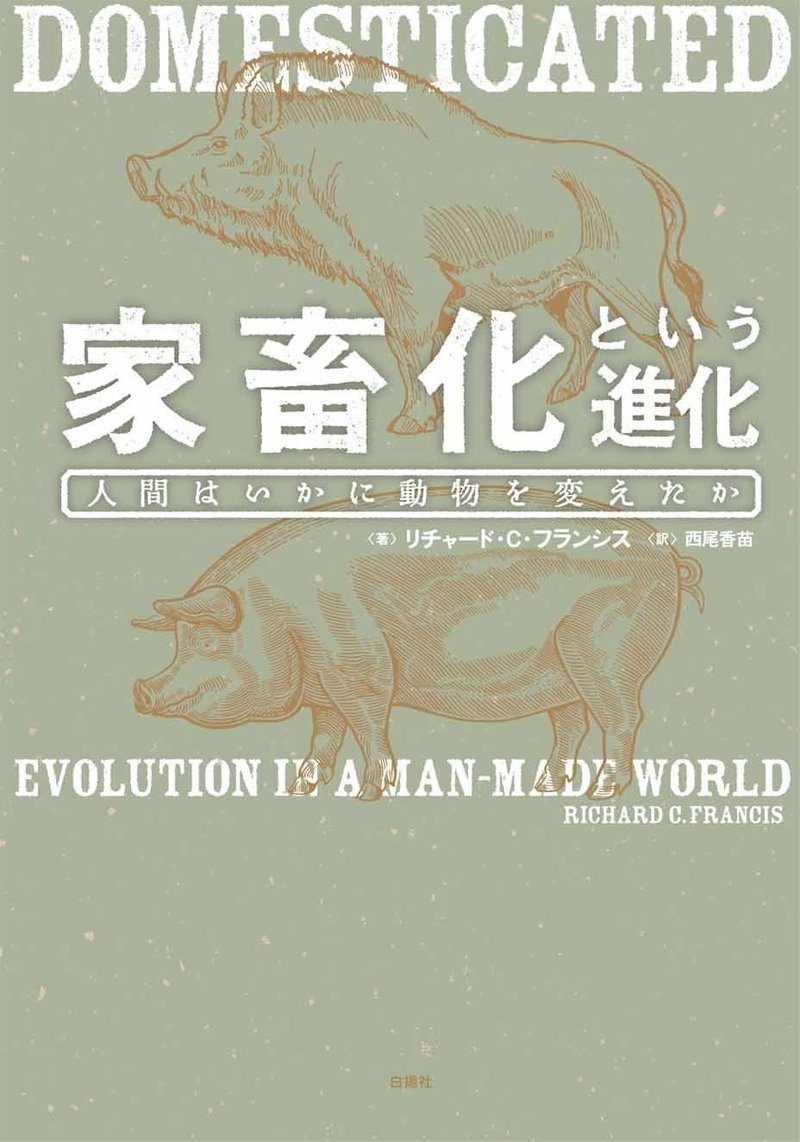
もしも家畜や作物がなかったなら文明など存在せず、わたしたちは今でも狩猟採集民のままで、かつかつの生活を送っていたことだろう。動物の家畜化や植物の作物化によって、それ以前にはありえなかったほどの余剰食料が手に入るようになったために、いわゆる新石器革命が引き起こされたのである。この革命は農業経済だけでなく都市生活のための土台になった。現代の文化があるのも、この革命をベースとして一連の技術革新が起こってきたおかげである。文明発祥の地が、オオムギやコムギ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ウシ、ネコが人間と決定的に親密な関係をもつようになった地域でもあるのは、偶然ではないのだ。
新石器革命が始まった当初、地球の人口は一〇〇〇万だったと見積もられているが、いまや地球上には七〇億を超える人々が住んでいる。人口の爆発的な増加は、人間以外のほとんどの生物にとって災難でしかない。しかし、幸運にも家畜や作物としての身分を保障されている生物にとってはそうではない。家畜や作物はわたしたちとともに繁栄の道を歩んできたのである。新石器時代以降、生物の絶滅率は、それ以前の六〇〇〇万年間に対して一〇〇〜一〇〇〇倍にもなっている。タルパン(ウマの祖先)やオーロックス(ウシの祖先)など、家畜化された動物の祖先(野生原種)の多くも新石器時代以降に絶滅した。だが、家畜のなかには絶滅したものはいない。ラクダやイエネコ、ヒツジ、ヤギについては、それぞれの野生原種は消滅の瀬戸際にいるが、家畜化された子孫たちは地球上の大型哺乳類のなかで最も多い部類に入るのである。進化という観点からすれば、家畜化されて損はなかったのだ。
だが、家畜の成功にはそれ相応の代償もある。進化の主導権を握られてしまうのだ。家畜や作物がどのように進化するか、その運命の支配権のかなりの部分を、人間は自然からもぎとってしまっている。そのため、家畜や作物は、進化の過程を理解するための多くの情報をもたらしてくれる存在になっているのである。実際、家畜や作物は非常にドラマチックな進化の実例なのだ。特殊創造説〔生物の種は天地創造の六日間に神が創造したものであり、それぞれの種はそれ以来変化していないという説〕の信奉者でさえも、オオカミからイヌへの変化は進化によるものであったことを、ある程度にせよ認めてはいる。家畜の作出では、特定の形質をもつ品種を作り出すために人為選択が行われる。ダーウィンは「自然選択」(自然による選択)と「人為選択」(人間による選択)はよく似た過程だと考えていた。だからこそ、イヌやハトの人為選択について、かなり注力して議論したのである。
新石器時代の人類と競合するだけでなく人間を捕食することもあったオオカミは、家畜化された最初の動物でもあった。この事実こそが、意識的あるいは無意識的に人間が進化に影響を及ぼす力をもっている証拠である。イヌやその他の哺乳類の家畜化過程の大部分において、人間は無意識的に進化に圧倒的な影響力を及ぼしてきた。この理由から、自然選択と人為選択の区別は実はかなり不明瞭なのだ。本書でこれから見ていくように、多くの場合、家畜化過程をスタートさせるのは人間ではなく動物自身である。理由はさまざまだが、動物が人間のすぐそばで生活するようになるのが第一歩である。この自発的な人馴れ〔原語は「self-taming」。二〇一七年、国立遺伝学研究所が「人になつく動物の遺伝子領域を解明」と発表した。そのなかで、「自ら人に近づく」ことを「能動的従順性」としている。人間の近くに自ら近づいてきたオオカミには、この「能動的従順性」があったといえるだろう〕の過程は、主として通常の自然選択を通じて起こる。人間による意識的な選択、つまり人為選択が行われるのは、家畜化過程のもっとあとの段階である。とはいえ、どこまでが自然選択でどこからが人為選択なのかははっきりせず、どちらとも言いがたい段階がかなり長く続く。この移行段階中、形質の選択における人間の重要性は増大していくが、意識的な要素はまだ部分的なものにすぎない。 実際、自然選択と人為選択の組み合わせはかなり強力であることがわかっている。イヌのサイズは、チワワからグレート・デーンまでかなりの幅がある。これは野生のオオカミどころか、絶滅種も現生種も含め、イヌ科(オオカミ、コヨーテ、ジャッカル、キツネなど)全体のサイズの範囲を超えている。イヌ科は四〇〇〇万年近く前の漸新世に出現した。その後、人間との関わりを通じて選択圧を受け、わずか一万五〇〇〇〜三万年の間に進化的な変化を遂げた。その変化はそれ以前の四〇〇〇万年間でのイヌ科動物の変化をはるかに超えているのである。
人間が引き起こしたイヌの進化では、変異が見られる形質はサイズだけにとどまらない。毛色や骨格にも変異が生じている。イヌの頭骨の形態はバリエーションに富んでいる。イヌ以外のイヌ科動物すべてに見られるバリエーションを軽く超えるどころか、食肉目(イヌ科の上位分類群で、イヌ科以外にはネコ、クマ、イタチ、アライグマ、ハイエナ、ジャコウネコ、アザラシ、オットセイなどが含まれる)全体のバリエーションをも凌駕している。
人間による選択がイヌの行動に及ぼした効果がドラマチックなのはいうまでもない。なかでも注目に値するのは、イヌが人間の意図を「読み取る」能力を進化させたという点だ。イヌは人間のジェスチャー、たとえば離れたところにある食べものを指さすなどの意味を理解する。野生のオオカミにはこんなことはできない。実際、人間の意図を読み取ることにかけては、人間に最も近い親戚であるチンパンジーやゴリラよりも、イヌのほうがよほど上手だ。ということはある意味、社会的認知に関しては、イヌのほうが大型類人猿〔チンパンジー、ゴリラ、オランウータン〕よりも人間に似通っているというわけだ。
その他の家畜の進化についても、人間が及ぼした影響はイヌにほとんど劣らず印象的なものだ。おとなしくて乳房の発達したホルスタイン種のウシは、気位が高く獰猛な野生原種であるオーロックスにあまり似ていないし、メリノ種のヒツジも野生原種であるムフロンには似ていない。ウシもヒツジも、家畜種と野生原種が分岐したのはほんの一万年前のことだ。短期間のうちにずいぶんと進化したものである。議論は、このビッグあるいはディープ・ヒストリーの次元を背景とするものである。
家畜化は加速された進化なので、生物学をよく知らない人にとって、進化がどのような過程をたどるのかを直観的に理解するためのうってつけの教材になる。進化は歴史的な過程だが、ほとんどの進化はかなり大きなタイムスケールで起こるため、知識の乏しい者にとってはなかなか理解しがたく、ましてや直観的に把握できるものではない。人間の精神には限界があることを考慮すれば当然だ。だが、家畜化はもっとわかりやすいタイムスケールで起きる。たとえば、イングリッシュ・ブルドッグというイヌの品種は、この一〇〇年間というわずかな時間で大きく進化している。家畜化という進化の過程を知ることにより、人類自身の歴史をも知ることができる。つまり、人類が記録を残すようになってからの有史時代と、有史以前(紀元前三万年〜紀元前五〇〇〇年)の時代、それよりもっと前の人類の進化の歴史がとぎれなくつながる、長大な流れとして見ることができるのだ。このような長大な歴史は「ビッグ・ヒストリー」と呼ばれることもあるが、わたしは「ディープ・ヒストリー」というほうが適切だと思う。本書で行っていく議論は、このビッグあるいはディープ・ヒストリーの次元を背景とするものである。
家畜化以前の時代の歴史(ディープ・ヒストリーの最もディープな部分)は、もちろん進化生物学、なかでも特に「系統学」という分野が扱う領域である。系統学とは、生命の系統樹上で各生物がどのようにつながるのか、その関係を再構成しようとする分野である。家畜化以前の時代と有史時代の境目となる時期についてもある程度のことはわかっているが、その多くは、動物考古学によって得られたものである。動物考古学は急速に発展中の分野で、古代人類の文化、動物学、自然史という三つの分野の専門知識を合体させるものだ。有史時代には人間は家畜を意識的に管理する段階に入ったことが、文献により記録されている。現在も意識的な管理は続いており、いい意味でも悪い意味でも比類なき変化を引き起こしている。
このような歴史的な背景は、それ自体が興味深いものである。同時に、進化がどのようにして起こるのかを理解するのに必要不可欠な情報でもある。家畜化された動物はどれもみなおなじみのものであるため、その性質がどのように変化してきたのか理解しやすい。進化生物学の近年の進展や最新の知見を家畜化というレンズを通して考察したい。それが、本書でわたしが主に目指していることだ。そのためには理解しやすいことが何より重要なのである。
家畜化のそれぞれのケースは、進化において自然ななりゆきで行われた一種の実験として見ることができる。「自然ななりゆきで行われた実験(natural experiment)」というのはつまり、進化の研究をするのに理想的ではあるが、計画されて行われたのではない実験という意味である。家畜化の逆過程である野生化もまた、自然ななりゆきで行われた実験だ。その一例はディンゴである。ディンゴはおよそ五〇〇〇年前に原ポリネシア人によってオーストラリアに移入され、オーストラリア奥地でペットから捕食者の頂点に立つものへと変貌した。その過程で、ディンゴはオオカミに似る方向へと進化した。実際、ディンゴにはオオカミともイヌとも異なる興味深い特徴が見られる。
このような、過去の家畜化や野生化という自然ななりゆきで行われた実験に加え、家畜化について現在まさに進行中の科学的実験もある。家畜化の過程を実験的に再現しようという試みであり、ひとえに進化の過程がどのように進むのかを解明したいという目的で行われている。
家畜化のどのケースを見ても、興味深くかつ他にはない特性があるが、全体に共通したテーマも立ち現れてくる。それは個別のケースと同様に興味深く、かつ進化について考えるうえで重要なものだ。そういったテーマのなかで最も意味深くかつ注目すべきものは、家畜化に伴って思わぬ結果が生じることだろう。人間がある一つの形質に注目して、その形質をもつ個体を選択すると、他の一見関係なさそうな形質にまで、意図せぬ影響を与えてしまうのだ。このような副産物は、自然選択による進化でも一般的に見られる特徴であることがわかっている。この副産物により、選択の対象となる形質の進化にブレーキがかけられたり、新たな進化の機会が生まれたりすることもある。
他にも本書全体に共通するテーマがある。表現型(行動的、生理的、形態的な形質を含む)の変化の程度とゲノム(その生物がもつ遺伝情報の全体)の変化の程度には厳密な相関関係がないことである。たとえば、家畜に大きな身体的変化が見られるのに、遺伝的な変化が驚くほど少ない場合もよくある。イヌとオオカミの遺伝的な隔たりは、両者の身体的な差異に比べて微々たるものだ。ブタやウシやウマにもこれはあてはまる。それによって三つめのテーマが浮かび上がってくる。人間が作り出す環境が生物の進化に対して与える影響は、ウマとイヌのように、ゲノムが(ということは進化的な距離も)大きく隔たっている生物に対しても驚くほど一貫している、ということだ。
だがしかし、本書で最も重要なテーマは、進化過程の保守的な性質である。家畜化で見られるように、極度に高速で起こる場合でさえも保守的なのである。進化についての通俗的な説明は、新しいものを生み出す面ばかりに注目しているものがほとんどである。これは適応万能論者の主張の要である。適応万能論者は、生物は多様な(そして限りのないように見える)方法でもって環境による困難に反応し適応して変化していくということを示したがっている。しかし、適応による変化に限りがないなんてとんでもない。実際はかなり制限されているし、その生物のそれまでの進化の歴史によってその方向性は限定されているのだ。事実、適応による変化はそれまで進化してきたものの端っこを改造するだけに制限されている。ペキニーズはオオカミの改造版であり、オオカミの祖先から丸ごと設計し直したものではないのだ。
進化生物学内で近年発展してきた二つの分野が、進化の保守的な面をとりわけ前面に押し出してきた。ゲノミクス(ゲノム情報の解析)と進化発生生物学(エヴォデヴォ)である。両者ともに本書では大きく取りあげている。
本書の構成
各章ではそれぞれ単一の生物(イヌ、ネコ、ブタなど)あるいは近縁な二種の生物(ヒツジとヤギなど)の家畜化に注目する。まず初めにその生物の家畜化の歴史や文化的な意義を説明する。次に、その生物とその野生原種が含まれる科の進化的な歴史を、系統樹上の位置も含め簡単に紹介する。人間が入念に作りあげてきた進化的な変化の背景情報を提供するためだ。各章の大部分は、これらの人工的な変化をもとに進化の過程についてどんなことがわかるか、新しいものを生み出す面と保存的な面との両方から検討する。最後の三つの章では人間に注目する。そのうち初めの二章では、人間の進化には自己家畜化の過程が含まれており、わたしたちの進化はたとえばオオカミからイヌへの移行と重要な点でよく似た関係にある、という仮説について考察する。最終章では、アフリカの動物相の取るに足らない構成要素にすぎなかった人類が、現在の支配者的な地位に上りつめたことを論じる諸説について考察する。人類が地球にどんどん手を加えていることを考慮するなら、われらが家畜動物たちは、未来の進化の先陣を切っているのである。
最後までお読みいただきありがとうございました。私たちは出版社です。本屋さんで本を買っていただけるとたいへん励みになります。
