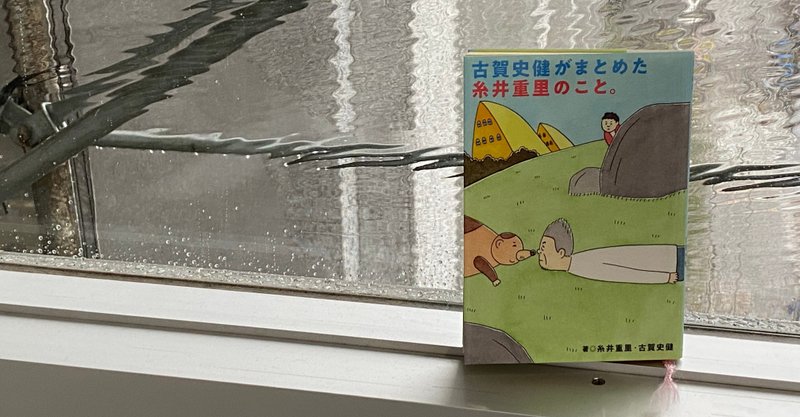
【広告本読書録:046】古賀史健がまとめた糸井重里のこと。<前編>
糸井重里/古賀史健 著 ほぼ日 発行
糸井重里さんといえば、過去にも『糸井重里全仕事』を取り上げたこともありますし、いまさら何の説明もいらないほどの文化人。最近は経営者でもあります。セゾンの堤清二さんのような文化系商売人とでもいいましょうか。
そんな糸井さん、意外と自分のことについてまとめられている書物がなかったようです。今回紹介する本は「自伝のようなもの」としてのおそらく最初で最後の一冊になると“まえがき”に書かれております。
ほら、上記サムネイルの引用文にも「自伝のようなもの」とあるでしょう。この本には糸井さんの幼少期から学生時代、コピーライターになるまで、糸井さんブーム全盛期、MOTHER開発の打ち明け話、そしてほぼ日についてまで糸井さんのこれまでの足跡が語られています。が、この読書録では糸井さんの自伝からぼくが興味関心のある箇所だけを抜き取って感想をつらつらと述べてまいります。
ぼくが知りたかった糸井さんのこと
ぼくが糸井さんのことをはじめて知ったのはテレビ番組『YOU』でした。ぼくは当時、というか今でもYellow Magic Orchestraというバンドが好きなのですが、そのYMOが出演する!ということでふだんめったに観ることのないNHK教育にチャンネルをあわせ、テレビの前で正座していたのでした。
いま、ふっとおもったんですが、当時はそういう情報をどこで手にいれていたんでしょうか。いまならリタゲとかなんとかもそうですが、とにかく個人の足跡を追って最適な情報が向こうからやってくるじゃないですか。昔はそんなものないから自分から取りにいってたんでしょうけど。インターネットがない時代の生活のことがどんどん記憶から薄れていってしまっています。
話を戻します。そのYOUで、いかにもやらされてる感あふれる司会のお兄さんが糸井さんでした。でもその頃のぼくには、その、やらされてる感がなんともカッコいいなあ、とおもえたんですね。妙に力んでいないというか。逆に一生懸命、汗かきながらやってるのがダサい。そんなふうにとらえていた若気の至りでございました。
そんなふうに知った糸井さんですが、当時、目を通していたサブカル誌でちょくちょくその名前を確認していました。そして興味をもって情報に触れていくうちにコピーライターという職業があるということも知ることになります。それがだいたい昭和58年とか59年あたり。まさか5年後に天皇が崩御するなんて誰も想像してなかった時代です。
それから時を経て令和元年。その間にいろいろな糸井さんにまつわるエピソードに触れてきたけれども、ぼくが知り得ない、というか知りたいのにわからなかった話がありました。それが、この本には載っていました。
会社員になるのが怖かった子供時代
糸井さんの幼少期の話で非常に共感したのは「大人になって社会に出るのが怖かった」ということ。会社員になりたくなかったんだそうです。もっといえば働きたくなかった。これ、なんとなくわかります。
ぼくも小学校5年生ぐらいの頃、あれは確かザ・ベストテンかなにかを見ているとき、ふいに将来への漠然とした不安が頭によぎったんです。なぜだかはわかりません。でもその不安感、恐怖感にも似た感情は本当にふいに、あっという間にぼくの心をとらえました。
その時に流れていたテレビコマーシャルがお菓子の『SBヘッドギア』だったことまではっきりと覚えているんですから、どれだけ子供心に強烈な印象を遺したかってことです。
ただ、ぼくが興味を持っていたのは幼少期ではありません。それよりも糸井さんがコピーライターになる直前と、なったばかりの頃のこと。糸井さん、なんといってもエキセントリックな人だから、あまり汗をかいたりべそをかいたりする姿をこれまで見せてきていないんですよね。
コピーライターになれると決めた
仕送りをしてもらいながら大学に通う糸井さん。学生運動に幻滅して、大学を辞めてしまいます。それでも卒業までの期間は仕送りしてほしい、と親に頼みます。それに応えるお父さん。すごくないですか?そのおかげで糸井さんはお金の苦労をすることなく、心豊かに青年時代を過ごします。
とはいえ仕送りとバイトだけでは…ということで仕事を探すのですが、前述の通り会社勤めは選択肢外。ということで手に職つけるか、といろんな専門学校の資料を集めたりします。
それがあるとき、知り合いの女の子から「わたし、いまクボセン(久保田宣伝研究所。現・宣伝会議)の『コピーライター養成講座』に通っているの」と教えられました。ぜんぜん興味もない、選択肢に入れたこともない道です、コピーライターは。ただ、その子が「アルバイトで書いたコピーで、1本4000円なんだ」と言うわけです。
これが稀代の、と冠されるコピーライター糸井さんとコピーの出会い。まずそのバイト代にびっくりします。そして次の瞬間、なんの根拠もないまま「おれは、コピーライターというものになれるのかもしれない」と思ったんだそうです。コピーはもちろん、文章だって書けなかったのに、です。
誰にすすめられたわけでもなく、どこかで文章をほめられた経験もなく、自分で勝手にそう決めちゃったんだというから驚きです。でも、もしかしたらそういうものなのかもしれないなあ、といまならおもえます。自分は…と振り返るとまあ似たようなもので、何の根拠もなかったですから。
あるとき、ポンと書けるようになった
そうやって「なれると決めた」コピーライターでしたが、なんと、糸井さんは養成講座時代にすでに評価されていたんですって。養成講座では若いし、生意気だし、全く問題外だったといいます。確か自著の『コピーライターの世界』でも、同期の魚住勉さんとダメ生徒だったとお互い言い合ってます。
糸井さんは、そのダメっぷりをカラーテレビの課題のコピー
リンゴは赤く。でも、家計簿は赤くなりません。
を引用して「笑っちゃうでしょ」と表現しています。これではダメだと。考えたフリをしているだけだって。
それが、あるときそれまでと明らかに違うコピーがポンと出来たという。アサヒビールの「本生」という新商品の課題。
本生には、贅沢をさせています。
これを黒須田伸次郎先生がすごくほめてくれたんだそうです。糸井さん自身もこれまで書いてきたコピーと違うことがわかったそうです。おおきな意味での発見がありますよね、といいます。
このコピーから周りの評価が変わっていった。広告業界の大御所、山川浩二さんなんかがよその人のところに糸井さんを連れて行くんです。糸井さんが「あ、糸井です」なんてあいさつすると、横でボソッと「彼、天才ですから」と付け加えるんですって。
やっぱり、糸井さんの広告作法って、マジックです。なにかのコピーができあがったときに「あっ、書けた!」ってなる。逆を言えばどんなに数を書いても「書けた!」という実感がないそうです。ううむ、このへん、もやもやしちゃいますね。。。
食えない仕事で育てられた
結局、糸井さんはサムシングというアパレル系の制作プロダクションに入ります。その昔、想像していたような居心地の悪い会社ではなかったそうですが、仕事がとにかくつまらなかったそうです。そして、その会社はすぐにつぶれてしまいます。
ただ、これは糸井さんすごいなとおもわせるエピソードなのですが、つまらない会社の仕事をしながら賞には積極的に応募していたんですね。入社してすぐに宣伝会議賞の銀賞を。そして銀賞ってのが悔しいから次の年は2つ応募したらそれが金賞と銀賞を獲ったんだそうです。すごい。
でも、ちっとも評判にならないし、どこからも引き合いの話がこない。賞を獲ってよそから引き抜かれるのを待っていたんですが、その前に倒産しちゃったというわけです。
そうして、ところてんのようにフリーランスになった糸井さん。最初はコピー以外で食っていたとのこと。おもしろいなあとおもったのが、CMのアイデア出し。友人のCMディレクターがクライアントへのプレゼンに持っていくCMのアイデアを毎回何本か考える。それだけで毎月初任給ぐらいのお金になっていたと。
いくらぐらいだったんでしょう。70年代後半の話です。ちょっと調べてみましょうか。『年次統計』という個人の統計ジャーナリストの方が運営しているサイトにデータが載っていました。それによると…
1979 (昭54) 109,500円 /145,952円
1978 (昭53) 105,500円/149,671円
1977 (昭52) 101,000円/151,725円
1976 (昭51) 94,300円/154,389円
1975 (昭50) 89,300円/161,758円
※左側の金額は現代の価値換算(出典:年次統計)
だいたい10万円、現代なら15万円ぐらいもらっていたんですね!
広告以外がいちいちぜんぶ楽しかった
糸井さんはそのころイラストレーターの湯村輝彦さんと仲良くなります。当時既に超一流のイラストレーターだった湯村さんがなぜか糸井さんのことをかわいがってくれて、一緒に仕事をすることに。
有名なところでいえば『ガロ』で連載していた『情熱のペンギンごはん』シリーズですね。他にも小さな連載など広告以外の仕事がたくさん舞い込んできます。それがいちいち楽しかった、と糸井さんは振り返ります。
その理由は、広告以外の仕事をメシのタネとして全くアテにしていなかったから。
『ガロ』なんて原稿料タダでしょ?ほかに連載があるといっても、せいぜい原稿用紙4枚程度。お金の面では全然話にならない。でも、アテにしてない仕事だったからこそ、失うものがない立場として、自由に遊ぶことができたんです。
そうやって、食うためではない仕事を楽しんでやっていたら、やがて周囲がほうっておかなくなるんです。アートディレクターの江島任さんや浅葉克己さんなどの先輩から声がかかって、どんどんとメジャーな仕事に巻き込まれていく。
ここにいてもいいんだ、から、おれにもできるな、へ
そうしていくうちに、糸井さんの中で自信のかたちが変化していったといいます。最初のうちは、先輩方にかわいがってもらうことで「ここにいていいんだ」という気持ち。それが少しずつ「これだったらおれにもできるな」に変わっていく。
やがて「これ、おれにやらせてくれたらよかったのにな」とおもうようになっていったそうです。実際にできたかどうかはわからないけれど、でも、自分のほうがおもしろくできる、と思っていたんでしょうね、という言い方で当時を振り返っています。
さて、このあたりから、いわゆる糸井さんがブームになっていくのですが…ちょっと長くなりそうなので分割します。どうしても糸井さんの話になるとおもしろくって、あれこれ深堀りしたくなっちゃいます。
次回、後編へとつづきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
