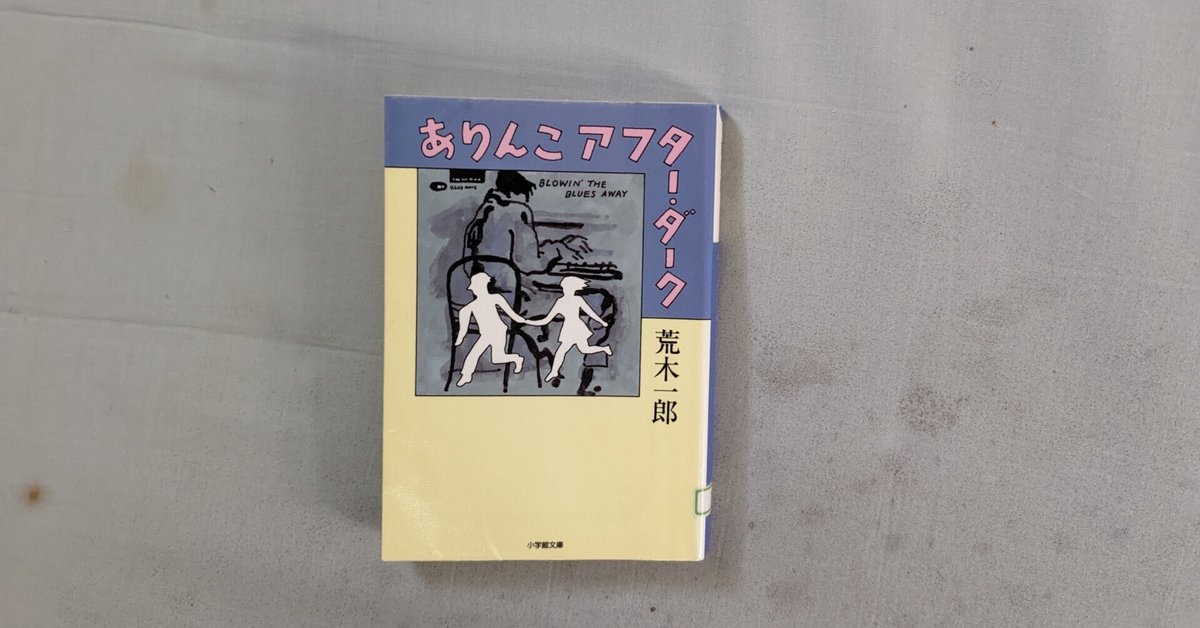
読書日記 荒木一郎・著『ありんこアフター・ダーク』 つかみどころのない人
■荒木一郎・著 『ありんこアフター・ダーク』 小学館文庫
私の数少ない友人の一人が、「荒木一郎がいい、荒木一郎がいい」と会うたびに言う。ちょうど10月末に『空に星があるように 小説・荒木一郎』が、小学館から出版されたばかりだと言う。荒木一郎本人が書く「小説・荒木一郎」というのも、とぼけているが、旧作を2冊、図書館から借りて読んでみた。
荒木一郎って誰だ? あしたのジョー2の音楽?
今時、荒木一郎といっても誰も知らないだろうし、私だって知らない。友人は私よりも数歳年下なのだが、なんで荒木一郎なんだろうか、尋ねたら、テレビアニメの「あしたのジョー2」の音楽が荒木一郎だったのだそうだ。
あしたのジョーのアニメは、連載中の1970年の「あしたのジョー 1」と、十年後の1980年の「あしたのジョー 2」の二つがあって、友人はこの「2」に、いたく感動していた。ちなみに私は尾藤イサオが主題歌を歌っている「1」しか見たことがない。
友人はアニメオタクな人でもあるので、音楽にも注目する。それで荒木一郎と出会ったようだ。「2」の脚本には、「大和屋竺も参加しているんですよ」と言われて、それには私も驚いた。大和屋竺は、70年代は映画、80年代はテレビで活躍した脚本家で、自身の監督した『荒野のダッチワイフ』『毛の生えた拳銃』なんていう映画作品もある。私が知らなかっただけで、アニメの脚本もけっこう書いていたという。
調べてみたら、大和屋竺は、「あしたのジョー 2」のほかにも、「ルパン三世」や「ガンバの冒険」、「天才バカボン」の脚本まで書いていた。肝心の荒木一郎は、「あしたのジョー2」では音楽全体を担当していた。オープニングとエンディングにそれぞれ2つあるテーマ曲の作詞作曲もやり、1曲は自分で歌ってもいる。YouTubeでサントラを聞くと、音楽はほぼジャズといっていい曲だ。そういう能力もあるひとなのだなと、今回、認識した。
荒木一郎は、シンガーソングライターの走りのような人で「空に星があるように」という曲だけを、私は知っていた。紅白歌合戦にも出ているらしい。俳優もやっていたので、私も顔はわかるが、しかし、何に出ていたのかは記憶にない。そんな感じで、私としては、荒木一郎のことは、なんとなく知ってはいるのだが、何をする人なのか、よくわからない人だった。
だいぶ昔の人という認識だったが、今回、経歴を見たら昭和19年生まれだったので、私の想像よりも10歳ほど若かったので驚いた。
ウィキペディアによると、芸能事務所をやっていたり、桃井かおりのマネージャーをやっていたり、小説も数冊出版していたり、将棋やマージャンはプロはだしで、マジックのプロでもあり、手品に関する著作が小説よりも多く出ていた。ますますつかみどころがなくなって混乱するのだが、かなり面白そうな人だと興味がわいた。
YouTubeで本人が歌っている動画をいくつか見た。全然力を入れないで、鼻歌みたいに歌う人だった。女性でたまに囁いて歌う人がいるけれど、男で鼻歌で通す人は、初めて見た気がする。しかし、かっこいいのかどうか、よくわからない。
渋谷を舞台にした自伝的青春小説
さて、小説『ありんこアフターダーク』だ。この小説は、1960年代初頭から、東京オリンピックが始まる前までの間の、主に渋谷を舞台にした青春小説だ。主人公の、17、8歳から、20歳までを描いている。だから50年どころか60年くらい前のハナシだ。
私がまだよちよち歩きの頃のハナシだ。当時の頃を想像してみても、東北で生まれ育った私には、田んぼとか舗装されていない道路が浮かぶばかりで、何の役にも立たない。
しかし、母親の実家が東京だったので、東京には小さい頃からきている。最初の頃は、都電で移動していた。都電は東京オリンピックを境に、地下鉄と取り替わっていったというから、都電があったあの頃が、この小説の舞台なのだと、かろうじて、ちょっとだけイメージが間に合った。
「ありんこ」というのは、渋谷の百軒店に、実際にあったジャズ喫茶らしい。そこに集まった若い人たちが、ジャズバンドを結成して、ダンスパーティーをやって、パーティー券をさばいたり、地元のヤクザと張り合ったり、ハイミナール中毒になったりする。
読み終えて、由緒正しい青春小説という印象を受けた。とてもよく出来た風俗小説と言えばいいのだろうか、当時の東京の風景が浮かんでくるようだった。
なんとなく石原裕次郎の日活映画を思い出させるような内容だったが、石原裕次郎の主演作品は、1950年代後半を舞台にしているから、時期的には、加山雄三の青大将シリーズの前半や、植木等の無責任男が合うことになる。青大将映画も無責任男も、さわやかすぎるが、あんな感じの風俗の不良版をイメージすればいいと思う。
と書いてみたけれど、テキトーだ。私は世代でいえば、角川映画ど真ん中の人間なので、裕次郎も青大将も無責任男も映画館で観たことがない。でもなんとなく、似ているものを思い出した。片岡義男だ。荒木一郎の青春は、渋谷だったけど、これを下北沢や神保町に移せば、片岡義男の青春と重なりそうだ。
この小説の出版は1984年だ。あとがきを読むと、本当にあったことしか書いていないというから、20年前を振り返って書いた自伝小説なのだろう。
大人っぽかった昔の十代
著者は実際に18歳から20までジャズバンドを結成して、ドラマーとして活躍している。当時は、この小説にもあるようにもう一つのバンドを加えて、二つのバンドのマネージメント業務のようなことをして、生活していたらしい。その後、シンガー・ソング・ライターのようなソロ歌手になったり、俳優になったりして、芸能界にデビューしている。だからこの小説に書かれているのは、著者のデビュー前までだ。
著者は、シングルマザーの家庭に育っている。母親は新劇の女優で、荒木道子という人だ。ネットやYouTubeで確かめてみたが、私には古すぎるのか、なんとなくあの人かなという程度にしか記憶にない女優だった。
当時の新劇の女優がどんなもので、そのシングルマザーの家庭がどういったものなのかも、さっぱりわからないし、想像もできない。裕福な家庭のボンボンだったのか、貧乏な家の子供だったのか、よくわからないのだ。どういう経緯で楽器を覚えて、ドラムをたたけるようになったのか、といったことは、この小説では一切描かれてない。しかし、ドラムが叩けて、作詞作曲が出来て、ギターが弾けるくらいだから、そういった方面には恵まれた環境にいたのだと思う。
この小説の主人公は、未成年だ。しかし、酒は飲むし、煙草も吸うし(サラムという洋モクが出てくるのだけど、セーラムのことだろうか?)、ナンパもするし、女の子を平気で捨てるし、ハイミナールという薬物を乱用しているし、地回りのヤクザとも張り合うし、自動車を持っていて運転もしている。女とはこいうものだ、みたいな女性に対する信念を持っていて、語ったりする。早熟というよりも、今の感覚だと30歳ぐらいな気がする。
小説は、バンドを解散して、女の子とも別れて、自分も薬を抜いて、渋谷のハチ公の交番の前で、まだ薬を常用している友人に薬をやめろと迫って殴っているところを、警官に取り押さえられる場面で、終わっている。せつない終わり方だけど、これからまっとうになるぞ、という希望も感じさせる。
著者は何度か留置所を体験しているらしい。それがトラウマになって、閉所恐怖症になったという。そのために、電車にも乗れず、飛行機にも乗れず、徒歩の範囲内でしか移動しない生活を何年もしたらしい。エレベーターは今でも苦手で、階段を使うのだそうだ。そういうことを話している20年くらい前のラジオ音源が、YouTubeにあった。
やっぱりつかみどころがない。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
