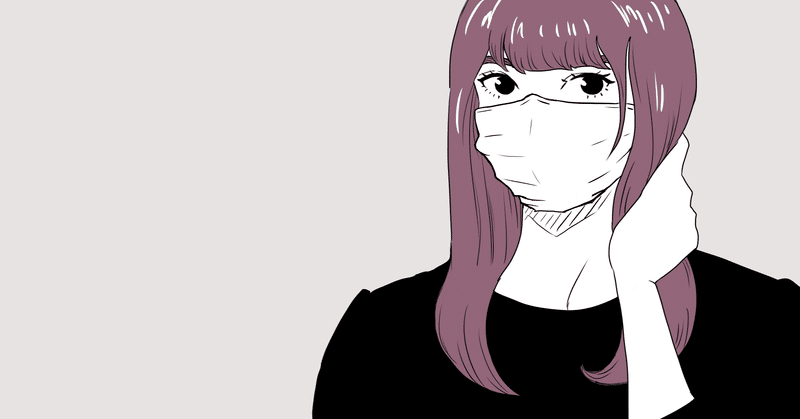
距離と妄想(6300字)
戦う君の歌を、戦わない奴らが笑いもしないし、聞いてもいないし、そもそも近くにいないだろう。
とくに最近は人と人との距離が離れすぎている。人類がようやく適切な距離感を獲得したとも言える。
物理的にも精神的にも。
アルバイト先の同僚である堀川塔花にも近づけなくなった。そもそも僕と堀川塔花の皮膚は1ピクセルたりとも重なったことはないし、重なることは未来永劫ないのだろうし、精神にいたっては宇宙的な規模で隔絶している。
堀川塔花の甘い香りも、堀川塔花が本当は何を考えているのかも、今の僕にはもう遠すぎた。死人のほうがまだ近く感じられる。僕たちのアルバイト先である仕出し屋の店長が自殺したばかりなので、余計にそう思う。
最近は葬式もほとんど執り行われない。しかし亡くなった店長の父親は、そこそこ名の知れた現代芸術家だ。正式な葬儀のかわりに、何やら趣向を凝らしたイベントを行うことにしたらしい。僕はそんなものには近づきたくもなかったけれど、堀川塔花が参列する可能性を思うと行かざるを得なかった。もっと正直に言うと、堀川塔花に対する原始的な暗い欲望が、このまま消えてしまうのが怖かった。決して表現することの許されないその欲望だけが今の僕を生きながらえさせていて、その欲望すら堀川塔花を肉眼で見なくなって以降は薄れる一方だったのだ。
41歳でこの世を去った店長・神崎夏子は実家暮らしをしていた。話には聞いていたが、父親の作品を展示した記念館と駐車場、日本庭園などを備えた広大な敷地だ。
僕が到着した頃には、ほとんどの参加者が駐車場に集合していた。屋敷の門を先頭に、老若男女が2メートルのディスタンスを保って整列させられている。運動会で使うようなテントが幾つか、それと十分な数の椅子が用意してあって、僕の2つ隣には堀川塔花がいた。
ぜんぶで30名ほどだろうか。
やがて最初の6名が中に招き入れられる。残された者はただ待った。みんなSNSを見たりお茶を飲んだりしている。堀川塔花は何もしていなかった。僕も何もしないことにする。
およそ20分で最初のグループが門から吐き出された。みんな晴れ晴れとした顔だ。次は堀川塔花と僕を含む新たな6人が招き入れられる。まるで遊園地のアトラクションみたいだと思う。
広大な庭に通された僕たちは、円形に配置された6つの切り出し岩にそれぞれ腰かける。列が一瞬乱れたのを良いことに、僕は堀川塔花の隣に座った。といっても距離は取られていて、しかも透明のアクリル板に隔てられている。
2か月ぶりに会った堀川塔花は薄汚れた板の向こうで喪服を着用し、正面を見ていた。まっすぐの前髪と白いマスクの狭間で燃える2つの目。まちがいなく堀川塔花だ。
僕たちが座らされている切り出し岩は、おそらくは墓石をイメージしたものだろう。中央に設置された白いオブジェを囲うように、6つの岩が等間隔に並べられている。オブジェは高さ2メートルほどの巨大なものだ。高級スイーツ店のモンブランのような形状で、何を意味しているのかわからない。
魂?
まさか。
さすがに稚拙すぎる。
オブジェのすぐ横には店長の父親が立っていた。この変てこな葬儀イベントの発案者である現代芸術家・神崎隆三。70手前のはずだが、若々しく、還暦のロックミュージシャンみたいな雰囲気だ。喪服ではなく、作務衣とコックコートの中間のような服を着ていた。
神崎隆三のスピーチが始まる。晴れていて、鳥の声が心地よい。現代芸術家のもごもごした言葉はほとんど聞き取れず、環境音に埋もれていた。僕は眠気に耐えながら、たまに視線だけを堀川塔花に移動させる。堀川塔花はアクリル板の向こうで絵画のように動かない。
スピーチが終わる。その直後、やや唐突に何かが始まった。白いモンブランのようなオブジェに映像が映し出されているのだ。亡くなった神崎夏子の思い出のスライドショーだと気づくのに少し時間がかかった。でこぼこのオブジェに歪んで表示されている。おそらく父親の作であろう抽象画や意味不明の映像作品も、突飛なタイミングで何度か挿まれた。薄気味の悪い実験音楽のようなものも流れている。B級ホラー映画のエンドロールみたいな曲だ。
娘の死を自らの芸術作品に昇華しようとでもいうのだろうか。だとしたら悲惨な出来と言わざるを得ない。このイベント自体が『才能の残骸』とでも名付けられるべき作品だった。ただし父親のシンプルな悲しみは、静謐な空間に意外なほどの率直さで解き放たれている。思ったよりずいぶん凡庸で、思ったよりずいぶん善良な人物なのだろう。
ふと気づくと、僕の反対側に座る40代とおぼしき女性が泣いていた。店長の友人だろうか。彼女の他には、涙を流すほどの人はいない。
堀川塔花も無表情だった。ただし、数珠を握りしめる蒼白い手の甲には血管が浮いている。
映像が終わると、6人は順番にスピーチをうながされた。神崎夏子との思い出について。事前に何の告知もなかった。僕はここに来たことを激しく後悔する。2年も働いたバイト先の店長とはいえ、母親とあまり年齢の変わらない女性だ。彼女との思い出はほとんどすべて、仕事に関する簡単なシーンで埋め尽くされている。
自分の番が来ると、僕はまとまりのない謝意を30秒ほど述べることしかできなかった。
次は堀川塔花だ。
堀川塔花は2年前、バイトの面接を受けたときのエピソードを語った。彼女は店長に、「右肩にタトゥーが入っているんですけど、そういうの大丈夫ですか?」と確認したらしい。
店長はこう答えたのだという。
「弁当の配達、水着でやると思ってる?」
斎場に爽やかな笑いが起きた。いかにも店長の言いそうなことだった。だけど僕は笑わない。堀川塔花の右肩にタトゥーが入っているというのは初耳だった。かなり意外な話だ。僕の想像の中の堀川塔花にタトゥーを刻むのは、なかなか骨が折れそうだ。
そのあと5分近くも堀川塔花は喋り続けた。思っていたよりずいぶん親密だったようだ。2人でライブを観に行ったり、箱根に1泊旅行したこともあるという。
バイト先の誰とも親しくしていないように見えた堀川塔花が。
全員のスピーチが済むと、それで僕たちのグループのイベントは終了ということらしかった。意外なほどあっさり追い出されてしまう。事前に危惧していたような奇妙さはあまり感じられず、むしろ簡素な印象の式だった。同じグループにいた6人は軽く会釈をしあって、三々五々に散っていく。堀川塔花も僕を一瞥しただけで、さっさと駅へ向かって歩き出してしまった。その背中に慌てて声をかける。
堀川塔花はゆっくり僕を振り返った。
何もかもが完璧に作動していた。
このような一瞬を、どうして永遠に保存しておけないのだろう。
「なに」とだけ堀川塔花は言う。
「少し話そうよ」と僕は言った。「どこか静かな場所で」
堀川塔花は考えるそぶりを見せた。年齢も近いし、2年も同じ店でバイトしていたのに、僕が彼女にこんな提案をするのは、かなり異様な気がした。それくらい精神的な接点はなかった。
「この近くに喫茶店あったな。そこで良い?」堀川塔花は歩き出す。「とても清潔な店だから」
その喫茶店はおそらく最近テーブルの数を減らしたのだと思う。向かい合わず、隣の席に座った僕たちの距離は十分に保たれていた。ここでも透明のアクリル板が僕と堀川塔花のあいだに立ちはだかっている。僕はもうアクリル板ごしにしか堀川塔花の顔を見ることはないのかもしれない。透明度がそれほど高くないアクリル板を挟んで、堀川塔花の姿は思い出のようににじんでいた。
2人のテーブルにコーヒーが慎重に運ばれる。
堀川塔花は砂糖もミルクもたっぷり入れて、丹念にコーヒーをかき混ぜた。
「店長と仲よかったんだね」と僕は切り出す。
「まあね。付き合ってたから」
「付き合ってた?」
「恋人同士だったって意味」
「店長と?」
「半年前までね」
「知らなかった……」
「言ってないし」
「別れたあとも普通に店で働いてたってこと?」
「まあね。お互い嫌いになったわけじゃないから」
「どうして別れたの」
「他にもっと好きな人ができたから」
「どっちに?」
「もちろん私に」
沈黙。
「まあ、その人のことはもう嫌いになったんだけど。全員が全員に対して無力で無抵抗だった、ってだけの話」
なんだかよくわからない。
そもそも堀川塔花とこんなに長い時間、2人きりで話したことがない。
不思議な気持ちだ。
「最近、家で何してた?」と僕は聞いた。緊急事態宣言の期間中、TVやなんかで散々見た質問だ。何度も何度も、どうしてこんなつまらないことを聞くんだろう……と思っていたのに、言葉に詰まると自分もそんな問いを発してしまう。
「リモートで授業始まってるし。ふつうに忙しいよ」
「ああ。大学生だもんね」
「大学生なのはそっちもでしょ」
「僕は去年辞めたんだよ」
「え、知らなかった」堀川塔花の瞳に初めて興味の色が浮かぶ。「なんで?」
「なんでかな」
「理由はないの?」
「理由はない」
「今は何をしてるの?」
「いくつかバイトしながら……その。生活をしてる」
「生活」堀川塔花はコーヒーを口に含んで、少し微笑んだ。「いいね」
「何もしてないんだけど」
「すてきなことだよ」
「そうかな」僕は少しだけ浮かれた。「タトゥー入れてるって言ってたよね、さっき。右肩に」
「ああ、あれ」堀川塔花は目を伏せる。「嘘だよ」
「やっぱ嘘なんだ」
「本当は脇腹に入れてる」
「脇腹……なんで脇腹?」
「いちばん痛い場所だって聞いたから」
「痛いからって理由で脇腹にしたの?」
「痛さにしか意味はない」
「なんのタトゥー? 龍とか?」僕はおもしろそうな顔をしながら、ぜんぜんおもしろくないことを言った。
「龍? ただの文字だよ。四字熟語」
「天下統一、みたいなやつ?」自殺したくなるほどつまらない発言ばかりが僕の口から放たれる。
堀川塔花は数秒黙って、ゆっくり口を開いた。
「無痛分娩」
「え?」
「無痛分娩、って彫ってる。脇腹に」
「……なぜ?」
「お兄ちゃんを産むとき難産で苦労したんだって。お母さんが。それで私のときは無痛分娩にしたらしいんだけど、めちゃくちゃ楽だったわ、産んだ記憶がないほどに。って毎日言われながら育ったので。それで無痛分娩と入れています。脇腹に」
途中からなぜか敬語で堀川塔花は言った。
「無痛分娩」と馬鹿のように僕は繰り返す。
「夏子さんだけだよ。私のタトゥー見たことあるの」
「夏子さん?」
「店長」
「右肩にタトゥーが入っているんですけど、そういうの大丈夫ですか?」
「弁当の配達、水着でやると思ってる?」
薄くなりかけた僕の欲望がまた少し色濃くなる。
堀川塔花はアクリル板の向こうで、コーヒーをひとくち飲むごとにマスクをずらしたり戻したりしていた。
コーヒーを口に含む瞬間だけ、彼女の輝かしい唇が光に触れる。呼吸が漏れる。喉が動く。
堀川塔花の立体的な挙動が、その大量の情報が、心の中に一気になだれ込んできて、僕はほとんど危機的なパニックに陥ってしまう。
どれくらい無言の時間が続いただろう。
「そろそろ帰ろうか。ゼミの課題が多くてさ」
カバンの中を整理しながら堀川塔花がつぶやいた。
もう会うこともないだろうな……と思いながら僕も立ち上がる。すると意外なことに、「LINE教えてよ」と彼女のほうから言い出した。
「いいの?」と思わず言いそうになって、卑屈さに気づき、慌てて言葉を飲み込む。「いいよ」と答えた。
「もうほとんど会うこともないだろうしね」iPhoneを操作しながら堀川塔花は言う。
彼女の名前は〈堀 川 塔 花〉と1文字ずつ空けた本名でLINEに登録されていた。
「なんでスペース空けてるの?」
「私の名前、分解すると景色みたいじゃない?」
堀 川 塔 花
「たしかに」
絵が描ける。
堀川塔花の気配が見事に溶け込んだ風景画だ。
それから、堀川塔花と一度もLINEのやり取りをすることのないまま、無限のような時間が経過する。
いまも僕は3つのバイトを掛け持ちしている。毎日Netflixを4時間も観て、多少の筋トレをこなし、マクニールだとかフォークナーだとかショーペンハウアーだとかラヴクラフトだとかを少しずつ読み、納得したり反発したりして、ニンテンドーSwitchを所持しておらず、Wi-Fiは弱く、リモート飲みをせず、1日に白米1合と冷凍食品と伊藤園の野菜ジュースなどを摂取し、決して怒らず、いつも静かに笑っておらず、各種SNSを巡回しては、ハッシュタグをじかに殴って砕きたい衝動に駆られている。
連帯するな。
孤独であれ。
無力でいろ。
僕のように。
堀川塔花のLINEのアイコンはたまに変わる。今は堀川塔花がベンチに座っている写真だ。遠すぎて顔はほとんど判別できない。
僕のアイコンは犬。
ふぬけにふさわしい。
ふぬけの行為だ。
妄想の中では毎日のように堀川塔花からLINEが届く。
こないだ私のタトゥー見せてって言ったよね?
そんなこと言ってないよ
言ってないかもだけど、そんな顔してたよ
そんな気持ちの悪い顔はしてない
笑
そういう意味じゃないよ
見たい?
まあ、見せてくれるなら
べつにいいよ、タトゥーくらい
脇腹の?
もうちょっと上まであるんだけど
堀川塔花がぎりぎりまでTシャツをめくる。生々しい脇腹を写真に収める。僕のiPhoneに画像が届く。
暗闇にしらじらと艶めかしい肌。
そこに刻まれた、とても神秘的な4文字。
無痛分娩
僕は笑った。堀川塔花もたぶん笑っている。自分の裸を鏡で見るたびに。そして僕はその裸にたやすく触れる。思いのままにする。
僕の妄想の力は、まだぎりぎり残されているのだ。
世界は遠からず元通りになるだろう。ウイルスは駆逐されるか、世界の景色の一部になる。堀川塔花の名前のように。
権力者たちは巧妙に立場を強化して、今よりもっと支配的になるだろう。弱者救済の言説だけが研ぎ澄まされて、上等のものになり、実際に弱者が救済されることはない。これまでの歴史とまったく同様に。
世界は再び欲望に併呑される。欲望を起点とした構造が、より抜け目なく隠蔽される。猫も杓子もバイオハザードのゲーム実況に手を染めるその裏で、ラクーンシティとリンクするように現実の傷と死も量産される。
もはや誰も彼もが引き金を引いていて、
一切合切がリアリティショーのできそこないだ。
世界の悪辣さと反比例するように、僕の欲望は痩せ細っていくに違いない。どうせ表に漏らすことは許されない、幼稚で悪趣味な妄想だ。堀川塔花との距離は今後一切縮まらず、脳内の堀川塔花もいずれは期限切れで動作不能に陥るだろう。それと同時に、僕の人間らしさのすべても停止するはずだ。どこかで本物の堀川塔花が、僕の想像なんか及びもつかない魅力的な女性である彼女が、自分の人生を切り拓いていくのとは対照的に。
僕の日々は仕事と読書でなんとか体裁を保たれている。不安と恐怖を目につかない場所に放置できている。これはすでに生活とは言えず、あるいはこれこそがまさに生活で、僕はこの生活に取り憑かれたまま生きていくしかない。若さはあっという間に失われ、視力が衰えたあとは何もすることがなくなり、それでも僕の生活は死ぬまで続く。堀川塔花が僕を振り返ったときの完璧な映像は、宇宙のどこかに永遠に刻まれた。アクセス権は僕にしかない。信じてもいない神に祈りながら、僕は堀川塔花の扇情的な肌に彫られた4文字のタトゥーと、堀川塔花の風景画のように清らかな4文字の氏名、その合計8文字を入手できたことに深く感謝している。朽ち果てながら。人生が再起動する可能性の低さに苛まれながら。今日もどこかで戦う誰かの歌に、耳を澄まして聞き入りながら。
