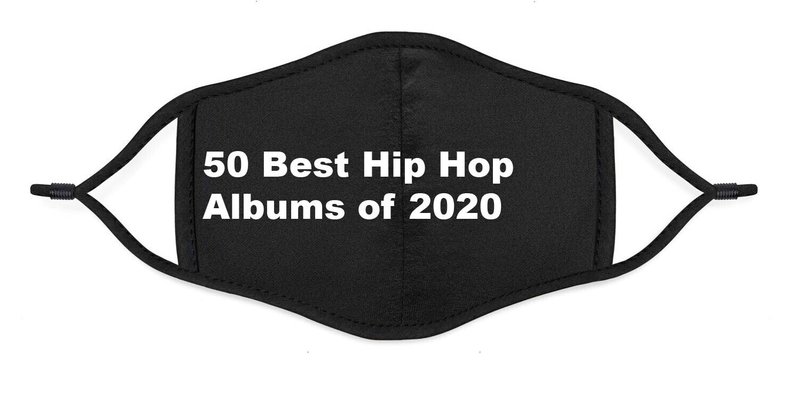
50 Best Hip Hop Albums of 2020
コロナ、BLM、そして人気ラッパーの死など悲しいニュースが続いた今年も、ヒップホップは素晴らしい作品をたくさん届けてくれた。その中から選んだ50枚の珠玉のヒップホップ・アルバム。
楽曲単位ではブルックリン・ドリル勢、UKドリル勢もたくさん聴いたけど反映させられず。
順位付けはなく、リリース日の順。一覧表(見出し)の下に各レビューがズラッと並んでいます。ジャケ写ではなくYouTubeを貼ったのはすぐに聴けるようにするためなので、ぜひ聴きながらどうぞ。
釈迦坊主『NAGOMI』(1.1)
これ元旦に出ていたのか。完全に忘れていた。この最後の「Alpha」がとにかくすごい。今年はいろんな客演にも呼ばれるようになり、そのどれもでその曲を釈迦坊主色に染めていた。なんだか今すぐにでもパッと引退してしまいそうないい意味での「軽さ」「危うさ」みたいなものが彼の音楽からは感じられて、いつもひりひりさせられる。裏方に回っちゃいそうな感じはすごいある。
Awich『孔雀』(1.11)
8月には『Partition』でユニバーサルからメジャーデビューした沖縄出身のラッパー。しかし1年を通じてよく聞いた、もはや流行語大賞と言ってもいいパンチライン「馬鹿ばっかだ全く」を生んだ「洗脳」を収録した今作はYENTOWNからの最後のリリース、そして彼女の名を飛躍的に広めた前作『8』の続編的な作品ということでより重要であるような気がする。前述の「洗脳」、そして次のねぶた囃子をサンプリングした「NEBUTA」(青森県民としては上がらずにはいられない)、Awichの小気味よい自由自在のフロウとChaki Zuluの挑発的なトラックが一体になった「Open It Up」、NENEと連帯したプッシー賛歌「Poison」、JP THE WAVYとのタッグ「Bloodshot」が連発される前半の流れは特に完璧。
Lunv Loyal『ZERO』(1.15)
デラックス盤が出るまでうっかりここに入れそびれるところだった、年初に出た大傑作。バンギンなビートの上をフィギュアスケーターのように時にぴょんぴょんと軽やかに、時に流れるように滑走していくLunv Loyalのフロウ。だがその表情は「真実を閉じ込めるこの国で/別に嘘つきがいても不思議じゃねえ」と鋭い。ビートもいちいちかっこいいが、「Spanking」の酩酊感は病みつきになること必至。
Mac Miller『Circles』(1.17)
遺作となった2018年の『Swimming』も「この続きが聴きたかった」と思う傑作だったが、その続きである本作を聴いてもなお「この続きが聴きたかった」と思う。とても暖かい手触りのこの作品を聞けば、同じ部屋の中で彼が歌ってくれているような親密な感覚が立ち上がり、その度に彼の不在を思い出す。それがとにかく悲しい。
D Smoke『Black Habits』(2.6)
Netflixのコンテスト番組『リズム+フロー』の初代優勝者が満を持して発表した「デビュー・アルバム」。現在35歳の彼はこれまでも裏方として着実なキャリアを築いてきた。だが彼はこのアルバムであくまで等身大な自分、そして自分を取り巻く環境を飾らずに音楽に封じ込めた。かの『good kid, m.A.A.d city』の続きを聴いているような、感動的な1枚。
Denzel Curry & Kenny Beats『Unlocked』(2.7)
Wu-Tang Clanを否が応でも想起させるような煙たいビートにDenzel Curryの叩きつけるようなラップがとにかく気持ちがいい。聴いていてエネルギーが爆発しそうになった作品だ。流出したファイルを追い求めて電脳世界でいろんな画風で描かれながら冒険するMVも素晴らしい。
Lil Baby『My Turn』(2.28)
今年は多くの客演やシングル曲もリリースし、1年中彼のヴァースを聴いていたせいでこのアルバムの記憶が薄れていた。しかしいま聴き返してもやはり乗りに乗っているラッパー特有の「最強モード」のような勝ち誇るオーラがプンプンに出ている。これほどまでに売れていて普段はあまりそういうことを歌わない彼がプロテスト・ソング「The Bigger Picture」を発表したことは、彼が本当に地に足のついたギャングスタ・ラッパーであることを証明した。いくら感謝してもしきれない。
I can't lie like I don't rap about killing and dope
But I'm telling my youngins to vote
殺しや薬についてラップしていない、なんて嘘はつけない
でも若い奴らには投票に行けと言う
(「The Bigger Picture」)
CHIKA『INDUSTRY GAMES』(3.3)
『XXL』誌が選ぶFreshmenの候補に選ばれていて知った。めっちゃいいじゃん!と思いながらこういう「温かい」音楽にはここ数年のXXL Freshmenは厳しいからな…と思っていたら見事最後の12人にも選出。サイファーでは犬を抱えるというユニークすぎるスワッグを発揮してて最高だった。寡作なのが少し残念な人ではあるが、来年以降一大傑作を残しそうな予感…。
Lil Uzi Vert『Eternal Atake』(3.6)
最も大衆に支持されているものが最も前衛的なことだってあるわけだけれど、Lil Uzi Vertはその好例だ。何百といるマンブル〜エモ・ラッパーの中でも彼がずば抜けているのはビート選びのセンスだ(それが彼一人に帰属するものなのかどうかは不明だが)。彼が乗るビートはどれもオブスキュアだ。奇妙だ。ヘンだ。だからどうしても彼の音楽は他の惑星からやってきたように聞こえる。それでそのままメインストリームで大人気を博しているのだから恐ろしい。
R.A.P. Ferreira『purple moonlight pages』(3.6)
聴き心地偏重主義の風潮には頑として反対のぼくであるが、このアルバムは圧倒的聴き心地の良さでハマりにハマった。哲学的で難解なリリックはほとんど読み込んでいない。ときおり見せるプログレッシヴな展開もR.A.P. Ferreiraは飄々とクールに乗りこなしていく、その快感が18曲、50分の間絶えることなく持続していく。ジャズ・ラップの新たな傑作としてずっと聴かれ継がれていくだろう。
Clear Soul Forces『ForcesWithYou』(3.13)
デトロイトの4人組のラスト・アルバム。90年代初頭の、A Tribe Called QuestやSouls of Mischief、ひいてはDe La Soulなどの「ニュースクール勢」に多かった復数MCを擁するユニットのあの感じが現代に蘇ったような、まるでカルピスウォーターみたいな爽快感が持ち味のめちゃくちゃいいラップ・アルバム。解散作っていうのもこの「青春感」に一役買っているのかもしれない。
Moment Joon『Passport & Garcon』(3.13)
リリースは3月13日。1月にリリースされたGEZANの『狂(KLUE)』と同じく、コロナなんかなくたってこの国にははじめから疫病が蔓延していたのだという現実を叩きつける。ネトウヨの陰謀論にまるまる乗っかってレイシストたちを嘲る「KIMUCHI DE BINTA」、Joyner Lucas “I'm Not Racist” にも似た雰囲気で対話をする「Home」、そしてそこから完膚なきまでに反撃する「CHON」の流れは圧巻。メッセージ性ばかりに目が行きがちだが、ベテランMCのHUNGERすらいち「キャスト」として配置し、アタマからケツまで隙のない構成で一大絵巻を描き出した手腕は、大きく影響されているであろうKendrick Lamarの『Good Kid, M.A.A.D City』に匹敵。<通天閣よりもでっかいチンチン>で始まり<スカイツリーじゃなくて君が居るから日本は美しい>と締めくくられるこの作品は、間違いなく日本のポピュラー音楽史に残る“金字塔”である。
なみちえ『毎日来日』(3.13)
まずはタイトルが優勝。どこか飄々とした佇まいやアティテュードにユーモアとシリアスをいとも自然に行き来するリリック、そしてオールドスクール的とも形容したくなる押韻スタイル。NHKのBLMデモ解説動画にもいち早く抗議の意を表明し、Zoomgalsの一員としても七面六臂の大活躍。様々なロールを一身に引き受けている(引き受け「させて」しまっているのはぼくも含めた社会全体である)彼女だが、本業である芸大生としての本分は最後の「あ1」で体感すべし。
Zebra Katz『Less Is Moor』(3.20)
ブルックリン・ドリルの興隆が目覚ましかった今年は、イギリスを経由したジャマイカのDNAを色濃く感じる1年だった。ジャマイカ系移民のニューヨーク出身のMC、Zebra Katzのこの作品は、グライム、ドリル、レゲエとも違い(またそのすべてを合わせたものとも言える)、インダストリアルなベース・ミュージックを基調としたトラックでバッキバキに染め上げられた異形の傑作。どこを向いても漆黒の闇、こんな音像で踊り明かす…そんな夜は今年、我々に与えられはしなかった。
Showy & DJ JAM『RED STONE』(3.25)
地味に感じてしまうほどに洗練された、余白はあるが隙のないヒップホップだ。
Knxwledge『1988』(3.27)
言葉少ななアルバムだ。確かにラッパーやシンガーが参加している楽曲は少ないものの、ソウル〜R&Bのサンプリングが主な構成要素になっているので歌声は多く含まれている。それでも言葉少なに感じるのは、Knxledgeがその歌声すら楽器・ツールとして完全に支配下においているからだ。言葉少なながら人がそこにいる感覚に貫かれているのは、それはKnxledgeの魔法のおかげである。
JP THE WAVY『LIFE IS WAVY』(4.8)
「Tokyo Drift Freestyle」での大スター感も半端なかったJP THE WAVY。思えば「Cho Wavy De Gomenne」が出たときにこれほどまでに息の長いラッパーだとは正直思ってなかった。ごめんなさい。あれから3年以上経つが、勢いが全然止まらない。このアルバムでは「興味がない」と繰り返し口にしている彼だが、彼のラップはいつ聴いても本当に混じりっけなしのWavyで、それがいい。
ACE COOL『GUNJO』(4.17)
「夢や希望のことは歌わない」と宣言する「REAL」で始まるこのアルバムで彼は自分の醜い内面をさらけ出している。そして最後の「27」「東京」「FUTURE」で再び歩みだす彼の姿に希望を見る。間違いなく日本トップレベルで上手いラッパーなのに無視されているのは全く理解できない。
Westside Gunn『Pray for Paris』(4.17)
今年はGriselda Recordsの1年だったとも言えるだろう。昨年11月の『Griselda』を皮切りに始まったこの快進撃は、Westside Gunnが3枚、Conway The Machineがアルバム1枚、コラボ作2枚、Benny The Butcherがアルバム1枚、さらに新人=Armani CaesarやBoldy Jamesのアルバムなど、とめどないリリース量でその勢いは天井知らずだった。その合間にも大量の客演仕事もこなし、ヒップホップ・メディアで彼らの名前を見ない週はなかったように思われる。正直どれも似た味(しかしクオリティは一定以上!)だからどれを選ぶかとなると個人の好み。というわけでWestside Gunnのこちらをば。
Polo G『The GOAT』(5.15)
今年のLil Durk再評価の機運もPolo Gがいなかったらなかったかも知れない。XXL Freshmenに文句なしの選出、あちこちに客演で引っ張りだこ、シカゴ・ドリルという枠を超えスター中のスターへ。そんな勢いがタイトルにも現れた本作を締めくくるのは、2 Pacの「Changes」と同ネタでアフリカン・アメリカンに対するポリス・ブルータリティを告発する「Wishing For A Hero」。44小節ノンストップのロング・ヴァースは彼なりの覚悟・責任感が現れた最も美しく勇気づけられる瞬間だった。
Medhane『Cold Water』(5.26)
これとMIKEの『Weight of the World』は、自粛期間の閉塞感とサウンド的にもリリック的にもビシっとマッチして、心の癒やしとなった。下半期はもっぱらチャラくて悪いヒップホップに興味関心が向いていたので、今回久々に聞き直してみて音響のエッジの立ち方に戦慄を覚えた。この ”NO CAP” のスネアの処理とかすごい。
Freddie Gibbs & The Alchemist『Alfredo』(5.29)
とにかく渋い。あまり開かれた感覚はなく、ホモソーシャル的・マッチョイズム的な側面もなくはない作品だが(だからこそグラミーにノミネートされているのも違和感)、この音楽の醸し出す渋さがもたらす快楽には抗いがたいものがある。The Alchemistは他にもBoldy JamesやConway The Machineとのコラボ作や、インストのビート・テープも何枚か出していて、どれも良かった。
Killah Priest『Rocket to Nebula』(5.31)
もともとはWu-Tang Clan周辺のクルーメンバーだったベテラン・ラッパー。この作品で初めて聴いたからこれまでどういう音楽をやっていたのかはよくわからないが、このアルバムはとにかく異形のヒップホップ・アルバムだ。ほとんどドラムレスでアンビエント風のトラックに、スピリチュアルで壮大なリリックが滔々と、スポークン・ワードのように乗せられる。Sun Ra級のメディテーション・ミュージック。
Run The Jewels『RTJ4』(6.3)
5月25日、ミネソタ州ミネアポリスで、一人の警官の膝が8分46秒もの間ジョージ・フロイドという青年の首を圧迫し続け、やがて死に至らしめた。それに対する怒り、抗議、そして美しく力強い連帯がものすごいスピードで世界中を駆け巡った。それを受けてKiller MikeとEl-Pの二人はアルバムのリリースを前倒し、6月3日にリリースされたのが本作だ。アルバムの本流はとにかく強烈なトラック群と二人のラッパーによる痛快なブラガドーシオ(ホラ吹き話)であるが、「ドルの札に書かれた奴隷主たちを見てみろよ」とがなる「JU$T」がどしんと響く。
ralph『BLACK BANDANA - EP』(6.10)
俺いる場所 水面下 But
上下ないとすりゃどうだ?
10月にはAbema TVの「ラップスタア誕生」シーズン4で優勝。衝撃的な低音ボイスとグライム〜UKドリル基調のビートを武器に、今年1番の衝撃を日本のヒップホップシーンにぶちかましたralph。「俺ならできるmakeするシーン」、その言葉通り来年以降さらなる台風の目になること間違いなし。準備してるぜ手のひら返し。
BandGang Lonnie Bands & Band Javar『The Scamily』(6.18)
令和のギャングスタ・ラップはサイバー犯罪だ!クレジットカード詐欺、個人情報抜き取り、スマホ1つで簡単に稼げる時代!Teejayx6が先鞭をつけた「Scam Rap(詐欺ラップ)」がデトロイトを中心に花開いている。性急なビートの上で詰め込むようにほぼしゃべるようにフロウするそのサウンドは荒唐無稽で新しすぎて、不思議な中毒性がある。歌詞はサイテー、音質も決して褒められたものではないが、憎まれっ子世にはばかってナンボ、スリの銀次が今日もあなたの耳元に現れる。
MIKE『Weight of the World』(6.21)
昨年の『Tears of Joy』も大傑作だったMIKE。本作も基本的にやっていることは変わらず、自身のプロデュースによるサイケデリックなループの上で滔々とラップしていく。それでもやはりぼくの耳が新鮮な驚きと喜びに包まれるのは、やはりEarl Sweatshirt『Some Rap Songs』の余震が今でも続いているからだろう。
Apollo Brown & Che Noir『As God Intended』(7.10)
38 Spesh、Flee LordなどのNYアンダーグラウンド勢とのコネクションも強いNYはバッファロー出身の女性ラッパーが、デトロイトのプロデューサー=Apollo Brownと組んだタッグ作。LocksmithとのタッグEP『No Question』が素晴らしかったこともありApollo Brown目当てで聴き始めたらChe Noirのラップも切れ味抜群で素晴らしかった。「暴力の中で育った」というそのライフスタイルをラップしながらも、「But do it twice as better 'cause you got the skin of a slave(=人の二倍やらなきゃいけない、だって奴隷の肌をまとっているから)」などレイシャルなトピックにも切り込む。
Blu & Exile『Miles: From an Interlude Called Life』(7.17)
オールドスクールなヒップホップでは最高峰の出来であるだけでなく、20曲入り95分の長尺を飽きさせることなく一気に聴かせる。アルバムというフォーマットを最大限に活かしたからこその快挙だと言える。アフリカ系の偉人たちの名前を列挙していく9分超の “Roots Of Blue” に胸が熱くなる。“blue” という色がテーマになっているものが多いが、“color (of skin)” そのものが主題となっていると言っていいだろう。
chelmico『MAZE』(8.26)
前作『POWER』にあまり乗れず一度は見限った。本当に申し訳ない!「Easy Breezy」も随分攻めた曲ではあるが、白眉は長谷川白紙を招いた「ごはんだよ」。ぶっ飛びまくったトラックにつられて、2人のラップもめちゃくちゃキレキレだ。凡百の聴き心地が良いだけのポップ・ミュージックに落ち着かず、こういう挑戦を続けていってほしい。
LEX『LiFE』(8.26)
今のLEXには全盛期のラッパーしか纏えないオーラが見える。だからこそこんな何でもありやりたい放題のアルバムですらしっかり彼一色だ。このまま、このまま行けよ。
Vritra『Sonar』(9.4)
Tyler, the Creator率いたOdd FutureからはFrank Ocean、Earl Sweatshirt、Sydなど今のポップ・ミュージック・シーンの中心を担うメンバーが数々排出されたわけだが、当然それ以外のメンバーたちも各々のキャリアをしっかりと歩んでいる。と書いておいてなんだが、このVritraというラッパーのことは全く知らなかったので、「こんな物を隠していやがったか!」と沸き立った。今作で13枚目のアルバムということで、音楽への並々ならぬ愛情を感じる。R.A.P Ferreiraとも通じるような、ジャズ・ラップの良作。
『Oll Korrect: OK TAPE - EP』(9.26)
中野HeavysickZEROで行われているヒップホップイベント「Oll Korrect」のコンピレーションEP。梅田サイファーの次はこっちだ!というのは安易な発想としても、今年はこういうクルーものの作品が国内ではあまりなかったように思う(コロナのせい?)。17人のラッパーが並ぶタイトル曲に忘れかけていた「パーティー」という概念を思い出させてもらった。
Sa-Roc『The Sharecropper's Daughter』(10.2)
活動歴はかなり長い彼女の、Rhymesayerからは初となるアルバム。自身の父親が実際に小作人として働いていたことから、父親と自分、そして合衆国の歴史を重ね合わせていく。スキルも一級品で、「私は女性の形をしたエーテルである」というリリックから漂う全能感が放つ説得力にひれ伏す1枚。
21 Savage & Metro Boomin『Savage Mode II』(10.2)
このアルバムについては、冒頭のモーガン・フリーマンの語りがすべてを言い表している。
崇高な理想を掲げる偉大な人物たちは何百、何千マイルという距離で隔てられることが多い。そしてたとえ同じ場所に生まれたとしても、何年も、何世代もの隔たりがあるものだ。しかし、何故かそんな2人が同じページに登場することが稀にある。そんな2人が同じ目標、同じ結果を目指してその力を合わせるとき、2人は1つの存在になる。単純に2人の特性を合計するのではなく、どうにかしてその2つをかけ合わせてしまうものだ。
Black Thought『Streams of Thought, Vol. 3: Cane and Abel』(10.16)
今年は客演も数多くこなし(そして参加作が他にも多数このベストには入っている)、最近ではElvis Costello、DJ Premier、T-Bone Burnett、Nathaniel Rateliff、Cassandra Wilsonとのスーパーグループ=Dopamineの存在を発表するなど、とにかく精力的だったBlack Thought。来年もひとつ、よろしくおねがいします。
clipping.『Visions of Bodies Being Burned』(10.23)
ラップはトラックに合わせるもの、確かにそうだがその「確かに」を疑ってみると、clipping.のような音楽が生まれる。トラックがラップに合わせる、いや、ラップとトラックが人馬一体となって駆け抜けていく。エクスペリメントでありながらわかりやすい派手な仕掛けも多く、エンタメ性も高い!
Busta Rhymes『Extinction Level Event 2: The Wrath of God』(10.30)
数々の客演仕事もこなし、この傑作アルバムもリリースし、今がキャリア絶頂のBusta Rhymes。「*and everyone liked that*」というミームがピッタリの、誰もが幸せになった大復活劇。ちなみにこの「Look Over Your Shoulder」は2020年にKendrick Lamarが発表した唯一のヴァースである。1年に1ヴァースでもキングの座は揺るがない。来年はアルバムが出たらいいな。
JPEGMAFIA『EP!』(11.6)
1年を通じてシングル曲を散発的にリリースしていたものをまとめた作品のため、ここに入れるべきかどうか迷ったが、曲のタイトルが全て大文字で「!」が使われているのはトランプのツイートをバカにしてとのことで入れることを決意した。というのは冗談として、相変わらずやりたい放題のエクスペリメンタル・ヒップホップで素晴らしい。
Power DNA『ANDHI - EP』(11.10)
正当な注目・評価を受けていないラッパーだ。10月に出していたアルバムも良かったが、その後リリースされたこのEPはビートの面白さが格別。未チェックなら要チェック。「帰るもクソもねえ/ここが家、舐めてんじゃねえ」と叫ぶ「外人」も重要だ。
Salaam Remi『Black On Purpose』(11.11)
今年のBLMデモでよく目にしたフレーズを素晴らしい形で楽曲にした「No Peace」、1939年に発表されていたプロテスト・ソング「奇妙な果実」やJames Brownのカバーも収録、さらにStephen Marley、Chronixx、Super Catなどレゲエ畑からもゲスト多数。ヒップホップ〜ソウル〜ジャズ〜ファンク〜レゲエを横断する、タイトルが示すとおりのブラック・エンパワーメント作。的確なプロダクションとゲストの人選も含め、手放しの称賛と連帯を表明したい。
Megan Thee Stallion『Good News』(11.20)
Cardi Bとの「WAP」は共和党のジジイどもすら怯え上がらせた。この「Body」でも自分の身体を誇り高く歌い上げる。「自分が自分であることを誇る」と宣っていたQダブよ、お前これ聴いてるか?そしてそんな記念すべきデビューアルバムの1曲目をディス曲で飾らせたTory Lanezにも中指を。
何度でも言うが、女性の体は女性のものだ!!!!!!!!!!!!!
Juicy J『The Hustle Continues』(11.27)
Jin Dogg『3rd High "起死回生" (mixed by DJ BULLSET)』(11.30)
既発曲も含む全13曲をDJ BULLSETがノンストップでミックスした1枚。ブーンバップからドリル、更にメロウなエモ・ラップまで実は何でもこなせるオール・ラウンダーだということがよく分かる1枚。「俺のShow 差別なしみんな殺す」のようなラインに隠された政治性含め、全く死角のないラッパーだ。
MC松島『たひ』(12.1)
イベントが次々に中止になる中、自身のYouTubeチャンネルで精力的に動画をアップしていたMC松島は日本のヒップホップ界でぼくが最も信頼しているオピニオンリーダーの一人である。今年一番「応援」「支持」という気持ちを持ったラッパーは彼だと思う。そんな彼の動画の中からラップの楽曲を中心にまとめた作品集が出たので、こうして年間ベストに入れさせてもらう。特に最後の「私は息ができない」はジョージ・フロイド殺害事件から6日後に公開された動画で、かなり参っていたぼくはこの動画にどれだけ励まされたことか。「MC松島」としての活動がこれで終了、とのことだけど、これからの活動も楽しみ。
Tobe Nwigwe『Cincoriginals』(12.13)
BET Awardでのエネルギッシュなパフォーマンスが素晴らしくて知ったヒューストンのラッパー。警官が間違った家に押し入ったために射殺されたブリオナ・テイラーについてラップした楽曲がきっかけで今年一気に注目を集めた。それはそのメッセージのみならず、Comtemporary Art Museum Houstonにて撮影されたヴィジュアル・アートの美しさも込みであろう(彼と彼のチームによるプロデュースのようだ)。「俺はお前らラッパーにとって父親のような存在だ」と歌うこの「Father Figure」は一見すると家父長制的とも取れるかもしれないが、それは白人と比べて圧倒的に高いアフリカ系アメリカン人の収監率と、それに伴う母子家庭の多さを踏まえてのラインだろう。アルバムの大半を手掛けるプロデューサーのLaNell Grantは女性で、妻のFATを始め多くのゲストも参加、コレクティヴが作り上げた開かれた作品という雰囲気が素晴らしかった。
Kamui『YC2』(12.19)
「アトロク」のサイバーパンク特集の中で、「みんな割れているスマホを使っているが、あれがサイバーパンクだ」みたいなことを言っているのを聞いて膝を打った。サイバーパンクは未来の話ではない、今の話である。ボカロや音声読み上げソフトを用いて作られたこの作品は、明らかにこの作品のジャケットになっているArca『KiCk i』やGrimesなど、同じく現在の音楽でありながら未来を志向するアーティストを連想させる。正直「体の拡張」というテーマとボカロ、「Tetsuo」という曲名から連想されるAKIRAリスペクトなどは食傷気味なモチーフではあり、決して時代の先取りをしたような作品ではないと思うが、それでも作品のクオリティとシーンの中でのユニークさにあっぱれ。
Campanella『AMULUE』(12.23)
19年9月に出したシングル「Douglas Fir」は日本語でのラップの技術を塗り替えるくらいの凄まじい1曲だった。それから1年が経ち、ようやくリリースされた4年ぶりのアルバム。日本語の音節を自由自在に接着させることで生まれるグルーヴが、引き続きRAMZAを中心としたプロデューサーによるトラックの上を誰よりも流麗に駆け抜けていく。
感染するmind追い払って歌い出したいtonight
ERAが参加したクラブ賛歌「Minstrel」のこの一節がこの1年を象徴している。
Lil Darkie『Swamp』(12.25)
某雑誌がMachine Gun Kellyが今年リリースしたポップ・パンク作を年間ベスト・アルバムの一つに挙げていたが、やれやれ、全くわかってないなと思った。パンク×ラップなら間違いなくLil Darkieがベスト・オブ・ベスト。他に類を見ない、Denzel Curryのハードな部分だけをひたすら蒸留したかのようなスタイルはパンキッシュなラップの一つの完成形だ。6ix9ineを(あえて)パクったようなジャケも最高。
Playboi Carti『Whole Lotta Red』(12.25)
Tyler, the Creator「EARFQUAKE」を聞けばわかるが、Playboi Cartiは何一つ何を言っているのかわからないのに、完璧にビートに声を乗せる。その刹那のひらめきのような、言語と感情の狭間のような、胎動のようなきらめき。たしかに冗長(24曲63分)ではあるが、決して「現行の流れに沿っただけの作品」ではなく、どう聴いたって意味のわからない、とんでもない作品だと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
