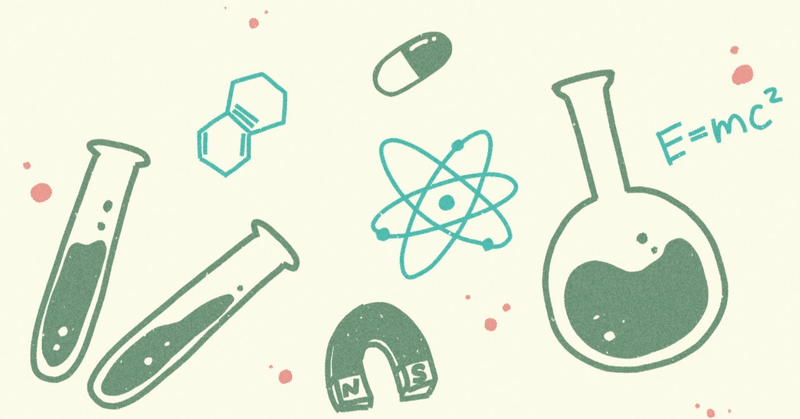
新規事業の探索を組織的に取り組む
6月1日の日経新聞で、「日本企業、戦略不全からの脱出(下) 競争と探索、比重見極めよ」という記事が掲載されました。同記事の一部を抜粋してみます。
企業が持続的に成長するには、既存事業の生産性を向上させて競争に勝ち、シェアの拡大を狙う競争戦略と、新たな領域を探索・開拓する探索戦略の両方が必要になる。難しいのは、両者を遂行する能力は根本的に異なるという点にある。
前者に求められるのは目標に向かって既存技術や製品を磨き上げる能力だが、後者に求められるものはどれが有望な技術領域なのかを探索し、見極めて用途を開発する能力であり、様々な試行錯誤と学習を伴う。前者は成果がすぐ出てくるが、後者は長い時間と継続的投資が必要であり、ある種の執拗さが要求される。
性質が違うこれら2つの活動を、企業内でいかにしてバランスよく遂行できるかが持続的成長のためには重要である。そのための一つのカギは、主力製品と探索製品の製品代替性に着目することだ。製品代替性とは、探索活動が生み出す成果が主力製品の需要や売り上げを代替する程度をいう。代替性が高い場合、探索から生まれる製品は主力製品の需要を減少させ、両者は共食いの関係になる。
例えばデジタルカメラの開発は、フイルムカメラ需要を大きく減少させ、両者は共食いの関係になっている。同様に、自動車産業で今後加速するEV(電気自動車)とガソリン車は製品代替性が高く、EVの台頭につれてガソリン車の需要は大きく減少する。
製品代替性が高い場合、探索が成果を生むほど既存事業で蓄積した技術やノウハウ、そして人材の価値は毀損するため、探索部門と既存部門の間にあつれきと対立が生まれやすい。それをいかにして回避できるのかという点こそが、製品代替性が高い場合の経営の要諦と言ってよい。対立を回避するためには部門の組織的分離が有効だが、近年の仏自動車大手ルノーによるEV事業を分社化する動きは、その観点から理解することもできる。
既存の事業を深めていく「深化」と、新しい事業を開拓する「探索」を同時に推進することは、「両利きの経営」としてその概念の大切さが叫ばれています。
先日も、ある企業様でお話した時に、社員の評価制度について話題になりました。同社様では、いわゆる目標達成度で社員を評価する仕組みを導入しています。それ自体は必要だと認識しているものの、立てた目標に対する達成度で評価されてしまうと、無難に達成できる目標に終始してしまい新しいことに挑戦しなくなるのが懸念されるということでした。同企業様では、目標の難易度も評価の対象とし、難易度の高い目標は達成できなくても相応の評価を与えるルールを導入しましたが、その効果の確認はこれからになります。
ひとつの部署やひとりの人に「既存」と「探索」の両方を求めていくことも、有益な取り組みです。しかしながら、成果の確実性が高い既存活動と、どうなるかわからない探索活動を同時に求めると、既存活動を優先させたくなるのが自然です。上記分社化の例は、組織によって役割を分けて探索活動に専念する仕組みにすることが、有力な方法のひとつであることを示しています。
その際にポイントのひとつとなるのが、既存活動に向いている人と探索活動に向いている人と、人によって異なることです。1のものを2や3に発展させることが得意で好きな人が、0から1をつくるのが得意で好きとは限りません。逆に、前者は好きではないが後者は好きな人もいます。
ある企業様でも、既存事業で成果をあげてきたエース社員を、その手腕を見込んで新規事業の専任担当にしたところ、まったく力を出すことができずつぶれかけてしまったということがありました。人材活用で留意したい視点だと思います。
他のポイントとしては、評価で適切な時間軸をもつことが挙げられます。同記事では次のような指摘もあります。(一部抜粋)
他方、製品代替性が低い場合、探索の成果が主力製品の需要減少につながることはないので対立は生じにくい。むしろこの場合、両者を補完しあう適切な仕組みを構築できれば、相乗効果を生み出し価値を増大させられる。
例えば化粧品の開発は写真フイルムの需要を減少させることはなく、製品代替性は低い。富士フイルムは新たな化粧品事業の探索に際して、フイルム事業で蓄積したコラーゲン技術などを転用して成果につなげた。製品代替性が低い場合は、部門間の経営資源の共有を促進して、相乗効果を生み出せるのかが経営の要諦になる。このように、製品代替性の程度に応じて解くべき経営課題が異なる。
さらに探索戦略の遂行に伴う大きな課題は、探索の誤検知をいかにして回避するかだ。ここでいう誤検知とは、探索途上の技術の真価を見抜くことができずに、誤って途中で中断・撤退してしまうことを指す。
例えば、米インテルの開発した世界初の演算処理装置が、パソコンの基幹部品としての役割を見いだすまでには約10年を要した。探索領域の革新度合いが高ければ高いほど、技術と市場の不確実性は高まり、成果が出るまで長期の粘り強い投資を要する。その間の収益貢献はほとんど皆無なために、常に中断圧力にさらされるという自然な傾向を持つ。
例えば経営破綻した米コダックは、富士フイルムよりも早く1980年代中ごろから医薬品関連領域の探索を開始していたにもかかわらず、事業化につなげることができずに途中で撤退した。時間とコストがかかる医薬品の探索よりも、すぐに収益につながるフイルム事業へ資金を振り向ける力が働いたからである。
記事では、富士フイルムの同分野での探索の開始が、実はコダックよりも遅かったことが紹介されています。しかし、長期的視野で粘り強く探索活動を継続し、その後事業化させ今に至っています。同社のようにできれば理想ですが、なかなか難しいことだと思います。新規事業の探索よりも既存事業の改良・改善のほうが、はるかに短期間で収益につながりやすく、経営資源の配分で優先されにくいためです。
長期的視野で探索活動を重視するというビジョンを公式に明言し、評価や組織マネジメントでそれを裏付ける仕組みをつくって取り組みを常態化させることが必要だと思います。そして、長期的な投資が可能になるだけの既存事業の収益性を高めておくこと、手元資金の厚みを高めて維持するなどの財務マネジメントが求められます。
さらにポイントとなるのが、外部資源の活用です。同記事では、次のような紹介もあります。(一部抜粋)
誤検知を導くもう一つの要因は、企業の認知限界に起因する。企業単独の評価能力には限界があるため、探索技術の潜在価値を見抜くことができずに途中で放棄してしまうことが往々にして見受けられる。広く知られた例では、米ゼロックスのパロアルト研究所(PARC)が、コンピューターの操作性を各段に向上させるGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)技術を発明したにもかかわらず、真価を見抜くことができずに放棄した例が挙げられる。
建設機械大手コマツが躍進する原動力になった、遠隔監視システム「コムトラックス」もそれに近い。その真価を最初に見抜き、曲折を経た開発の続行を経営陣に促したのは外部の建機レンタル企業だったのである。レンタル事業を行っている企業は、貸し出した建機の遠隔監視ができる点に大きな価値を認めたのだが、当時のコマツにとっては想定外の用途だったはずだ。
企業の認知限界を超えるための方策は、内部で閉じられた評価プロセスではなく、広く外部の視線を取り入れる仕組みを構築することだろう。自らの知を外部の目に積極的にさらすオープン化の活用は、その一つの手段である。
上記にあるように、探索活動によって得られている可能性に気づく能力が、組織内の人材だけでは限界があることが挙げられます。加えて、事業計画や事業活動で「深化」だけではなく「探索」がどれぐらい行われているのか、そのPDCAに組織外の人材が関与することで、現状の気づきと改善につながる効果もあります。
私も企業の役員会議や企画会議に参加する機会がありますが、社内の皆さんが気が付かないうちに、議題やテーマが既存活動の戦術のみになってしまっていることがあります。組織内の風土・慣習・あつれきなどと無縁の外部の立場・視点を活用することで、現状の振り返りと評価にもつながると思います。
<まとめ>
新規事業の探索を促すには、相応の仕組みと取り組みが必要。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
