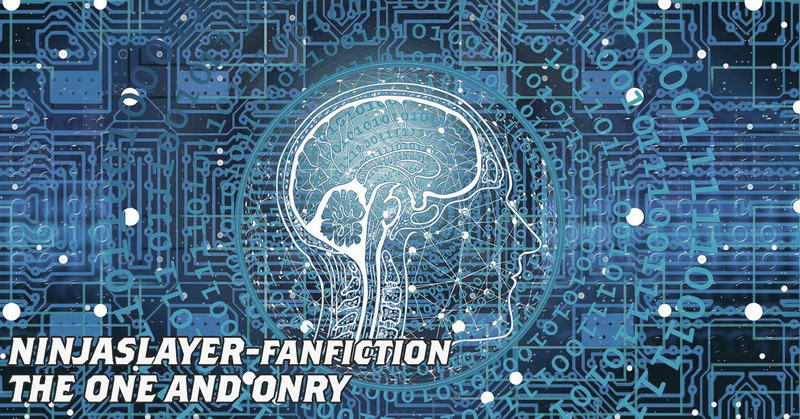
ニンジャスレイヤー二次創作:ザ・ワン・アンド・オンリー
重金属酸性雨降りしきるストリートに、今日も無数の人々が行き交う。ネオサイタマにとっての普遍的光景である雑踏の喧騒とネオンの光。しかしこの街がそういった日常を取り戻してから、未だ日は浅い。
「……」
ストリートを歩く一人である全身義体のサイバーゴス少女が、歩みを止めずにつぶやいた。磁気嵐が消失し、月が砕かれ、日本という国が消失してからの、全土を未曾有のケオスが吹き抜けた。その爪痕を、人々は確実に埋めようと足掻いている。
彼女の名はユンコ・スズキ。世界で唯一のバイオニューロンチップからの復活を遂げた再生者である。しかしその事実を知る者はごくわずかであり、多くの人々に対して、彼女は未だ何者にもなり得てはいない。今のユンコはストリートの中の最小単位に過ぎない。
「これなら、もうすぐ……」
ユンコは歩みを進めながら、思考する。己の将来のこと。ネオサイタマのこと。そして――
(どう、言おう)
あの日から、常に自分の心の片隅に存在し続ける者。いや、それは占有と言った方が正しいのだろう。どんな時もリソースのほんの数%を占有する、決してキル不可能なプロセス。
だが、それでもユンコは掴みかねている。彼我の関係について。どうしたいか。どうなりたいか。それすら不定形だ。ありふれた恐怖や焦燥などとも違うような、ただただ彼女自身の胸中に抱えたものを具体化できずにいる。
「……もしかして、ユンコ=サン?」
「エッ?」
思考中、不意にかけられた一声。反射的に顔を向けた先にいたのは、ジャケット&タンクトップとカーゴパンツの色白の女。ブルーのサイバーサングラスが明滅し、体格のよい男と並んで歩いていた。ユンコは少しして、記憶の中からそれらしき人物を探し当てる。
「……ウイチャン=サン?」
「ヤッタ! 覚えててくれた!」
それはかつて、ユンコが師であるナンシー・リーとともに救出した女の名であった。旧知……と言えるほど深い付き合いがあったわけではなかったが、その関係は確かな感謝と信頼によるものだった。
「知り合いかい、ウイチャン」
脇の男が声をかけた。そこそこ大柄だが体付きは標準的。声のトーンからしても、どこにでもいる普通の男……という印象を与えるものだった。
「昔ちょっとね。恩人なんだ」「へえ」
「えっと、ドーモ……ユンコ・スズキです」「ドーモ。タギマ・ヨシオです。ウイチャンにこんな知り合いがいたとは」
奥ゆかしく頭を下げる仕草が、タギマと名乗った男の人柄を表しているようにも見えた。
「ユンコ=サン、今帰り?」
ウイチャンはサイバーサングラスを外し、ユンコの方へと歩み寄る。色こそ白いものの、昔よりもはるかに健康的な印象をまとっていた。
「もしご飯まだなら、一緒に食べに行かないかい?」
「エッ、まだ……だけど。そんな、悪いよ。邪魔するみたいで……」ちらりとタギマの方を見る。すると、タギマも口を開いた。
「俺のことなら気にしなくていいさ。久しぶりに会ったんだろう。……こんな時代だ。明日無事に会える保証なんてないんだから、積もる話があるなら全部してしまえばいい。俺は適当にそのへんでメシ食ってるよ」
ユンコはタギマの言葉に対して何かを言おうとしたが、何も言えなかった。何を言ってもシツレイになるような気がしたからだ。
「……じゃあ、お言葉に甘えます」「今度埋め合わせはするよ、ヨシオ=サン。アリガト」「ン、気にしないでいい……」
タギマは若干照れくさそうに頬を掻いた。ユンコの目から見ても好ましい青年であることは間違いなさそうで、ユンコの中のウイチャンへのイメージを崩さないものであることが、妙に嬉しかった。
「ま、テキトーに連絡してくれ」
「ヨロコンデー。それじゃ、どこ行こうか」
◆
二人は手近な回転スシ・バーへと足を運んだ。ユンコは基本的にスシしかエネルギーにできぬ身体であるが故だ。上等なオーガニック・トロなどは期待できないが、このようなシチュエイションで多くを求めるつもりはない。それよりも、かつての知人との予期せぬ語らいの機会に巡り会えたことが、いくらか気分を高揚させていた。
「私のオゴリだからさ、遠慮せずに食べておくれよ。ユンコ=サン」
「アリガト……でも、いいの?」
「何言ってるの。昔は助けられてばっかりだったんだから、今度はこっちがいい格好する番」
「じゃあ、お言葉に甘えて」
そう言うと、ユンコはレーンに流れてきたトロ・スシを頬張る。悪くない。
「おっと、本当に遠慮ないや」「……恩人だからね」
そう言うと、わずかな沈黙のあと、二人はこらえきれずに同じタイミングで笑った。それはユンコにとっても、随分久しぶりの感覚だった。
「ナンシー=サンは元気?」「うー……ん、どうだろう」
思わぬ返事に面食らうウイチャン。ユンコはどこから説明するべきか、やや迷った。
「アマクダリとの最後のミッションで、その、ソウルワイヤード状態に」「……それって」
ユンコはウイチャンの考えたことがすぐにわかった。かつての彼女も、それに似た危機を経験していたからだ。肉体と精神の分離……
「なるほど、ね……他人事とは思えないな。でも、その様子じゃ?」
「うん、確証はないけど……きっと今もコトダマ空間にいる。またいつ戻ってきてもいいように……肉体も保管してもらってるから」
「あのナンシー=サンだものね……私もそう信じるよ」
ウイチャンはそれ以上無理に聞き込むでもなく、慰めるでもなく、ただユンコの語った言葉を受け入れた。その対応はユンコにとっては喜ばしいものであり、ナンシーに対する想いの幾ばくかを共有できる相手と言えた。
「……なんだかしんみりしちゃいそうだし、私の話でもしたいところだけど……何から話そうか」
「うーんと……あれからどうしてたの?」
「少しの間ニチョームで世話になってたけど……やっぱりちょっと水が違ってね。どこもかしこもドタバタする中を転々として、なんとか生きてきたよ」
彼女が無事にあの混乱期を生き抜いていてくれたことは、ユンコにとっての少なからぬ救いであった。ユンコ自身、激動の只中を、知人や仲間と駆け抜けてくるだけでも必死であったのだ。
「本当に、よかった」「せっかく救ってもらった生命さ。そう簡単にくたばる気はないよ」
ウイチャンはそう言うと、マグロ・スシを咀嚼した後、さらに話を続けた。
「今はUNIXバーで働いててね。さっきのタギマ=サンとも、そこで知り合ったんだ」
「そうだ。タギマ=サン……!」
ユンコはスシを食べる手を止め、ウイチャンへの視線を強めた。
「ははは、そんなに気になる? 私達のこと」「あっ、ごめん、いや……なんていうか……」
「いいよいいよ。自分でもちょっと意外だっていう自覚はあるしね。……まぁ、甘えさせてもらってる……ってとこかな」
そこからのウイチャンの表情は、一段優しくなったように見えた。ユンコの知らない表情だった。
「私は元々電子ドラッグなんかに溺れてた人間さ。多分、ユンコ=サンよりよっぽど弱い。……なるべくひとりでやっていこうって思ってたんだけどね。タギマ=サンが気にかけてくれて。しんどくなってたの、見抜かれたんだな」
ユンコは聞き入っていた。そこに下世話な好奇心がなかったと言えば嘘になるが、ウイチャンという人間がどういう男女の関係を紡いできたのかということについては、今の自分にとって何らかの助けとなるような気がしたからだ。
「……もっと色々聞きたい?」
真剣に聞き入るユンコの様子を見たウイチャンは、一転して意地の悪い笑みを浮かべた。
「アイエッ、それは、アー…」
「まァ、多分君が想像してるような感じだよ。求められれば応じるし、求めれば応じてくれる。ギブ&テイク。ウィン・ウィンな」
「そうなんだ……」さらりと言ってのけるウイチャンは、自分よりずっと大人に見えた。歳を聞いたことはないが、同年代のような気分でもあり、ナンシーと話している時のような気分にもなる。独特のアトモスフィアを持っていた。
「ユンコ=サン、もしかして」ウイチャンの目が細まった。
「なんか困ってることとかあるのかな、男絡みで」「ウェッ!?」
見事に見透かされてしまっていた。サイバネ心臓が高鳴り、ユンコは言葉に詰まる。が、それは暗に肯定を意味しているのと同じことである。
「言いにくいことじゃなかったら、相談に乗らせてもらうよ」
ウイチャンは問い詰めるでもなく、ただ穏やかにこちらの言葉を待った。ユンコはやや思案する。なにせ、「彼」との関係を他者に相談したことなどこれまでにほとんどなかったのだ。ナンシーがいれば色々と話していたのだろうが。
だが、すぐに心は決まった。ひとりで抱えていてもなんともならない段階に入っていると、自分でもわかる。どんなに整然と思考しているつもりでも、それだけではどうにもならないのが人間の脳内というものなのだから。
「えっとね……うん。男の子。の、ことなんだけど……」そこで、沈黙。
「言いにくいなら……」「いや、違うの」
ユンコは頭をひねる。どう話すべきか。うまく言葉にできない。そして、いっそのことそのまま出力してしまえばよいという結論に至った。ウイチャンは、それができる相手だ。
「私ね、わからないんだ。その……彼とのことが、よく」
「ふむ……『とのこと』が、ね。続けて」
「はっきりと告白をしたわけでもなくて……いつも一緒にいるわけでもなくて……いや、その。LAN直結は割と、してるんだけど……」
話していて、体温が上がってゆくのを感じる。なんらかの反応を返してくるマイコ回路を、どうにか押さえつける。
「うん。大丈夫。無理はしないでいいからね」ウイチャンの声はあくまでもカウンセラーめいて優しい。
「多分、好き……ってことなんだと思う。でも、それまでに私が考えていたようなこととは、色々な何かが決定的に違っていて……それで、自分でもよくわからない」
ユンコは言い終えてふう、と息を吐く。入れていたチャを一口で飲み干した。ウイチャンは残っていたタマゴ・スシを口へ放り込むと、皿を一端脇へとやった。
「そうだね……ちょっとずつ詰めていこうか」「うん」
「まず大事なところ。その彼とは今もうまくやれてる?」「やれてると思う。シンパシーっていうか……とても波長が合う感じ。別に同じサイバーゴスでもないし、趣味や性格はぜんぜん違うんだけどね。……たまにケンカはするけど」「なるほど」
ウイチャンは顎に指を添え、またいくらか考えた後に、口を開く。
「自分では付き合ってると思ってるけど、相手がどう思ってるか……みたいな類の不安ではない?」その言葉を聞いて、ユンコはまた思考の迷宮の中から、どうにか言葉を探し出す。
「アー……彼がどう思ってるのかは、そんなに気にしてない。むしろ、私と同じような気持ちじゃないかなって」
「うん」
「でも、付き合ってるかって言われると……なんだか、変な感じがする。素直にそうだって言えない。言いたくない」
「ふーむ」
それはユンコの偽らざる感覚であった。だが、ならばどういう表現が適切なのか、見つからない。わからない。それが論理負荷となってニューロンを圧迫しているような。
「……一般的なプロセスを踏んでいない恋愛ってのは、よくあるものだとは思うけれど」「そうだね。そう、なんだけど」「ごめん、別に責めてるわけじゃないんだ。ただ……うん……」
ウイチャンの表情は真剣そのものであった。それは自分がかつての恩人だからというだけではなく、本人の人柄によるものなのだろう。そのことをユンコは、何よりも感謝した。
「少しだけ私の話をするね」「あ、うん。大丈夫」
「私もね。タギマ=サンとの関係。曖昧なんだ。流れでそうなったっていうか……正直、付き合ってるかって言われると微妙だと思う。対外的にそう言うことに抵抗はないし、できる限りのことはしてあげようと思ってる。でもいつ自然消滅してもおかしくないし……そうなっても、多分そんなにショックじゃない」
ユンコは黙って頷きながら、ウイチャンの話に耳を傾ける。
「十年後も一緒にいるかって言われると、まず……いないんじゃないかな。ユンコ=サンはどう? その彼と、ずっと一緒にいたい? いると思う?」
「……いたい。絶対にいる」
ユンコは自分でも驚くほど、すんなりとその言葉が出てきていた。
「他の女に取られたりしたら、悔しい?」
「……ファッキングファックだね」
一段下がったユンコの声のトーンを聞いたウイチャンが吹き出し、すぐに小声で謝った。
「……一般論としてだけど。私の目からはとびっきり恋してるように見える」
ユンコは何かを言いたい衝動をこらえて、ウイチャンの言葉を待った。
「ただ、ユンコ=サンの場合は、それじゃ定義できないんだろうな」
「定義?」
「私もね、なんとなくわかるんだ。今の関係を適切に表す言葉がないって思ったりする。言葉は定義だからね。それを口に出した瞬間、相手の頭の中にある普遍的な意味に置き換えられてしまう」
「あっ……」
ウイチャンのその言葉を聞き、ユンコの中で何かが腑に落ちたような気がした。
「もっとも、私と違ってユンコ=サンのは……大きすぎる気持ちや感覚を一般的などの言葉にも当てはめきれないって感じなんだろうけど。そのあたりは、サイバーゴス気質でもあるのかな」
「うん……うん。そうだ。恋人とか、付き合ってるとか、そういうありきたりな言葉で私たちの関係が定義されてしまうのは、嫌だ」
ユンコの声には力が込もっていた。不定形だった自分の中の何かに輪郭が生まれ、はっきりと知覚でき、向き合えるようになった。恋人。パートナー。バディ。夫婦。ソウルメイト。……どれでもない。あるいは、そのどれでもある。
在りし日に胸の内で叫んだ言葉が頭をよぎる。前例の無い何か。きっと自分は、彼とそう在りたいのだ。自分達の関係を、自分達だけのものにしたいのだ。
「いいね。その顔。ユンコ=サンらしい」
「……そう?」
「ああ。出会った頃の、ユンコ=サンの顔だ」
――数年前。まだ、自分がそこいらの無軌道大学生と大して変わらない存在だった頃。あの頃と比べて、自分はやはり変わっていったのだろう。ナンシー以外の大人とも本格的な交流を持ち、幾分かは成長していったのだろう。
しかし、あんなシンプルなことに気付けなかったのは、あの頃に持っていた何かをどこかに置き忘れてしまっていたからか? などというセンチメントがよぎる。否定はすまい。しかしあの頃に戻りたいなどとは思わないのが、ユンコ・スズキだった。忘れ物は、ウイチャンが届けてくれた。
「ありがとう。ウイチャン=サン。色々、吹っ切れたような気がする」
「それはよかった。もう……大丈夫?」
「どうかな」
ユンコは苦笑いを作ってみせた。
「結局は、自分のワガママだから。世間の定義なんてファックユー。私は、私が納得できる定義を見つけたい。でも」
ウイチャンは無言で頷いた。
「ワガママ言うばかりじゃダメってことも、わかってるつもりだから」
愛好のサイバーゴス・ファッションは、反抗のためのプロトコルであり、ユンコにとっても然りであった。だが、彼女はもう無軌道大学生ではない。生きるためには社会と関わり、人と関わり、折り合い、居場所を見つけてゆくしかないことを知っている。サイバーゴスのためのユンコ・スズキではなく、ユンコ・スズキのためのサイバーゴスなのだ。
彼女は決して反抗を捨てはしないが、決して反抗に染まりもしない。
「とりあえず、彼に全部話してみる。抱えてたこと全部。で、相談」
「クールだよ、ユンコ=サン」
「えへへ、ドーモ」
……その後は、改めてスシを食べながら、他愛のない話をした。支援スタッフの後押しを受けて、猛勉強していること。自分なりに父の遺志を継ごうと思っていること。「彼」とのあれやこれや……楽しい時間は、すぐに過ぎていった。
◆
「今日はごちそうさまでした」
「ううん。お役に立てたようで何よりだよ」
そう言うと、ウイチャンはポケットからメモを取り出し、ユンコに差し出した。
「私のアドレス。よかったら連絡ちょうだい」
「うん。また連絡するよ。今度は私が奢る番」
「それはそれは、トロばっかり食べてたお返しをしなきゃいけないねぇ」
「……自慢のサイバネボディだから仕方ないの」
そこで、また笑い合う。
ウイチャンからの連絡を受けたタギマの姿が見えると、ユンコは名残惜しさを抑えて、今日というの日の別れを告げる。
「オタッシャデ」
「オタッシャデ」
ユンコ・スズキが「彼」と誓いを交わし、誰もが認める何者かになるのは、もう少しだけ先のことだ。
【ザ・ワン・アンド・オンリー】終わり
スシが供給されます。
