
現場目線を大事に、信頼獲得を|ファンファーレ代表取締役 近藤志人【後編】
「社会課題をテクノロジーの力で解決する」というミッションを掲げ、事業開発を進めているファンファーレ。労働人口不足で立ち行かなくなる産業廃棄物業界の課題解決に取り組んでいます。
noteではファンファーレ代表取締役・近藤のインタビュー記事をお届けします。前編では、なぜ近藤が起業することになったのか背景や思いをインタビューしました。
後編では、現場での評価や苦悩、そしてファンファーレでの働き方について聞きました。
プロフィール
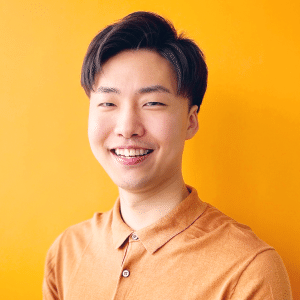
近藤志人(ファンファーレ株式会社 代表取締役)
1991年生まれ。美大出身のUXデザイナー兼経営者。crewwにて大手企業の100件以上の新規事業創出に関わった後、リクルートにて組織開発・大規模プロダクト開発などを経験。その後、2019年ファンファーレを創業。AIを活用した廃棄物業者向けの業務支援サービス「配車頭」を提供。
現場目線で関係構築を第一に
■8年もの準備期間を経て起業されたファンファーレの現在の手ごたえについて聞かせてください。
近藤:弊社の事業が経産省の主催する「始動 Next Innovator 2019」というプログラムに採択されていて、国としてもこの業界課題というのを支援したいと思っていただいています。

また、東大IPCの1st Round(シードベンチャーに対する支援活動)にも採択されているんですけども、そのパートナー企業の方からも、ゴミを出さない企業はなく、この業界の課題の解決を応援したいと評価をいただいています。
評価いただく際の視点は、私が現場に行ったときに感じることと通じるところがあります。現場の産廃業者の人とIT屋ってかなり距離があるので、外部からIT屋さんが入ってきたときに「ソトノヒト」というような印象を持たれることが多いです。
私が入っていくときは、とことんその業者さんの動きというのを理解していて会話を始めるので、会話を進めていくうちに「仲間として一緒に社内の課題や労働環境を解決していこう」という目線になってくださるんですね。そうした現場目線で対外的に業界の課題を伝えるので、「この業界課題がこんなものだとは知らなかったよ」「ここまで大変なことがあるんだね、じゃあ応援したいね」というような共感を支援先の方々から得られているのかなと思っています。

■廃棄物業界の現場にITを導入しようという試みについて、現場の方々の反応はいかがですか?
近藤:現場としても、労働人口が不足していて既存リソースでどうやって効率的に回していくのかというのを考えているので、何かしなきゃいけないという危機感はあります。
ただ産廃業自体はある程度利益の見込めるビジネスなので、危機感はあるもののドラスティックに業界とか自分の会社を変えていこうというのは外部からのアクションが無いとなかなか難しいという印象を持っています。
「弊社の配車アルゴリズムを使って一瞬で配車表が組めます!」と謳って産廃業者に提案に行ったとしても、向こうからすると、"メールを使います"、"ログイン機能があります"っていうだけでも覚えるのが大変なのに、配車アルゴリズムって何?みたいに、魔法の杖みたいな感じでどうしても捉えられてしまうところがあって、どこへ行ってもそんなこと絶対できないと言われることが多いです。
なのでまずは関係構築をすることが大切で、関係構築ができたあとに「じゃあちょっとできるかどうか1回試してみようか」と言っていただいて、実際に弊社のアルゴリズムで作成した配車結果を持っていく。そうすると「あ、ほんとにできるんだね」と実感していただいて徐々に信頼獲得していく。このプロセスがとても重要だと感じています。
ファンファーレは業種問わず優秀なメンバーが集まっている。チームとしてさらなる躍進を。

■ファンファーレのこれからの展望について教えてください。
近藤:弊社を応援してくれる方々が集まっていて、一緒に弊社のサービスを作っていこうというクライアント様もいてくださっているという状態で、あとは期待するものをきちんとクライアントに届けるための開発をしっかり進めていくという段階です。
一方で開発メンバーやCSメンバーなど、まだチームが十分にそろっていない状態です。弊社の目指そうとしている世界だったり、社会課題をITの力で解決していきたいということに共感いただける方に、まずは業種を問わずいろんな形で入っていただけると嬉しいなと思っています。
■ここまで近藤さんのお答えを聞いていると論理的な方だなという印象を受けるのですが、メンバーにはどのようなコミュニケーションをとっていますか?
近藤:難しい質問ですね。自分が論理的かどうかはわからないですが、人がなにか行動するときって「心の納得」と「頭の理解」の両方が必要だと思っています。
私はどちらかというと元来「心の納得」を先行させるタイプだったんですけども、社会人経験を積む中で、「頭の理解」をどうやって作り、他者に対して伝えていくかを考えないと一緒の方向に向かって進めないんだなというのを実感しました。なので、メンバーやクライアントに対して会社の方針をなるべく言語化をするように心がけています。
現在ファンファーレは、本当に優秀な人たちにジョインしてもらっていると思っています。スキルが高く、自律的に動いてくれています。創造的な業務は、今の優秀なみなさんにお願いして、それ以外の業務はお金や、私の工数をなるべくかけて自動化したり、アウトソースして効率的な事業推進を心がけています。

また、弊社のような小規模のスタートアップの組織的な強みは、「局所最適解と全体最適解の調和」だと考えています。
つまり、自律性の高い個人がマネジメントを挟まずに、目の前の業務の局所最適解として成果物を出し続けていても、会社の全体最適にブレなく繋がっているという状態です。その組織の強みを活かすためにできることは、会社の全体最適解の認識がずれないように、会社運営の透明性をなるべく上げる、そして各人の成果物が会社全体にとってどのような貢献になっているかを出来る限りシェアすることを心がけています。
例えば、オンラインのコミュニケーションの中で週間レポートのような報告書をシェアしています。ファンファーレ・ウィークリーニュースというもので、週の頭に先週までに起こった事を経営・営業・開発の3つの観点でアップデートするようにしています。
営業の方も「開発のデータベースの設計が終わりました!」みたいな事に一緒になって喜べる状態を作るのが大事だなと思っています。
■現在のチームメンバーはどういった構成でしょうか?
近藤:私とCTOの経営メンバーが2人のほか、営業2名、開発がインフラ、バックエンド、フロント、アルゴリズム、UI/UXの役割で7人程でやっています。
営業の体制は産業廃棄物業界で長年システム導入の営業を行ってきた方2名にサポートいただいており、いいものを作って売ることができるという状態を作っています。外部のパートナーの方にかなりの割合で入ってもらっておりますので、弊社としては徐々に内製化していきたいと思っています。

■外部の方も含めた社内の雰囲気について教えてください。近藤:共通している雰囲気としてはみんなが同じユーザーの課題に向き合っているという点です。全員の職能が異なりますし、副業の方も多いので関わる方のコミット量もそれぞれなんですけど、結構議論は効率的に進むことが多いと感じています。それは事業課題が明確で、皆が共感している状態だからだと考えています。それぞれの専門性の高い話はお互いに理解できなくてもユーザーの課題認識が揃っていれば、効率的に議論が進められるという印象です。
■最後に、この記事を読んでいる読者の方にお伝えしたいことがあれば教えてください。
近藤:弊社はこれからも更に成長していきたいと思っているので「こういったお手伝いだったらできるかもしれない」みたいなことがありましたらお気軽にコンタクトしていただければと思います。
また、直接サポートはできないんだけども共感してくれたという方もいるかもしれないので、記事を読んで自分が何か挑戦しようと思うときに、こういった人もいるんだなと思っていただいて、少し背中を押された気持ちになっていただけると嬉しいなと思います。
お話ありがとうございました!
弊社では社会課題への解決に熱い思いを持った仲間を募集しています。カジュアル面談からでもご連絡いただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/7041862/original/448c6ce8-df1d-43d9-acaf-b8838cbc49d9?1626310212)
/assets/images/7106160/original/cd217d06-f01b-451a-acdf-12b857b0a1c0?1624964716)