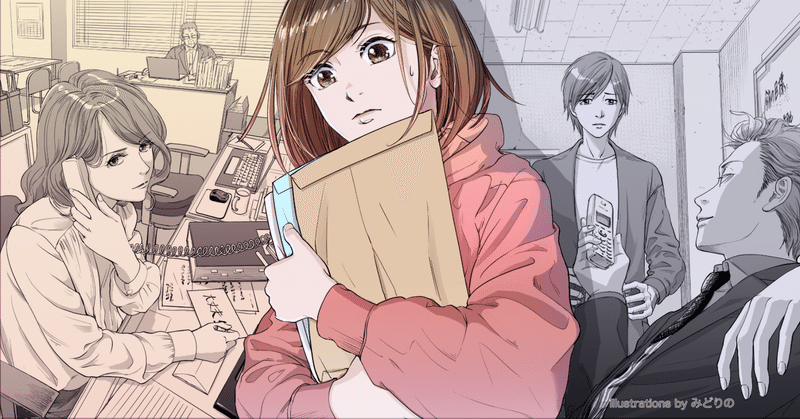
0310:小説『やくみん! お役所民族誌』[3]
第1話「香守茂乃は詐欺に遭い、香守みなもは卒論の題材を決める」(3)
<前回>
*
全国47都道府県の全てに、少なくともひとつは、国立大学が存在している。それは、終戦後に新たな教育制度を構築する際、教育の機会均等を実現する目的でそのような方針が立てられたからだ。国立大学は、それぞれの地域で低廉な学費により優秀な人材を育成し、戦後日本の経済復興に大きな役割を果たした。
過疎県・澄舞にも国立の総合大学が設置されているのは、そういうわけだ。おかげでみなもは、家計負担の小さい地元進学をすることができた。
人口規模に相応して、澄舞大学は全国の国立総合大学の中では小規模校だ。それでも二つのキャンパスに六学部五千人あまり、大学院生を入れれば六千人を超える学生と八百名近くの教員を擁する高等教育機関の存在は、この地域の貴重な知的資源として機能している。
そうした事実の一方で、医学部を除いて入試偏差値は50前後と、決して高くない。その現実が、県内高校生の進学時の県外流出と、逆に県外からの流入に繋がっている。今や学生の実に7割以上が県外出身者だ。
秋宮秀一もまた県外組で、偏差値と学費と実家からの距離を総合的に考えた結果、地元・丘尼(おかあま)市から特急で2時間40分、山地と県境ふたつを越えた先の澄舞大学に進学した。
こうして、澄舞大学で出会う運命が、二人の前に用意された。
*
親元から離れて独り暮らしを始めるこの年頃は、間違いなく恋の季節だ。恋愛は出会いとコミュニケーションのふたつの要素から生まれる化学反応、ホルモンスイッチが連動するかどうかで成否が分かれる。
スマートに異性を誘える性格の者は、早くからパートナーを見つけ、青春を謳歌する。そうでない者にも、青年期社会集団で生活をしていれば、出会いは幾度だって訪れる。後はコミュニケーションを重ねた先に、二人のスイッチが入るかどうかだ。
秋宮秀一は、誠実で人当たりの良い青年だ。しかし恋愛に関しては、決してスマートな性格とは言えなかった。異性に対して、友人としてならともかく性的パートナーとして付き合うのにどんなふうに誘えば良いのか、見当もつかなかった。入学して最初の二年間、出会いらしきものは幾度か彼の前に出来したが、戸惑ううちに次々と通り過ぎて行った。「幸運の女神には前髪しかない」という古代ギリシアの箴言を実感する二年間だった。その分、勉強とサークル活動に打ち込んだ。
大学生のうちに彼女を作る事は無理かもしれない、と半ば諦めの境地にあった3年生の春、年下の女神が現れた。
入学式当日からしばらくは、学生サークルによる新入生争奪戦が繰り広げられる。秀一たち総合文芸研究会の企画する新歓イベントを訪れた十数人の新入生の中に、香守みなもがいた。素直に(可愛らしい娘だな)と思った。「可愛らしい」とは、見た目だけの話ではない。会話の内容、佇まい、ふるまい。どれもが明るく人懐こく、周囲をリラックスさせるものだった。秀一の目には、新入生たちの中でみなもはひときわ輝いて見えた。人間としても、異性としても。
もちろん、そこまでだ。2個上の先輩として、秀一は分け隔てなく新入生たちと接した。特定の相手にセクハラになりかねないアクションなぞ起こせる筈もない。
一ヶ月後、会に残った新入生は6名。その中にみなもが含まれていた。
*
みなもが大学に入るまで文化人類学の名前を意識したことは、たった一度しかない。
16歳の夏に高校の図書室で、ふと上橋菜穂子『精霊の守り人』を借りた。軽い興奮状態で読み終え、奥付を確認した。著者の肩書きが文化人類学者とある。初めて目にした言葉だったので、wikipediaで調べた。「民族・社会間の文化や社会構造の比較研究」、ふーん、なるほど。実際には何もわかってはいなかったのだけれど、作品のイメージに似合っている気がした。そのままこの学問の名前は記憶の底に沈んだ。守り人シリーズの続刊も読む機会のないまま日々が過ぎていった。
志望校は経済的に地元の澄舞大学ほぼ一択だったが、学部学科は消去法で選んだ。理系は勘弁、教育は柄じゃない、法律や経済は堅苦しそう。そうして残ったのが法文学部社会文化学科だった。
受験偏差値52.5。成績的に平均あたりをうろうろするみなもには、必ずしも楽観できない状況だった。みなもは友人たちに「やる時はやる女」と呼ばれていた。小学生時代からそれを裏付けるエピソードには事欠かない。受験も同じで、秋から始めた数ヶ月の猛勉強で現役合格を果たした。
大学では何かの学生サークルに入ろうと心に決めていた。高校時代は、入学当初にピンと来る部活動がなく、そのままずるずる帰宅部で過ごしたことが密かな悔いとして残っていた。
澄舞大学の学生サークルは、高校のそれよりバラエティ豊かに思えた。いくつかの面白そうなサークルの新歓企画に参加した中で、最初はあまり気のなかった総合文芸研究会が結果的に肌が合い、入会した。そこに居たのが、二年先輩の秋宮秀一だった。
好きな小説って何、という定番の部室雑談の中で、みなもがいくつかの作品と共に『精霊の守り人』の名を挙げた時、秀一が反応した。
「守り人シリーズ、いいよねえ。全部読んだ?」
「いえ、精霊だけです」
「もったいない、シリーズ全部持ってるから貸すよ? お勧め。あとね、ラジオドラマは録音してるし、アニメとテレビドラマも録画してるから。それぞれの監督が原作のどこに注目しどこを捨てて自分自身の表現に組み直したか、比較すると面白いよ」
サークルとは「好き者」の集まりだ。総合文芸研究会もまた、会員それぞれに偏愛作品を持ち、それを他人に薦める情熱に溢れた、良い意味でオタクの集まりだった。秀一も間違いなくその一員だ。
みなもは気圧されつつも、秀一がこの作品群を心底好きなんだということを、好感を持って受け止めた。
「じゃあ、まず精霊の続き、貸してください。少しずつ読んでみます」
彼女はすぐにハマり、それがやがて文化人類学を専攻に選ぶことに繋がったのだから、人生は分からないものだ。
*
二人の仲が恋人に発展したのは、出会いから三ヶ月余り経過した7月のことだ。
秀一のアパートでは「映画鑑賞会」が頻繁に開かれ、サークル仲間たちがよく出入りしていた。みなもはほぼ皆勤賞で参加し、二人きりになることも増えてきた。
いつしか自然と、互いに異性として意識するようになっていた。それでいて、互いになかなかアプローチできない。それもまた、若さのひとつの形だ。
最初に勇気を振り絞ったのは秀一の方、なのだろう。
その日、みなもは秀一の部屋でクッションにもたれて、秀一と映画を見ていた。意識の三分の二は映画に集中していたが、残りは秀一を意識していた。
少し離れて床に腰を下ろしていた秀一が、立ち上がって冷蔵庫から缶ジュースを取り出し、「どうぞ」とみなもの体越しにテーブルの上に置いた。そのまま、さっきよりずっと近くに留まっている。
「ありがとうございます」
言いながら、みなもの手は缶に伸びない。意識の四分の三が、すぐ背後の秀一の気配に向けられていた。
「クッション、半分ちょうだい」
そう言って、秀一がみなもの背後から同じクッションに体を預けてきた。軽く身体が接触することになる。こんな風にしても嫌じゃない、嫌がられない、という信頼が既に出来ていた。
「面白い?」
耳元で秀一が言った。
「うーん」
とだけ、みなもは応えた。秀一に十分の十。映画のことなんか、もうどうでもいい。
秀一の腕がみなもの腕の上に被さった。手が手を握る。みなもは少し体を硬くして、ゆっくり振り向いた。秀一の顔がすぐ側にあった。
「先輩?」
「俺、香守さんのこと、好きだよ」
間近で秀一の頬が二度痙攣した。緊張している先輩は可愛いな、とみなもは思った。
「知ってました」
みなもは秀一の頬に軽くキスをした。互いの体臭を感じる距離。秀一はみなもに覆い被さり、首筋にキスを返した。
そこで、動きが止まった。
「……言いにくいけど、俺、初めてなんだよ」
「ふふ、私もですよ……私、友達からなんて呼ばれてると思います?」
みなもは、女の子の顔をしていた。ドキドキしながら、秀一は答えようがなく、こう応えた。
「なんて呼ばれてるの?」
「やる時は、やる女」
みなもは下から秀一を抱き寄せ、唇を重ねて舌を絡めた。2秒。3秒。4秒。5秒。もっと。互いの鼻息が頬に当たる。脳の血流がくるくると舞う。全身で相手の存在を感じる。体臭はもう媚薬だ。性器が甘く溶け始める。
二人のスイッチが、完全に連動した。
みなもは体を入れ替えて上になり、秀一の耳元でささやいた。
「私に任せて」
後になってこの時のことを思い返すと、
(あれ、手を出したのって、もしかして私の方?)
と思わないでもない。でもまあ、最初にくっついてきたのは秀くんの方、ということで。
*
付き合い始めると、いつも一緒にいたくなるものだ。
秀一は自宅から遠く離れてのアパート住まいだから、特段の支障はない。しかし市内の実家から通っているみなもは「口実」を必要とした。
最初は「課題を一緒にするから、友人の家に泊まるね」と言っていたが、それが週に二度となり三度となって、やがて滞在時間が逆転すると、隠し通すのは難しくなる。
母親に「彼氏ができた」と打ち明けると、母は
「わお」
と顔を輝かせた。「根掘り葉掘りは聴かないけど、どういう人?」と根掘り葉掘り聴かれた。話しだすと、それまで隠していたのがバカらしくなるくらい、自然にいろんなことを話せた。そうだよ、別に隠す話じゃあ、ないんだ。
翌朝には父親にも伝わっていた。母と父の間ではなんでも筒抜け、それは分かっていた。
父親は娘に男が付き纏うのを嫌がる、というのが古典的な物語パターンだし、現実の世の中でも一般的かもしれない。でも香守家ではそうではない。
「にゃも、おはよう。ウェルカム・トゥ・ザ・大人の世界!」
開口一番そういった父の満面の笑みに何の屈託もなく、みなもの肩の力が一気に抜けた。とりあえず「なんで『大人の世界』だけ日本語なん」と突っ込んだ。
翌年、二人は決断を迫られることになる。秀一が四年生となり、卒業後の進路を決めなければならない。秀一は元々、出身地の丘尼に帰るつもりだった。しかしそれは、遠距離恋愛になることを意味する。または別れるか、だ。
二人とも、別れるなんて、考えられなかった。遠距離恋愛も、できれば避けたかった。将来は結婚するのだろうとなんとなく思っていたが、まだまだ先の話だ。
結論を先延ばしにして大学院に進学することも一度は考えた。そうすればみなもの卒業まで大学に残ることができる。しかし、同じ行政法学ゼミに、早くから院進を公言していた友人・早瀬泰彦がいた。彼の能力・資質に、自分は及ぶべくもない。秀一はそう痛感していた。
秀一は、澄舞県庁と丘尼県庁、それから国家二種を受験し、全てに合格した。ギリギリまで悩んだ末に、澄舞県庁に就職を決めた。
さすがに澄舞に残るには両親の了解を得なければならず、秀一はみなもを連れて丘尼の実家に戻った。両親からはかなり厳しい意見も向けられたが、みなも自身は温かく歓迎され、最後には澄舞県庁への就職を認めてもらうことができた。
次に問題となるのがアパートだ。就職をすると衣類などどうしても物が増え、今の6畳1Kでは手狭だ。もう少し広いアパートなら、みなもと一緒に暮らすこともできる。通学に一時間かかるみなもにとっても、大学近くに拠点を持つことはメリットが大きかった。
今のアパートからさほど離れていない場所に、すぐに入れる6畳+4畳半の物件が見つかった。大学まで徒歩数分、澄舞県庁にも自転車で20分見ておけば余裕だ。築年数が古く初任給の手取りでどうにか賄えそうな家賃ではあったけれど、少なくとも学生である残り半年は、実家に支援してもらわなければならない。もしかすると、その後もしばらく。
「うちは構わないけど、まだ学生なのに同棲なんて、みなもさんのご両親が許さないんじゃないの? 特にお父様は」
秀一の母親の心配は、一般的な「娘の親」について妥当だ。しかし香守家に対しては杞憂だった。週の半分以上を秀一の新しいアパートで暮らすようにしたい、そうみなもが切り出した時、父は手を叩いてこう言ったのだ。
「よーし、我々に孫ができるのが早いか、にゃもに新しい弟か妹ができるのが早いか、競争だあ!」
それを聴いた母は背中を丸めて茶をすすり、「はあ?」と耳に手をやった。
そう、香守家の父と母は、少し変わっていた。
【続く】
--------(以下noteの平常日記要素)
■【累積34h24m】本日の司法書士試験勉強ラーニングログ
実績147分、不動産登記法終了。次は演習かと思ったら記述式か。
■本日摂取したオタク成分(オタキングログ)
『アサシンズプライド』第8~9話、メインストーリーに近い部分で一段落。『sonny boy』第3話、相変わらずいい感じ。押井守、今敏、湯浅正明の系譜かな。『ひぐらしのなく頃に 卒』第6話、いんさーん。『死神坊っちゃんと黒メイド』第4話、もしかすると1話からここまででちゃんと観たのは今回初かも。いいね、第一話時点ではプチエロコメかと思ったけど、実は少年誌の爽やかな香りがする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
