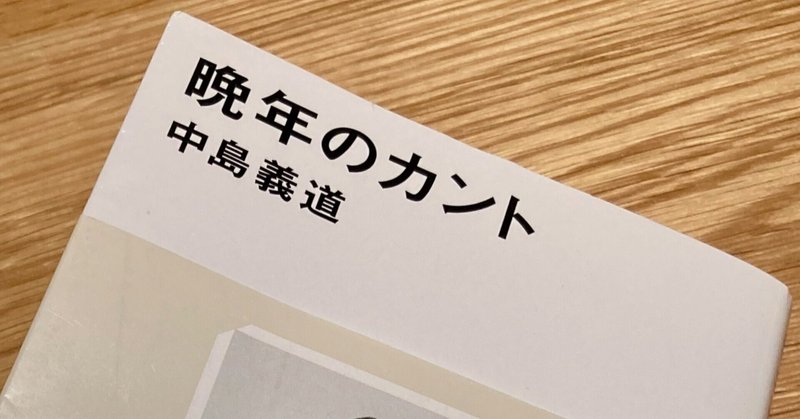
「さらば愛しきアウトロー」と晩年のカント
映画「さらば愛しきアウトロー」をAmazon Prime Videoでみる。いい作品だった。
ストーリーは実話に基づいている。ロバートレッドフォードが主演の銀行強盗役を演じる。1930年代の少年時代から、1980年代高齢にいたるまで数え切れない窃盗や強盗を犯し、収監されるがそのたびに脱獄を繰り返した一人の男の物語。
一方で、追いかける40才なりたての刑事を演じるのは、ケイシー・アフレック。いつも悶々と憂鬱な表情の役柄が多いが、この作品でも人生の下り坂の始まりに、日々、憂鬱な気分が冴えない表情に浮かんでいる。警察の組織になじめず、仕事を辞めたくて仕方がない「不惑」歳の刑事役がハマっている。
原題は「The Old Man & the Gun」。こちらの方が数段いい。インローかアウトローであるか、あるいは合法的か非合法かという問題は、副次的テーマ。年をとっても人間は、生涯、自分の信念を貫き通して、魂の自由に忠実に生ききることができるかという、もっと大きな命題。
真の意味で「自由」なのは強盗か、あるいは、未来を悲観することで現在を自己弁護し続けるその他大勢のありふれた人間の側なのだろうか。押さえた演出によって、その対比が鮮明に浮き上がる。
この作品は、許されうる限りの大音量での鑑賞を勧めたい。優雅な音楽に漂うようにロバートレッドフォードが登場し、続いて、ダニー・グローヴァーとトム・ウェイツが画面に登場。皆、年を食っているが、なんとも味わい深い。この3人が静かに紳士的な銀行強盗をするというおとぎ話のようなシーンを観るだけでも僕は満足できる。しかも、セリフは最小限だが、大切なシーンでは、明らかにビル・エバンスの名曲”Peace Piece”をモチーフにしたとしか思えない優美な曲が静かに流れる。
映画の終盤、警察に逮捕されることを覚悟した男は、車を捨て、馬に乗り薄明の草原を駆ける。そのマントを羽織ったシルエットは、「明日に向って撃て!」で怪盗サンダンス・キッドを演じたロバートレッドフォードへの最大限の敬意だ。共演したポール・ニューマンもジョージ・ロイ・ヒル監督も、もはやこの世にいない。このシーンはジーンと泣けた。
実際、この映画の完成後、ロバート・レッドフォードは俳優業の廃業を宣言したそうだが、たしかに映画愛に溢れている。
この映画を観ながら、ちょうど先頃出版された中島義道「晩年のカント」で知った大哲学者の一人の男の生き様を無意識に投影していた。
第一に「真実性の原理」に従い、その後に己の「幸福の原理」に従うべき人間が、己の幸福を最優先させる「転倒」を起こすこと。それこそ人間のもつ「原罪」だとカントはいう。
著者の中島氏は74歳。カントの研究者として、18世紀のドイツ(プロイセン公国)にて80年の生涯を過ごした晩年のカントが字義通り、己の提示した生き方を貫いたと言えるか徹底的に検証する一冊。いわゆる「実践理性批判」にはじまる「実践三部作」の著者として、キリスト教を信条とする政府への批判を表明しながら、一度取り下げ弁解したカントの哲学者としての「実践力」不足への不満を隠さない。毒を飲んで死んだソクラテスと比較し、負けている、と中島氏は手厳しい。
ただ、国王亡き後、再び、キリスト教より科学と論理に従うべきであるという近代科学主義を復活させたカントの晩年を称える。当時、キリスト教会に反旗を掲げる言論を吐くとは、文字通り命懸けの行為であった。
その後の国際連盟、国際連合への礎となったとされる、カントの「永久平和論」の成り立ちの背景の現実。また、当時、プロイセンの大学では、神学、法学、医学の3学部が教育機関の最高権力として君臨していたが、「哲学」を第一学部にすべしという主張をしているカントの先見性も本書で紹介されている。当時すでに「知の巨人」として欧州全域で名をとどろかせていたカントの最晩年の日常はある意味とても人間くさかった。
「幸福に生きる」のか、あるいは「真実に生きる」べきなのか。50歳になったばかりの自分を「晩年」のはじまりと表現する気はさらさらないが、人生の「黄昏学」をこっそりと学び始めている。
