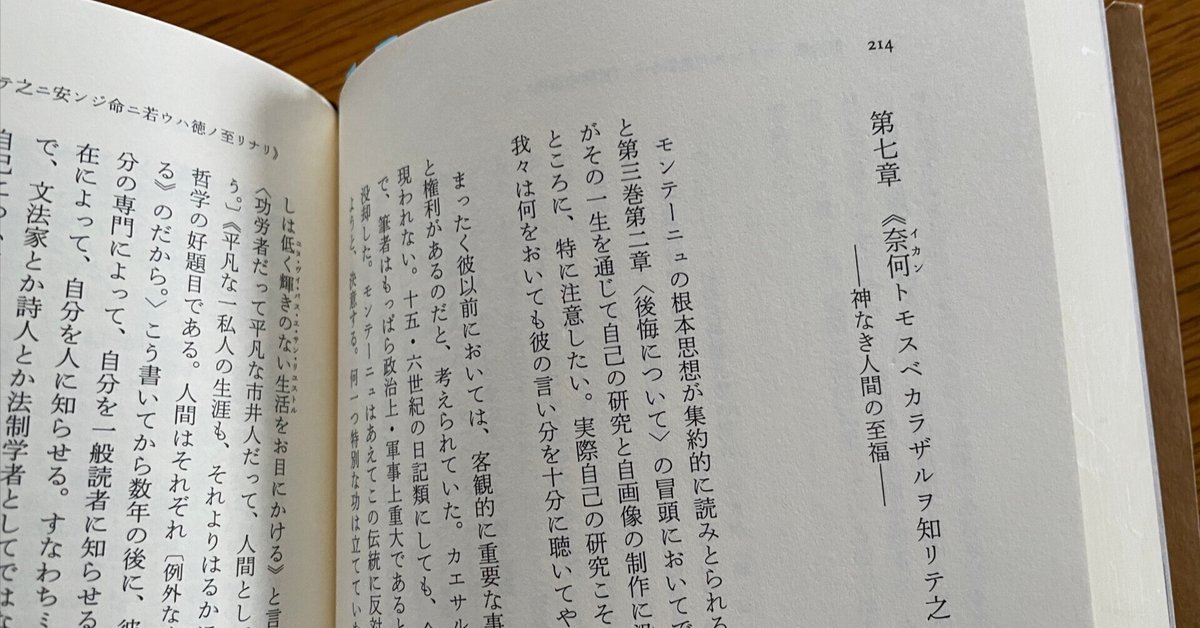
『モンテーニュ逍遙』第7章
第七章 《奈何トモスベカラザルヲ知リテ之ニ安ンジ命ニ若ウハ徳ノ至リナリ》 ──神なき人間の幸福──
(pp.214-236)
自ら其の心に事うる者は、哀楽前に易り施さず、其の奈何とも可からざるを知りて、之に安んじ命に若う。徳の至りなり。
(自分の心に忠実であるには、目前の哀楽に心動かされず、人の能力の限界をよく見きわめて、それを運命として受け入れていくこと、これが最上の徳というものです。)
神なき人間の惨めさ、
神とともにある人間の至福。
『随想録』全篇にわたり、万物流転・生々変化の思想を展開する一方で、モンテーニュは、すべての人間にはある不変のもの(あるいは普遍のもの)が備わっているとも主張する。
本章では『随想録』第3巻第2章「後悔について」からの引用が多く、この章を軸にして語っている。本書全体で大きな拠り所としているモンテーニュの言葉、《世界は永遠の動揺に過ぎない》とか《人間はそれぞれ人間の本性を完全に身にそなえているものだ》も、「後悔について」の冒頭で登場する。
モンテーニュの運命随順・諸行無常の態度は、悲壮で深刻でもなく、ましてやニヒリズムとはまったく無縁の、平静で満足した朗らかなものだったのではないか?...
(本章より)
ここに我々は、モンテーニュという人が、少年時代から老年に至るまで、終始一貫して一つの一般的基本的思想を堅持したことを、ほかならぬミシェル自らの口から聞いたのであるから、誰にもこれを疑う権利はない。これまでのように韜晦であるとか誇張であるとか言う余地はもはやなくなる。ただ問題になるのは、《一般的思想》(imagination generale)とか《一般的意見》(opinion universelle)とか言っているのは、具体的に言ってどのような内容をもっているのかということである。(p.221)
「一般的」という語からは、その語義から少しずれて「ありふれた」とか「あたりまえの」「変哲もない」というイメージのほうが湧いてくることもあるが、本書や『随想録』を読むにあたっては、「普遍的」「万人に共通する」といった本来の意味であらためて捉えたい。
人間ひとりひとりは変化流動してとどまらず、千態変容であるけれども、その根底深処には《人間性の心髄本質》(forme entiere)が宿っていて、それは各人において同一であるという考え方に立ってみると、宇宙はモンテーニュに一つの秩序として映る。(p.224)
《どんな事柄においても、それがすんでしまったらどのようなことになっても、わたしはあまりくよくよしない。まったく、それらは始めからそうなるべきであったのだという考えは、わたしを苦悩から解放してくれる。(...)》(p.225)
『随想録』「後悔について」(III・2・946)より
だからモンテーニュは諸行無常、世界は永遠の振子運動だという現実を確認し、一切は空であると結論するのである。ただここに是非注意しなければならないのは、それをどんな調子で彼が語るかということである。悲壮深刻な語調をもって語るのでもなければ、冷淡嘲侮の調子で言いすてるのでもない。全く満足せる人の平静な態度をもって、彼は人間の空しさを語るのである。我々の空虚も、我々が世界の秩序に安んじて順った結果として見る限り、我々はすでにある程度空虚を克服しているからである。空虚を悲しみもせず悔いもせず、静かに落ちついて受け入れるのは宇宙の生命と合一することであって、エピクロスの〈アタラクシア〉、荘子の〈虚静恬淡〉、親鸞の〈自然法爾〉と同じ心境であると考えられないであろうか。〈奈何トモスベカラザルヲ知リテ之ニ安ンジ命ニ若ウハ唯有徳者ノミ之ヲ能クス〉(『荘子』)と認めるなら、モンテーニュは正に有徳者であり至人であろう。だがモンテーニュはもっと平易にこれをただ〈オネトム〉と呼ぶのである。《百姓もオネトムでありソクラテスもまたオネトムだ》と彼は言うのである。彼から見れば、形而上学者だけがオネトムではないのである。(p.228)
オネトム (honnête homme) … 紳士、君子人。さらに解釈を加えれば、物事の道理、人間としての分際(分相応)をわきまえた人、といったところか。本書事項索引参照。
つまりモンテーニュは、人間にはおのずから人間としての分際すなわち限界があることを知っているから、それ以上のことをあえてなし遂げようとしたり、それができなかったからとて自分を責めたりするような愚かな真似はしない。(p.229)
実際「後悔」という語は、我々の力に及ばない事柄には本当はあてはまらないのだ。さよう、むしろそれは「遺憾」というべきなのだ。
そして彼の根本思想をはっきりと打ち出すために、《神なき人間の至福》(Félicité de l’homme sans Dieu) とか《知恵(叡智)なき人間の悲惨》(Misère de l’homme sans la sagesse) とかいう言葉を、《エッセー》というきわめて謙虚な標題の傍に、副題として書きそえてみたい気がする。(pp.234-235)
信じられないことのようだが、同時代人シャロン、同国人パスカルよりも、中国古代の哲人荘子の方が、ずっとモンテーニュの近くに居る。二人は同じ思想を持っていたと言ってもよいくらいに思う。おそらくそれはすでに言ったとおり、同じ宇宙・大自然を、共通してその思想の源泉として持ったからであろう。 (p.236)
ピエール・シャロン Pierre Charron, 1541-1603 … 哲学者、神学者。モンテーニュとも交友があった。モンテーニュの影響(とくに懐疑主義的側面)を受けて『知恵論(知恵について)』を書いている。
関根秀雄著『新版 モンテーニュ逍遙』(国書刊行会)
関根秀雄訳『モンテーニュ随想録』(国書刊行会)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
