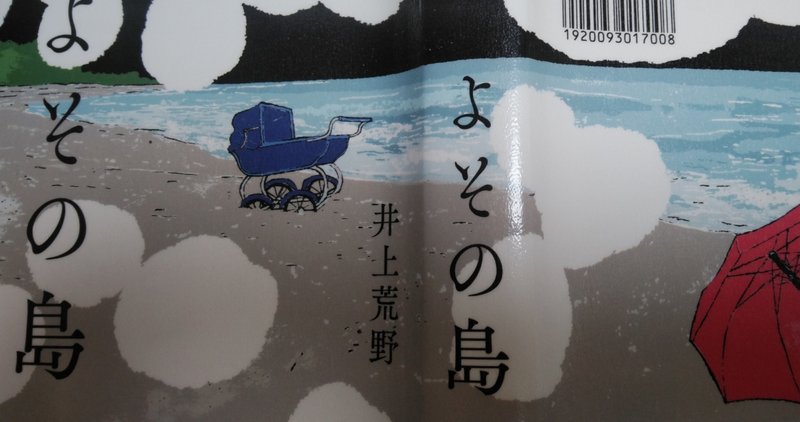
井上荒野『よその島』(中央公論新社)、老いに向き合う?
読売新聞に連載されていた井上荒野『よその島』を読む。
連載当初から「よその島」というタイトルだったのか、物語の一番最後で、「よその島」というフレーズが初めて出て来て、激しく胸を突かれた。作者は最初から、ここに向かって書いてきたのか。
76歳の骨董品店店主の碇谷義朗と70歳の妻蕗子、70歳の作家野呂晴夫の3人が、東京での住居を畳み、とある島に家を買い、共に暮らすことになる。家政婦として雇った仙崎みゆかとその小学生の息子宙太も一緒に暮らす。それなりの人気作家とテレビの鑑定番組のレギュラーもやっていたことのある古物商、それなりの財産はあるのかもしれないが、やや現実離れした設定。本土に用事があればその都度飛行機で移動することになり(島の場所は特に触れられていないが、イメージとしては九州の離島か)、レストランのシェフをしていたというみゆかを、家政婦というあいまいな立場でどのように雇用しているのか。年金は?、とか妙に細かいところが気になるが、義朗と蕗子が抱える秘密、晴夫が隠していること、それぞれのモノローグが繰り返され、矛盾とかなかなか明らかにされない焦点とか、みゆかが島に付いてきた理由とか、小説の半ばまで読んでも、すべてがもやもやとしている。そして、晴夫の小説が映画化されることになり、この島でロケが行われることととなり、新たな登場人物が物語のなかに流れ込んできたことをきっかけに、3人がそれぞれに繰り広げている物語の乖離が激しくなってきて、遂に現実が読者の前に提示される。
そこに至るまでに、思い出とか、恋愛の予感とか、後悔とか、様々な要素が三人によって語られる。その中に浮かび上がるのが「老い」だ。
身体の不如意、記憶の混濁、思い込み、それはわたしにとっても意外と近いものなのかも、と思うと、どう老いるか、ということを選べるようで選べない現実が自分を少しずつ縛っていくような気持になる。そういう意味で、この小説は、読み手の年齢によってかなり違った感想を持つことになる小説なのかもしれない、と思う。
そもそも、小説の原点に立ち返り、人は七十代になって、それまで慣れ親しんできた環境を捨てて新しい生活に入ることが出来るものか、というのも、個人差とか、それぞれの人の置かれた状況によるだろうが、自宅を畳んで子どもの家で同居する、とか、老人ホームに入る、とかではなく、元々何の地縁もない場所に家を購入して他人と住む、というその勇気が持てる人はあまりいないような気もする。将来を心配し過ぎても仕方ないが、どう老いてどう死ぬのか、考えずにはいられないので、この小説のきらきらとした部分よりも、口を広げた暗闇を、ついつい覗き込んでしまう。
ついこの間、同じ作者の『あたしたち、海へ』(新潮社)を読んで、高校生の生態とか人間関係について思いを巡らしたりしたばかりだが、女子高校生より70歳の老女の語りの方が身に浸みる、そんな自分の年齢にも直面したことである。
#読書 #読書感想文 #井上荒野 #よその島 #読売新聞 #老い #あたしたち海へ #中央公論新社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
